一度も稽古することなく門馬三郎の心明活殺流道場を去った姿三四郎ですが、それで完全に縁が切れたわけではありませんでした。
矢野正五郎の門下となって1年半が過ぎた頃、紘道館ではもはや右に出る者がないまでに強くなった三四郎の身の上に、ある事件が起きます。
その日、行きつけのそば屋長寿庵で、いつものように内儀のお幸と他愛のない話をしていた三四郎に、彼女が突然言い寄ってきたのです。
彼はまだ20歳と若い上に、なかなかのイケメンでした。整った顔立ちのうちには澄んだ眼が輝き、唇紅く、濃い眉とつやのある髪が大きな魅力となっていました。後家とはいえ、40に手の届かぬ熟女のお幸は、純心な三四郎に酒を飲ませて誘惑しようとします。ところが、その濡れ場に現れた、1人の遊び人風の男がありました。
男の名は仙吉、偶然にも彼は、門馬たちが矢野正五郎を襲撃した際に、学習院講師の集まりから帰る正五郎を見張っていて、門馬に知らせる役割を果たした人物でした。
お幸の情夫気取りの仙吉にとって、自分の女に手を出した(もちろん、誤解ですが)上に、門馬道場を後ろ足で砂をかけるようにして出て行った三四郎は、無事に帰すわけにはいかない許されざる相手です。腕に自信があり、血気盛んな若者である三四郎は、仙吉に売られた喧嘩をつい買ってしまいます。
仙吉とその子分は合わせて4人。三四郎は匕首<あいくち>や心張棒<しんばりぼう>を手にした遊び人たちをあっさりと片づけます。しかし、戦闘の興奮にすっかり頭に血が上り、駆けつけてきた巡査たちをも投げ飛ばして逮捕されるという大騒動に、事態は発展してしまいました。
幸い、矢野正五郎の文学士と学習院職員という肩書が功を奏し、三四郎は司直の手から逃れることができました。紘道館に戻った三四郎は、破門こそ免れたものの、師範から稽古禁止を言い渡されます。
紘道館と矢野正五郎の顔に泥を塗る大きな過ちではありましたが、この事件は彼におのれの慢心を気づかせ、人間的な成長を促す契機となりました。
そして、長い稽古止めが解かれた時、紘道館はいよいよ柔術諸流との闘いを開始します。警視総監の三島通庸<みちつね>が、警視庁武術大会への参加を要請してきたのです。
それに先立って、海運橋の天神真楊流八谷孫六の道場開きに招待された紘道館は、門馬三郎の心明活殺流と模範試合をすることになりました。
紘道館柔道にとって、公式に行われる初めての他流試合です。
余談ですが、この試合が世間の噂の的になっているさなか、質屋を訪れた三四郎に、番頭がこんなことを言うシーンがあります。
「なんしろ、心明活殺流なんて、名前から文明開化じゃないし、荒っぽい、おっかない柔術だって言うじゃありませんか」
心明活殺流(山田實著『yawara 知られざる日本柔術の世界』によれば、「正しくは殺活心明流」というそうです)は竹内流や天神真楊流、起倒流などのように現在まで伝わってはいませんし、詳しく書かれている資料も見つけられなかったので、実際にどのような柔術だったのかは、残念ながらわかりません。
ただ、その遣い手である門馬(実在)はだいぶ荒っぽい人物だったようで、原康史著『実録 柔道三国志』に「剽悍<ひょうかん>な風貌は豹を思わせる心明活殺流の門馬三郎である。門馬の柔術の殺伐さには定評があった」と書かれており、実戦的強みを持った喧嘩柔術であったとしています。
 昭和48年に刊行された新潮文庫版『姿三四郎』
昭和48年に刊行された新潮文庫版『姿三四郎』
「御高弟二名、御差遣<ごさけん>下されたく候」
との招待状に、選ばれたのは矢野門下中最古参の戸田雄次郎と、実力No.1の姿三四郎でした。
道場開き当日、少年たちの紅白試合がすみ、堤宝山流の古風な鎧組打の形や、道場主自身による天神真楊流の当身の形が披露された後、いよいよ紘道館柔道対心明活殺流柔術、因縁の対決が始まりました。
まずは雄次郎が、活殺流免許皆伝の八田千吉を迎え討ちます。
試合は一方的なものとなりました。万世橋で師匠の矢野正五郎に苦杯をなめさせられた八田は、組み合わずに相手の足を掬い、すぐ寝技に入って絞め、逆を取る稽古に専念してきましたが、自然体で無造作に向ってくる雄次郎の動きに、まったく隙を見出すことができませんでした。逆に一瞬の隙をつかれて襟と袖をつかまれ、鋭い小内刈で何度も尻もちをつかされたあげく、反撃せんと押しに出たところを雄次郎得意の巴投げで3間(約5m)も距離のあった活殺流陣営の席まで吹っ飛ばされてしまいました。
その後は、組んではまた投げられると、両手を前に突き出して、道場中を後ずさりして駆け回るという醜態をさらし、見かねた検証役の八谷の「それまでっ、それまで」という叫び声に救われたのでした。
平成8年に刊行された講談社文庫版『姿三四郎』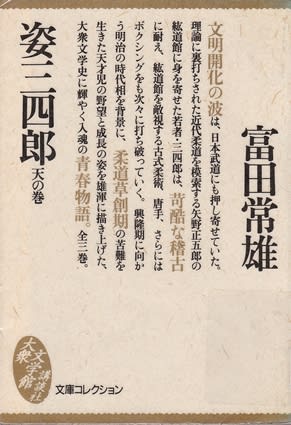
汗もかかず、息も切らさずに選士控席へ戻ってきた雄次郎に代わって席を立った三四郎の相手は、一度は師と仰ごうとしたあの門馬三郎でした。
きれいに頭が禿げ上がり、赭顔<あからがお>の大男である門馬の形相は、まるで悪鬼のようでした。
門馬は礼もせず、仁王立ちのまま言い放ちます。
「来い!冷やかし入門の見せしめに、稽古をつけてやる」
試合がスタートし、組み合うや否や、門馬は三四郎の襟を深く取って、右手で稽古着の前を鷲づかみすると、ダッ、ダッ、ダと床を鳴らして右へ右へと三四郎を引きずり回しました。いささかも逆らうことなく、引かれるに任せて足を運ぶ三四郎、押さば引け、引かば押せという、柔道本然の心のままの動きでした。
いくら力任せに引きずり回しても、抵抗せずに一歩先に移動してしまうので、門馬は三四郎の体勢を崩すことができません。逆にこちらがバランスを崩して危機に陥ることになります。
そのことに気づいた門馬は、一息入れると、両手を三四郎の袖深く差し込んできました。深く組みさえすれば、体力で上回る自分の技は、充分に効力を発揮するだろうと考えたのです。それを嫌うかのように、一歩飛び下る三四郎を追って、門馬が袖を深く取り、腰投げにいこうとしました。すると、嫌っていたはずの三四郎が、予想に反して自分の方から門馬の両袖を深く取ってきたではありませんか!
次の瞬間、三四郎は身体を真後ろへ捨て、左足を門馬の後股にかけていました。門馬は三四郎の上を越えて、毬のように飛んでいきます。崩れてはいましたが、隅返<すみがえし>の体勢でした。
門馬が飛んだ先には道場の羽目板がありました。ガンという響きを立てて激突した門馬は、羽目板から1間(約182cm)手前にうつ伏せに倒れたまま動かなくなりました。
門弟や同門の柔術家たちに担がれて、奥の座敷へと運ばれていった門馬三郎は、意識不明の重体に陥っていました。
医者によれば、打ち所が悪かったというよりも、長年にわたる大酒が原因の卒中だということでした。
自分のせいではないといくらかホッとした三四郎でしたが、門馬を見舞った彼は、そんな安堵の気持を吹き飛ばされてしまいます。門馬の娘が、父親の枕許からきっと彼を睨みつけるのを見たのです。
「人殺し!」
粗野な早口でそう言った彼女の眼は、憎悪に激しく燃えていました。身も心も凍らせるその悪意に満ちた眼は、三四郎に他流と覇を競っていくということが、単に武術家同士の生死を賭けた闘いを越えて、周囲の人間の幸不幸をも左右する苛酷で非情な修羅の道なのだということを、まざまざと思い知らせました。
姿三四郎の長く険しい道のりの幕開けとなったこの他流試合デビュー戦ですが、元ネタとなったと思われる勝負が、実際に行われています。
ただし、そこには三四郎のモデルである西郷四郎は登場せず、試合をするのは戸田雄次郎のモデルで小説『姿三四郎』の著者富田常雄の実父でもある富田常次郎のみです。
そして対戦する相手は、心明活殺流ではなく、良移心当流の中村半助でした。
そう、古流柔術の命運を賭けて、三四郎と警視庁武術大会で激闘を演じ、彼に想いを寄せる乙美の養父である村井半助のモデルとなった人物です。
【参考文献】
原康史著『実録 柔道三国志』東京スポーツ新聞社、1975年
富田常雄著『姿三四郎 天の巻』講談社、1996年。同『姿三四郎 (上)』新潮社、1973年
山田實著『yawara 知られざる日本柔術の世界』BABジャパン出版局、1997年
矢野正五郎の門下となって1年半が過ぎた頃、紘道館ではもはや右に出る者がないまでに強くなった三四郎の身の上に、ある事件が起きます。
その日、行きつけのそば屋長寿庵で、いつものように内儀のお幸と他愛のない話をしていた三四郎に、彼女が突然言い寄ってきたのです。
彼はまだ20歳と若い上に、なかなかのイケメンでした。整った顔立ちのうちには澄んだ眼が輝き、唇紅く、濃い眉とつやのある髪が大きな魅力となっていました。後家とはいえ、40に手の届かぬ熟女のお幸は、純心な三四郎に酒を飲ませて誘惑しようとします。ところが、その濡れ場に現れた、1人の遊び人風の男がありました。
男の名は仙吉、偶然にも彼は、門馬たちが矢野正五郎を襲撃した際に、学習院講師の集まりから帰る正五郎を見張っていて、門馬に知らせる役割を果たした人物でした。
お幸の情夫気取りの仙吉にとって、自分の女に手を出した(もちろん、誤解ですが)上に、門馬道場を後ろ足で砂をかけるようにして出て行った三四郎は、無事に帰すわけにはいかない許されざる相手です。腕に自信があり、血気盛んな若者である三四郎は、仙吉に売られた喧嘩をつい買ってしまいます。
仙吉とその子分は合わせて4人。三四郎は匕首<あいくち>や心張棒<しんばりぼう>を手にした遊び人たちをあっさりと片づけます。しかし、戦闘の興奮にすっかり頭に血が上り、駆けつけてきた巡査たちをも投げ飛ばして逮捕されるという大騒動に、事態は発展してしまいました。
幸い、矢野正五郎の文学士と学習院職員という肩書が功を奏し、三四郎は司直の手から逃れることができました。紘道館に戻った三四郎は、破門こそ免れたものの、師範から稽古禁止を言い渡されます。
紘道館と矢野正五郎の顔に泥を塗る大きな過ちではありましたが、この事件は彼におのれの慢心を気づかせ、人間的な成長を促す契機となりました。
そして、長い稽古止めが解かれた時、紘道館はいよいよ柔術諸流との闘いを開始します。警視総監の三島通庸<みちつね>が、警視庁武術大会への参加を要請してきたのです。
それに先立って、海運橋の天神真楊流八谷孫六の道場開きに招待された紘道館は、門馬三郎の心明活殺流と模範試合をすることになりました。
紘道館柔道にとって、公式に行われる初めての他流試合です。
余談ですが、この試合が世間の噂の的になっているさなか、質屋を訪れた三四郎に、番頭がこんなことを言うシーンがあります。
「なんしろ、心明活殺流なんて、名前から文明開化じゃないし、荒っぽい、おっかない柔術だって言うじゃありませんか」
心明活殺流(山田實著『yawara 知られざる日本柔術の世界』によれば、「正しくは殺活心明流」というそうです)は竹内流や天神真楊流、起倒流などのように現在まで伝わってはいませんし、詳しく書かれている資料も見つけられなかったので、実際にどのような柔術だったのかは、残念ながらわかりません。
ただ、その遣い手である門馬(実在)はだいぶ荒っぽい人物だったようで、原康史著『実録 柔道三国志』に「剽悍<ひょうかん>な風貌は豹を思わせる心明活殺流の門馬三郎である。門馬の柔術の殺伐さには定評があった」と書かれており、実戦的強みを持った喧嘩柔術であったとしています。
 昭和48年に刊行された新潮文庫版『姿三四郎』
昭和48年に刊行された新潮文庫版『姿三四郎』「御高弟二名、御差遣<ごさけん>下されたく候」
との招待状に、選ばれたのは矢野門下中最古参の戸田雄次郎と、実力No.1の姿三四郎でした。
道場開き当日、少年たちの紅白試合がすみ、堤宝山流の古風な鎧組打の形や、道場主自身による天神真楊流の当身の形が披露された後、いよいよ紘道館柔道対心明活殺流柔術、因縁の対決が始まりました。
まずは雄次郎が、活殺流免許皆伝の八田千吉を迎え討ちます。
試合は一方的なものとなりました。万世橋で師匠の矢野正五郎に苦杯をなめさせられた八田は、組み合わずに相手の足を掬い、すぐ寝技に入って絞め、逆を取る稽古に専念してきましたが、自然体で無造作に向ってくる雄次郎の動きに、まったく隙を見出すことができませんでした。逆に一瞬の隙をつかれて襟と袖をつかまれ、鋭い小内刈で何度も尻もちをつかされたあげく、反撃せんと押しに出たところを雄次郎得意の巴投げで3間(約5m)も距離のあった活殺流陣営の席まで吹っ飛ばされてしまいました。
その後は、組んではまた投げられると、両手を前に突き出して、道場中を後ずさりして駆け回るという醜態をさらし、見かねた検証役の八谷の「それまでっ、それまで」という叫び声に救われたのでした。
平成8年に刊行された講談社文庫版『姿三四郎』
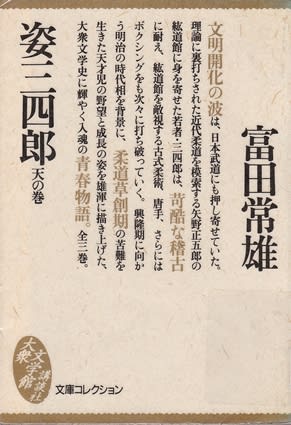
汗もかかず、息も切らさずに選士控席へ戻ってきた雄次郎に代わって席を立った三四郎の相手は、一度は師と仰ごうとしたあの門馬三郎でした。
きれいに頭が禿げ上がり、赭顔<あからがお>の大男である門馬の形相は、まるで悪鬼のようでした。
門馬は礼もせず、仁王立ちのまま言い放ちます。
「来い!冷やかし入門の見せしめに、稽古をつけてやる」
試合がスタートし、組み合うや否や、門馬は三四郎の襟を深く取って、右手で稽古着の前を鷲づかみすると、ダッ、ダッ、ダと床を鳴らして右へ右へと三四郎を引きずり回しました。いささかも逆らうことなく、引かれるに任せて足を運ぶ三四郎、押さば引け、引かば押せという、柔道本然の心のままの動きでした。
いくら力任せに引きずり回しても、抵抗せずに一歩先に移動してしまうので、門馬は三四郎の体勢を崩すことができません。逆にこちらがバランスを崩して危機に陥ることになります。
そのことに気づいた門馬は、一息入れると、両手を三四郎の袖深く差し込んできました。深く組みさえすれば、体力で上回る自分の技は、充分に効力を発揮するだろうと考えたのです。それを嫌うかのように、一歩飛び下る三四郎を追って、門馬が袖を深く取り、腰投げにいこうとしました。すると、嫌っていたはずの三四郎が、予想に反して自分の方から門馬の両袖を深く取ってきたではありませんか!
次の瞬間、三四郎は身体を真後ろへ捨て、左足を門馬の後股にかけていました。門馬は三四郎の上を越えて、毬のように飛んでいきます。崩れてはいましたが、隅返<すみがえし>の体勢でした。
門馬が飛んだ先には道場の羽目板がありました。ガンという響きを立てて激突した門馬は、羽目板から1間(約182cm)手前にうつ伏せに倒れたまま動かなくなりました。
門弟や同門の柔術家たちに担がれて、奥の座敷へと運ばれていった門馬三郎は、意識不明の重体に陥っていました。
医者によれば、打ち所が悪かったというよりも、長年にわたる大酒が原因の卒中だということでした。
自分のせいではないといくらかホッとした三四郎でしたが、門馬を見舞った彼は、そんな安堵の気持を吹き飛ばされてしまいます。門馬の娘が、父親の枕許からきっと彼を睨みつけるのを見たのです。
「人殺し!」
粗野な早口でそう言った彼女の眼は、憎悪に激しく燃えていました。身も心も凍らせるその悪意に満ちた眼は、三四郎に他流と覇を競っていくということが、単に武術家同士の生死を賭けた闘いを越えて、周囲の人間の幸不幸をも左右する苛酷で非情な修羅の道なのだということを、まざまざと思い知らせました。
姿三四郎の長く険しい道のりの幕開けとなったこの他流試合デビュー戦ですが、元ネタとなったと思われる勝負が、実際に行われています。
ただし、そこには三四郎のモデルである西郷四郎は登場せず、試合をするのは戸田雄次郎のモデルで小説『姿三四郎』の著者富田常雄の実父でもある富田常次郎のみです。
そして対戦する相手は、心明活殺流ではなく、良移心当流の中村半助でした。
そう、古流柔術の命運を賭けて、三四郎と警視庁武術大会で激闘を演じ、彼に想いを寄せる乙美の養父である村井半助のモデルとなった人物です。
【参考文献】
原康史著『実録 柔道三国志』東京スポーツ新聞社、1975年
富田常雄著『姿三四郎 天の巻』講談社、1996年。同『姿三四郎 (上)』新潮社、1973年
山田實著『yawara 知られざる日本柔術の世界』BABジャパン出版局、1997年












