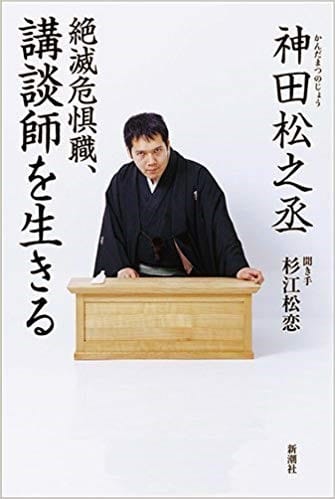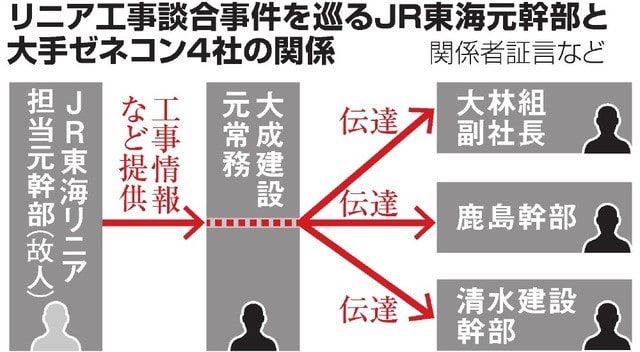源平男性史 第一部
インドのアッサム地方のナガ族は、今でも日本人にそっくりだといわれるが、国が広大のせいなのか、ギリシャ侵入時代に混血したせいで、 カシミール高原など北方民族は鼻が高く二段鼻も多く、目が深い彫りの整った容貌である。 「リスレー分類法」によれば、インド民族は、「トルコ・イラン型」「インド・アーリヤ型」「スキト・ドラヴィタ型」「アーリョ・ドラヴィタ型」「モンゴロイドラヴィタ型」「モンゴロイド型」「ドラヴィタ型」の七つに分けられるが、1931年のグハ分類法は、南インドのチェンチュ、クルンバ、マラヤ、イエルバ族のような、 オーストラリア土人型の、縮毛暗褐色肌のプロト・オーストラロイド型に更に七種を、人類学的見地からこれに加えている。 従って用いられている言語も、世界中インドほど種類の多い国はなく、欧亜系三十種以上に土語二百余種類が今も使われている。 もちろん1947年の独立以来は、インド連邦はヒンズウー語。パキスタンはウルドゥ語が、公用語となってこれで教育され、新聞や放送もそれを使っている。
しかし南インドの土語であるサンターリー語や、ムンダー語、テルグ語では、男性自身はmaraと共通されていて、日本でも、昔の豪い人は、自分自身のことを、「mara」と自称し、これが、「柿本人麿」とか「和気の清麻呂」といった具合に、男である処の人名となり、文字ではmaroと転化し、やがて子供、つまり男童に限って、 「石童丸」とか「牛若丸」となって、丸の字をあてるのは何んであろうかとなる……。
日本男性史はここから始めねばならない。 きわめて卑近すぎて憚りもあるが、現在にあっても女性自身の原語によって、その出身地が判り得るのとそれは同じことなのである。 インドの古代宗教は、日本では「梵天」として伝わっているブラフマン。それにヴイシュヌ、シヴァの三神をそれぞれ、「世界の創造神、維持神、破壊神」とし、 三神一体となしているが、今のヒンズウー教では、ヴィシュヌ信仰がその主となっている。 しかしシヴア信心では、「世界の創造、破壊すべて神の恩寵をうけるシャクティ(女性)」とされるから、この派のヨーガ(瑜伽)信仰では、男女交合の歓喜天を祭り、エクスタシーのことを、ヨーガともいう。つまり、そうした行為を、「ヨガリ」とか「ヨガリの声をあげる」というのも、語呂合せでない。『和訓架』にもちゃんとでている。
「ねもころに奥をなかねそ(先のことまで取り越し苦労しても始まらん)まさかし(現実的に)よがば(良ければよいではないか)」 と『万葉集』三四一〇番の古歌にもあるごとく、その、 「よが」は上古の日本で東国の方言となり、これが後になると濁点がとれ、西国でも、「よかばい」「よかばってん」など用いられるようになる。 処が、今では「よがる」といえば、「気持良がる」などと満足する時の表現にするが、「る(留)」は昔は否定詞だから、反対になって、「夜離る」か「よがる」のことで、これは自動下二段活用となり、(男女の交渉の切れたこと)を意味するようになり、「よがれむ床の形見ともせよ」と『後拾遺和歌集(一〇八六年に藤原通俊撰の勅選集)』に出てきたり、 「『源氏物語』の明石の巻」にも、何もせず語り明したと、「よがることなく語らいにくれ給う」などともなる。
さて、この信仰は日本では、「歓喜天」とか「歓喜仏」の名で、男女和合の信仰として伝わり、松平定信か老中になったとき、和合を豊作にたとえたのだが、 米作の良からんことを願って、「天明八年正月二日、松平越中守一命はもとより、わが妻子の命をもかけまするゆえ」と、本所吉祥院歓喜天へ祈願文をあげたごとく、日本ではひろく信心されていた。
さて前述したが、今でもインドのカダル族やプラヤン族といった成人の身長平均一メートル余の倭小民族は、 (人並みに背の高がらんこと)を望むのか、シャクティとよぶ彼らの万能の女神に対し、その好まれると思える男性の象徴を切断し、恭々しく供える儀式が、 ペラマビクラン峡谷などでは、今も行なわれているが、やたらにそこを切断しては、どんな男でも死んでしまう。
だから死人のものを、もいで来て供物にするというが、カダル族などでは石又は木で、その模型を作って供えたり、又はシャクティを祀った祠への道案内に立てている。 しかし日本では、陽物を祀ったりするのは淫祠扱いされているので、そうした記録や文献は見当らず、松平定信のごとく、「男女和合=五殻豊穣」といった結びつけをして、 そうした陰陽を祀るところは、みな豊作を祈る農民の単純な願望の現れとするか、(雄しべと雌しべ)(花粉がっいて実る)といった理科知識が当時からあっての事とは、どうも信じられない気がする。また、話は違うが、「マロ」と自称するのは、お公卿さんであるが、彼らの、かっての盛装というのは、「置眉」といって、眉の上に黒丸をつけたものだが、カダル族は今でも身分の高い酋長一家は、額に黒丸をつける風俗かある。
ヒンズゥー教では婦人が赤い丸を額に、ぽつんとつける風習があるから、インドでは珍しくもないが、カルカッタの街角で、小男が額に黒丸を二つ付けているのに出逢った時は、 さすかにぎょっとさせられ、はっとして、 「……牛若丸」と思わず口走ってしまった記憶がある。だから、マラから転じたマロが、日本でも高貴な公家のシンボルのように扱われる風習があったればこそ、
「男性自身」のことを、仏家の筆を弄ぶの徒、つまり坊主たちが、それに、「魔羅」の文字をあて、色欲の戒めに用いたのが、やがて一般に広まったものであろう。 というのも、他の国では原住民とか土着民の類は、進攻勢力によって根絶しにされるか、さもなくば脱走して逃亡するものだが、なにしろ日本列島は四方が海である。 だから逃げたくても、一人一人でばらばらには遁れようもない。そこで、やむなく縮こまって雑居して居る内に、体制側の豪い男は、 「マロが」とか「マラが」といっているので、自分らも同じ男ではないかというので、それを真似して用いだしたものであろうか。ペルシャ語でマラガは上陸の意だが……
男を売る平家 平家は美男美女揃いだった
さて、源義経の実存は、反っ歯で見苦しい小男だったというが、平家の方は清盛を始め、みな美男子揃いだったらしい。 なにしろ平敦盛のごとく他に比類ない美少年も居たことゆえ、怪しむにはたらぬかも知れぬが、どれもこれもが粒揃いだっというのは何故だったのだろうか。 安徳帝をうみ奉った徳子こと建礼門院が、絶世の美女だったという点からしても、その父清盛が美丈夫だったことは裏書きできる。 なにしろ清盛の母の泰子は、多勢の御所の女人の中から特に選ばれて、至上の寵をえていたというゆえ、その美貌の遺伝かも知れないが 他の平家の所謂、御一門、つまり、「平の記号をもった他の面々」がやはりみな美しかったことの謎は何だろうか。
これまで説明してきたように、彼らの出身がシュメール地方のスメラからペルャこ湾へかけてとなると、そこはアレキサンダー大王以来しばしば白人の侵略をうけている。 そして平の忠盛が日本史に現れてくる頃たるや、向こうは、「十字軍」がヨーロッパで編成され、その騎士団が何回もくり返しては、攻めこんできていた頃に当るのである。
そうした白人たちが大挙して侵入してくるという事は、現地におびただしい混血児が産れる結果をもたらす。 だから平の忠盛やその家臣の平の家貞あたりも、ヨーロ系の白皙の皮膚をもった男達だったかも知れない。 そして彼らや平の姓をもつその連中が、御所で非常に人気を得たというのも、禁中に仕える女官たちの関心をひいたが故のこととも想える。 というのは時代は下がるか織田信長が、その頃当代無比とよばれた美少年で、「男郎花(おとこえし)」の異名さえあった万見仙千代を、摂津伊丹城主荒木村重より取りあげ、これ見よがしに御所へ伴させたところ、その美しさに幻惑された命婦や女嬬があられもなく、黄色い喚声をはりあげて追いかけ廻した話さえある位だから、その当時にあっても、 「まあ眉目うるわしの殿御ではないか……」と、面喰いの女官達に騷がれ持てはやされ、その人気によって御所内に勢力をはり得だのではなかろうか。
これは後世の江戸時代の千代田城でも同様で、大奥の女中たちの人気がなくては立身出世もできかねたというから、御所でもやはり同じだったものとみてよかろう。
平清盛は美男子だった 平家の公達も美男が多かった
また、昔の教科書などには、 「常盤御前雪中の図」なる絵がでていたものである。 後に義経になる牛若丸や今若丸、乙若ら三人の子を抱えた常盤か、子供らを庇うために雪の中を逃避行したが、やがて三人の子を助けて貰うために、清盛に操を許して命乞いをするという、 崇高な母性愛の教訓だった。 しかし学校でそう教わったときには、まだ子供だったゆえ操を棄てる常盤に同情し感激し、もしもの時には自分の母親もそうであって欲しいと、私などは心の中では願望したものだが、 大人になってから考えると、どうも話が違うようである。あれは三人も子を産んだ三十近い常盤の方で、清盛の美男ぶりに憬れたのと、 生活の安定を求めるため、三人の子を手土産代りに伴って行って、自分の方から売りこみに行ったのではなかろうか。
なにしろ未経験な若い娘ではないし、子供らの父親の源義朝は死んでいるのだし、「……操を破る」というのは大げさすぎはしまいかと想う。 それから清盛は、平の基盛を初め出身がまったく不明な男を、次々とみな自分の養子扱いをしている。普通こうした場合は、 (その親に義理があるから引取って養育する)といった形式を考えやすいが、清盛は何故か子供でない既に成人した一人前の青年を、次々と養子にしているのである。 もちろん清盛には、重盛、重衡らの男子も多くて普通なら養子の必要などない。 では娘婿にするためかといえば、一人娘の徳子には高倉帝という尊い御方があって、のちの安徳帝まですでに産れていた。 つまり養子などすることはないのに、次々と養子にして御一門の内に加えているが、これは何故であろうか?
また、これも判りきったことだが、清盛が平のグループでは総帥であり、仁安二年からは位は人臣の最高の位をしめる太政大臣にまでなっているのだから、 他の者は彼より身分が低く家来なみだった筈である。となると日本のしきたりとしては、 (娘を嫁にやってしまう際は、身分の下の者へ)という事は有るが、養子をとる場合は、同格か目上から入れることに不文律がある。 なのに清盛のごとく、何処の誰やら素性が一切不明と『平氏系図』にまで明記されて居るようなのを、次々と養子として組み入れてしまうという事は常識的では有り得ないことである。
そして基盛もそうだが、これが今回、養子にしました者でありますと、まるで芸者の御被露目のごとく、御所へ伴ってゆき各局へ挨拶廻りに歩かせると、すぐ御座敷が掛るがごとくに、 それらの者は適当に何らかの名目がつけられて、従五位下にすぐ任官。それから次々とお覚えめでたく立身というコースを辿っている。従来の解釈は、 (清盛の勢力によって出世させられたもの)とするが、それだけで済まされるものだろうか。
京の太秦寺は、昔は景教をひろめるために建立されたのか、「波斯寺(ペルシャ)」の別名があったというが、そこの宝物の中に『密宗編義』といった短歌みたいなのがあったと、 寛文年間の『京雀』には出ている。 しかし、どんな内容かは紹介されていないので不明である。だが西歴934年から1055年まで、セルジュクトルコに占領されるまで栄えていたペルシャのブジード王朝の法典は、 「kita」つまり「キテ」とよばれる五七五調で、古代ペルシャ時代からの短歌形式による詩みたいな具合のものであるが、その中に、
「美女をもて王にすすめて官につく。われは美男を王妃に献ぜん」といった立身の要領をとく詠草があって、 これは宮廷詩人ナスル(914-943)の作だと伝わっている。つまりペルシャ宮廷では王のハレムへ美女をおくりこむのと同様に、宮中の貴婦人へ美男を贈る風習もあったものらしい。
『メアリースチュアート』をかいた作者も、その中ではっきりと、当時の英国女王エリザべス一世にやはり美男が献上され、女王がペチコート姿で夜になると次々と廻って歩くことを書いているが、 欲望も本能だから向うでは女性とて当り前だったらしい。
日本の男性史の追求
さて、日本男性史において特筆したいのは、その伝を清盛は自分もやったのではないか、いうことである。 つまり若い時には自分が御所の中の有力な婦人の気嫌をとり結び、やがて年をとってそれが厄介になってくると、己れのピンチヒッターに眉目よき青年を養子ということにして、 身代りに立てていたのではないかと考えられる。 といってこれは突飛な発想でもなんでもない。『大奥の生活』などの本をみれば、「お部屋さま」とよばれた側室は三十歳になると、「御床ご遠慮」の制度で、 自前の部屋子である若くて綺麗な女中を、身代りに出していたとあるから、清盛の時代であっても、彼が御床ご遠慮した後は基盛らを身代りに差出して、宮中の貴婦人の寵をうけさせていたとしても、 それは変でもなんでもない。 孝謙女帝の御代に、弓削道鏡が御床御用の奉仕をしたとする例はあるが、きわめて能率的に身代りを稼動させて効率をあげていたのは、平氏をおいては他にはないかも知れない。 つまり、「男を売る」というのは、これから起きた言葉ではあるまいか。まあ念のために遡って日本の男性の歴史を追及してみることにする。
万葉の時代の男たち
「几有者左毛右毛将為乎恐跡 振痛袖可忍而有香聞」というのが、『万葉集』の中に入って居る天平二年(730)太宰師大伴氏に、児島という女性が贈った歌とされて居る。 漢字の羅列だから鹿爪らしいが、判りやすく音よみにすると、最初は枕言葉で、 「オホナラバ、カモカモセンヲカシコミト、フリタキソデヲ、シノビテアルカモ」と今はこれを読み、その意味もきわめてくだけて、
「九州の大宰府へ防人として行かっせるというで、腰の軍力に縋りっき連れて行きゃんせ何処までもと訴えたが、連れて行くのは易すけれど、女のせない御用船で、 下関から九州への連絡船に女人は乗れぬと悟された。だから私は振りたい袖さえも、その衝動にかられて泣きだしてしまってはと、貴方の門出に女の涙は禁物と耐えて忍び、 じっと見送って忍んでいるかも」と解釈して居る。しかし戦時中の 『万葉集詳解』にあっては、「晴れて大君に召されたる命はえある朝ぼらけ。妻たる者は雄々しく右毛左毛の額にたれてくるのをかきあげ、きりっと髪を結び鉢巻をしめ、召集のきた夫は、 もはや自分の夫ではなく大君のものであると、謹みかしこみ恐れ、死んで還れと勇ましく、痛い位に日の丸の旗をもつ袖をふって、銃後はたとえ苦しいことがあっても忍んで報国の至誠をつくすから、 安心せよと見送った日本軍国女性のかいがいしくも勇しい歌である」となっていた。
チンチンカモカモの意味
しかし『万葉集』の730年頃に、そこまで軍国主義に徹していたか、どうか疑わしい。 文字通りに訳せば 「およそ誰でもそうだろうが、右毛左毛をすり合せて、チンチンカモカモを、まさになしたいは、これ女性の欲し求めるところ、なのに相手のお前が防人にされ、弓矢をもって出征させられるとは恐しいことだ」というのが、反戦的だが本筋のようで、そして、 「それでは残るこの身はなんとしよう。困ってしまうじやありませんか。ですから行っちや駄目、だめって痛い位に袖を引張って止めたのに、それなのに貴方は、女より仕事だと征ってしまわれた。 残された私としては欲求不満に、栗の木に花の咲く頃、その樹の下で香りをかいで、カモカモのことを忍んで居るしかないのです……」 といった意味あいになってきて、雄々しき軍国女性のイメージより、性の悩みに悶えなき涙する万葉時代の女性の相聞歌になる。
この「右毛左毛」をカモカモとよぶ万葉集九六五の歌にっいては、「右にしたり左にしたり・・・ああしたりこうしたりして、ほしい儘にいろんな事をする」 といったように、『古語辞典』では逃げて居るが、女性の身体で、左右に毛の分かれて生えて居る個所は決って居るから、それは男性の願望を現す語句とされ、『古今集』の序にも、 「今を恋いざらめ、かも」その九〇九では、「誰を、かも、知る人にせむ」と用いられて居る。もちろん知る人というのは、何かを知る人という意味で、名前を知るといったような、 そんな単純浅薄な仲のものではないらしい。だから江戸期の黄表紙でも、
「別ぴんじやねえか、かもって、かもかもしたいじゃありゃあせんか」とか、「しめ切った小部屋で、ちんちんかもかもしてる最中に、とんだ邪魔が入りゃあがって」といった具合に使われてきて居る。 つまり万葉時代にあっては、女性はまだ、後世の道徳家や歴史家がとくような形ではなく、きわめておおらかに性をうたいあげていたものらしい。 だから、その十九年後に孝謙女帝が立たれたもうた後、前にもすこしふれたが、「道鏡のあれが良いとの思召し」という事になっても、別にどういう事もなかったのであろう。 なにしろ、この時代は、インドのシバ神が、まだ羽ぶりをきかせて居て、前にもふれたが、「シャクティ信仰」つまり女尊男卑の世で、「カミさま」は、これ女に限られていた。 子宮に新しい生命を宿し、これを生誕させる能力をもつ女性こそ、森羅万象の生みの親として、あがめられていた時代である。
だから、女である神さまへのお供物は、(お好みになられるもの)つまり、そのものずばりに、男性のそれ自身をという事になった。 しかし八世紀の頃とはいえ、人間の男はミミズではない。ちょん切られたら、また伸びてくる処かそれでは命まで危い。死んでしまう恐れもある。もちろんシャクティ信仰では、「己れの一物を、パイプカットして捧げた男は来世において、極楽に生れ変り、より仕合せになれる」ことにはなって居るが、日本人の男は、
今も昔も現実的だから、「死んでから天女とコイッスできるより、現世で女房となんして居る方が増しである」と、イミテーションに、 そっくりな形をした石を見つけてきたり、木を削って同形の物を作って納めた。しかし、一つの女神にモデルとはいえ沢山の物を集めると、千成瓢箪のようになってしまう。
そこで日本では、「女神を祀った祠へ参拝する人の為の道標」つまり今日の交通標識のように使われだした。 だから現在の円盤の中の、ウナギのような標識矢印の線が、よく視るとそれに似通っているのも、そのせいかも知れない。 つまり、今でも田舎へゆくと、「道祖神」というのが残って居るが、あれがその名残りである。後には、歓喜天信仰の影響で、女性のものに似た自然石や木を共に祀って、 五穀豊穣の守り本尊にして居る処もあるが、これもインド宗教である。しかし七八一年に政変があって、百済大高野新笠の生み奉った桓武帝が即位される迄の日本はどうも、 「女上位」そのものの世の中で、要領よく代物弁済の形で、似た石や自然木を見つけてきて奉納せぬ限り、つかみ出され、ちょん切られた男は多かったらしい。
「埴輪」といって人形や馬の形が粘土でこしらえられて居る物の中に、男のそこが欠除して居るものが発見されるのを、考古学者は、「破損」という見方をしているが、 あれは、「ちょん切られ」の実相を示し、初めからへし折って埋められて居るのである。 平城京つまり奈良時代にあっても、そうした遺物は多く、奈良県国立文化財研究所の、「平城宮跡発掘調査会」の保管して居る中にも、そうした部分切断土偶が混って居る。 また、その部分を拡大したモデルなみの、「男茎形(おはせがた)」の実物も奈良朝の遺品にある。
隔全長十八・三センチ、直茎三センチ、亀頭部尖端尿道口からニセンチ下に第一条溝、一センチの間をおいて第二条溝、十五センチ離れた個所に幅広い刻み目を入れ、 二つに分けホーデンを形どって居る極めて、シリアスな物で、もしこれが当時の実物大であるなら、「青丹よし奈良の都」の男の持物は、相当のものだったらしい。
また女上位であった天平時代なのに、やはり男に不自由した女人も居たのか、「木製円筒尖端の亀頭の下に、やはり二条の溝がつけてあり、下端に指を挾み動かす用にか、 きびす掛けと袮する紐で足にくくりっける為にか、二又に分かれて出来て居るもの」といった柔かい布でも冠せれば今でも使用できそうな張形が、平城宮の遺跡からは発掘され、 大切に保管されて居る。つまり奈良の都の女官たちは、「男とは、あれが付いて居ればこそ、よいものでござりまするな」と、他に愉しみもない時代ゆえ、 もっぱらそれのみにふけり、時には、「切りますわよ」と本当に切断したり、後になって、それが朽ちてゆくのを惜しんで、木で同じ形をこしらえ、「昔を今になすよしもがな」と自慰的使用をしていたのかも知れぬ。おおらかと云えば云えるが、男の立場ではあまり嬉しい世でもなかったろう。
玉葉の時代
九世紀に入って書かれたという、 『古語拾遺』に、大地主神が、田を耕して居る者をねぎらって、牛を殺し食させた。すると御歳神がこれをきいていたく怒り、 「牛は聖なるものである。これを殺し、あまつさえその肉を食させるとはなんたる事か」と蝗の大群を空から呼び集めて、 「呪われてあれ」とそれに命じたから、蝗の大群は、すぐさま田をおおい一粒の米も残さず、みな食いつぶしてしまったという。 ここまでの神話はインドにも、まったく同じものが今も伝承されて居る。
がさて、日本のにはこの後があって、白猪、白馬、白鶏を屠り、牛の霊を葬って謝罪した上大地主神は、女神であられる御歳神の御気賺を直して貰うために、 男茎形を作って、これを田の溝の口においたところ、その尖端から慈雨が射精され、枯れた田は蘇って、豊かに実り直しをしたというのである。インドよりポルノ的傾向か甚しい。
つまり今でも母体のことを田とか畑といい、「おれの種はよいんだが、畑が悪いから、うちの子供の出来か悪い」などと、用いられる起りは此処から始るらしいが、 「御歳神=女神=田畑」といった農本思想は後になっても、 「神祇官」によって守り伝えられ、「祈年祭」の式典には、白猪、白馬、白鶏の肉を供える慣習となって、これが二十世紀の今も残って居る。 さて、「白」というと、清潔とか純粋さを象すように思い勝ちだが、それは現在のテレビの洗剤CMの見過ぎによる影響で、奈良や京にあってはカラ系の神社は別だが朝廷では、 白は忌まれるものであって、御所の最下層の雑役夫のことを、「白丁」とよぶのも、このせいであり、平安遷都後百七十年たった源平合戦においても、 「白旗をもつ木曾義仲」を後鳥羽帝が忌み給い、赤旗党の平氏の方に好意的であらせられたのも、事によったら、理由はこれであるのかも知れない。
もちろん、夷をもって夷を制する御所の方針で、義仲は、同じ白旗党の頼朝に討たせたが、頼朝もそこはよく知って居たから、「また夷をもって夷の政策をとられては、叶わん」というので、 義経や伯父の行家が、公家に結びっくのを警戒し恐れたのである。 処が、その方は防ぎ切れたが、頼朝は、「女の怖しさ」を、うかっにも知らなかったらしい。まだ八世紀までの女上位の風潮が、十二世紀のその頃にも残っていたであろうから、薄々はそれを弁えて居たかも知れぬ。と書くと、尤もらしいが、恐らくまだそうではなかったろう。 藤原氏や平氏の方では男尊女卑だったから、見下す立場をとって舞を舞わせる女には白い水干を着せたりしていた、これは兼好法師の、『徒然草』にも、 「道憲入道舞の手の中に興ある事ども選び、磯の禅師といいける女に押しへてまはせけり。白き水干にそう巻をささせ、白烏帽子をひき入れたりければ・・・」 とあるように、これを「白拍子」などと、わざわざ差別して白付けで呼んで居たりしていた。 処が原住系のミナモト族というのは、八世紀以前から日本列島に住っていた、かっての、俘囚の裔だから、これはどうしてもその反対で、「女尊系」であった。
だからしてこの結果が、「源頼朝」にしても、左馬佐であって、「佐(すけ)どの」と政子にもいわれて居るのである。 今日では、スケというとスケベといった発想をしがちだが、この佐はそうではなく、「次長」又は「次官」、補佐の佐なのである。 だから、それでは、 「頼朝は、誰のセカンドで、カマクラ政府のチーフは本当は何者だったのか」の疑念も起きる。 また『吾妻鏡』というのを、あずまと読んで、『東鑑』の文字もあて、関東のことと今では解するが、素直に文字にこだわれば、 「マイ・ワイフ」の意であり、それでは正式に頼朝にとっての妻は誰だったかと云うことになろうというものである。 また、この時代の長寛二年(一一六四)から、正治二年(一二〇〇)まで丹念につけた九条兼実の日記のことを、 『玉葉』又は『玉海』ともよぶが、これは、『語遺義解』によれば、「玉門の左右をおおうを玉葉という」また、「玉門の内が大きい場合をさす」とある。
といって、玉門がエメラルドやルビーのアーチでないことは、読まれる向きには知識かあるであろう。ということは、九条兼実が日記をつけて居た十二世紀後半たるや、 「玉門を覆う葉のごときもの」とか、「玉門の奥が海のように広く、水分また多く湿っていた状態」が、その日記の別名になった事実から推量してみて、相当な女権時代だったことが計り知れる。 すると、その玉葉をもち、偉大なる玉海を身体の奥深くに、有していた女人は誰なのかといえば……それは頼朝をして、「吾妻」とよばせた相手だったことになる。 如何に彼女の玉葉や玉海が問題にされていたかは……その人の名を、今ではMASAKOと読むから判らなくなって居るが、その当時から十六世紀まで、 「大政所」とか「北政所」といわれた秀吉の母や、ねねにしても、決して、MASADOKOROとは呼ばれていない。
だから、頼朝の妻だった女人も、なんと呼ばれていたか判るだろうし、猫は、「タマ」といっても、人間の女ならば、 「おたま」とよぶことを考えれば、彼女も、「お」をその名の上につけて云われて居だろうことも判るし、それゆえ二十一世紀の現在に到るも、玉葉、玉海、玉門に代る普遍的女性名詞に、 それが、彼女の名がずばり用いられて居る周知の事実からも、(ペルシャにはスーサの並びに、それにそっくりな地名がある)「阿魔将軍」と呼ばれた彼女の権勢は判るというものである。 もちろん江戸時代元禄期以降の、儒教輸入による男尊女卑をもって、これが昔からと誤っている歴史屋や、その書くものを下敷にする人の手に掛っては、「阿魔」も「尼将軍」と可愛らしくなるが、彼女の生れ育った伊豆伊藤(現在は伊東)は、諏訪神社文書によって判るような特殊地域なのである。
シャクティ信仰を飽く迄も久しく、もちこたえてきた古い土着民の隔離別所だったから、女が強かったのも当り前のことで、まあ頼朝は、 菜摘御前を初め他の側室は彼女に斬殺されたが、自分のそこを 切られなかったのが、せめてもの慰めだったのであろう。
しかし頼朝も、己れの一物は難を免れたものの、せっかくの血統は、もろに彼女によって絶たれてしまった。 なにしろ源頼朝の妻なのに、堂々と「平政子」と名のるような女だったから、頼朝の血筋はもとより、「梶原景時」「畠山重忠」「和田義盛」「三浦義村」といった源氏家臣団まで、 根こそぎにみな殺掠してしまい、騎馬民族系である崇神王朝系の北方種族を、せっかく朝鮮語で、「カマクラ(屯、つまりタウンのこと)」と名をづけた土地から一掃してしまった。
だから、ようやく命拾いした者も、北条体制の追捕をうけて住む所もなく、かって七世紀から八世紀に設けられた捕虜収容所、つまり橋も掛っていない川の向うへと逃げこんだ。 どうも今の歴史では、源も北条も同一視してしまって居るが、大陸系ツングース種の源氏を滅して、政子がその親兄弟に、インド系に近い西南アジア土着民の国家体制をとらせたからこそ、 北条時宗の代になって、蒙古や朝鮮から攻めこまれたのである。 頼朝の時には、高麗とも、南宋とも行ききがあって、相互不可侵条約のようなものが結ばれていた史実があったが、北条氏になると、 「頼朝らの先祖は向うが、マザーランドだったろうが、われらは違うのである」と放っておいた。 だから元のフビライが、「怪しからん」と高麗の播阜(はんぷう)を嚮導役として、1268年正月に、貢物を出せと命じてきたのである。つまりこれが元寇の起りのようである。 神風といわれるモンスーンが吹いてくれたので、日本は助かったものの台風シーズンでなかったら取り返しがっかなかったろう。 つまり政子の玉葉のため、この日本は未曾有の国難にあい、ひとつ間違えば滅亡させられる処だったのだから、女は今も昔も恐いという他はない。