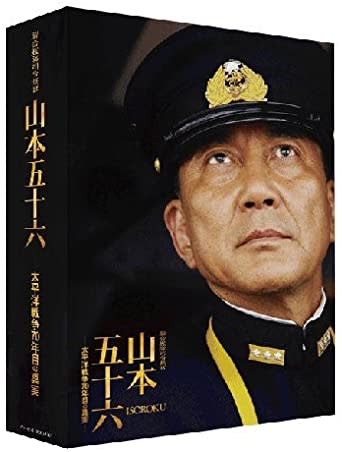日本の悪女とは、誰に対して悪い女かという事がまず命題になる。
男と女はまるで違うのであるから、男にとって思うようにならぬ存在として見れば女で悪女でないのは珍しいくらいのものである。
ではその女自身にとって悪いのが、それでは悪女かと云えば、これまたそうでもないらしい。
何しろ女は良い結果は自分の所為にしたがるが、そうでないのは他のせいにするからである(ここは女性には異論の在るところでしょう)では何だろう?となってしまう。
勿論明快にして簡単な区分法もある。
○消極的に他に気兼ねしながら生きたのが、善女。
○積極的に思いの儘に生きたのが、悪女。
男と女はまるで違うのであるから、男にとって思うようにならぬ存在として見れば女で悪女でないのは珍しいくらいのものである。
ではその女自身にとって悪いのが、それでは悪女かと云えば、これまたそうでもないらしい。
何しろ女は良い結果は自分の所為にしたがるが、そうでないのは他のせいにするからである(ここは女性には異論の在るところでしょう)では何だろう?となってしまう。
勿論明快にして簡単な区分法もある。
○消極的に他に気兼ねしながら生きたのが、善女。
○積極的に思いの儘に生きたのが、悪女。
といったのが、有りふれた解釈なら、
○無名で埋もれてゆき、忘れられるのが善女。
○有名で死後も取り沙汰されるのが悪女。
こうした判別の仕方もあるだろう。
○無名で埋もれてゆき、忘れられるのが善女。
○有名で死後も取り沙汰されるのが悪女。
こうした判別の仕方もあるだろう。
とは言え、後世にその名が残るという事は、「その人が本当に偉大だったとか、素晴らしかった、又は人間的に立派だった」等にはあまり関係はないのである。
死後にもその名が残るのは、その名前が後世の人間の銭儲けのタネになるか、否かの問題である。
死後にもその名が残るのは、その名前が後世の人間の銭儲けのタネになるか、否かの問題である。
例えば明治時代でも、夫をこよなく愛し自己犠牲の限度を超し命までも捧げたような女は数限りなく居たであろう。
しかしそれが、おたねやおまさでは、良くても生前その村役場から「節婦」として表彰された位の処が関の山である。
そして死んでしまえば、最早その役場の記録にさえ残されていない。処が、節婦の代わりに毒婦と冠句の上の一字が違うと、話しは全く違ってくる。
しかしそれが、おたねやおまさでは、良くても生前その村役場から「節婦」として表彰された位の処が関の山である。
そして死んでしまえば、最早その役場の記録にさえ残されていない。処が、節婦の代わりに毒婦と冠句の上の一字が違うと、話しは全く違ってくる。
時移り星変わっても、高橋おでんの名は三歳の子供では無理だろうが、70歳ぐらいな男女ならおよそ知っていよう。
かっては邦枝完二の名で長崎謙二郎がそれを書き、今も一枚一万円位の原稿料でやはりお伝を書き飛ばす小説家や、それを掲載して三十万部売り捌く小説雑誌や、また単行本にして儲ける出版社があるからである。
つまり彼女は今だに堂々と飯の種になる素材であり、いいかえれば利用価値が有るせいだろう。
かっては邦枝完二の名で長崎謙二郎がそれを書き、今も一枚一万円位の原稿料でやはりお伝を書き飛ばす小説家や、それを掲載して三十万部売り捌く小説雑誌や、また単行本にして儲ける出版社があるからである。
つまり彼女は今だに堂々と飯の種になる素材であり、いいかえれば利用価値が有るせいだろう。
といって、彼女が後藤吉蔵と金をとって寝た位のことが、どうというのでもない。
疲れて寝ている処を殺した位の事なら、男の一物を部分的に切断して逃げた阿部定の方がまだはるかに扇情的であるともいえる。
では、何が彼女を毒婦とか悪女といった冠詞の下に有名にしたか、明治大正昭和と時には芝居にまでなって儲けの種になったかと云えば、これは権威の裏づけのせいだろう。
といって、後世のマスコミに寄与した故に、正何位の追贈位を貰ったとか、文化勲章を交付されたのではない。それは何といっても東大の権威によってである。が、何も彼女が名誉卒業生に選ばれたのでもなく、
ただ彼女の肉体の一部が余りにも巨大だったから、それでアルコール漬けとされ東大医学部標本室にあるの、在ったとの噂が広まって、それからして、
疲れて寝ている処を殺した位の事なら、男の一物を部分的に切断して逃げた阿部定の方がまだはるかに扇情的であるともいえる。
では、何が彼女を毒婦とか悪女といった冠詞の下に有名にしたか、明治大正昭和と時には芝居にまでなって儲けの種になったかと云えば、これは権威の裏づけのせいだろう。
といって、後世のマスコミに寄与した故に、正何位の追贈位を貰ったとか、文化勲章を交付されたのではない。それは何といっても東大の権威によってである。が、何も彼女が名誉卒業生に選ばれたのでもなく、
ただ彼女の肉体の一部が余りにも巨大だったから、それでアルコール漬けとされ東大医学部標本室にあるの、在ったとの噂が広まって、それからして、
「そこは伸縮する筋肉だから、巨大だからといって標本にされるのは可笑しい」とか、
「処刑といっても昔は絞首刑だけでなく、河童が尻子玉を抜く如く、女は彼処まで切り取られるものなのか」と、こうした疑問を抱くより、
「東大に見本として残されるぐらいなら、さぞかし名器であったろう。虎は死して皮を残すというが、高橋おでんは皮と肉をアルコール漬けで残した、えらいもんである」といった形而下的な浅薄な評価が普及した結果が、
「処刑といっても昔は絞首刑だけでなく、河童が尻子玉を抜く如く、女は彼処まで切り取られるものなのか」と、こうした疑問を抱くより、
「東大に見本として残されるぐらいなら、さぞかし名器であったろう。虎は死して皮を残すというが、高橋おでんは皮と肉をアルコール漬けで残した、えらいもんである」といった形而下的な浅薄な評価が普及した結果が、
「東京帝国大学責任保証・悪女の鑑」とし、「毒婦高橋おでん」の評判を高め、それゆえ後世の売文業や出版社を潤し、彼らによって流布された小説本によって、ますます人口に膾炙され悪女の見本となったものらしい。
これはおかしな言い方かも知れぬが事実とはつまりそうしたものなのである。
つまり、概念的な悪女は何処にも此処にも居て、男の観察からすれば、女とはどれもこれも悪女でないのは居ないようだが「悪女」としてはっきりそれが公認されるには条件がいるらしい。
つまり、「官許」とでもいうのだろうか、権威による公認か、さもなくば何とはなしに権勢というものが、付き纏っていなくてはならぬようである。
これはおかしな言い方かも知れぬが事実とはつまりそうしたものなのである。
つまり、概念的な悪女は何処にも此処にも居て、男の観察からすれば、女とはどれもこれも悪女でないのは居ないようだが「悪女」としてはっきりそれが公認されるには条件がいるらしい。
つまり、「官許」とでもいうのだろうか、権威による公認か、さもなくば何とはなしに権勢というものが、付き纏っていなくてはならぬようである。
浅茅ケ原で鎌を砥いで旅人を殺し、身ぐるみ剥がして奪ったにしても、何の権力の翳りも無いのではとても悪女の範疇には入れて貰えない。処が、白子屋おくまの場合は、
「奉公人の手代と不義密通をなし、婿を殺害に及びし候段は、稀代の悪女といふ他はなく、引廻しの上獄門仰せつけられ候なり」と、いくら自白させられてしまったとはいえ、はたして真実はどうなのか、
手代が巻き添えにする為、嘘をついたのかもしれぬが、お上のお裁きでこうなってしまえば彼女は天下晴れての、認められた悪女という事にされてしまう。
勿論、これは官許の悪女とはいえ、権力のお仕着せみたいに作られてしまった方だか゜、クレオパトラにしろサロメしろ楊貴妃にしろ、そこに権勢の存在があったから、
彼女らは晴れがましく「悪女の座」を確保することが出来、不死鳥の如くその名を今に伝えて居られるのである。
「奉公人の手代と不義密通をなし、婿を殺害に及びし候段は、稀代の悪女といふ他はなく、引廻しの上獄門仰せつけられ候なり」と、いくら自白させられてしまったとはいえ、はたして真実はどうなのか、
手代が巻き添えにする為、嘘をついたのかもしれぬが、お上のお裁きでこうなってしまえば彼女は天下晴れての、認められた悪女という事にされてしまう。
勿論、これは官許の悪女とはいえ、権力のお仕着せみたいに作られてしまった方だか゜、クレオパトラにしろサロメしろ楊貴妃にしろ、そこに権勢の存在があったから、
彼女らは晴れがましく「悪女の座」を確保することが出来、不死鳥の如くその名を今に伝えて居られるのである。
日本悪女考
今でこそ九州女は情があってよいとされている。しかしそれは、「女は三界に家なし」とか「女は幼は親に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従え」と徳川後期に入っての儒教で押さえつけられた後の話である。
戦国期での九州女は実に凄まじかった。竜造寺の妻、ねこも凄まじい猛女だったが、大友宗麟の母や妻は、男を丸裸にして竹筒をある箇所にはめて折らせて愉しんだとも謂われる程である。
戦国期での九州女は実に凄まじかった。竜造寺の妻、ねこも凄まじい猛女だったが、大友宗麟の母や妻は、男を丸裸にして竹筒をある箇所にはめて折らせて愉しんだとも謂われる程である。
だから大友宗麟の老臣立花道雪の娘げんのごときも、日本最初の鉄砲隊を編成し、「最初(はな)は立花の娘子軍」といわれるくらい、九州の山野に活躍したものである。が、のち年下の立花宗茂を迎え仲睦まじく暮らした、げんは悪女ではなかったらしいが、大友の姑や嫁はめちゃくちゃで直接に裸にされて吊り殺しにされた男は十余名というが、その為に起きた「耳川合戦」で死傷した男女は一万の余にのぼると、ローマ法王庁のイゼズス派の記録にも残されている。
南北朝の頃。九州はあらかた宮側についたのに、豊後の大友親世だけが足利尊氏につき、南朝方の菊池武朝らと戦うこと七十二回。その内七十一回までは負けたが、七十二回目には、世の中が足利氏のものになったので勝つことが出来た。このため「頑張る者こそ最後には勝つ」と、ここで豊前、豊後、筑前、筑後、肥前肥後の六国を領国として貰い受けた大友氏は足利将軍家より「九州探題」の任命さえ受けた。
(注)南朝とは朝鮮高麗系の勢力で河野水軍、土井氏、対馬の宗氏、菊地氏などで、宮方。北朝とは中国明国勢力で足利氏は明の後押しで日本で傀儡政権を作った。従って南北の争いとは、日本における明と高麗の代理戦争だったのがが実態。
その72回目には、世の中は足利氏のものになったので、勝つことが出来た。
だから今日の北九州から熊本までの九州半国を従え、大友氏は栄えに栄えた。さて、宗麟は、初めは大友義鎮といい、その生母は「伏見宮貞常親王」の王女であった。現代の感覚でゆくと、皇族の妃殿下が九州の大名へ御降嫁とは変だが、この後の江戸時代になっても、後水尾帝の女御みぐしの局は後西天皇の御生母だが、局の末妹の貝姫は銀子二十貫で陸奥へ身売りして、伊達政宗が購ってその子忠宗の側室の一人にしたところ、生まれたのが己之助。
その72回目には、世の中は足利氏のものになったので、勝つことが出来た。
だから今日の北九州から熊本までの九州半国を従え、大友氏は栄えに栄えた。さて、宗麟は、初めは大友義鎮といい、その生母は「伏見宮貞常親王」の王女であった。現代の感覚でゆくと、皇族の妃殿下が九州の大名へ御降嫁とは変だが、この後の江戸時代になっても、後水尾帝の女御みぐしの局は後西天皇の御生母だが、局の末妹の貝姫は銀子二十貫で陸奥へ身売りして、伊達政宗が購ってその子忠宗の側室の一人にしたところ、生まれたのが己之助。
のち仙台六十二万石の伊達綱宗となった時。従兄の後西様が人皇百十一代で在世中だったので、秘かに共に討幕を謀り、天皇からは伝奏園池中納言が奥州へ下向。伊達家からは原田甲斐が京へ何度も往復している。つまり、
『樅の木は残った』などの伊達騒動というのは、徳川時代に歪曲され、でっち上げされたものの引き写しにすぎなくて事実ではない。本当は朝廷と伊達藩が組んでの討幕運動だったのである。さて話は戻るが、
『樅の木は残った』などの伊達騒動というのは、徳川時代に歪曲され、でっち上げされたものの引き写しにすぎなくて事実ではない。本当は朝廷と伊達藩が組んでの討幕運動だったのである。さて話は戻るが、
大友宗麟の生母も綱宗の生母と同じように売られてきた身で早世した。そこで父の大友義鑑は次々と妻を新しく取り替えた。
やがてその内に到明が生まれた。父義鑑は若い妻が気に入りなので、長男の宗麟を廃して到明を跡目にしようとした。しかし、もうその頃は足利末期の天文の世である。重臣達は、「宗麟様は二十余歳なのに到明様はまだ幼児である。とても、戦火風雲急な今の時勢にこれでは御家がもたない。」
と、斉藤播磨守や小佐井大和守らの良識派は反対した。しかし戦国時代の女人は、儒教で押さえつけられた江戸時代後期のおとなしい女とは違う。到明の母は、かっかとしてしまい、「我が子の跡目に邪魔立て致すとは、なんと憎っくき奴ではないか」と、すぐさま腹心の家来を差し向けてまんまと瞞して捕らえさせた。
やがてその内に到明が生まれた。父義鑑は若い妻が気に入りなので、長男の宗麟を廃して到明を跡目にしようとした。しかし、もうその頃は足利末期の天文の世である。重臣達は、「宗麟様は二十余歳なのに到明様はまだ幼児である。とても、戦火風雲急な今の時勢にこれでは御家がもたない。」
と、斉藤播磨守や小佐井大和守らの良識派は反対した。しかし戦国時代の女人は、儒教で押さえつけられた江戸時代後期のおとなしい女とは違う。到明の母は、かっかとしてしまい、「我が子の跡目に邪魔立て致すとは、なんと憎っくき奴ではないか」と、すぐさま腹心の家来を差し向けてまんまと瞞して捕らえさせた。
そして二人の老臣を裸にひんむいて、これを松の木に逆さ吊りにした。二人とも首筋を腫らして苦しみ、とうとう血を吐き悶絶した。すると、奥方は、すぐ斉藤と小佐井の上の首と下の首をぶった切らせた後、「この両人に一味して、まだ我が子を跡目に立たたんとするを邪魔をしようとする輩が居よう。片っ端から捕らえて一人残らず首を切ってしまえ」と、判っている人名の中から宿老の、津久見美作守、田口蔵人以下次々と名を呼びあげた。
さて、この名を呼ばれた者の近親や縁者で、奥御殿に仕えていた者もいたから「これは大変だ」と、そこで急ぎ知らせた者が居る。だから津久見や田口らは驚き、「ひとかどの武士を殺すのに、丸裸にむいて吊し殺しとは、いくら女人の浅はかさとはいえあまりに残酷すぎる、座してそのような辱めを受けて殺されるよりは、先んずれば制するというゆえ、反対に片づけてやる」
と、どうせ捕らえられて殺されるのは判っていたから逆襲を計った。そして奥御殿へ斬りこみ、奥方や到明だけでなく、ものはついでと、「えい、毒をくらわば皿までじゃ」と、たまたま泊まっていた大友義鑑までを叩っ斬ってしまった。これが有名な「大友家の二階崩れ」で、天文十九年二月の事とされている。
と、どうせ捕らえられて殺されるのは判っていたから逆襲を計った。そして奥御殿へ斬りこみ、奥方や到明だけでなく、ものはついでと、「えい、毒をくらわば皿までじゃ」と、たまたま泊まっていた大友義鑑までを叩っ斬ってしまった。これが有名な「大友家の二階崩れ」で、天文十九年二月の事とされている。
【バスク人来日】
さて、フランシスコ・ザビエルといえば、通説では、「有難いキリストの御教えを初めて日本へもたらしてくれた聖者」というように評価されて、西欧心酔主義者からおおいに崇拝されている。しかし純血白人主義を標榜して欧州を席巻したナチスが、ザビエルが創めたも同じのイゼズス派の教会を焼き、その師父やシスターまで目の敵にしたのは何故かとなる。
なにしろ日本では当時のイゼズス派も、サンフランシスコ派もごっちゃなので何も判っていない。が、現在のスキーの名所のアンドロ共和国。つまりスペインとフランスの真ん中のバスク地方というのは、古代インドにアンドラ国の地名が歴然とあったごとく、「ヨーロッパの東洋」とか「古代有色人種が逃げ隠れ住んでいた地帯」といった扱いで、まあ日本で言えば全体が落人か、道のない山地といったような特殊地方なのである。
だからヨーロッパで魔女裁判の始まった頃。
だからヨーロッパで魔女裁判の始まった頃。
彼らバスク人は狩り出されて、高慢ちきな女や残忍な女を捕らえては丸裸にむき、車裂きや火炙りにして、教会の御用をうけたまわっていた。
つまりはザビエルにしても、なにも文字や会話も通じぬ東洋へわざわざ乗り込んできたのは、布教という目的ではなかった。
ローマ法王庁にあっては、白人と同じように扱って貰えぬ彼らとしては、箒に跨って東の空へ逃げたとされる魔女達の行方を追って、それを捕らえて功名をたてんとしたのである。それゆえ一五三四年八月十五日にパリのモンマルトの丘で誓いをたてたロヨラら七人のグループが、教皇ポーロ三世によって、僅かな人数なのにイゼズス会戦闘教団として特に許されたのである。
つまりはザビエルにしても、なにも文字や会話も通じぬ東洋へわざわざ乗り込んできたのは、布教という目的ではなかった。
ローマ法王庁にあっては、白人と同じように扱って貰えぬ彼らとしては、箒に跨って東の空へ逃げたとされる魔女達の行方を追って、それを捕らえて功名をたてんとしたのである。それゆえ一五三四年八月十五日にパリのモンマルトの丘で誓いをたてたロヨラら七人のグループが、教皇ポーロ三世によって、僅かな人数なのにイゼズス会戦闘教団として特に許されたのである。
つまり魔女狩り専門の非白人グループ教団だったゆえ、ヒットラーはその弾圧をさせたのである。
さて、このザビエルが日本へ来たのは、天文十八年八月十五日で、初めは鹿児島へ海賊号とよぶジャンクでインドのゴアから到着した。しかし領主島津貴久と巧く行かず、ザビエルは京へ行こうとして豊後の府内を通りかかり、新城主となった大友宗麟と逢った。そして天文二十年九月にもザビエルは山口からの帰りに又面会している。
どうして二人は意気投合したかと言えば、勿論中国人の通訳を入れての話だが、「女人とは表面では優しそうでも、一皮剥けば恐ろしいもので、愚かしき者の中には美女も居るが、賢いと自認している者の殆どは悪女でしかあり得ない」と、ヨーロッパではその当時魔女狩りの最中ゆえ、ザビエルがしきりと力説すればそれに対して「如何にも、如何にも尤もなことである」と大友宗麟もその継母に散々に不快な目にあっていたから、
「女人は外面菩薩で、内面夜叉と申すが、口先だけは優しそうで巧いことをいうてもいざ本性を現すとなると女人ぐらい恐ろしいものはない」と賛成したのだろう。
さて、このザビエルが日本へ来たのは、天文十八年八月十五日で、初めは鹿児島へ海賊号とよぶジャンクでインドのゴアから到着した。しかし領主島津貴久と巧く行かず、ザビエルは京へ行こうとして豊後の府内を通りかかり、新城主となった大友宗麟と逢った。そして天文二十年九月にもザビエルは山口からの帰りに又面会している。
どうして二人は意気投合したかと言えば、勿論中国人の通訳を入れての話だが、「女人とは表面では優しそうでも、一皮剥けば恐ろしいもので、愚かしき者の中には美女も居るが、賢いと自認している者の殆どは悪女でしかあり得ない」と、ヨーロッパではその当時魔女狩りの最中ゆえ、ザビエルがしきりと力説すればそれに対して「如何にも、如何にも尤もなことである」と大友宗麟もその継母に散々に不快な目にあっていたから、
「女人は外面菩薩で、内面夜叉と申すが、口先だけは優しそうで巧いことをいうてもいざ本性を現すとなると女人ぐらい恐ろしいものはない」と賛成したのだろう。
「だったら国中の女の中で、意地の悪いのや可愛げのないのは、片端から捕らえて裸に剥いて丸焼きにしたらよろしい。我らイゼズス派はその方面ではエキスバートゆえ、おまかせ下さい。」と、巧く行けばその中に探し求めるヨーロッパより脱走した魔女が居るかも知れんと思うから、ザビエルはしきりに力説した。
「が、女はとかくうるさいもの、もし焼き殺されると知って、集団で暴動でも起こしたら如何なされますぞ」と宗麟は、大友家代々の家老を二人まで裸で吊し殺した継母やその手伝いをなした侍女共のことを思い出してぞっと身震いした。すると、「大丈夫、そうした暴動には遠くから撃ち払える鉄砲なるものがある」と答えた。「相手が女人では近寄って毒づかれ、その上かじりつかれる心配もあるが、あの鉄砲なるものさえあれば遠くから始末できるからよろしかろう」
と、天文十二年に種ガ島から伝わった鉄砲の評判は知っていたから合点したところ、「宜しい。今はサンプルとして数丁しか持ち合わせていないが、インドのゴアから小銃だけでなく大砲も寄付し、弾丸を飛ばすに欠かせぬ火薬の原料の硝石もつけてお分けしよう」と話は纏まった
【西国盛衰記】
と、天文十二年に種ガ島から伝わった鉄砲の評判は知っていたから合点したところ、「宜しい。今はサンプルとして数丁しか持ち合わせていないが、インドのゴアから小銃だけでなく大砲も寄付し、弾丸を飛ばすに欠かせぬ火薬の原料の硝石もつけてお分けしよう」と話は纏まった
【西国盛衰記】
大友宗麟
平戸の松浦や鹿児島の島津などでは、何とかして火器の方は似せた模倣品が造れたが、肝心な硝石は日本中何処を掘っても産出しない。だから信仰のためでなく硝石欲しさにイゼズス派へ入信した。
今も昔も日本人は資源入手の為には何でもやる国民だった。しかし大友宗麟だけは、継母のお陰で女の怖さが身にしみていたゆえ、直ぐさま本心から「魔女狩り」に協力を誓った。ザビエルはその後直ぐ豊後の大分湾から印度のゴアへ戻り、
マラッカから中国大陸に近い上州島へ行き死んでしまって二度と帰っては来なかった。しかし、
今も昔も日本人は資源入手の為には何でもやる国民だった。しかし大友宗麟だけは、継母のお陰で女の怖さが身にしみていたゆえ、直ぐさま本心から「魔女狩り」に協力を誓った。ザビエルはその後直ぐ豊後の大分湾から印度のゴアへ戻り、
マラッカから中国大陸に近い上州島へ行き死んでしまって二度と帰っては来なかった。しかし、
「ブンゴ王の大友宗麟との密約が出来ている」との遺命によって、東洋を押さえていたイゼズス派はポルトガル船をことごとく豊後へつけさせた。つまり、「豊後の繁栄は以前の十倍にも二十倍にもなった。
何故かと言えば博多や鹿児島、平戸に入港していた南蛮船が一隻残らず大分湾に入るようになったからである。
大友の殿は洗礼を受けていないのにまことに不思議な事である」と『西国盛衰記』に出ているのもこの所為によるらしい。
何故かと言えば博多や鹿児島、平戸に入港していた南蛮船が一隻残らず大分湾に入るようになったからである。
大友の殿は洗礼を受けていないのにまことに不思議な事である」と『西国盛衰記』に出ているのもこの所為によるらしい。
さて宗麟の最初の妻は丹後の一色氏から来ていたのだが、やがて家老の田原家の娘を見染めてしまって、早速これと入れ換えていた。
しかし彼女は、紀元前八七五年からイスラエルの王であったアラブの妻のイザベラの如く、血を見ること水を見るごとしと、領内の気に入らぬ者は女子供でも大の大人でも片っ端から逆さ吊りにして咽喉をかき切って殺してしまった。
だから、その当時の宣教師の書いた記録である「西教史」には、「東洋のイザベラ」と彼女のことを渾名している。
そしてイゼズス派の宣教師は、
「彼女こそ東洋へ逃亡してきた魔女の化身であろう」と考え、宗麟に対してその身柄の払い下げを求めた。しかし彼女はそれを耳にすると、「この身を魔女としてローマとやらへ連れていくとは何たる事ぞ」
そして直ぐさま兄で、今は家老になっている田原紹忍へ連絡して兵を集めさせると、「キリスト教徒は今やこの臼杵の城下町を占領しようと不穏な企てをしている」と、
イゼズス派の教会を包囲させた。そこで神父らは立て籠もって銃で応戦しようとした。当時日本を管区とするイゼズス司祭は「四つ目のカブラル」と呼ばれる眼鏡をかけた司祭だったが、
直ぐさま臼杵を離れていた大友宗麟へ事件発生の連絡を取った。
(わが妻や田原一族の反乱によって教会を敵とし火薬の原料の硝石が入手出来なくなり、逆にそれが他の大名に渡るようになったらわが大友家は危うくなる)と宗麟も仰天してしまい、背に腹は換えられぬとばかりここで決心して、
「余は今やすでに他の女を妻にした。其方は離縁である。速やかに城を出て兄の田原紹忍の許へ行け」と、鉄砲隊をつけた使いを直ちに臼杵城へやって脅しすかし説得させた。
しかし彼女は、紀元前八七五年からイスラエルの王であったアラブの妻のイザベラの如く、血を見ること水を見るごとしと、領内の気に入らぬ者は女子供でも大の大人でも片っ端から逆さ吊りにして咽喉をかき切って殺してしまった。
だから、その当時の宣教師の書いた記録である「西教史」には、「東洋のイザベラ」と彼女のことを渾名している。
そしてイゼズス派の宣教師は、
「彼女こそ東洋へ逃亡してきた魔女の化身であろう」と考え、宗麟に対してその身柄の払い下げを求めた。しかし彼女はそれを耳にすると、「この身を魔女としてローマとやらへ連れていくとは何たる事ぞ」
そして直ぐさま兄で、今は家老になっている田原紹忍へ連絡して兵を集めさせると、「キリスト教徒は今やこの臼杵の城下町を占領しようと不穏な企てをしている」と、
イゼズス派の教会を包囲させた。そこで神父らは立て籠もって銃で応戦しようとした。当時日本を管区とするイゼズス司祭は「四つ目のカブラル」と呼ばれる眼鏡をかけた司祭だったが、
直ぐさま臼杵を離れていた大友宗麟へ事件発生の連絡を取った。
(わが妻や田原一族の反乱によって教会を敵とし火薬の原料の硝石が入手出来なくなり、逆にそれが他の大名に渡るようになったらわが大友家は危うくなる)と宗麟も仰天してしまい、背に腹は換えられぬとばかりここで決心して、
「余は今やすでに他の女を妻にした。其方は離縁である。速やかに城を出て兄の田原紹忍の許へ行け」と、鉄砲隊をつけた使いを直ちに臼杵城へやって脅しすかし説得させた。
さて、いくら婦人が獰猛でも銃口に包囲されては仕方がない。やむなく引き上げていった。これで宗麟はひとまず臼杵の教会を救ったが、日本管区長カブラルの機嫌を損なって、
もし南蛮船が入津しなくなっては困るからと心配して、ザビエルと初めて逢ってから二十七年だが「フランシスコ」と、ザビエルと同じ名を取って洗礼名として、四十八歳で改宗をした。
もし南蛮船が入津しなくなっては困るからと心配して、ザビエルと初めて逢ってから二十七年だが「フランシスコ」と、ザビエルと同じ名を取って洗礼名として、四十八歳で改宗をした。
が、それでもまだ宗麟は安心できなかった。またしても難問題が出てきた。なにしろイゼズス派では攻め込まれたのを根に持ってか、宗麟の言いつけ通りに兄の家へ退去した前婦人を、魔女として引き渡しを求めてきたからである。
「糟糠の妻は堂より下さず」というが、宗麟は前婦人が異国へ連れ去られて丸裸にされ、蒸し焼きにされるのは忍びず、何とかして許しを乞おうとした。そこで教会の機嫌をとるため、
「彼は日向に兵を出した。そこにキリスト教徒だけの都市を造り、四方に十二の教会を衛星の如く建て、イゼズス派に捧げる目的を持って・・・・・」と、向こうの記録にあるが、三万五千三百の大軍を率いて、神のやさかえを讃え、仏門の異教徒を撃つため出陣した。
「糟糠の妻は堂より下さず」というが、宗麟は前婦人が異国へ連れ去られて丸裸にされ、蒸し焼きにされるのは忍びず、何とかして許しを乞おうとした。そこで教会の機嫌をとるため、
「彼は日向に兵を出した。そこにキリスト教徒だけの都市を造り、四方に十二の教会を衛星の如く建て、イゼズス派に捧げる目的を持って・・・・・」と、向こうの記録にあるが、三万五千三百の大軍を率いて、神のやさかえを讃え、仏門の異教徒を撃つため出陣した。
日本管区長のカブラル初め、イルマン、ルイ・アルメーダ以下も先頭に立った。「国崩し」と名づけた日本では初めての青銅砲二門も引っ張って、大友宗麟は大進軍したのだ。しかし薩摩から馳せ向かってきた島津義久と、その弟の義弘は強かった。
それに「青い目の南蛮人に国土を荒らされるな」とふれ回ると、何度も外敵の侵入を受けている九州人たちは一致団結して薩摩勢に協力して迎え撃った。そこで後に「耳川合戦」と呼ばれるが、三万五千の大友軍は各所で土民のゲリラに悩まされ敗退した。そしてこの結果島津と大友とは九州での地位が逆転してしまった。このため天正十四年三月、やむなく滅亡しかけの大友宗麟は京の聚楽第へゆき、豊臣秀吉の庇護を求めた。
それに「青い目の南蛮人に国土を荒らされるな」とふれ回ると、何度も外敵の侵入を受けている九州人たちは一致団結して薩摩勢に協力して迎え撃った。そこで後に「耳川合戦」と呼ばれるが、三万五千の大友軍は各所で土民のゲリラに悩まされ敗退した。そしてこの結果島津と大友とは九州での地位が逆転してしまった。このため天正十四年三月、やむなく滅亡しかけの大友宗麟は京の聚楽第へゆき、豊臣秀吉の庇護を求めた。
これで九州征伐の口実の出来た秀吉は二つ返事で承知した。
翌年、秀吉の九州征伐は敢行された。勇猛な島津兄弟も天下の大軍を向こうに廻しては抗しえず、降参をした。
さて、本来ならば日本国内にキリスト教の別世界を作ろうと兵を動かした大友宗麟なのだから「この売国奴め」と罰せられてもしかるべきなのに、何のお構いもなく、彼は悠々と豊後津久見で、五十八歳まで安楽に暮らし得たのは、
「いくら離縁したとは申せ、長年連れ添った女房を魔女として南蛮人に渡したくなかった気持ちは判る。男として見上げたものよ」と、秀吉が特に許したからだという。しかし大友宗麟の継母といい、その妻といい、男を逆さ吊りにして虐殺する趣味があって、ローマ法王庁にもその名が記録されているのは、日本の悪女としては国際的貫禄であるといえよう。
翌年、秀吉の九州征伐は敢行された。勇猛な島津兄弟も天下の大軍を向こうに廻しては抗しえず、降参をした。
さて、本来ならば日本国内にキリスト教の別世界を作ろうと兵を動かした大友宗麟なのだから「この売国奴め」と罰せられてもしかるべきなのに、何のお構いもなく、彼は悠々と豊後津久見で、五十八歳まで安楽に暮らし得たのは、
「いくら離縁したとは申せ、長年連れ添った女房を魔女として南蛮人に渡したくなかった気持ちは判る。男として見上げたものよ」と、秀吉が特に許したからだという。しかし大友宗麟の継母といい、その妻といい、男を逆さ吊りにして虐殺する趣味があって、ローマ法王庁にもその名が記録されているのは、日本の悪女としては国際的貫禄であるといえよう。
(注)バチカン図書館は歴史、法律、哲学、科学、そして神学を目的とした研究図書館でもあり、研究に参照が必要である場合や出典の明記に気をつければ誰でも利用できる。
だから興味のある方や疑り深い方は、どうぞ是非現地に赴いて確認して頂きたい。「東洋の部」には日本の戦国期関係の報告書が幾らでもあり、難解な華文字のものも在るが、親切な司書が翻訳してもくれる。
だから興味のある方や疑り深い方は、どうぞ是非現地に赴いて確認して頂きたい。「東洋の部」には日本の戦国期関係の報告書が幾らでもあり、難解な華文字のものも在るが、親切な司書が翻訳してもくれる。