
「若き詩人への手紙」は、一人の青年が直面した生死、孤独、恋愛などの精神的な苦痛に対して、孤独の詩人リルケが深い共感にみちた助言を書き送ったもの。「若き女性への手紙」は、教養に富む若き女性が長い苛酷な生活に臆することなく大地を踏みしめて立つ日まで書き送った手紙の数々。その交響楽にも似た美しい人間性への共同作業は、我々にひそかな励ましと力を与えてくれる。
高安国世 訳
出版社:新潮社(新潮文庫)
本書には、2篇の書簡集が収録されている。
どちらも相手の手紙は掲載されていないので、具体的にリルケと、若い詩人ないし若い女性との間で、どのような内容のことが話し合われたか、細かくはわからない。
加えて、抽象的、観念的な話が多く、意味が容易につかめないところがある。
そういう点、決して読みやすい作品ではないだろう。
しかし胸に響かないというわけでもないのだ。
たとえば『若き詩人への手紙』。
この中でリルケが言いたいことは、自分自身を追求せよ、ということに尽きるように思う。
たとえば、
「自分の内へおはいりなさい。あなたが書かずにいられない根拠を深くさぐって下さい」とか、
「どうかあなたの内をになっていらっしゃる世界に思いを馳せて下さい」という言葉がある。
それは結局のところ、自分の創作の源泉は自分にあるからこそ、自分の内部をしっかりと見つめ、そこから自分にしか出せないものをくみ上げることが重要だっていうことなのだろう、と思ったがどうだろう。
だからこそ、そのためにリルケは孤独を愛せ、とも言っており、興味深い。
「孤独を愛して下さい。あなたに近い人々が遠く思われる、とあなたは言われますが、それこそあなたの周囲が広くなり始めたことを示すものにほかなりません」
という言葉はおもしろい。
そうか、孤独にはそういう見方もあったのか、と驚く思いだ。
リルケの思想の中心は、自分の内部から湧き出るもので、自分が何を表現するか、ということにあるように思う。ある種、芸術至上主義的だ。
たとえば次の一篇、
「創作するものにとっては貧困というものはなく、貧しい取るに足らぬ場所というものもないからです」
それは、貧困を恐れず、金銭的なものに流されず、自分の信じる芸術の道を突き詰めよ、という風に読めなくもない。誤読かもしれないけど。
でもそういう行為って、才能がある人間だけに許されることなのでは?と感じてしまう。
しかしリルケなりの覚悟はうかがえて興味深かった。
ともあれ自分の生き方を含めて、いろいろ考えさせられる一品である。
『若い女性への手紙』もそれなりに楽しめた。
手紙の相手の女性が日を追うごとに何かと苦境に立たされているらしい。
リルケは最初女性に対して、抽象的な言葉を駆使して人生を語っている。
愛に関する文章も、孤独を肯定するような文章も、どこか現実感を欠いているような気がしなくはない。
しかし女が「土地に立ち向」かうあたりから、現実的に女性を励ましているように見えるのだ。
そして女性がアルゼンチンに行こうと考えているときは、年長者らしく穏やかに、彼女の性急の行動をいさめている。
他人の人生と関わるのは面倒なことだ。
でもリルケは女性に対し、なるべく優しい言葉で説得している。
そこからはリルケの優しく思慮深い性格を見る思いがして、目を引いた。
評価:★★(満点は★★★★★)










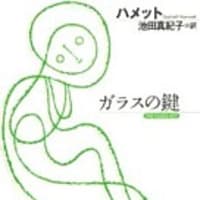

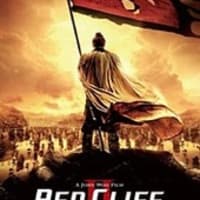
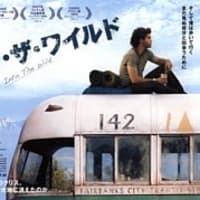
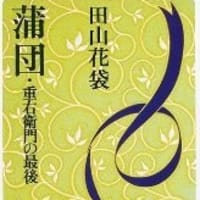
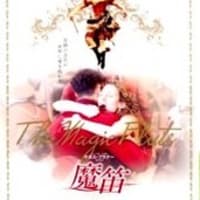
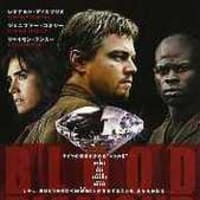
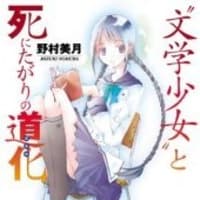
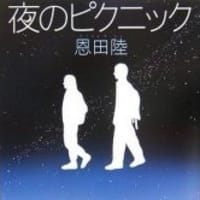








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます