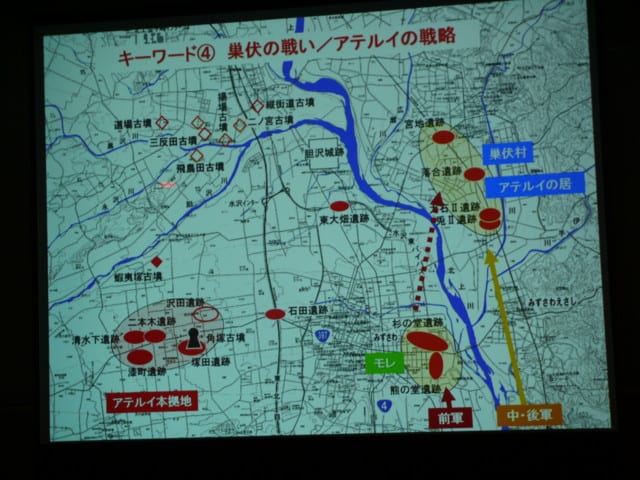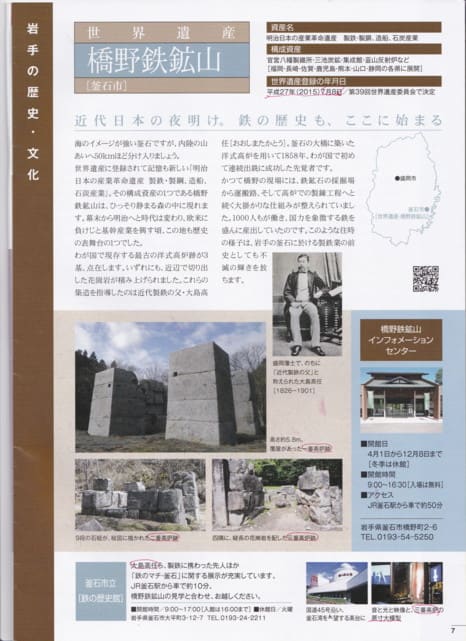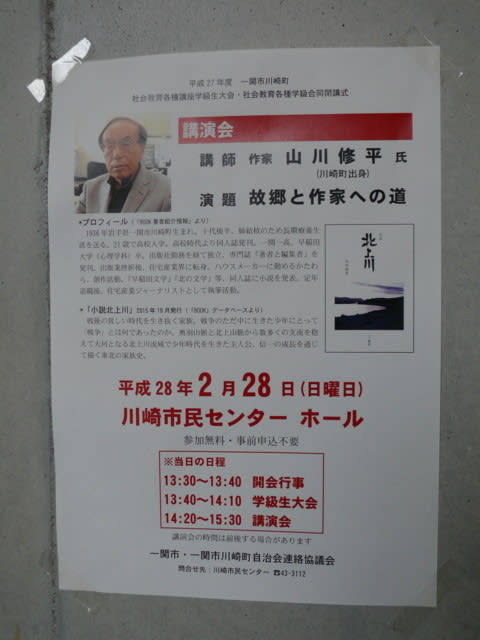2016年5月11日(水)、一関市立芦東山記念館(大東町渋民字伊勢堂71-17)主催の平成28年度第1回館長
講座『真田一族の動向』と題する講演会が開催されたので、妻と共に聞きに行ってきました。(13:00~14:
30時)。現在放送中のNHK大河ドラマ『真田丸』に関係する話でもあり、とても興味深く聞いてきました。

配布された4ページ余のプリントを基に話がなされましたが、NHK大河ドラマを毎回観ているので、良く理解
することができました。ドラマはほぼ歴史的事実を踏まえて制作されていると思いました。
テレビドラマは、真田信繁(通称・幸村)を主人公にした物語ですが、歴史的事実は武田信玄に仕え、真田家
の礎を築いた信繁の祖父の幸隆(幸綱)[一徳斎(いっとくさい)]辺りからしか記録に残っていないそうです。
その頃の真田氏は、信州(長野県)上田盆地一帯を支配した滋野党(しげのとう)の一員で、海野(うんの)氏
の庶流。
天文10年(1541)5月、甲斐(山梨県)の武田信虎の海野平(うんのだいら)攻め[小県(ちいさがた)海野
平合戦]により、真田郷の真田幸隆(幸綱)は、宗家の海野棟綱(むねつな)と共に上野国(群馬県)へ亡命。
その後、武田信玄(信虎の子)に召し出される。
天文20年(1551)、幸隆は調略(策謀)と奇襲で村上義清の支城砥石城(といしじょう)[長野県坂城(さか
き)町]を乗っ取る。その功績により旧領を回復、砥石城の山裾に城下町を作る。
天文22年(1553)、真田昌幸(まさゆき、幸隆三男、信繁の父)は武田信玄の人質、小姓として仕え、その
後、頭角を現して武将となる。[幸隆(幸綱)には4人の男子がいたが、長男・信綱は、天正2年(1574)父の
死で家督を相続したが、二男・昌輝と共に天正3年(1575)の長篠合戦で武田信玄の先鋒となり戦死。三男の
昌幸が2兄死後真田家を相続。四男の信尹(のぶただ・昌幸の弟)は、天正10年武田家滅亡後、北条から家康
に仕えて幕府の旗本となる。]
天正2年(1574)5月、幸隆病死(62歳)。天正3年(1575)5月、三河(愛知県)の長篠合戦(織田信長
・徳川家康連合軍と武田勝頼軍の戦い)で真田信綱・昌輝の二兄が戦死したので、三男の昌幸が真田家を相続し、
岩櫃(いわびつ)城(群馬県東吾妻町)を拠点に活躍する。
天正8年(1580)、昌幸は安房守を名乗り、上野の名胡桃城(なぐるみじょう、群馬県沼田市)・沼田城を攻
め取る。昌幸は独立大名へと進む。
天正10年(1582)3月、武田勝頼自刃(37歳、武田氏滅亡)。昌幸は織田信長に従属。6月2日の本能寺の変
後、旧武田領は無主の地として徳川・上杉・北条三氏の草刈り場となったので(天正壬午の乱)、昌幸は上杉景
勝に従属、7月、北条氏直に属したのち、10月、徳川家康に寝返り、北条攻めに参加。
天正11年(1583)、昌幸、家康の支援を受けて上田城(上杉景勝の侵入防備のための前線基地)を築城。
天正13年(1585)、昌幸、沼田城の割譲を拒否して徳川氏から離反、上杉景勝に従属。同年閏8月2日、上杉
景勝と連携して、上田城を攻めた徳川勢を撃退、真田信之も奮戦する(第1次上田合戦、徳川勢7000人、真田勢
2000人)。この合戦後、豊臣秀吉に臣従し、大名として自立する。
天正14年(1586)、家康大坂城で秀吉に会う(秀吉に臣従)。秀吉、関東・奥羽の諸大名に戦闘行為の停止を
命ずる。(惣無事令)。
天正15年(1587)、昌幸、秀吉に従属。秀吉の命により家康の与力大名となる。
天正17年(1589)2月、信之は家康の許に、信繁は秀吉の許に人質として出仕(徳川・豊臣二分の芽生え)。
この年、秀吉の裁定で沼田城を北条に割譲。沼田城代の猪俣邦憲(いのまたくにのり)、名胡桃城主の鈴木重則
をだまして名胡桃城を乗っ取る。この名胡桃城事件が惣無事令に違反したと激怒した秀吉は、北条氏討伐を決定。
昌幸は前田利家を総大将とする北国軍に加わる。
天正18年(1590)7月、北条氏直、秀吉に降伏する。北条氏政・氏照兄弟は切腹、氏直は高野山へ追放されて
北条氏滅亡。秀吉、奥州仕置(奥羽仕置)に向かう。
江戸に入った家康は、真田信之を沼田城主とする。ここで信之は父昌幸から独立して徳川大名となる。信之の妻
は徳川四天王の一人本多忠勝の娘小松殿(こまつどの、家康の養女)。
慶長5年(1600)、昌幸は徳川家康に従い、信行・信繁と共に、会津の上杉景勝討伐のため出陣。その途次、
石田三成から勧誘がきた。下野国犬伏(いぬぶし、栃木県佐野市)で、真田一族の去就を決断するために密談し、
昌幸と次男信繁(妻は石田三成の盟友大谷吉継の娘)は石田三成方、長男信之(妻は本多忠勝の娘)は徳川家康
方に付くことに決定する。このように一族が分裂したことを、通説では「真田存続の策」と言われているが、伝
説とみる考えもある。
慶長5年(1600)9月6日、昌幸・信繁は第2次上田合戦(徳川勢3万8000人、昌幸・信繁の真田勢2500人)
で、徳川秀忠勢をゲリラ戦術で撃退したが、9月15日の関ケ原合戦で三成方が敗れたため、昌幸・信繁は連座の
死罪を免れて紀州(和歌山県)高野山へ流罪。のち紀州の九度山(くどやま、和歌山県九度山町)に屋敷を建て
て移る(父子の助命は信之と本多忠勝の嘆願によるという)。信之は沼田領6万7000石に上田領6万8000石が
加増されて、13万5000石となる。
慶長16年(1611)、昌幸、九度山で死去(65歳)。九度山での生活は困窮し、真田紐を織る。紀伊の庄屋や
豪農は信繁に好意的だったようだ。
慶長19年(1614)、豊臣家からの誘いを受けた信繁は、九度山を脱出して大坂城に入り、大坂冬の陣で大坂
城東南隅の真田丸で徳川方に大損害を与える。
慶長20年(1615)4月、信繁、大坂夏の陣で討ち死に。大坂城炎上。
元和8年(1622)10月、上田藩主の真田信之は松代(当時は松城)13万石に転封(てんぽう)、大名として
存続する。真田信之は堅実で地味な現実的な生き方をし、性格は慎重で誠実であったが、内面は質実剛健と言え
る人物だったようである。万治元年(1658)、93歳で死去。なお、猿飛佐助・霧隠才蔵・三好青海入道などの
「真田十勇士」は架空のヒーロー。しかし、現実には真田忍者の活躍があったことが知られている。(以上、
当日配布のプリントを基に作成。)