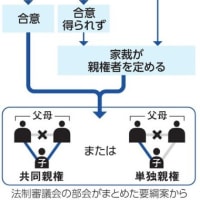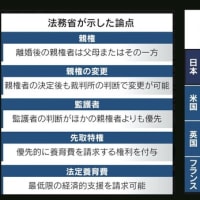1990年,政府白書で新しい児童扶養制度の構想。新たな行政機関(児童扶養庁 (CSA)の設置構想
1991年 児童扶養法案が全党賛成で成立。白書提案がほぼそのまま実現。児童扶養制度創設。
1993年 CSAが福祉行政管轄下に。
1997年 ブレア政権 児童扶養政策の改革に着手
1998年「わが国の基本として,子どもは両親から経済的,情緒的扶養を受ける権利がある。」と改革宣言
1998年緑書「まず子どもを―児童扶養への新しいアプローチ」
1998年緑書「わが国の新しい野心―福祉のための新しい契約」
1999年白書「福祉のための新しい契約―子どもの権利と親の責任」で,具体的な制度改革案
2000年 制度改正。公式の簡素化。共同監護への配慮から、子どもの宿泊日数に応じた養育費の減額の実現。不払いに対する自動車免許証の没収などの制裁
2001年 CAFCASS(カフカス・子どもと家族の法律を支援するサポート機関http://www.cafcass.gov.uk/)設立 面接交渉違反の罰則立法(軽犯罪法違反)。
2005年 政府が、離婚した親が子どもに会う方法を改善するための新しい対策の導入を提案
① 面会交流の関する裁判所の権限の強化(面会交流プログラムへの参加義務付け・裁判所決定不履行時の制裁措置(社会奉仕・外出禁止命令・制裁金・法廷侮辱罪としての罰金や刑務所への収監)
② 裁判所に持ち込む前の親同士のメディエーション(調停)の奨励
③ 家庭事件の審問を迅速にするための新たな指針。
当事者へのカウンセリングやアドバイス、教育的プログラムの実施、 面会交流の総合的支援をする場所として交流センター設置を提案
2006~2007年 300万ポンド(約6億円)の予算
2007~2008年 450万ポンド(約9億円)の予算(了承済み)
先進国では、面会を大人側の権利としてとらえた概念はすでに過去のものであり、その目的は子の最善の利益の促進であるという認識で一致しています。
『子どもの最善の利益のために』
これが現在、家族法を考える上で原動力になっている基本的な考え方です。
イギリスでも現在、「子の権利と親の責任」、つまり子は親に扶養される権利があり,親の子に対する扶養責任は夫婦関係が終了しても続くという考えが主流になっています。
もちろん日本と外国の社会状況や家族観の違いはありますが,子の利益,子の意思を尊重することは児童の権利条約との関係で世界的傾向として一致しています。
「子どもだったら親の離婚をどう思うのか?」という観点から見れば、今起こっている難しい問題の解決も自然と答えが決まってきます。
子が親を想う気持ちは世界共通と思います。
諸外国の先例は、日本の場合にも大いに参考になると思います。
(文責:辻くにやす)
1991年 児童扶養法案が全党賛成で成立。白書提案がほぼそのまま実現。児童扶養制度創設。
1993年 CSAが福祉行政管轄下に。
1997年 ブレア政権 児童扶養政策の改革に着手
1998年「わが国の基本として,子どもは両親から経済的,情緒的扶養を受ける権利がある。」と改革宣言
1998年緑書「まず子どもを―児童扶養への新しいアプローチ」
1998年緑書「わが国の新しい野心―福祉のための新しい契約」
1999年白書「福祉のための新しい契約―子どもの権利と親の責任」で,具体的な制度改革案
2000年 制度改正。公式の簡素化。共同監護への配慮から、子どもの宿泊日数に応じた養育費の減額の実現。不払いに対する自動車免許証の没収などの制裁
2001年 CAFCASS(カフカス・子どもと家族の法律を支援するサポート機関http://www.cafcass.gov.uk/)設立 面接交渉違反の罰則立法(軽犯罪法違反)。
2005年 政府が、離婚した親が子どもに会う方法を改善するための新しい対策の導入を提案
① 面会交流の関する裁判所の権限の強化(面会交流プログラムへの参加義務付け・裁判所決定不履行時の制裁措置(社会奉仕・外出禁止命令・制裁金・法廷侮辱罪としての罰金や刑務所への収監)
② 裁判所に持ち込む前の親同士のメディエーション(調停)の奨励
③ 家庭事件の審問を迅速にするための新たな指針。
当事者へのカウンセリングやアドバイス、教育的プログラムの実施、 面会交流の総合的支援をする場所として交流センター設置を提案
2006~2007年 300万ポンド(約6億円)の予算
2007~2008年 450万ポンド(約9億円)の予算(了承済み)
先進国では、面会を大人側の権利としてとらえた概念はすでに過去のものであり、その目的は子の最善の利益の促進であるという認識で一致しています。
『子どもの最善の利益のために』
これが現在、家族法を考える上で原動力になっている基本的な考え方です。
イギリスでも現在、「子の権利と親の責任」、つまり子は親に扶養される権利があり,親の子に対する扶養責任は夫婦関係が終了しても続くという考えが主流になっています。
もちろん日本と外国の社会状況や家族観の違いはありますが,子の利益,子の意思を尊重することは児童の権利条約との関係で世界的傾向として一致しています。
「子どもだったら親の離婚をどう思うのか?」という観点から見れば、今起こっている難しい問題の解決も自然と答えが決まってきます。
子が親を想う気持ちは世界共通と思います。
諸外国の先例は、日本の場合にも大いに参考になると思います。
(文責:辻くにやす)