表現の現在―ささいに見える問題から 26 (町田康『スピンクの笑顔』より)
町田康は、猫を飼っていて猫に関する本を出していた。あるときから犬も自宅に飼うようになり、犬が登場する本も書き始めた。本書はその犬のスピンクシリーズの4冊目で最終巻だという。次のような箇所がある。
1.
(引用者註.自宅にポチと呼ばれている人間の主人とその妻の美徴さん、そして犬たちがいる。自宅の天窓からの朝の光が差していて、しだいに暑くなってきてまずいのではないかと語り手でもある犬のスピンクが考えて)
そうなると面倒なので、私はポチに念波を送りました。ポチが、「おっ、なんか暑いのお。日除けのテントを張り出そう」とまるで自分が思ったように思わせるためです。こういうことをポチは雑誌の談話取材などで、「犬とは心が通じるからおもしろい」などと言っています。
ところがどうしたことでしょう。ポチはまったくそれに気がつかず、まるでフグのような顔をして夢中で本を読み耽っています。
そんなにおもしろい本なのか。ならば仕方がない。言葉で言うしかない。と、立ち上がって太い声で、「湾」と言いました。それでもポチは本を読むのをよしません。そこで、もう一度、「椀」と言ってやると、ようやっと、「なんやねん、スピンク、うるさいのお」と言って本を置き、私のところにやってくると、私の頭と背を撫でるので、さらにもう一度、「王」と言うと、ようやっと、美徴さんに向かって、「これなにを言ってるかわかんないんだけど、なんかさあ、暑くない」と言い、日除けのテントを張り出しに行きました。
( 『スピンクの笑顔』P30-P31 町田康 講談社 2017.10月)
2.
ポチは見るからに頼りない足取りで遠ざかっていき、やがて石浜の先の、岩の連なりに取り付くと、ますます危なっかしい足取りで突端に向かい、やがて見えなくなりました。
ポチはなかなか戻ってきませんでした。私はポチが足を滑らせて海中に没してしまったのではないか。そして、岩場に取り付くことができず、海中でアップアップしているのではないか。そんなことを思って心配になり、座り直して、美徴さんの目を凝(じっ)と見て、ワン、と太い声で吠えました。
ちょっと様子を見にいってやったらどうだ。と言ったのです。
しかし、美徴さんは、その意味するところを了知せず、スマートホンを弄(いじ)くっています。そこで、もう一度、ワン、と言い、少し間を置いて、立ち上がり、後ろ足をジタジタしながら、ワン、ワン、ワン、ワン、と立て続けに吠えました。
そうしてようやっと美徴さんは目を離し、そして言いました。
「う-るさい」
ショボボボホン。尻尾が一気に下がって、口がアクアクしました。
そのときキューティーが海の方に向かって吠えました。
振り返ると、ポチが石浜をよろよろ歩いていました。私はうれしくなって、また、ワン、と吠えました。キューティーもポチを呼ぶように、ワンワン、と吠えました。それを見た美徴さんは、今度は怒らずに、「よかったねぇ、スピンク。ポチ、帰ってきたねぇ」と言いました。
私は美徴さんを見あげ、「よかったね、帰ってきたね」と言いました。キューティーの尻尾が左右にパタパタ揺れていました。
( 『同上』P118-P119)
この作品は、作者を彷彿とさせるポチと呼ばれている作家の主人とその妻の美徴さん、そこに飼われている三匹の犬、スピンク、キューティー、シード(作品の終わり辺りでもう一匹やってくる)や猫たちの物語である。ここでは猫たちはほとんど登場しない。そして、夏目漱石の『吾輩は猫である』と同様に動物が語り手になっている。犬のスピンクが語り手の作品である。
この作品も夏目漱石の『吾輩は猫である』という作品を無意識的な前提や参照として作られているのかもしれない。そして近代からさかのぼってそれ以上のつながりはよく見えないけれども、たとえばアイヌの神話には動物が語り手になる一人称の物語がある。(知里幸惠編訳『アイヌ神謡集』には、「梟の神の自ら歌った謡」がある)また、柳田国男の『雪国の春』の「語り部の零落」の章には遙か昔の神話やその語りを常民の視点から捉えた文章もある。現代や近代からはそのような遙か昔の世界は一般にもやがかかった不明の世界に見えるはずであるが、そのような世界につながりをつけることは可能だと思うし、つながりはつけられるべきだと思う。メモ程度に記しておくだけにしてここでは触れない。
ところで、この作品では、作者を彷彿とさせるポチと呼ばれている作家の主人は少し犬のような性格を持っているとされ、語り手の犬のスピンクと主人のポチは気持ちや意思や考えていることを念のような形で交わし合うことができるとされている。そして、この作品自体が語り手のスピンクが語ることを主人のポチに「念波を送り」、主人のポチが書いているとされている。また、犬同士は、気持ちや意思や考えていることを交わし合うことができるとされている。
しかし、人間と犬の関係の有り様は、普通は引用部「2.」にポチと美徴さんとのやりとりとして描写されているようなものが、わたしたちには自然なものと見えるだろうと思う。したがって、上に記したような作品の設定は、夏目漱石の『吾輩は猫である』の語り手である猫の設定と同様に、設定とその展開する作品世界に読者が面白みを感じることはあっても、設定自体をあり得る現実性と見ることはないはずだ。
しかし、この作品は、たぶん作者にとっては、この作品の設定自体が現実味を十分に持つと感じられるような、犬たちとの交流の日々の物語であり、また普通の作品ではやりにくい、語り手の犬のスピンクを通した視線による作者の批評、つまり作者の自己批評の物語にもなっている。犬や猫を飼い、いっしょに日々を過ごしている人々とそうじゃない人々との間には、感じたり見えたりする世界の違いがあるように思われる。犬や猫などの動物と無縁に日々生活している読者なら、この作品の設定に対して、そんな馬鹿なことはないよなと思いながら、作者町田康の独特の語りの世界に入り込んで行き、いつしかその設定にも慣れていくという風になるのだろうと思われる。
引用部「2.」のポチと美徴さんとのやりとりは、「ちょっと様子を見にいってやったらどうだ。と言ったのです。」という部分があるとしても、だいたい普通のレベルの人と犬との関わり合いの描写になっている。犬を飼っている人なら、この引用部「2.」の場面のように犬の発する「ワン」にはいろんな犬の気持ちや考えが込められているとわかるはずである。
ところで、引用部「1.」の描写は、引用部「2.」の描写とは少し違っている。
語り手のスピンクが、主人のポチに「念波を送」るのは気持ちや考えを交わし合うことができると見ているからだ。そのような描写がなされるのは当然のこととして、この作品に対して現実的に言えば、作者も作者の分身である主人のポチ同様「犬とは心が通じるからおもしろい」と思っており、人間は犬や猫と気持ちや考えを交わし合うことができると考えているからだ。しかし、「これなにを言ってるかわかんないんだけど」とあるように、人と犬との気持ちや考えを交わし合うのもいつもうまくいくとは限らない。
ここで、興味深いのはスピンクが、「ワン」とは言わずに、「湾」、「椀」、「王」と言っていることである。これを作者が作中で時折見せる言葉遊びのようなものと見なさないとすれば、どう理解できるだろうか。
犬の同じ「ワン」でも込められた気持ちや指し示す意味において、異なることがあるということはなんとなくわかる。しかし、その違いを読み取ることは難しいと思う。我が家には野良猫出身の雌の猫が二匹いる。一方の猫はほとんど鳴かない猫だけどもう一方の年上の白猫の方はよく「みゃあ」と鳴く。この猫とは七年くらいつきあっているけど、そのいろんな区別がありそうな「みゃあ」を読み解くことはできない。つまり猫の気持ちや指示しているものがよくわからない。
猫や犬同士は、「みゃあ」とか「ワン」とかしか鳴かないのに、どうやって気持ちや考えを伝え合っているのだろうかとわたしはふしぎに思うことがある。ここでの「湾」、「椀」、「王」という区別は、語り手のスピンクが、主人のポチに「日除けのテントを張り出し」てほしいということを訴えている表現の言葉になっており、その過程での言葉の強弱を示しているように見える。だから、「ワンワンワン」と「ワンワン」と「ワン」の区別の表現と同じものと見なすことができると思う。
ところで、「ワン」とは言わずに、「湾」、「椀」、「王」と言っていることで思い出したことがある。これを人間世界の人間的な表現と見なせば同様のことがある。たとえばおなじ「馬鹿」という言葉でも、親愛の情がこもった場合もあれば、相手を軽く責める場合、あるいは相手をきつく批判する場合もある。そして、そのいずれの表現であるかは、その場の状況や前後の話の流れ(書き言葉であれば文脈)によって判断することができる。書き言葉では、「馬鹿」は「バカ」や「ばか」というちがう表記はあっても、上の「ワン」のようにかき分けることはしない。話し言葉の場合には、語調の強弱などで区別がなされている。
また、以下の文章によれば、現在では「母」や「叔母」などと区別されているけれど、遙か昔、あるいは近代に残存していた未開的な社会では、それらを同じ「母」という言葉で表現していたということがあったらしい。この作品で同じ「ワン」でも、「湾」、「椀」、「王」と区別した表現をしたように、同じ「母」でも、たとえば「ハハ」「ハーハ」「ハハー」のように区別していたのだろう。おそらく、言葉ははじまりの単純さから、しだいに分化して複雑化してきたのであろうということは一般に想像できることである。その過程には、死語と流行語など、いわば言葉の死や誕生や再生の物語も含まれていたはずである。
では子どもにとって実の「母」や実の「父」と親族組織がひろがっていったために 「母」とは(引用者註.ママ 「とか」か)「父」とか呼ばれることになる母方の兄弟(伯叔父)や姉妹(伯叔母)はおなじ呼称なのにどう区別されるのだろうか。マリノウスキーによれば、おなじ「父」 や「母」と呼ばれても、実の「父」「母」と氏族の「父」たちや「母」たちとでは感情的な抑揚や前後の関係の言いまわしによって呼び方のニュアンスがちがい、原住民はそれが実の「父」や「母」を呼んでいるのか、氏族の「父」たちや「母」たちのことか手易く知り分けることができると述べている。またこの地域の原住民の言葉(マラヨ・ポリネシアン系)には同音異義語がおおいのだが、それは民族語として語彙が貧弱なためでも、未発達で粗雑なためでもない。おおくの同音異義語は比喩の関係にあって、直喩とか暗喩とかはつまりは言語の呪術的な機能を語るものだと述べている。 わたしたちがマリノウスキーの考察に卓抜さを感じるのはこういう個所だ。たとえば「母」という言葉は、はじめはほんとの「母」にだけ使われる言葉だった。それがやがて「母」の姉妹にまで使われることになった。これは子どもの「母」の姉妹にたいする社会的な関係がほんとの「母」にたいする関係と同一になりうることを暗喩することにもなっている。そこでこのふたつの「母」を区別するために「母」という呼び方の感情的な抑揚を微妙に変えることにする。これによってほんとの「母」と、「母」の姉妹との社会的同一性とじっさいの差異を微妙にあらわし区別することになる。子どもの世代がこの同一性と差異に耐えられないほどの社会的な関係の変化やずれを体験したとき別称がはじめて実際の場面で登場しなくてはならない。
(「ハイ・イメージ論9」の「贈与論」P7-P8 『吉本隆明資料集115』 猫々堂 2012年5月)
この最後の部分の「別称」の登場については、たぶん関連すると思われる個人的な体験がある。わたしたちは、今はもう忘れてしまっているとしてもとても小さい頃の母親の呼び方を持っていたはずである。そして、その呼び方が生涯続いていくとは考えられない。どこかで「別称」を誰もが体験するのではないだろうか。私の場合は、思春期と言われる時期に「別称」に変更した覚えがある。家族の外の世界に出たこともあり、思春期という時期でもあり、気恥ずかしくなって今までの母の呼び方を変えたのだったと思う。















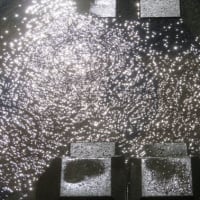




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます