ファッションについてのメモ
―鷲田清一『ひとはなぜ服を着るのか』を読んで
鷲田清一の『ひとはなぜ服を着るのか』を読んだ。
鷲田清一は、哲学を専攻していたということは知っていて、朝日新聞に載っている「折々のことば」でなじみがある程度だが、吉本さんの鷲田清一の本(『モードの迷宮』)の書評 https://allreviews.jp/review/824 がきっかけでこの本を読んでみた。
まず、哲学を研究していてファッション論というのはちょっと意外である。もっと正確には、旧来的な哲学のイメージや旧来的な知の感覚からの視線では、意外であると言うべきである。鷲田清一は、「はじめてファッションについて論じたとき」の周りの知の視線について記している。
わたし自身が―わたしは大学ではいちおう西洋哲学・倫理学の教師として講義をしている―哲学者でありながら、ファッションについて文章を書きだしたときには、相当な抵抗があった。抵抗といえばかっこいいが、要するに侮蔑され、冷笑されたのであった。わたしがはじめてファッション論を書いたとき、哀しい想い出だが、哲学の恩師のひとりに、ファッション雑誌の言語分析をしたロラン・バルトの『モードの体系』のことを言うふりをして「世も末だな」と言われた日のことはいまも忘れない。
(『同上』「はじめてファッションについて論じたとき」 P277-P278)
哲学が、この世界の渦中での人間的な諸活動や行動について本質的に考えるものだとすれば、ファッションについて論じてもなんら的外れではない。しかし、純文学同様に哲学も旧来的な威勢の良さを失ってきているといっても、いろんな分野において旧来的な感覚や考え方の残骸が現在でもまだまだたくさん残っていて、学問世界に拘わらず、人間社会でも誰もが日々当面している問題だと思う。哲学や純文学の凋落と大衆文学(エンターテインメント文学)の隆盛というような過程は、言葉が、凝り固まった局所性を打ち崩して総合性としての人間にさらに近づき人間的な課題に真に包括的に答えようとする過程のように見える。これは言葉の主流の振る舞いのように見える。
本書の記述や本の紹介によれば、ファッションを服飾等の分野としてではなく、人間的な表現や思想として取り上げ論じてきているのは西欧、特にフランスだったようである。鷲田清一は、ジャン・ボードリヤール(消費社会の分析をした人とか名前しか知らない)のファッションに関する言葉も援用している。そのせいか、本書の文体は、日常の身近な気づきを織り込みつつも少しポストモダンがかった言葉になっている。
鷲田清一の文章からいくつかひろい出してみる。まず、ファッションが万人の日々の生活に関わるものとして、さらにそれがわたしたちの世界との関わり方を示していたり、関わり方を変えたいという欲求の表現(スタイル)でもあると把握され、つぎのように描写している。
ひとはこうした感受性のモード(様相)を、センスだとかテイストと呼ぶ。今日、ファッションはそういう感受性のモードをひとびとのあいだでもっとも濃(こま)やかに確認する媒体となっている。あのひとの生き方、あのひとのふるまい方、あのひとの感覚・・・・・・そう、ファッションとは生存と感受性のスタイルのことだ。
服の趣味、ネクタイやトランクスの好み、眉や髪のかたち、眼鏡やバッグの型といった身体の表面だけではない。心地よい音楽、壁に貼るポスター、ベッドのシーツ、お気に入りのアーチスト、買い置きのドリンク、行きつけのバー、休日に乗り回すバイク、ひとのネットワーク。それら身体環境のすべてがファッションの構成要素となりうる。じぶんが身体を浸す空間の雰囲気、その感覚的な様相がファッションなのである。その様相の感覚というのは、時とともに大きく揺らぎながらも、それじたいとしては想像以上に緻密である。
(『ひとはなぜ服を着るのか』 P253-P254 鷲田清一 ちくま文庫)
もういちど言おう。化粧、着衣、装飾。ファッションとは身体の表面の変換作業である。そして、身体がわれわれの感覚媒体であるかぎりで、ファッションは世界との関係のモード(様相)変換そのものを意味する。その意味で、ファッションとは感受性のスタイルであり、そのたえざる変換として定義できる。じぶんの限界を超えたいという欲望が、ファッションという都市の表面に鳥肌が立つように浮き立つのである。
(『同上』 P256)
この鷲田清一のファッションの捉え方―そのどこまでが西欧のファッションの捉え方の影響で、どこからが鷲田清一独自の考えかを区別することはわたしにはできないが―からすれば、わたし(たち)はなんと貧しいファッションのなかに埋没していたのだろうという思いがする。わたしの場合はファッションというものに大して気を配らず無頓着であった。今もそうした状態にさして変化はない。中学校から高校までは一日の大半が制服という事情もあるが、大人になっても男は特にそんなに積極的にファッションに関心を示さないというのが一般的な社会だったように感じている。
ところで、「ファッション」という言葉は、わたしの耳の記憶や歴史の中では日常生活から外れたものとしてイメージされる。現在ではわたしたちの日常生活の中に根を下ろしていて、その言葉に異和感や場違いだという意識はなくなっている。それだけわたしたちの生活や社会が以前より豊かになり余裕も出てきたのだろう。別の言い方では、大きく変貌して十分に西欧化されてきたと言ってもいい。
わたしが育ってきた昔の感覚では、「ファッション」などに凝るのは「不良」のイメージが強い。二昔前には、社会的なイメージとしては、服や頭髪などの「ファッション」に凝ってエレキギターを弾いたりするのは、「不良」のイメージだった。振り返れば、あっという間に社会の様相が変貌してしまった。もちろん、いい意味であり、ずいぶん開放的で自由になったと思う。それはわたしたちのアジア的なものの中から生まれ出たのではなく、残念ながら外来の西欧的なものの滲透が促したものだと思う。そうしたことと対応するように鷲田清一が上に述べているような人間的な表現や活動としてのファッションということは、わたしたちに異和感なく受け入れられるようになった。この鷲田清一のファッション概念によれば、芸術や文学の表現もファッションの表現も人間的な表現として同一の地平で見わたせるようになっている。本書はすぐれた考察だと思う。
従来なら、例えば文学の領域からファッションの世界を眺めたら、ちょうど文学自体の中で純文学と大衆文学とが価値序列の中にあったように、ファッションの世界を自分たちの文学的な表現と同列の人間的な表現という見方は一般になかったと思われる。ファッションは表現と見なされず文学より劣ったものと見なされていたと思う。それと対応するように、ファッションの世界の中でも自分たちの作り上げるものを表現や作品であるという意識は薄かったろうと思う。こうして現在の芸術や文学の表現もファッションの表現も人間的な表現として同一の地平という捉え方が割と人々に受け入れられやすい状況になってきた。
昨日、9月2日(日)のテレビ番組『情熱大陸』は、ヘアメイクアーティストの活躍の番組だった。偶然途中から観てしまった。ファッション論であるこの『ひとはなぜ服を着るのか』(鷲田清一 ちくま文庫)を読み終えたばかりだから、なおさら興味深かった。しかし、顔に化粧を施したりしていくのを見ていて、女性には普通のことかもしれないが、男のわたしからはそこまでするのかという印象だった。つまり、そんなことにまで細かく心配りするなんてめんどくさいなあという感じだった。
次に、私の関心に沿っていくつか抜き出してみる。
①
そう言えば、顔というのは不思議なものです。じぶんの印というよりじぶんそのものであるのに、その当のじぶんには絶対にじかには見えません。じぶんからは無限に隔てられています。その顔に、他人は語りかけ、反応してきます。わたしの顔はまずは他人にたいしてあるのです。
服にもそういう面があります。服というとすぐ「センス」が問題にされますが、それは〈わたし〉の自己表現であると同時に、いやそれ以上に、他人の視線をデコレートしたり、他人の存在を迎え入れたり、ときには他人の存在を拒絶したりもする、そういうそのつどの他者へのかかわり方の様相(モード)のことを言うのではないでしょうか。衣服はじぶんだけのものではないのです。他人を拒絶する場合でも、他人が唾を吐きかけそうな服をわざと身につけることによって、そういう姿勢を他人に向けてしめすのですから。(『同上』 P161-P162)
②
関係が顔にとって本質的であるというのは、理由がある。じぶんの顔は、じぶんでは見えない。じぶんの顔は、じぶんの顔をまなざす他人の顔のその変化を見ることで、わたしが想像するものでしかない。つまりわたしの顔じたいが、他者の顔を介してはじめて手に入れられるものであるのであり、他者の顔についても同じことがいえるのだから、本質的に顔は関係のなかにあるのであって、けっしてそれだけで自足している存在ではないわけである。(『同上』 P168-P169)
③
化粧とは顔の表面の造作を演出することだと言えるが、しかし化粧を見る側からいえはそうなるが、化粧する本人からすれば造作がどう変わったかほんとうはじかに確認しようがない。じぶんの顔はじぶんでは絶対に見ることができないのだから。つまり、化粧するときひとは、ほんとうはじぶんの空想的なイメージと戯れているだけなのだ。わたしたちはいつも、じぶんが想像するものを真似ているだけなのである。(『同上』 P178)
自分の「顔」も「服」も「化粧」もその全体を自分が見渡すことができないということ。したがって、それらは本質的に関係のなかにあるというふうに鷲田清一は捉えている。こういう自分の顔や化粧や服を自分では直接見わたせないと言うことは、たぶん誰もが気づいたり思ったりしたことがあると思うが、そういう万人に当てはまる感覚や感受を思想に取り込むことはとても大切なことだと思う。この件に触れている箇所がある。
ファッションこそ他人がじぶんにたいして抱くイメージ、じぶんがじぶんをそこへと挿入するセルフ・イメージのモデルを提示するものだからである。
ファッションにどうしてそんな力があるのか。ファッションは、ひとがまぎれもないひとつの身体として他人たちのあいだに現れでるときの、その様式を意味するからだ。そして、ここが重要なのだが、そういう身体の存在そのものが当の個人にとっては、物ではなくイメージというレヴェルでしか確証できないものだからである。わたしは他のひとたちが見るこのじぶんの顔をじぶんではけっして直視することができないし、じぶんの髪型もからだ全体のシルエットもふるまいの型もじぶんではじかに確認することはできない。じふんで見たり触れたり聴いたりできる身体のいくつかの部分、他人の眼が教えてくれるもの、鏡や写真の映像・・・・・・それらの断片的な情報をまるでパッチワークのようにつぎはぎしながら、想像力の糸でひとつの全体像へとじぶんで縫い上げるよりほかに、じぶんの身体全体にかかわることはできないからである。そう、他人がわたしにたいして抱くイメージとどんなずれがあるかをも勘定に入れながら、ときに深く傷つきもしながら、おそるおそるみずからの身体像をかたちづくってゆくしかないのだ。
そのようなセルフ・イメージは、わたしたちが「共同体」のなかに深くはめ込まれて生きているときには、なにか確固とした枠組みのなかで思い描くことができたし、またそうしかできなかった。が、今日、わたしたちは好むと好まざるとにかかわらず、生まれてすぐに「社会」というもののあらゆる象面に接続され、そこに深く組み込まれてしまう。ひとりひとりの存在様式は、外見やふるまいの様式をそのつど選択し、わがものとしてゆくなかで、つまりは「社会」の広大な神経組織のなかで編まれるしかない。そのモデルをファッションが提供してくれる。(『同上』 P254-P255)
ここでは、単に現在的な状況だけが切り取られて語られているわけではない。太古の「わたしたちが『共同体』のなかに深くはめ込まれて生きている」状況もきちんと踏まえられている。過去や太古は、形を変えながらも現在に深く潜在しているはずである。したがって、あらゆる思想や論考は、単に現在のみを切り取るのではなく過去や太古における人間の振る舞いも考慮に入れる必要があると思う。いわば、現在まで歩みたどってきた人類の総合性において考えることが、その思想や論考を普遍的なものにすると思われる。
例えば、人間は自分の顔や姿を直接的に全体を見ることができないが、鏡を用いると間接的ではあれ自分を見渡すことができる。この「鏡」というものは現在では、辞書の「人の姿や物の形を映し見る道具」という機能性で捉えられている。初めて鏡に触れた子どもなら、また別様の感じや感覚を持つのかもしれない。
鏡には「水鏡」という言葉もある。その言葉ができたのは新しいかもしれないが、鏡が普通の人々に普及する前は、その水鏡を用いて自分の姿を見ていたのかもしれない。また、祭りの化粧などでは、互いに他人の化粧を施し合って、他人の姿から自分の姿を想像していたのかもしれない。歴史の具体のイメージを肌合いで理解するのはむずかしい。しかし、おそらく現在の同様の振る舞いの中にも太古の姿は保存されているような気がする。
鏡は、古事記の天岩戸の場面にも登場するし、三種の神器の一つと言われる八尺鏡(やたかがみ)も古事記に登場する。また、「中国の歴史書『三国志』「魏志倭人伝」には239年魏の皇帝が卑弥呼に銅鏡百枚を下賜した」とする記述もあるという。つまり、「鏡」に対する意識は、太古の宗教性を帯びたイメージや視線と現在の機能的な視線というように大きく違っている。しかし、鏡が広く普及してくるとそういう宗教性を帯びたイメージや視線も少しずつ薄らいできた。鏡ひとつとっても、このようなイメージと視線の変位がある。たぶんふるいイメージや視線は、わたしたちの意識の深い層にしまい込まれていると思う。このことも現在のイメージや視線に何らかの形でくり込んで考えるべきだと思われる。











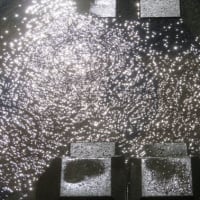








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます