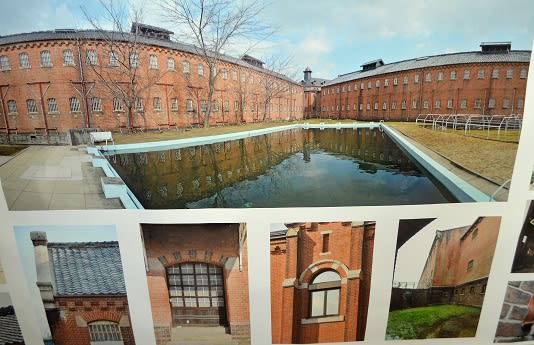晩秋の大和路 ~紅葉めぐり 『冬が来る前に』
秋が深まれば深まるほど、日ごとに空気の透明感が増していくようだ。
紅葉しきれないまま、立ち枯れとなる木も多い。
やがて、冷たい北風が冬を伴ってやってくる。
晩秋の大和路風景は談山神社から。






寒さにブルッと震え、思わず立てたコートの襟。
見上げる空高くに届かぬ想いを伝えてみる。
冬が来る前に・・・
迷いを断ち切れないまま。









![]()
![]()
人気ブログランキングへ
![]()
にほんブログ村















































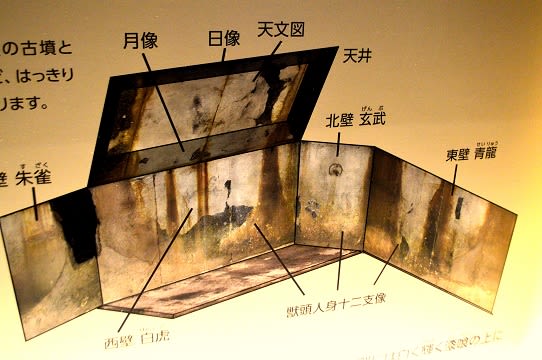

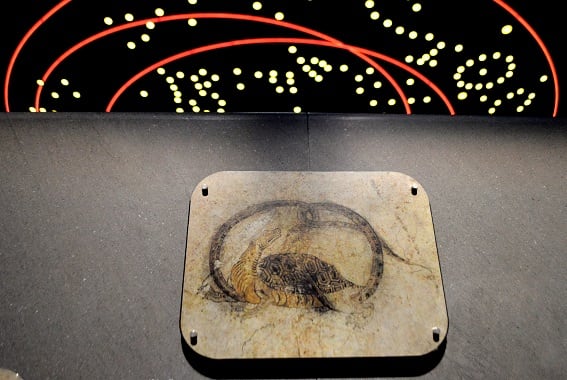
























































































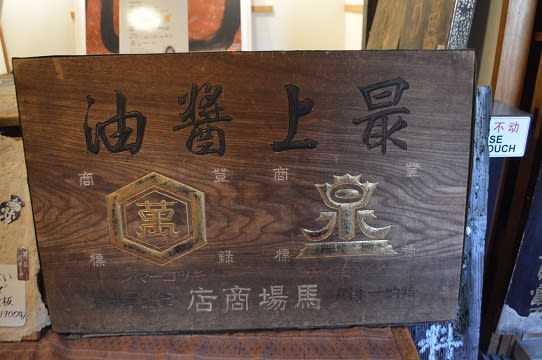


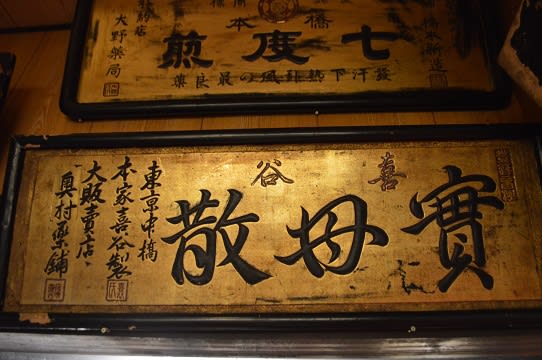


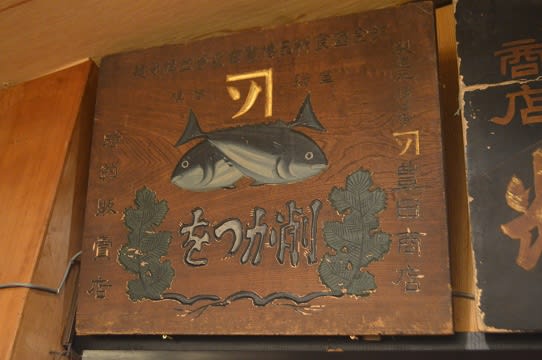





































 「
「

 「くも」
「くも」