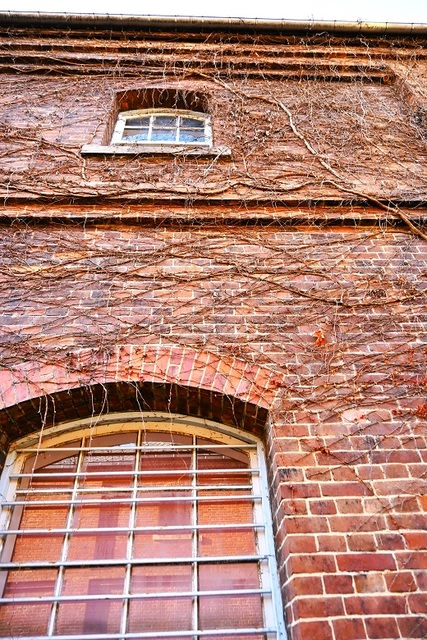アオサギと京都府立植物園 ~賀茂の流れに

葵祭ご一行が下鴨神社で神事を終え、加茂街道に到着するまでの間、雑踏を避けるように賀茂川沿いを散策した。
賀茂川沿いは私にとって、昔から一番好きな散策コース。
川沿いのベンチに座ると手が届きそうな、すぐ近くにアオサギが留まっていたが私は気にもせず、昼食のパンを食べていた。
アオサギは物思いに耽っているようにじっとしていたが、そのうち、ふと目があった。
何か話したいようにみえたが、双方、無言で見つめ合うだけだった。
沈黙を破るように私が「おまえ、この前、ジブリに出てたよな。」とつぶやくと、驚いたように飛び立っていった。
次の瞬間、上空を飛び回っていたトンビが急降下してきた。
あっという間に私が手に持っていた食べかけのパンを引っさらっていった。



トンビはパンをしっかりと、つかんでやがる。
「アオサギもパンが欲しかったのかな。シャイだから、言えなかったんだ。」
今頃になって、気がついた。

そのあと、久々に京都府立植物園に行ってみた。薔薇が満開だった。


 比叡山を借景。
比叡山を借景。
 牡丹やポピーも満開。
牡丹やポピーも満開。



































































































































 ソワレHPより
ソワレHPより