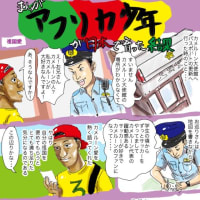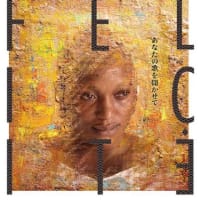先般、コンゴ民主共和国の英雄記念日にちなんで、旧宗主国との関係をお話しした。
国家英雄を讃える日
第一話 ローラン・デジレ・カビラ
第二話 パトリス・ルムンバ
コンゴとベルギー
前編
後編
その後実は続編をまとめていたが、アップの機会を失っていた。きょうは突然ながらその「続編」を少々。
そもそもコンゴの生い立ちに戻りたい。
コンゴ盆地には、古くから先住民による王国の隆盛があり、独自の文化を育み、栄えていた。コンゴ川下流域、現在のガボン、二つのコンゴ、アンゴラあたりに栄えたコンゴ王国がよく知られる。キコンゴ語がよく話される地域に重なる。
15世紀以降、大航海時代を迎え、アフリカには、ポルトガル、スペイン、そして英仏もアフリカに進出。キリスト教の布教、交易、そして奴隷貿易などが進められた。19世紀に列強による植民地化が進み、イギリスの縦断政策、フランスの横断政策などと聞けば、世界史などでもご存知の方も多いのではないか?
その頃、現在コンゴが位置する中部のアフリカはどうなっていたのかといえば・・・そこはジャングルに覆われ、人を寄せ付けない地。文字通り「暗黒大陸」とされてきた。
そこに異常な関心を有したのが、ベルギーの国王、レオポルト二世であった。彼は私財(といっても国民から巻き上げたものだが)を投げ打って資金提供を行い、スタンレーやリビングストンといった探検家にこの地を探検させる。そしてここがベルギー国王の支配の範囲であることを示す旗を立てて行った。
1884~1885年には植民地再分割のため、ベルリンで国際会議が開催される。この会議では植民地の帰属と境界が再画定されアフリカの植民地が列強の既得権として確認された。アフリカにとって悪夢年といわれる。その結果、東アフリカの多くが英領に、西アフリカの広い範囲は仏領に。そしてコンゴは・・・なんとレオポルト2世の私領とされたのである。時差もある広大な土地が、一国王のお庭とされたのである。
この結果、一つ興味深いことが発生する。下の地図はアフリカ大陸を雄大に流れるコンゴ川の河口付近のもの。この川の南はアンゴラ領(旧ポルトガル領)である。ではコンゴ川北側をみると。。。。コンゴ領を挟んで、こちらにもアンゴラ領カビンダ。つまりアンゴラの「飛び地」があるのだ。


(ナショナルジェオグラフィックウェブサイトより)
なぜこのようなことになっているのであろうか?歴史的にみればギニア湾岸にはまずポルトガルが渡来し領有。のちにレオポルト二世がコンゴ川の管轄権をとったので、ポルトガル領が分断されてしまったというわけだ。そして今日現在もこのような形になっている。
このカビンダという地。隣接しているコンゴ共和国は旧仏領、独立後は社会主義の道を歩んだ。石油が取れる。その後、アンゴラも75年の独立後、社会主義化。その狭間にクチバシのように領土をもつコンゴ民主共和国(当時ザイール)は資本主義諸国に支えられた。カビンダには反アンゴラ政府の武装勢力、サビンビ率いるUNITAが展開。冷戦構造のパワーポリティクスの中で、極めて地政学的、そしてキナ臭い土地となって行く。
歴史、地政学上のお話はまだまだ色々書くべきことがあってここには収まらない。また機会を改めよう。
そして先般2010年のアフリカカップサッカーのアンゴラ大会で、トーゴ代表選手団に不幸が襲いかかったのもこの地だ。
コンゴとベルギーを振り返る上で大切な歴史の経緯、国王のお庭とカビンダのおはなし。今日はここまで。
(おわり)
国家英雄を讃える日
第一話 ローラン・デジレ・カビラ
第二話 パトリス・ルムンバ
コンゴとベルギー
前編
後編
その後実は続編をまとめていたが、アップの機会を失っていた。きょうは突然ながらその「続編」を少々。
そもそもコンゴの生い立ちに戻りたい。
コンゴ盆地には、古くから先住民による王国の隆盛があり、独自の文化を育み、栄えていた。コンゴ川下流域、現在のガボン、二つのコンゴ、アンゴラあたりに栄えたコンゴ王国がよく知られる。キコンゴ語がよく話される地域に重なる。
15世紀以降、大航海時代を迎え、アフリカには、ポルトガル、スペイン、そして英仏もアフリカに進出。キリスト教の布教、交易、そして奴隷貿易などが進められた。19世紀に列強による植民地化が進み、イギリスの縦断政策、フランスの横断政策などと聞けば、世界史などでもご存知の方も多いのではないか?
その頃、現在コンゴが位置する中部のアフリカはどうなっていたのかといえば・・・そこはジャングルに覆われ、人を寄せ付けない地。文字通り「暗黒大陸」とされてきた。
そこに異常な関心を有したのが、ベルギーの国王、レオポルト二世であった。彼は私財(といっても国民から巻き上げたものだが)を投げ打って資金提供を行い、スタンレーやリビングストンといった探検家にこの地を探検させる。そしてここがベルギー国王の支配の範囲であることを示す旗を立てて行った。
1884~1885年には植民地再分割のため、ベルリンで国際会議が開催される。この会議では植民地の帰属と境界が再画定されアフリカの植民地が列強の既得権として確認された。アフリカにとって悪夢年といわれる。その結果、東アフリカの多くが英領に、西アフリカの広い範囲は仏領に。そしてコンゴは・・・なんとレオポルト2世の私領とされたのである。時差もある広大な土地が、一国王のお庭とされたのである。
この結果、一つ興味深いことが発生する。下の地図はアフリカ大陸を雄大に流れるコンゴ川の河口付近のもの。この川の南はアンゴラ領(旧ポルトガル領)である。ではコンゴ川北側をみると。。。。コンゴ領を挟んで、こちらにもアンゴラ領カビンダ。つまりアンゴラの「飛び地」があるのだ。


(ナショナルジェオグラフィックウェブサイトより)
なぜこのようなことになっているのであろうか?歴史的にみればギニア湾岸にはまずポルトガルが渡来し領有。のちにレオポルト二世がコンゴ川の管轄権をとったので、ポルトガル領が分断されてしまったというわけだ。そして今日現在もこのような形になっている。
このカビンダという地。隣接しているコンゴ共和国は旧仏領、独立後は社会主義の道を歩んだ。石油が取れる。その後、アンゴラも75年の独立後、社会主義化。その狭間にクチバシのように領土をもつコンゴ民主共和国(当時ザイール)は資本主義諸国に支えられた。カビンダには反アンゴラ政府の武装勢力、サビンビ率いるUNITAが展開。冷戦構造のパワーポリティクスの中で、極めて地政学的、そしてキナ臭い土地となって行く。
歴史、地政学上のお話はまだまだ色々書くべきことがあってここには収まらない。また機会を改めよう。
そして先般2010年のアフリカカップサッカーのアンゴラ大会で、トーゴ代表選手団に不幸が襲いかかったのもこの地だ。
コンゴとベルギーを振り返る上で大切な歴史の経緯、国王のお庭とカビンダのおはなし。今日はここまで。
(おわり)