平吉 毅州/虹のリズム 8.踏まれた猫の逆襲/演奏:松本 あすか
今、小2のYちゃんが練習しているのは、
故平吉毅州さんの「虹のリズム」におさめられた「踏まれた猫の逆襲」
だれもが耳にしたことのある「猫ふんじゃった」の続編ともいえる曲です。
作曲者不詳の「猫ふんじゃった」は国によっていろんなタイトルで
親しまれている曲ですが、
こではそのネコくんが逆襲してきます。
曲の冒頭のテーマのリズムは「ネコふんじゃった」と同じ
前者は下がる音形なのに対して、こちらはパターンが逆になって、
ネコが今にもとびかかってくるようです。
それから、二拍子のこの曲。
私自身は子供の頃、二分の二拍子と四分の四拍子、同じようにとっていて、
なぜ曲が重たくなるのだろう?と、やたら速く弾いてみたりでした^^;
拍子の違いは、実際に2拍子で歩いて歌ってみるとわかりますよ。
また、「ネコふんじゃった」は♭が6つ、「ふまれた~」は♯が1つ
調声の持つ色合いの違いもおもしろいですね。
この曲にも歌詞があるの?と、時々生徒さんにたずねられますが、
「踏まれた~」のほうは、ピアノのために作られた曲で、
歌詞はなくとも、この曲の音楽そのものが歌で、それが伝わるよう弾きたい
最後はテーマがちらっと顔を出して、リフレインしながら去っていきます・・・
楽しくて、それでいて、なぜか私はせつなくなる曲。
猫くん、元気でがんばって
コンクールにもしばしばとりあげられるこの曲。
難易度を、あえていえばバイエルの (ほぼ今は使いませんが) およそ60番以降。
でもリズム感あふれるチャーミングな曲、
小さい子も大人の初心者さんもまずはチャレンジして、と思います。
さあ、みなさんのはどんなふうな猫くんになるか楽しみですね











 」と言いだしたら、みんなが窓を向いて
」と言いだしたら、みんなが窓を向いて 」って喜んでいましたよね
」って喜んでいましたよね










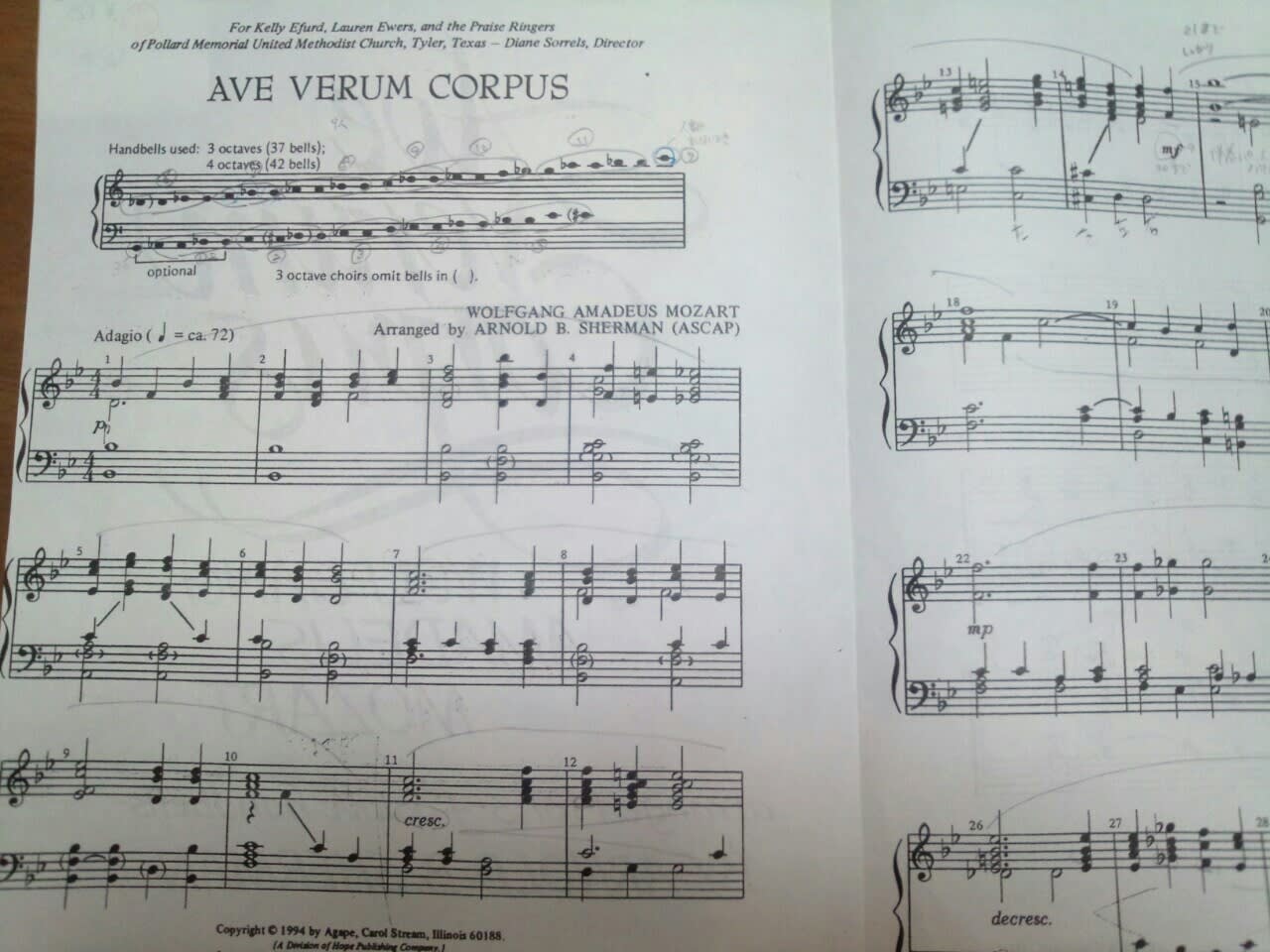





 )
)
 とおこられました
とおこられました )
)
 ~ 休憩 ~
~ 休憩 ~ 

 」「イノシシに会った~
」「イノシシに会った~ 」などと言って帰ってくる日もありましたが
」などと言って帰ってくる日もありましたが









 ますますこわくて弾きにくく、
ますますこわくて弾きにくく、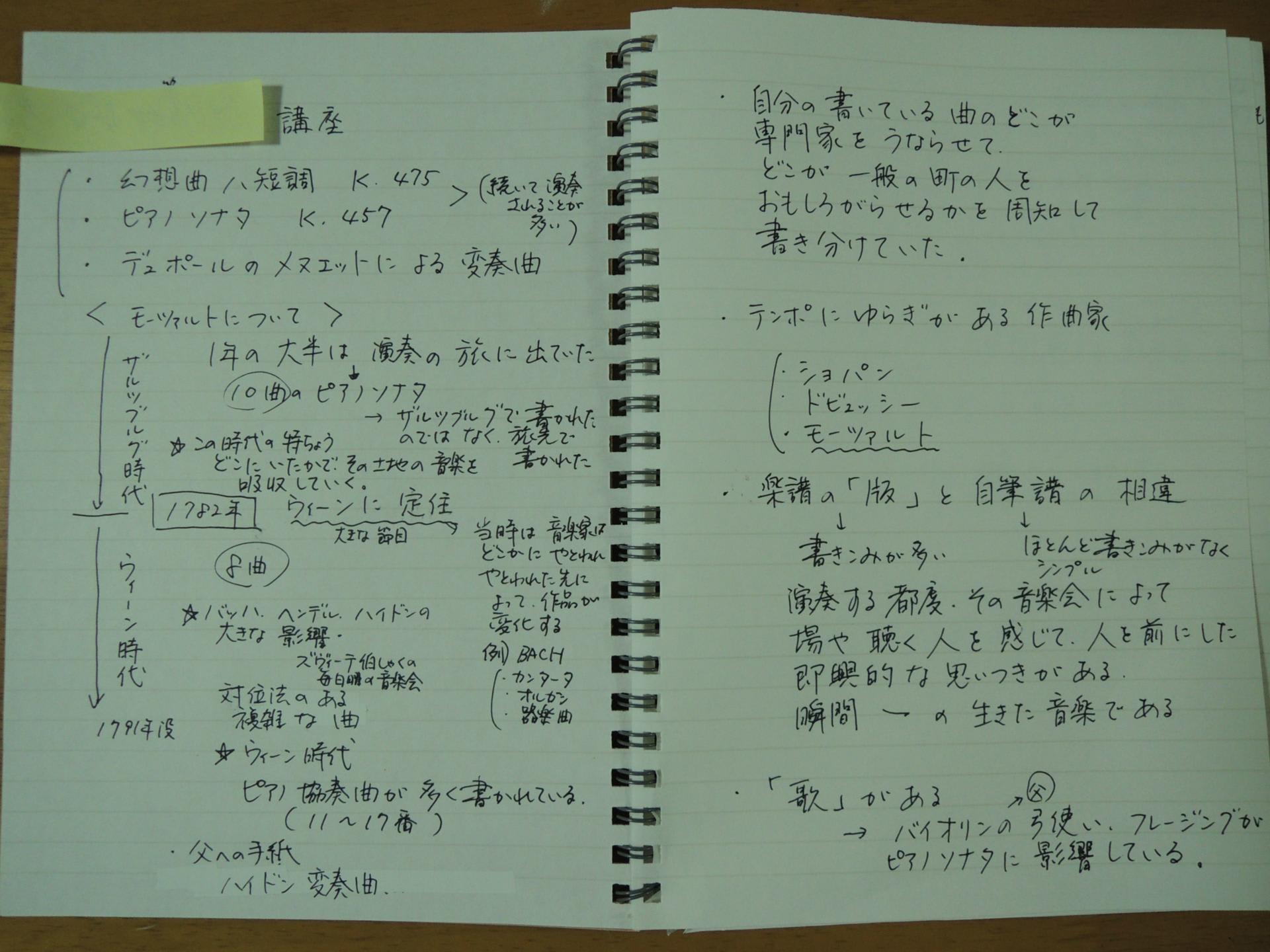
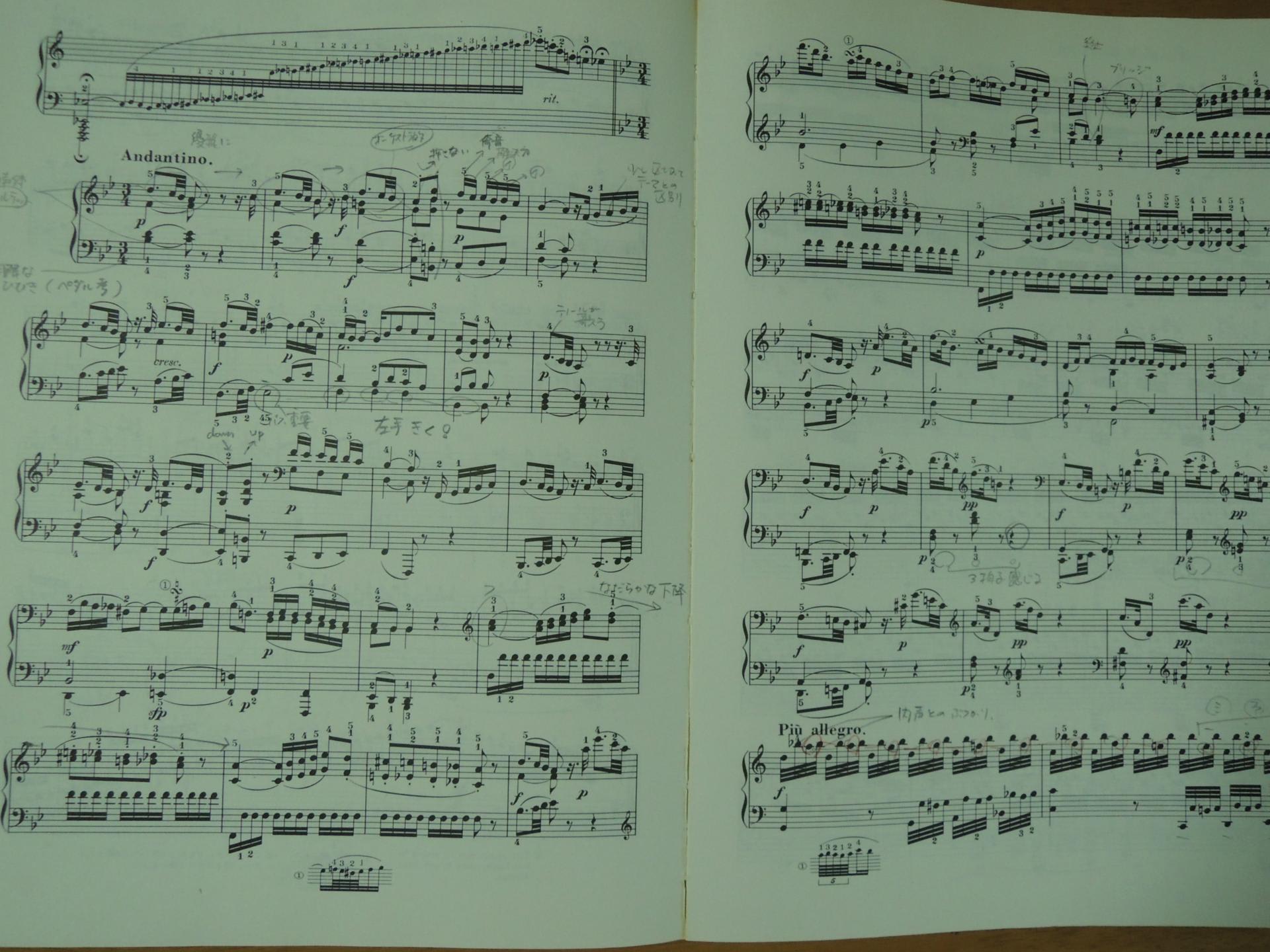
 」と、
」と、
