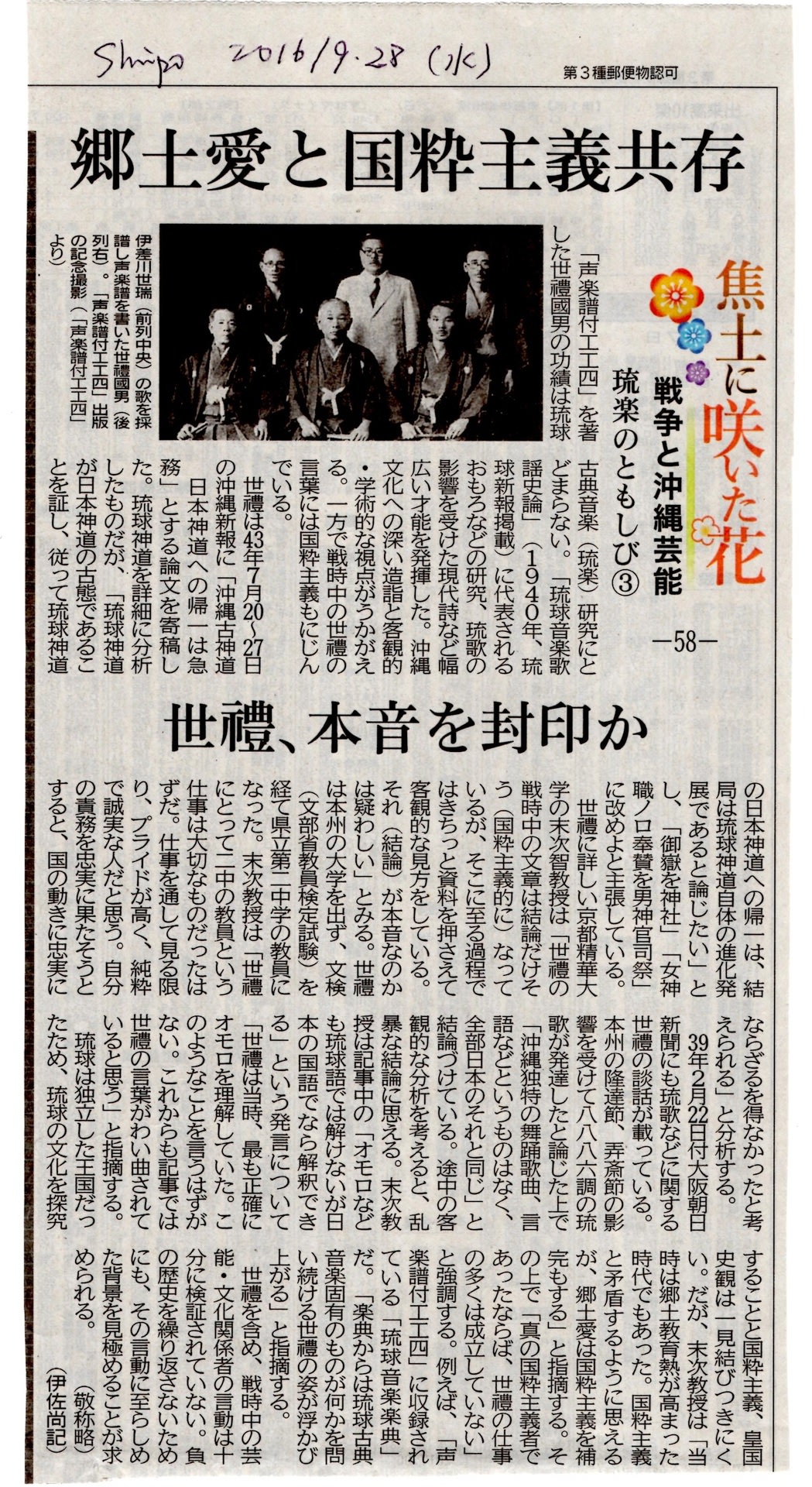
上の新聞の中身と異なりますが、近代1879年から1945年までの66年間の近代化の過程は色々な意味で深く検証されないといけないのですね。近代化(同化)、皇民化、対する異化もあったのですが、二つに引き裂かれる近代沖縄の姿が見えてきますね。
以下は戦前の芸能を見た時の所見です。(メモ)
近代以降の遊廓と遊廓で保存された芸能などに興味をもっているのですが、戦前の古典の大家にとって遊廓は古典や民謡を保存・継承・発展させるためにとても重要なトポス(場所)だったことは事実ですね。古典の大家と遊廓の「沖縄のヘタイラ」のような美らジュリとの関係も興味深いですね。世禮さんや伊差川大先生方が遊廓で尊敬され、リーダーとして処遇されたことも確かだと言えますね。以前、このブログでも紹介したのですが、世禮さんの詩集には色艶があり、佐藤惣之助さんの詩集とも異なる内からの遊廓の色合いが出ていますね。内国植民地沖縄を遊廓で堪能する惣之助さんとは異なりますが、また内からにじみ出る艶かしさです。詩論を書いてみたいです。
沖縄の古典音楽の祖といわれる湛水親方と仲島遊里ができる以前のジュリ思戸との関係の綾は、近世から近代まで琉球・沖縄の芸能の時空で象徴的な存在ですね。



















