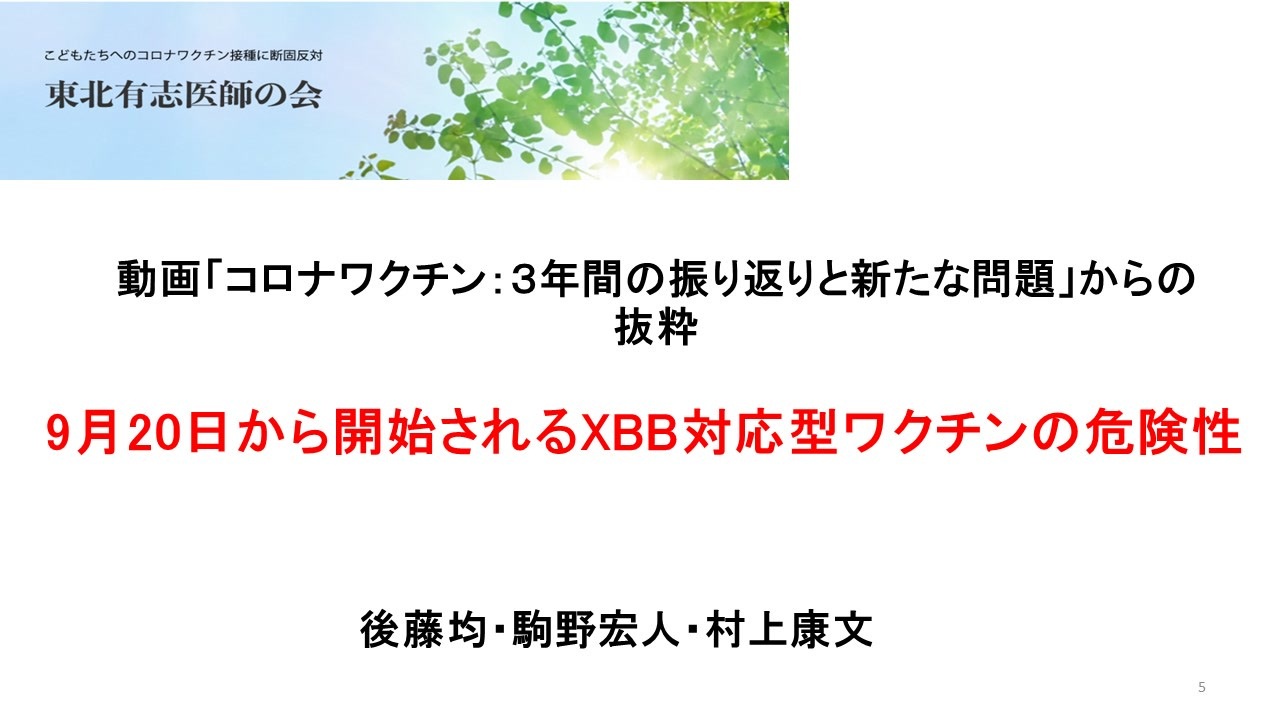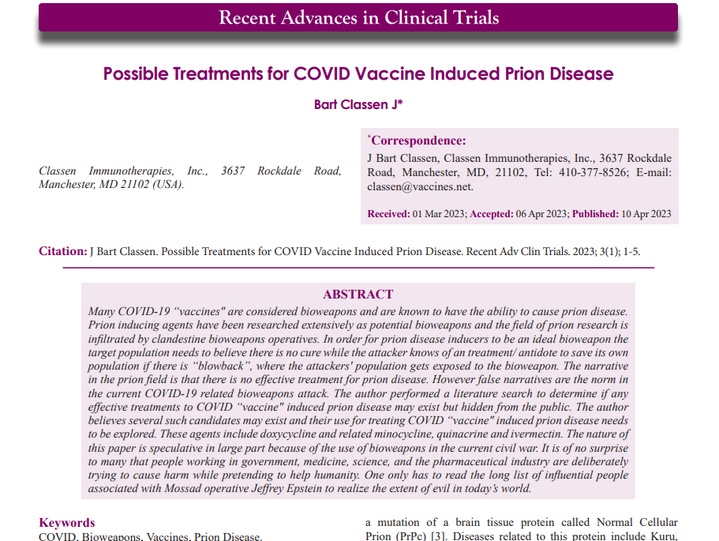mRNA型ワクチンを接種した場合には、思わぬマイナス面もあるようです。「抗体依存性感染増強(ADE)」や「抗原原罪」という作用です。これはウイルスを防ぐよりも逆にウイルスに感染しやすくなったり、また過剰な免疫機能により病いを引き起こしたり、同種のウイルスの抗体の産生を抑制してしまうようです。
1.抗体依存性感染増強(ADE)
コロナウイルス(スパイクタンパク質のあるワクチン)が抗体に結合して食細胞などに捕食されると、通常ではそこで終わるはずなのに、コロナウイルス(スパイクタンパク質があるワクチンも)はその食細胞に耐性があるため、その食細胞の受容体を使ってさらに違う細胞に感染することができるようです。
ADEには2種類のメカニズムがあるようです。
(1)トロイの木馬(感染増強、マクロファージ破壊)
コロナ(スパイクタンパク質)抗体があればあるほど(コロナワクチンを接種すればするほど)、免疫細胞のマクロファージを「トロイの木馬」として本来感染できない免疫細胞にも感染させたり、マクロファージそのものを破壊してしまう。
(2)サイトカインストーム(炎症反応)
コロナ(スパイクタンパク質)抗体とコロナウイルス(スパイクタンパク質)が結合した抗原抗体複合体により、補体が活性化され抗体抗原複合体が攻撃されます。またこの抗原抗体複合体がマクロファージなどFc受容体をもっている細胞とさらに結合すると、サイトカインが過剰に分泌されて炎症反応を引き起こすことがあります。それが続くとサイトカインストームとなり次から次へと炎症が起こり、慢性炎症につながることもあるようです。慢性炎症になると、細胞が壊れて線維化していき、臓器は機能不全になるようです。
「コロナウイルスのスパイクタンパクは人間の細胞表面の受容体ACE2に結合します。このためコロナウイルスは通常ACE2を表面にもつ細胞に感染します。コロナウイルスに対する抗体があると、抗体に取り囲まれたコロナウイルスは食細胞マクロファージに捕食されます。たいていのウイルスはここでおしまいです。コロナウイルスは食細胞に耐性で、免疫系をトロイの木馬として利用します。抗コロナ抗体があると、コロナウイルスは通常は感染できないはずの免疫細胞にも感染できるようになるのです。ADEが起こるとコロナワクチン接種者の方がコロナウイルスによりかかりやすくなり、また感染した場合ウイルスの症状が暴走しやすくなります。
抗体依存性感染増強 (ADE) には少なくとも2種類のメカニズムがあります。一つは上記のように抗体を介してマクロファージに感染する機構。ウイルスによってはマクロファージ内で増殖できます。あるいは増殖できなくともマクロファージを殺して枯渇させる事によって免疫系を暴走させるウイルスもあります。もう一つの機構は抗体と複合体を作ったウイルスが免疫系を刺激し、炎症系を暴走させる仕組み (サイトカインストーム) です。いずれの場合も抗体の存在がウイルスの感染を誘導し、免疫系の症状を暴走させます。
…ADEによる人類の大量死はウイルス学者、免疫学者から警告され続けています。こうした事態が本当に起こるかは誰にもまだ分かりません。そもそも世界中の誰も経験が無いからです。科学的、人道的に考えて、危険性が指摘されていながらのコロナワクチンの大量接種は始めるべきではありませんでした。(引用終わり)」
「抗体依存性感染増強 (Antibody-dependent enhancement, ADE) とは、ウイルス粒子と不適切な抗体とが結合すると宿主細胞への侵入が促進され、ウイルス粒子が複製される現象である。不適切な抗ウイルス抗体は、食細胞のFcγ受容体(FcγR)または補体経路を経由して目標の免疫細胞のウイルス感染を促進する。ウイルスと相互作用した後、抗体は特定の免疫細胞または補体タンパク質の一部で発現されるFcγRに、Fc領域で結合する。この相互作用は、免疫細胞によるウイルス抗体複合体の食作用を促進する。
…1960年代にRSウイルスワクチンに関して初めて報告された。 通常は、食作用後はウイルスが分解されるが、ADEの場合は逆にウイルスの複製が引き起こされ、その後免疫細胞が死滅することがある。つまり、ウイルスは免疫細胞の食作用のプロセスを「誑かし」、宿主の抗体を「トロイアの木馬」として使用する。抗体-抗原相互作用の強さが特定の閾値を下回ると、ADEが誘発される。この現象は、ウイルスの感染力と毒性(virulence)の両方につながる可能性がある。 (引用終わり)」
「サイトカイン (cytokine) は、細胞から分泌される低分子のタンパク質で生理活性物質の総称。生理活性蛋白質とも呼ばれ、細胞間相互作用に関与し周囲の細胞に影響を与える。 」
「…免疫細胞は病原体やがん細胞などの異物を体内で認識すると、IL-1やIL-6、TNF-αなどの炎症性サイトカインを誘導することによって生体の炎症(異物排除)を促し、免疫反応を活性化させます。
一方、IL-10や、TGF-βなどの抗炎症性サイトカインは、こうした免疫反応が過剰にならないよう炎症を抑制する作用があります。
しかし、ウイルスの侵入や薬剤投与などが原因で炎症性サイトカインと抗炎症性サイトカインのバランスが崩れ、炎症性サイトカインの分泌が過剰になると、次々と炎症反応が起こります。この結果、自分の細胞まで傷づけてしまう現象を「サイトカインストーム」と呼びます。
サイトカインストームが起こると、感染症の重症化や自己免疫疾患などの疾患をもたらすことがあります。また血管内凝固症候群や心筋梗塞や脳梗塞、低酸素血症などを引き起こしてしまいます。
特に高齢者や基礎疾患を持つ人に起こりやすいことがわかっており、サイトカインストームを引き起こさないためには、免疫が正常に機能していることが重要だと言えるでしょう。(引用終わり)」
「…やっかいなことにコロナウイルスではACE2を介さずに感染するFc受容体依存性感染が起こり得ます。
ウイルスに結合した抗体が、マクロファージなど免疫細胞の表面にあるFc受容体に結合すると、細胞内にウイルスが侵入します。免疫細胞がもつエンドサイトーシスという細胞外の物質を取り込む作用を利用しています。そうして取り込まれたウイルスが免疫細胞で増殖するとADEが起こります。
…スパイクタンパク質やウイルス、そして特異抗体(特定の抗原に特異的に結合する抗体)がたくさんあるとどのようなことが起きるかというと、抗体を介してスパイクタンパク質やウイルスが結合し合って、団子状態になります。これを抗原抗体複合体と呼びます。
このようにして抗体と新型コロナウイルス(またはスパイクタンパク質)が集まった抗体抗原複合体が形成されると、そこに補体という物質が集まってきて補体自身が活性化されます。活性化した補体は抗原抗原複合体にある細胞膜に穴をあけて壊します。また、抗原抗体複合体がマクロファージなどFc受容体をもっている細胞と結合すると、サイトカインが過剰に分泌され、高熱や激しい炎症反応を起こすことがあります。最悪の場合、サイトカインストーム(サイトカインの大量産生による障害)を引き起こす可能性も出てきます。(『ウイルス学者の絶望』より引用終わり)」
「免疫機能において重要な役割を担う「補体」は、血液中に含まれるタンパク質の一種であり、C1~C9までの9つの種類があります。
…補体には9種類あり、それぞれが連鎖的に活性化することで、抗原の細胞膜に小さな穴を空けて死滅させます。 (引用終わり)」
宮坂先生が上記の本で、ADEについて、「善玉抗体」・「悪玉抗体」・「役なし抗体」という用語を使って、分かりやすく説明されていました。またHLA(抗原提示分子といわれる)には個人差が大きく、その感度の違いにより善玉抗体ができやすい人や悪玉・役なし抗体ができやすい人がいるとのことです。
なお宮坂先生は、ワクチン開発でスパイクタンパク質をそのまま(「善玉・悪玉・役なし」のすべてを)ワクチン抗原としていることについて懸念を抱かれていました(この本の出版は2020年12月です)。
「 …どうして、善玉抗体、悪玉抗体、役なし抗体ができるのでしょうか?
その一つの理由は、ウイルス粒子上にそれぞれの抗体を作らせる目印(抗原)が存在するためです。図7-2は、1個の新型コロナウイルス粒子がヒトの細胞に結合するところを示しています。
【図7-2】
ウイルス粒子表面には、スパイクタンパク質という釘のような構造のほかに、われわれのからだが目印として認識するような分子がいくつかあり、ここでは、3種類のもの(●、▲、■)を示しています。●はスパイクタンパク質がウイルスの受容体であるACE2と結合する部位に存在し、一方、▲と■はスパイクタンパク質上のACE結合部位の部分に存在します。もし、●に対して抗体ができると、抗体はスパイクタンパク質とACE2に結合することを阻害することとなり、このような抗体は中和抗体(=善玉抗体)として機能します。
▲はACE2と結合部位以外の場所にあるので、この目印に対して抗体ができても、抗体はウイルスに対して何もしません。このようなウイルスは、役なし抗体ということになります。
■は特別な部位で、この部分に抗体ができると、抗原・抗体複合物が食細胞に取り込まれるようになります。
食細胞は通常、ウイルスを取り込んで殺すのですが、未熟な食細胞がウイルスを取り込むと、殺菌作用が弱く、ウイルスが増えることになります。つまり、食細胞へのウイルス感染が起こります。このような未熟な食細胞は、肺などの臓器に多数存在するので、このような抗体がいったんできると、肺を含む複数の臓器に感染が及び、感染拡大することになります。つまり、このような抗体は感染拡大を進めるものであり、悪玉抗体といえます。
…どの目印を一番認識しやすいか(=どのような抗体を作りやすいか)には、かなり個人差があるようです。
…HLAの観点から見ると、●の分解産物を結合しやすいHLAを持つ人は、●に反応しやすいので、中和抗体を作りやすい人であり、感染から快復しやすい人である可能性があります。一方、▲や■の分解産物を結合しやすいHLAを持つ人はは、新型コロナウイルスに対する防御がうまくできず、抗体ができても病気から快復せずに、特に■に対して抗体を作る人は重症化しやすいということになります。
…私の眼からすると、ウイルス粒子を丸ごと使うのでなく、特定の抗原を使う方が良いと思われます。というのは、●を主な抗原としたときには、ワクチン投与によりもっぱら中和抗体ができる可能性が高いからです。一方、間違って■を抗原として選ぶと、悪玉抗体も同時にできることになります。…心配なのは、現在開発されつつあるほとんどのワクチンがもっぱらスパイクタンパク質全体をワクチン抗原としていることです。『新型コロナ7つの謎』より引用」
サイトカインなどにより炎症が慢性化すると、細胞は線維化して臓器は機能不全に陥ってしまうようです。
「…炎症が続いた組織では細胞が死に始め、そのために組織の細胞構造が壊れ、そこに周囲の結合組織から繊維成分が入り込んできて組織の柔軟性が失われ、硬くなります。これが線維化とよばれる現象です。つまり正常な細胞が次第に減って繊維成分で置き換えられていってしまうのです。こうなると組織の機能は次第に低下し、元に戻りにくくなってしまいます。
…炎症があまり長く続くと、臓器の機能が低下し始め、やがては大変な事態へとつながるのです。(『免疫と「病」の科学』より)」
2.抗原原罪
今一つ分からないのですが、抗原原罪とは、いったん作ってしまった抗体を有効活用するために、新たなウイルスが感染しても、すでに出来上がったウイルスの抗体のアミノ酸配列や立体部位の一部に共通部分があると(すでに感染したウイルスの部分に似ていると)、資源を節約するために、その一部分が似ている新たなウイルスに完全合致した抗体は作られない(出来上がったもので済ませる?)という訳でしょうか?
「免疫系はウイルスや細菌などの病原体に遭遇した際に、免疫記憶を優先的に利用します。例えばウイルス感染の場合、最初に出会ったウイルス株の印象がいつまでも強く免疫系の記憶に残り、その後に同ウイルスの変異株に感染した際にも変異株に特異的な抗体を作らずに以前の株に対しての抗体ばかりを産生してしまうという事が起きるのです。このように免疫系が病原体に最初に出会った時の記憶に固執し、変異株感染時に柔軟で効果的な反応ができなくなってしまう現象が「抗原原罪 (original antigenic sin)」です。病原体の最初の変異体の感染時に誘導された抗体やT細胞は、レパートリーフリーズと呼ばれる抗原原罪の対象となります。抗原原罪はウイルスや細菌のような病原体だけではなくワクチンに対しても起こります。
…ウイルス感染後、ウイルス抗原に特異的な抗体に加えて長寿命の記憶B細胞が生成され、抗体と記憶B細胞の両者が感染防御に働きます。ウイルス再感染の際には、抗ウイルス抗体を産生する記憶B細胞が優先的に再活性化されるため、ナイーブB細胞 (抗原と結合し活性化された事がないB細胞) が新規抗原に反応するよりもはるかに速く感染に対応する事ができます。一方、ウイルスのタンパクが突然変異によって変化する「抗原ドリフト」が起これば、ウイルスは免疫記憶から逃れる事ができます。突然変異はランダムですが、免疫系をすり抜ける変異株が自然選択によって競争を生き残りやすくなるからです。しかし記憶B細胞が産生する抗体は、変異株で変化したエピトープへの結合が不十分な上に、変異株に特異的なナイーブB細胞の活性化を阻害します。その結果、変異株に対する免疫反応が不十分となり、感染症の重症化にも繋がるのです。
…抗原抗体複合体によってナイーブB細胞上のIgM抗体とFc受容体 (FcγRⅡb) が架橋される事によりナイーブB細胞の活性化が抑制される事が抗原原罪の作用機序です。(引用終わり)」
「抗原原罪(こうげんげんざい original antigenic sin)とは、一度インフルエンザに感染した人がその時のインフルエンザ株の持っていたエピトープ以外のエピトープに対し、その免疫原性に関わらず反応できなくなっている現象のこと。この現象は、二次反応におけるナイーブリンパ球と記憶リンパ球との相互作用によって説明される。
…免疫系の正常な働きによって抗体やエフェクターT細胞が獲得されると、それらは同じ抗原に対して反応するナイーブリンパ球が活性化されるのを抑制する。
…以前に感染したインフルエンザ株(A株とする)と一部同様のエピトープを持つインフルエンザ株(B株)に感染したとき、A、B共通のエピトープに対する抗体は迅速に産生されるものの、Bには存在するがAには存在しないエピトープに対する抗体は対応するナイーブB細胞が抑制されるので、産生される抗体の量が著しく低くなる現象のことである。Aと同じエピトープを持たない株(C株)に感染したときはこのような現象は見られない。 (引用終わり)」
「エピトープ(英: epitope)は、抗原決定基(英: antigenic determinant)とも呼ばれ、免疫系、特に抗体、B細胞、T細胞によって認識される抗原の一部である。抗体は、病原微生物や高分子物質などの抗原と結合する際、その全体を認識するわけではなく、抗原の比較的小さな特定の部分のみを認識して結合する。この抗体結合部位を抗原のエピトープと呼ぶ。エピトープは抗原性のための最小単位である。 特定抗原の侵入により生成された抗体は,その抗原と同一あるいは類似のエピトープを持つものとしか反応しない。通常、複数のエピトープが1つの抗原に含まれている。エピトープに結合する抗体の部分はパラトープ(英: paratope)と呼ばれる。
…タンパク質抗原のエピトープは、その構造やパラトープとの相互作用によって、配座エピトープ(英語版)と線状エピトープ(英語版)の2つに分類される。配座エピトープと線状エピトープは、そのエピトープが採る三次元立体配座(関与するエピトープ残基の表面の特徴と、抗原の他のセグメントの形状または三次構造によって決定される)に基づいてパラトープと相互作用する。配座エピトープは、不連続なアミノ酸残基の相互作用によって決まる三次元的立体配座によって形成される。対照的に、線状エピトープは、連続したアミノ酸残基の相互作用によって決まる三次元的立体配座によって形成される。 (引用終わり)」
このエピトーブというのが抗体が認識する「記号コード」になるようです。
「T細胞(ティーさいぼう、英: T cell, T lymphocyte)とは、リンパ球の一種で、骨髄で産生された前駆細胞が胸腺での選択を経て分化成熟したもの。細胞表面に特徴的なT細胞受容体(T cell receptor;TCR)を有している。末梢血中のリンパ球の70〜80%を占める。名前の『T』は胸腺を意味するThymusに由来する。
…末梢に存在するほとんどの成熟したT細胞は、細胞表面のマーカー分子としてCD4かCD8のどちらかを発現している。CD4を発現したT細胞は他のT細胞の機能発現を誘導したりB細胞の分化成熟、抗体産生を誘導したりするヘルパーT細胞として機能する。このCD4陽性T細胞は、後天性免疫不全症候群(AIDS)の病原ウイルスであるヒト免疫不全ウイルス(HIV)や、成人T細胞白血病(ATL)の病原ウイルスであるヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV-1)が感染する細胞である。CD8陽性T細胞はウイルス感染細胞などを破壊するCTL(キラーT細胞)として機能する。(引用終わり)」