今日(15日)の夕刊に,病院開設を申請した医師に対して県知事がした病院開設中止勧告の取消訴訟について,最高裁が,訴えを門前払いした一,二審判決を破棄して,審理を地方裁判所に差し戻し,実質審理をするように命じたという判決をしたことが報じられている。
この訴訟の対象となった中止勧告とは,病院の病床数については,都道府県の定める地域医療計画(医療法30条の3)というもので,その上限が設定されており,これを上回る病床数となる病院の解説申請がされたときには,県知事が,その病院の開設を中止するように勧告するというものである(医療法30条の7)。
それで,話が厄介なのは,この中止勧告に従わなかったからといって,病院の開設が不許可にされるわけではなく(病院の開設に都道府県知事の許可が必要なことは医療法7条),病院の人員と施設についての基準(医療法21条等)を満たせば,病院の開設は許可されることになる,というところにある。すなわち,中止勧告に従わなかったからといって,病院の開設ができなくなるわけではないのであり,その意味では,中止勧告によって,開設を申請した申請人には何の不利益もないことになる。
これまでの下級審判決は,そこのところをとらえて,申請人に法律的な不利益を与えない,行政指導的な勧告については,裁判で争うことはできないとしてきていた。これは,処分性の問題といって,行政の相手方である私人の権利義務に法律的な影響を及ぼさない行政の行為は,裁判の対象にはできないというのは,行政訴訟の確固たる原則であった。
しかし,この中止勧告については,健康保険が使えるいわゆる「保険医療機関」の指定(健康保険法63条3項1号)の際に,中止勧告に従っていないときは,保険医療機関の指定を受けられないという結果となるもので(健康保険法65条4項2号),病院の側としては,相当の不利益が予想されることになる。健康保険が使えない病院,すなわち自由診療しか受けてくれない病院というのは,患者側から見てとても使いにくい,はっきり言ってそんな病院には余程の金持ちしか行かないということになり,病院として成り立たなくなる。今回の訴訟では,この点をどう考えるかが問題となったのである。
これまでの下級審判決は,中止勧告を受けた段階では,まだ病院は設置されておらず,保険医療機関の指定の申請も出ていないのだから,それは健康保険法の問題で,保険医療機関の指定の申請が却下されてから,訴訟を起こせばよいという考え方に立っていた。たしかに,病院を開設しても,保険医療機関の指定を受けずに運営することもあり得ることで,そんなのは,紛争になったことがはっきりしてから訴訟に乗せればいい,それより早いところで訴訟になるのは,場合により審理の無駄だというのも,一つの考え方ではあるし,それがどちらかといえばオーソドックスな考え方であったように思う。
しかし,今回の最高裁判決は,中止勧告と保険医療機関の指定が,実際上密接にリンクしているという「健康保険法の規定の内容やその運用の実情」を重く見て,病院の開設の段階で,中止勧告の適法性を争わせようとしたものということができる。
それは確かに,病院の建物ができて,スタッフも揃ったところで,保険医療機関の指定拒否処分を争うというのは,とんでもない無駄が生じる。そういう意味で,今回の最高裁判決は,結果の現実問題としての妥当性を考慮したと評価することができると思われる。

この訴訟の対象となった中止勧告とは,病院の病床数については,都道府県の定める地域医療計画(医療法30条の3)というもので,その上限が設定されており,これを上回る病床数となる病院の解説申請がされたときには,県知事が,その病院の開設を中止するように勧告するというものである(医療法30条の7)。
それで,話が厄介なのは,この中止勧告に従わなかったからといって,病院の開設が不許可にされるわけではなく(病院の開設に都道府県知事の許可が必要なことは医療法7条),病院の人員と施設についての基準(医療法21条等)を満たせば,病院の開設は許可されることになる,というところにある。すなわち,中止勧告に従わなかったからといって,病院の開設ができなくなるわけではないのであり,その意味では,中止勧告によって,開設を申請した申請人には何の不利益もないことになる。
これまでの下級審判決は,そこのところをとらえて,申請人に法律的な不利益を与えない,行政指導的な勧告については,裁判で争うことはできないとしてきていた。これは,処分性の問題といって,行政の相手方である私人の権利義務に法律的な影響を及ぼさない行政の行為は,裁判の対象にはできないというのは,行政訴訟の確固たる原則であった。
しかし,この中止勧告については,健康保険が使えるいわゆる「保険医療機関」の指定(健康保険法63条3項1号)の際に,中止勧告に従っていないときは,保険医療機関の指定を受けられないという結果となるもので(健康保険法65条4項2号),病院の側としては,相当の不利益が予想されることになる。健康保険が使えない病院,すなわち自由診療しか受けてくれない病院というのは,患者側から見てとても使いにくい,はっきり言ってそんな病院には余程の金持ちしか行かないということになり,病院として成り立たなくなる。今回の訴訟では,この点をどう考えるかが問題となったのである。
これまでの下級審判決は,中止勧告を受けた段階では,まだ病院は設置されておらず,保険医療機関の指定の申請も出ていないのだから,それは健康保険法の問題で,保険医療機関の指定の申請が却下されてから,訴訟を起こせばよいという考え方に立っていた。たしかに,病院を開設しても,保険医療機関の指定を受けずに運営することもあり得ることで,そんなのは,紛争になったことがはっきりしてから訴訟に乗せればいい,それより早いところで訴訟になるのは,場合により審理の無駄だというのも,一つの考え方ではあるし,それがどちらかといえばオーソドックスな考え方であったように思う。
しかし,今回の最高裁判決は,中止勧告と保険医療機関の指定が,実際上密接にリンクしているという「健康保険法の規定の内容やその運用の実情」を重く見て,病院の開設の段階で,中止勧告の適法性を争わせようとしたものということができる。
それは確かに,病院の建物ができて,スタッフも揃ったところで,保険医療機関の指定拒否処分を争うというのは,とんでもない無駄が生じる。そういう意味で,今回の最高裁判決は,結果の現実問題としての妥当性を考慮したと評価することができると思われる。











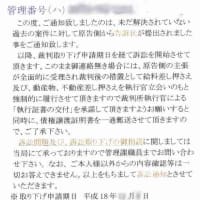
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます