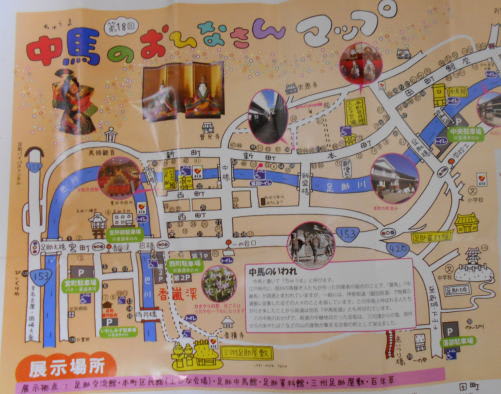足助の町並みを散策したあとは、昼食をとり、いよいよ飯森山城に登りました。

駐車場からみた飯森山城。この山の麓が有名な紅葉の名所香嵐渓と呼ばれるところです。
昼食をとったお店で「ここから飯盛山に登れますか。」と聞いたところ、「すぐそこですよ。私も小さい頃はよく登りましたよ。今はすっかり、道がよくなって、登りやすくなりましたよ。」と、教えていただけました。
案内版
なるほど、お店のすぐ前が登り口でした。

登り口の脇にあった案内板。しかし、かろうじて題字の『飯森山城』が判読できるだけで、本文には何が書いてあるのか、さっぱり分かりませんでした。
太子堂
道は石が敷いてありました。しかし、かなりの急勾配で、途中で足が痛くなるほどでした。登り始めるとすぐに太子堂がありました。説明を読むと太子講の人たちが造ったとありました。足助の町に太子講の信仰があったことがわかりました。

太子堂
物見櫓の跡?
急な勾配の石の坂を登っていきますと、やがて道は土の道となりました。そして中腹になにやら郭らしき平地がありました。

ここに物見櫓のようなものがあったのではないでしょうか。ここから木が無ければ足助の町が一望できます。
虎口?
登り始めて20分ぐらいで、ようやく虎口らしきものが見えました。

虎口らしきもの
郭?
その上は郭らしき平地になっていました。

郭らしき平地。頂上を1郭とすれば3段目に当たります。
さらにその上に、頂上から2段目の郭らしき平地がありました。

主郭
主郭に登ってみると、残念ながら説明板が無く確かめることは出来ませんでした。代わりに東屋がありました。

頂上に設けられた東屋。外国の方たちによって建てられたとの説明がありました。
ということで、飯森山城は、櫓台、虎口、郭など遺構らしきものはありましたが、確かめることは出来ませんでした。これもきちんと調べてみたいと思います。

駐車場からみた飯森山城。この山の麓が有名な紅葉の名所香嵐渓と呼ばれるところです。
昼食をとったお店で「ここから飯盛山に登れますか。」と聞いたところ、「すぐそこですよ。私も小さい頃はよく登りましたよ。今はすっかり、道がよくなって、登りやすくなりましたよ。」と、教えていただけました。
案内版
なるほど、お店のすぐ前が登り口でした。

登り口の脇にあった案内板。しかし、かろうじて題字の『飯森山城』が判読できるだけで、本文には何が書いてあるのか、さっぱり分かりませんでした。
太子堂
道は石が敷いてありました。しかし、かなりの急勾配で、途中で足が痛くなるほどでした。登り始めるとすぐに太子堂がありました。説明を読むと太子講の人たちが造ったとありました。足助の町に太子講の信仰があったことがわかりました。

太子堂
物見櫓の跡?
急な勾配の石の坂を登っていきますと、やがて道は土の道となりました。そして中腹になにやら郭らしき平地がありました。

ここに物見櫓のようなものがあったのではないでしょうか。ここから木が無ければ足助の町が一望できます。
虎口?
登り始めて20分ぐらいで、ようやく虎口らしきものが見えました。

虎口らしきもの
郭?
その上は郭らしき平地になっていました。

郭らしき平地。頂上を1郭とすれば3段目に当たります。
さらにその上に、頂上から2段目の郭らしき平地がありました。

主郭
主郭に登ってみると、残念ながら説明板が無く確かめることは出来ませんでした。代わりに東屋がありました。

頂上に設けられた東屋。外国の方たちによって建てられたとの説明がありました。
ということで、飯森山城は、櫓台、虎口、郭など遺構らしきものはありましたが、確かめることは出来ませんでした。これもきちんと調べてみたいと思います。