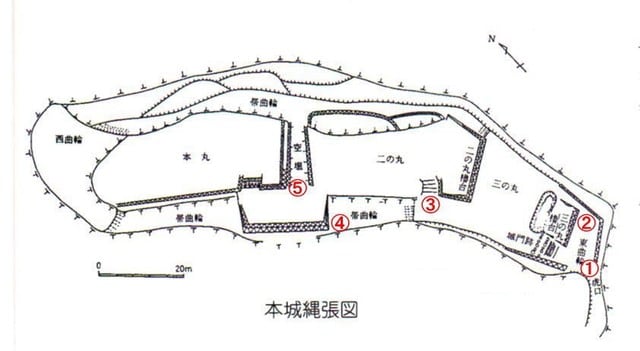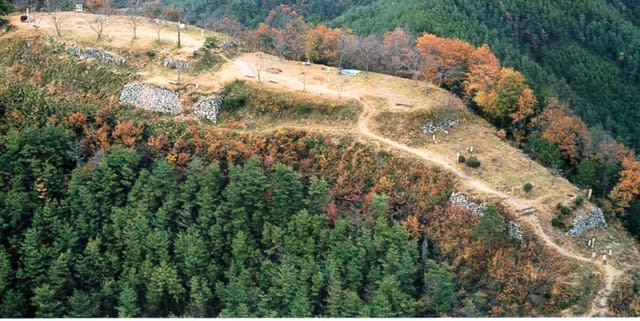黒井城を降りたら次は、興禅寺です。
興禅寺は、黒井城を落とした明智光秀の家臣斎藤利光が館を構えた場所です。
ここで春日局が生まれたとして、有名になりました。NHK大河ドラマ「春日局」(大原麗子主演)のときは、多くの観光客が訪れたと旅館の人もおっしゃっていました。

NHK大河ドラマ「春日局」の大原麗子さん

七間堀と高石垣
まず目に入るのは、立派な石垣と堀です。「七間堀」というそうです。
石垣としては、中央部石橋付近が野面積みでその他は切り込みはぎの工法で造られているそうです。いかにも元武士の館という感じがしました。
お福(春日局)関連の「史跡」がありました。

お福産湯の井戸

お福腰かけ石
黒井城関連では、寛永3年に黒井城の門材を使って建てたといわれる惣門がありました。

惣門
春日町と春日局について、春日の出だから春日局と言われたのか、春日局が出たからこの辺りを春日というのか、どちらが先だろうと話し合いながら見学しました。もしかしたら、ただの偶然かもしれませんが、どっちでしょうか。
興禅寺は、黒井城を落とした明智光秀の家臣斎藤利光が館を構えた場所です。
ここで春日局が生まれたとして、有名になりました。NHK大河ドラマ「春日局」(大原麗子主演)のときは、多くの観光客が訪れたと旅館の人もおっしゃっていました。

NHK大河ドラマ「春日局」の大原麗子さん

七間堀と高石垣
まず目に入るのは、立派な石垣と堀です。「七間堀」というそうです。
石垣としては、中央部石橋付近が野面積みでその他は切り込みはぎの工法で造られているそうです。いかにも元武士の館という感じがしました。
お福(春日局)関連の「史跡」がありました。

お福産湯の井戸

お福腰かけ石
黒井城関連では、寛永3年に黒井城の門材を使って建てたといわれる惣門がありました。

惣門
春日町と春日局について、春日の出だから春日局と言われたのか、春日局が出たからこの辺りを春日というのか、どちらが先だろうと話し合いながら見学しました。もしかしたら、ただの偶然かもしれませんが、どっちでしょうか。