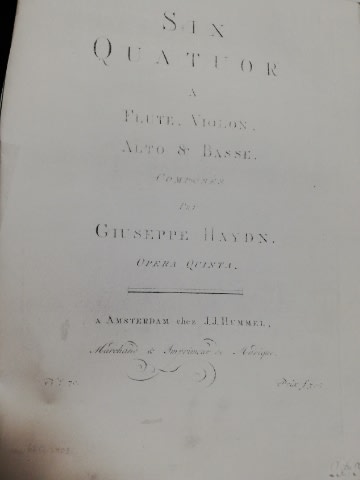京都、今出川大宮のF先生のレッスンに伺いました。
モーツァルト四重奏Adurを見て頂きました。
カルテットの前に、レッスンしていただくはずでしたが、都合で前後してしまいました。
でも大丈夫です。
6月にAdurをもう一度仕上げるのとGdurを合わせます。
今ではl先生コロナでお休みなので、高山セミナーで出会っていたⅠ先生のお弟子さんのF先生にお願いしました。
前回Ddurで構え方を変更。
そして、今回Adur。
Adurは他の四重奏 と違って 弦楽器がいい音のする ポジション(音域)で フルートも吹きます。
音を作る 協奏曲のような音でなく もう少し穏やかで包み込むように。
fのタンギングは 弱くお腹で切る。
pは舌で切りましょう。
モーツァルトの音
全般的に言えることですがタンギングは息できるように エアーアタック という感じで 音はたくさんすぎないように。
装飾音符は 八分音符のように吹かないで ポコアクセント と思ってください。
ロングトーンはふわっと空気感を大事に バイオリンをよく聞いて
メヌエットは一拍目が大事です。
明るく威張った感じ で はじめの アフタクト は 八分音符で練習して その時のタンギングのままで 付点音符 十六分音符を吹きましょう。
ターンの下の音はナチュラルで。
最後の楽章 ロンド は モーツァルトによく出てくる2拍目から始まるロンドです。
2拍目の頭の音を大事に吹きましょう。
タンギングは息を多い目に明るく。
しばらく レッスンに入ってなかったので大変刺激になりました。
目が覚めた感じです。
まだまだやり残していることはあります。
頑張ります。