ときどき、「東大数学の解き方」で訪れる方がいます。
まずは、難易度です。
2009年度の東大前期の理系数学の①~⑤の解答を掲載しました。
⑥もあるのですが、割愛を致します。
難易度は、標準問題の融合問題が多いということが特徴としてあげられます。
融合問題が多いということは、苦手な分野を作ると点数が取れないということです。
まんべんなく、どの分野の標準問題をこなして、融合問題に対応する準備が必要であります。
解き方は、標準問題を解けるようにすることです。
そうすると、東大前期の数学は解けると思います。
ときどき、難問が出題されますが、標準問題を解ければ、自然と解けるようになると思います。
なぜ、融合問題が多いのか?
大学の数学は、より抽象的な数学になります。
抽象的な数学は、考え方、具体的から抽象的へなど、広い視野が求められます。
例えば、ε-δ論法(解析学)、環(代数学)などがそうです。
ε-δ論法は、極限についてを厳密に取り扱う論法です。 大きい、小さいの概念が中途半端に考えているのかが分かります。
環は、計算法則についての定義からさまざまな定理を導きだしています。 5次方程式には一般解の公式が存在しないのも、環⇒体⇒ガロア理論より証明されています。
抽象数学を高校生にはそのまま出題が出来ないので、融合問題として出題していると思われます。
抽象数学が理解が出来れば、必ずしも解ける訳ではありませんが、基礎学力を問うには、融合問題が適していると思われます。
※ε-δ論法、環などは、高校の範囲を超えるので、今は知る必要はないです。
まずは、難易度です。
2009年度の東大前期の理系数学の①~⑤の解答を掲載しました。
⑥もあるのですが、割愛を致します。
難易度は、標準問題の融合問題が多いということが特徴としてあげられます。
融合問題が多いということは、苦手な分野を作ると点数が取れないということです。
まんべんなく、どの分野の標準問題をこなして、融合問題に対応する準備が必要であります。
解き方は、標準問題を解けるようにすることです。
そうすると、東大前期の数学は解けると思います。
ときどき、難問が出題されますが、標準問題を解ければ、自然と解けるようになると思います。
なぜ、融合問題が多いのか?
大学の数学は、より抽象的な数学になります。
抽象的な数学は、考え方、具体的から抽象的へなど、広い視野が求められます。
例えば、ε-δ論法(解析学)、環(代数学)などがそうです。
ε-δ論法は、極限についてを厳密に取り扱う論法です。 大きい、小さいの概念が中途半端に考えているのかが分かります。
環は、計算法則についての定義からさまざまな定理を導きだしています。 5次方程式には一般解の公式が存在しないのも、環⇒体⇒ガロア理論より証明されています。
抽象数学を高校生にはそのまま出題が出来ないので、融合問題として出題していると思われます。
抽象数学が理解が出来れば、必ずしも解ける訳ではありませんが、基礎学力を問うには、融合問題が適していると思われます。
※ε-δ論法、環などは、高校の範囲を超えるので、今は知る必要はないです。










![nC[n/2] / (2^n)の極限値](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/68/2b/6b4fd29f1a2b270f66bf26b2bcf261f8.jpg)
![nC[n/2] / (2^n)の極限値](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/cd/85fa12c15d78459fe2ed64771b449dac.jpg)
![nC[n/2] / (2^n)の極限値](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/24/7f/8133232db1841611e6bfdf75e1e6abde.jpg)
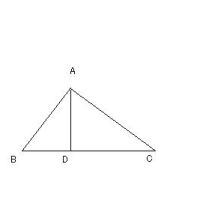
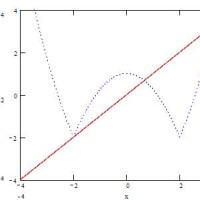
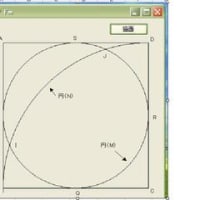
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます