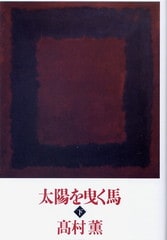去年の暮れに浜田晋先生は亡くなられていた。
東京の上野で精神科診療所を開業して、下町の精神科医を33年勤められた後引退しておられた。
「はじめに」によると、この書は真宗大谷派の首都圏広報誌「サンガ」に、1992年から連載されているものからまとめたものである。
「はじめに」から抜粋。
< そして、今、私83歳。私自身も老いた。
その間、わが国は世界に例をみない高齢化社会をむかえた。日本という国家自体も老いた。
したがって「老い」の問題は、医療界のみならず、すべての日本人の最大課題となった。
ところが肝腎の老人精神医学は混迷の中にある。急激な時代の変化に、医療も看護も介護も「社会」もついていけていない。そこは百鬼夜行の世界といってよい。
私は危機感をもっている。その想いが本書の底を流れていよう。>
「ぼけ」と「痴呆」の間から抜粋。
<人は生まれ、育ち、働き、老い、そして時にぼけ、そして死ぬ。それはしごくあたりまえのことなのである。>
常に「人間とはなにか」ということを考え続けておられた方だと思う。
東京の上野で精神科診療所を開業して、下町の精神科医を33年勤められた後引退しておられた。
「はじめに」によると、この書は真宗大谷派の首都圏広報誌「サンガ」に、1992年から連載されているものからまとめたものである。
「はじめに」から抜粋。
< そして、今、私83歳。私自身も老いた。
その間、わが国は世界に例をみない高齢化社会をむかえた。日本という国家自体も老いた。
したがって「老い」の問題は、医療界のみならず、すべての日本人の最大課題となった。
ところが肝腎の老人精神医学は混迷の中にある。急激な時代の変化に、医療も看護も介護も「社会」もついていけていない。そこは百鬼夜行の世界といってよい。
私は危機感をもっている。その想いが本書の底を流れていよう。>
「ぼけ」と「痴呆」の間から抜粋。
<人は生まれ、育ち、働き、老い、そして時にぼけ、そして死ぬ。それはしごくあたりまえのことなのである。>
常に「人間とはなにか」ということを考え続けておられた方だと思う。