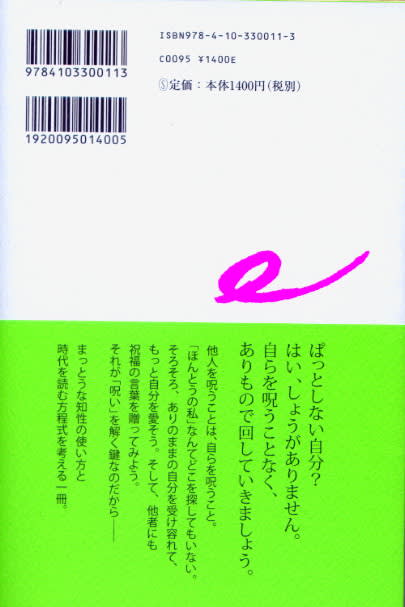やはり新聞の書評を読んで買った本だけど、とても興味深い内容だった。
この本は、(訳者あとがき)に書かれているように<急性の細菌性髄膜炎で七日間昏睡に陥り、大脳新皮質が機能していなかった間に脳から独立した意識がきわめて深い体験をし、死後の世界が存在する科学的根拠を得たという話>である。
<著者の言葉によれば、臨死体験をすることによってわかったのは、「意識こそが、存在のすべてにかかわる唯一の実体」であり、「(中略)物質世界とその時空は巧みに組み立てられた幻想であって、そのおおもとにあるものは、神聖なひとつの意識である。意識は脳の活動に伴う現象ではない。物質世界とそこで見えているものの上位にあり、外から物質世界を支える、それよりはるかに豊かなもの」だった。(訳者あとがき)>
エベン・アレグザンダー氏の証言はとても魅力的で、信じられると感じて、嬉しかった。
この本は、(訳者あとがき)に書かれているように<急性の細菌性髄膜炎で七日間昏睡に陥り、大脳新皮質が機能していなかった間に脳から独立した意識がきわめて深い体験をし、死後の世界が存在する科学的根拠を得たという話>である。
<著者の言葉によれば、臨死体験をすることによってわかったのは、「意識こそが、存在のすべてにかかわる唯一の実体」であり、「(中略)物質世界とその時空は巧みに組み立てられた幻想であって、そのおおもとにあるものは、神聖なひとつの意識である。意識は脳の活動に伴う現象ではない。物質世界とそこで見えているものの上位にあり、外から物質世界を支える、それよりはるかに豊かなもの」だった。(訳者あとがき)>
エベン・アレグザンダー氏の証言はとても魅力的で、信じられると感じて、嬉しかった。