NHK 海外ネットワーク8月28日 ブログ上再録
道傳愛子キャスター
8月18日から中国とロシアは初めての合同軍事演習を行った。
新聞報道はファイブ☆スターさんからどうぞ。
参加したのは中国側8000人とロシア側1800人
ロシアの有力紙によると費用は大半を中国が負担したと言う。
この情報はチナヲチさんにも記述がありました。
CCTVの番組から
「中露合同軍は制海権、制空権を握った後、上陸作戦を敢行、猛烈な速さで上陸を決行し、戦車の攻撃とヘリコプターでの空爆を行った。」
中国は台湾への攻撃を想定していると言う見方がある。
「連合軍が攻撃をはじめた。宣伝ビラを入れた砲弾を打ち、敵に心理的打撃を与える。」「あらゆる方向から敵を追い込み殲滅する。作戦は成功した。」
司令部には中国の曹剛川、ロシアのイワノフ両国防相。
イワノフ国防相曰く「中露の軍人が実戦形式で訓練できることをうれしく思う。」
1969年中ソは小さな島を巡って軍事衝突、しかし冷戦後は関係は改善、今では中国軍がロシア軍から上陸作戦の手ほどきを受けていると言う専門かもいる。
2大国の合同演習は国際社会に波紋を投げかけた。しかし両国は第三国を牽制する意図なく国際テロや分離独立の動きに共同で対応するものであるとした。
中国人民解放軍 梁光烈総参謀長曰く
「演習は第三国に向けられたものでも第三国の利益に関わるものでもない。いかなる国にも脅威を与えないはずである。」
今回の軍事演習はまず先立って18日にウラジオストックで図上演習が行われた。
その後、23日から山東半島で実戦的、上陸、海上封鎖訓練が行われた。
中国のねらいを北京の奥谷龍太特派員に聞く
山東半島で演習が行われたのは中国側の強い意向、台湾での有事を想定してるものと思われる。台湾の独立阻止には武力行使も辞さないとしてきた中国は、アメリカの介入にも対抗できる抑止力を持つことを目指してきた。
上陸作戦、海上封鎖の訓練が行われ、揚陸艦や水陸両用戦車も投入された。
台湾は反発しているが、ゆるぎない中国の強い意思を示し、ロシアとの連携により米に対抗する力の誇示が目的と思われる。
ロシアのねらいがウラジオストックからレポートされる。
プーチン政権の裏には激しく変動する中央アジア情勢がある。4年前から中央アジアには同時多発テロを機として米軍が駐留、今年になって相次いで旧ソ連時代からの政権が崩壊、民主化の波が押し寄せてきたことにロシアは脅威を感じてきた。
ロシアは中国と共に中央アジアから米軍の撤退を求め、関係を強めてきた。
8月16日モスクワ航空ショーに最新の兵器が並んだ。ロシアにとって中国は最大の武器の輸出先、プーチン大統領は自らパフォーマンスで売込みに懸命であった。
プーチン大統領曰く、
「我が軍は航空宇宙分野で最先端、ロシアは伝統的に高い知性が集まり、ロシアの航空機は実に手ごろな価格である。」
65Km/hで障害物を飛び越えるいわゆる「飛ぶ戦車」、エンジン音が静かで敵に探知されないディーゼル潜水艦などが中国に売られている。
ロシアの武器売却51億ドルのうち中国向けは23億ドルにものぼった。
ロシア軍バルエフスキー参謀総長曰く
「ロシア製兵器を仲間である人民解放軍に買ってもらいたい。ロシアの兵器は信頼性が高く修理や改良が簡単だ。」
ウラジオストックの権平恒志特派員がレポートする。
軍需産業を建て直し、強いロシアを復活させたいプーチン政権、アメリカを牽制し、戦略的関係を高めることで中国と利害が一致した。
道傳キャスター 「中国にとってロシアとの結びつきを強めるねらいは?」
奥谷特派員 アメリカ一極支配を警戒していることはロシアと一致している。今回演習にはSCO(上海協力機構)に加盟する中央アジア諸国からの国防相がオブザーバーとして招かれた。中国は中央アジアで米国主導の民主化が進み、西部国境の新疆ウイグル自治区で分離独立運動を活気付けることに神経を尖らせている。
さらに経済成長に伴い、エネルギー資源を必要としている為、天然資源が豊富な中央アジアでアメリカの影響力が大きくなることを防ぎたいという思惑がある。
東は台湾の独立を阻み、西では中央アジアとの結びつきを深めたい。ロシアとの連繋にはアメリカを牽制するねらいが込められている。
米国は今回中露合同軍事演習をどう見ているか。
ブルックス研究所、マイケル・オハンロン上級研究員に聞く。
道傳「軍事演習を通じて中国はアメリカにどんなメッセージを送ろうとしたのか?」
オハンロン
演習それ自体は確かに心配するほどのものではない。しかし地政学的には重要である。
中露がアメリカおよびその同盟国に伝えようとしていることのひとつは、両国が「対テロ戦争」や国際社会をリードする手法をめぐってアメリカに不満をもっているということ。
中露は互いの関係強化によって米に対抗していくことを言おうとしている。とりわけ台湾問題をめぐって中国は「アメリカが自分の思っているほどには周辺諸国から支持を得ていない」というメッセージを発しつづけている。
今の世界情勢でアメリカの影響力に対抗できる仲間を持ったことを中国は喜んでいる。
道傳「国際的な政治状況の中で米は中国の軍事力増強にどうかかわっていくのか。」
オハンロン
今の中国は非常に早いペースで軍事力増強を進めている。おそらく数年前の予測を上回る早さである。もちろん軍事力そのものも懸念すべき材料だが、もっと心配すべきなのは軍事力の強化によって中国が自分には台湾攻撃の能力があると思い込んでしまう恐れがあることである。たとえアメリカが台湾問題に介入しに来ても排除できると思うかもしれないし、在日米軍基地を攻撃して日本がアメリカを支援できないように威嚇することも可能だと考えるかもしれない。
あるいは去年、中国の潜水艦が日本の領海に入り込んだ時のように中国がその力を見せつけるような行動に走ってしまう恐れもある。中国の軍事力増強はまずそれ自体が脅威である。さらに中国の指導者が「攻勢に出ても他の国から反撃されるような重大な結果を招くようなことはない」と思い込む懸念もある。このように中国の軍事力の近代化には常に危険と懸念がつきまとう。
道傳「アジア全体の軍事力バランスで中国の軍事力を見る場合、アメリカの見方としては中国がある種の不安定要因となるか?」
オハンロン
中国は必ずしも地域を不安定化するわけではない。しかし中国は我々(米国)を非常に神経質にさせる。米国は貿易と投資によって中国の成長を助けているが、そうした支援こそが中国の脅威を高めてしまうという意見がある。一方で中国がより民主国家であるよう、促していかなければならない。「そうなればたとえ力があっても周辺諸国を脅かそうとはしないだろう。」という考え方がある。
中国に対するアメリカの見方は相矛盾して複雑でありひとことでまとめるのが難しい。中国は同盟国ではないが、敵国でもない。今は敵というよりむしろ友人だがそれもいつまで続くかわからない。だからこそアメリカは将来に備え、さまざまな選択肢を持っておこうとしている。
道傳愛子キャスター
8月18日から中国とロシアは初めての合同軍事演習を行った。
新聞報道はファイブ☆スターさんからどうぞ。
参加したのは中国側8000人とロシア側1800人
ロシアの有力紙によると費用は大半を中国が負担したと言う。
この情報はチナヲチさんにも記述がありました。
CCTVの番組から
「中露合同軍は制海権、制空権を握った後、上陸作戦を敢行、猛烈な速さで上陸を決行し、戦車の攻撃とヘリコプターでの空爆を行った。」
中国は台湾への攻撃を想定していると言う見方がある。
「連合軍が攻撃をはじめた。宣伝ビラを入れた砲弾を打ち、敵に心理的打撃を与える。」「あらゆる方向から敵を追い込み殲滅する。作戦は成功した。」
司令部には中国の曹剛川、ロシアのイワノフ両国防相。
イワノフ国防相曰く「中露の軍人が実戦形式で訓練できることをうれしく思う。」
1969年中ソは小さな島を巡って軍事衝突、しかし冷戦後は関係は改善、今では中国軍がロシア軍から上陸作戦の手ほどきを受けていると言う専門かもいる。
2大国の合同演習は国際社会に波紋を投げかけた。しかし両国は第三国を牽制する意図なく国際テロや分離独立の動きに共同で対応するものであるとした。
中国人民解放軍 梁光烈総参謀長曰く
「演習は第三国に向けられたものでも第三国の利益に関わるものでもない。いかなる国にも脅威を与えないはずである。」
今回の軍事演習はまず先立って18日にウラジオストックで図上演習が行われた。
その後、23日から山東半島で実戦的、上陸、海上封鎖訓練が行われた。
中国のねらいを北京の奥谷龍太特派員に聞く
山東半島で演習が行われたのは中国側の強い意向、台湾での有事を想定してるものと思われる。台湾の独立阻止には武力行使も辞さないとしてきた中国は、アメリカの介入にも対抗できる抑止力を持つことを目指してきた。
上陸作戦、海上封鎖の訓練が行われ、揚陸艦や水陸両用戦車も投入された。
台湾は反発しているが、ゆるぎない中国の強い意思を示し、ロシアとの連携により米に対抗する力の誇示が目的と思われる。
ロシアのねらいがウラジオストックからレポートされる。
プーチン政権の裏には激しく変動する中央アジア情勢がある。4年前から中央アジアには同時多発テロを機として米軍が駐留、今年になって相次いで旧ソ連時代からの政権が崩壊、民主化の波が押し寄せてきたことにロシアは脅威を感じてきた。
ロシアは中国と共に中央アジアから米軍の撤退を求め、関係を強めてきた。
8月16日モスクワ航空ショーに最新の兵器が並んだ。ロシアにとって中国は最大の武器の輸出先、プーチン大統領は自らパフォーマンスで売込みに懸命であった。
プーチン大統領曰く、
「我が軍は航空宇宙分野で最先端、ロシアは伝統的に高い知性が集まり、ロシアの航空機は実に手ごろな価格である。」
65Km/hで障害物を飛び越えるいわゆる「飛ぶ戦車」、エンジン音が静かで敵に探知されないディーゼル潜水艦などが中国に売られている。
ロシアの武器売却51億ドルのうち中国向けは23億ドルにものぼった。
ロシア軍バルエフスキー参謀総長曰く
「ロシア製兵器を仲間である人民解放軍に買ってもらいたい。ロシアの兵器は信頼性が高く修理や改良が簡単だ。」
ウラジオストックの権平恒志特派員がレポートする。
軍需産業を建て直し、強いロシアを復活させたいプーチン政権、アメリカを牽制し、戦略的関係を高めることで中国と利害が一致した。
道傳キャスター 「中国にとってロシアとの結びつきを強めるねらいは?」
奥谷特派員 アメリカ一極支配を警戒していることはロシアと一致している。今回演習にはSCO(上海協力機構)に加盟する中央アジア諸国からの国防相がオブザーバーとして招かれた。中国は中央アジアで米国主導の民主化が進み、西部国境の新疆ウイグル自治区で分離独立運動を活気付けることに神経を尖らせている。
さらに経済成長に伴い、エネルギー資源を必要としている為、天然資源が豊富な中央アジアでアメリカの影響力が大きくなることを防ぎたいという思惑がある。
東は台湾の独立を阻み、西では中央アジアとの結びつきを深めたい。ロシアとの連繋にはアメリカを牽制するねらいが込められている。
米国は今回中露合同軍事演習をどう見ているか。
ブルックス研究所、マイケル・オハンロン上級研究員に聞く。
道傳「軍事演習を通じて中国はアメリカにどんなメッセージを送ろうとしたのか?」
オハンロン
演習それ自体は確かに心配するほどのものではない。しかし地政学的には重要である。
中露がアメリカおよびその同盟国に伝えようとしていることのひとつは、両国が「対テロ戦争」や国際社会をリードする手法をめぐってアメリカに不満をもっているということ。
中露は互いの関係強化によって米に対抗していくことを言おうとしている。とりわけ台湾問題をめぐって中国は「アメリカが自分の思っているほどには周辺諸国から支持を得ていない」というメッセージを発しつづけている。
今の世界情勢でアメリカの影響力に対抗できる仲間を持ったことを中国は喜んでいる。
道傳「国際的な政治状況の中で米は中国の軍事力増強にどうかかわっていくのか。」
オハンロン
今の中国は非常に早いペースで軍事力増強を進めている。おそらく数年前の予測を上回る早さである。もちろん軍事力そのものも懸念すべき材料だが、もっと心配すべきなのは軍事力の強化によって中国が自分には台湾攻撃の能力があると思い込んでしまう恐れがあることである。たとえアメリカが台湾問題に介入しに来ても排除できると思うかもしれないし、在日米軍基地を攻撃して日本がアメリカを支援できないように威嚇することも可能だと考えるかもしれない。
あるいは去年、中国の潜水艦が日本の領海に入り込んだ時のように中国がその力を見せつけるような行動に走ってしまう恐れもある。中国の軍事力増強はまずそれ自体が脅威である。さらに中国の指導者が「攻勢に出ても他の国から反撃されるような重大な結果を招くようなことはない」と思い込む懸念もある。このように中国の軍事力の近代化には常に危険と懸念がつきまとう。
道傳「アジア全体の軍事力バランスで中国の軍事力を見る場合、アメリカの見方としては中国がある種の不安定要因となるか?」
オハンロン
中国は必ずしも地域を不安定化するわけではない。しかし中国は我々(米国)を非常に神経質にさせる。米国は貿易と投資によって中国の成長を助けているが、そうした支援こそが中国の脅威を高めてしまうという意見がある。一方で中国がより民主国家であるよう、促していかなければならない。「そうなればたとえ力があっても周辺諸国を脅かそうとはしないだろう。」という考え方がある。
中国に対するアメリカの見方は相矛盾して複雑でありひとことでまとめるのが難しい。中国は同盟国ではないが、敵国でもない。今は敵というよりむしろ友人だがそれもいつまで続くかわからない。だからこそアメリカは将来に備え、さまざまな選択肢を持っておこうとしている。














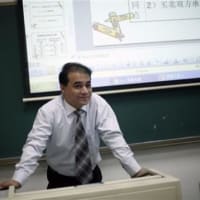



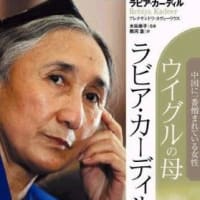

テレビ番組のテキスト化って骨の折れる仕事だと思いますが、情報受信者にとっては非常に有益なものですね。
この記事も大変おもしろく読ませていただきました。
お疲れ様でした。
どうも、自分でオリジナルの記事を書く能力がないものでこういうのに頼ってしまいます。(汗
テレビで聞き流していたときはわからなかったのですが、中国が伝単入り砲弾を使っているとは興味深かったです。
Jonahさんもまた意見をお聞かせ願えれば幸いです。江北日記再公開期待しております。
有難うございました。