昨夜未明 寒河江にとって久々の大量の雨が降る
今年は異常気象なのか 隣市ではドシャ降りの雨が降り冠水した所があるにも
寒河江はポツポツ程度の雨量の日が数回とあった事を記憶している
田畑はすっかり乾燥しており 我が家のかあちゃん 猫の額の畑いじりが好きな故
日々 車で畑に水やりに夕方より出かける日が続いた

先日 苗木商売の同級生より トラック一杯の白菜苗木を頂き 雨上がりの朝より
ルンルン気分で 実家の畑へと 移植しに出かける
親父は全く 畑仕事をする気はなく 畑に足を運んだ事もない
クローラー修理 昨年の事を顧みれば 「修理お願いします」と言われ「あ~ いいよ」
と受け取ってしまい 数日後には「稲刈り始まるので 早く 早く」の電話攻めにて
体の事を考える事なく 深夜まで作業した経験を思い出し 今年は修理内容にては
「オーダーストップ」と言う 飲食店の様な事を実行した
稲作農家の方に聞くに 一週間~10日程早く稲刈り始める様で速い方は天候次第では
明日より始める方も居られた

ストップ掛けた今日は 人並みの日曜とし 腰痛再発しないよう休養とる
9月14日から始まる「寒河江まつり」 外に出て見ると某町内会では早々「子供みこし」を
ワッショイ ワッショイの掛け声と共に町内をくまなく練り歩いていた
フローラ寒河江内テナントに用事あり行って見ると
「歴代 寒河江祭りポスター」が展示されており 改まって過去を思い出させる

1954年(昭和29年)8月1日 寒河江町、西根村、柴橋村、高松村、醍醐村が
合併し 寒河江市となり 同年11月1日には白岩町、三泉村を編入した時より
10年目の祭りポスター 背景には長岡山が描かれ 八幡神社境内にあった
消防署の「火の見櫓」が右上に描かれ 花火まで上がっている(ホントかなぁ~)
街並みは近代ビルらしき描かれてはいるが 親父の記憶では この様な高層ビル
などなかった(駅方面より見た景色らしく 現在も高層は極わずか)
きっと将来 この様になるであろ~と書いたのかも ・・・・・・・
20枚の歴代ポスターある中を見る限り 元祖仮装行列 長年続き 後 武者行列
と化し 時には アームレスリング大会も行われたと知る
今や ”みこしの祭典” がメイン行事となり 面白楽しく見学させて頂いた
仮装行列はなくなってしまった チョッピリ祭りの楽しみが減ってしまった






20枚ある中より古い順と思われますが ポスターには年代が書いてなかったので
展示順に写真アップ
残りのポスターは フローラーで見学してください
他 子供たちの御輿ポスター展もありました
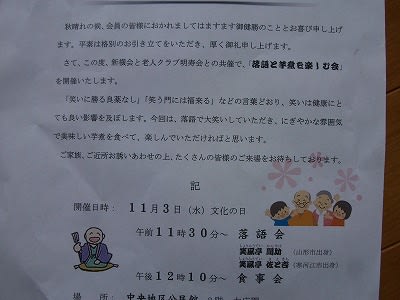










 澄江寺
澄江寺




 持ち 見学するぞう~
持ち 見学するぞう~ 

















