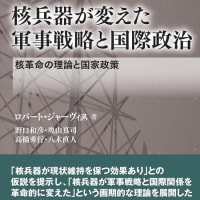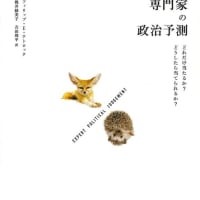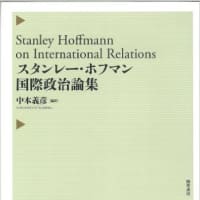日本中が注目する全国高校野球「甲子園」大会開催中に、刺激的なタイトルの新書が発売されました。氏原英明『甲子園という病』新潮社、2018年です。

氏原氏は、以下の問題意識から本書を執筆したそうです。
「これまで日本人の心を打っていたはずの『甲子園』は、正気をうしなっている…『甲子園中毒』によって何が生じているかに気付いてくれるよう願って、この本を記す」(7-8ページ)。
多くの日本人そして高校球児の「正気」を失わせる「甲子園」とは、いったい何なのでしょうか。ある高校球児の回想によれば、「甲子園が魅力的すぎる」(23ページ)のだそうです。どうも、この「魅力」に病理の根源があるようです。では、何が高校野球「甲子園」大会を多くの人の「正気」を失わせるほど「魅力的」にしているのか。残念ながら、私は本書に「答え」を見つけることができませんでした。ただし、異常なほどメディアが取り上げることと関係しているのは、誰もが疑わないでしょうiRONNA。
1つのアマチュアスポーツに過ぎない高校野球「甲子園」大会は、なぜ国民から受信料を領収して運営されている公共放送局であるNHKにより、毎年欠かさず全試合、実況中継されるのか、私は常々不思議に思っています。NHKウェブサイトによれば、NHKは「公共の福祉と文化の向上に寄与することを目的に設立された公共放送事業体」です。そうだとするならば、甲子園大会をNHKが全国に配信することは、「公共の福祉」と「文化の向上」に寄与するのですよね。
日本国憲法にも規定されている「公共の福祉」は、さまざまな事典にいろいろな定義が紹介されていますが、つきつめると「社会全体の利益」という意味のようです。「文化の向上」は、これも捉えどころがない概念ですが、文部科学省によれば、どうやら芸術や歴史などの保護や振興といったようなイメージのようです。他方、高校野球は芸術ではなく、スポーツです。ですから、高校野球「甲子園」大会を全試合、受信料の一部を使って放映することは、素直に考えれば、「文化」を向上させるとは言えないでしょう。
残るのは、「公共の福祉」です。NHKが多大なコストを支払ってまで高校野球「甲子園」大会を番組として全国に流す目的は、それが「公共の福祉」に合致するからだということになります。果たして、そうなのでしょうか。本書では、甲子園大会に出場した投手が「常軌を逸した事態」に追い込まれて、「虐待シーン」とまで表現される事件がいくつも紹介されています(31-32ページ)。こうした次々と起こる「常軌を逸した事態」を無批判に放映することが、なぜ「公共の福祉」になるのか、私にはまったく理解できません。
本書に戻りましょう。大学で教鞭をとる教育者の端くれとして気になるのは、「甲子園」を「聖地」とする高校野球は「教育の一環としての学生野球」(高野連ウェブサイトより)なのかということです。この点について、氏原氏は吐き捨てるように批判します。
「長時間練習が甲子園出場につながったことや深夜までの練習が『感動ストーリー』としてメディアに描かれるのは高校野球ぐらいだろう。教育的観点がどこにもない異常な環境は考え直すべきだろう」(134ページ、下線は引用者)「私学の強豪校などは寮を完備して専用の野球場で練習に打ち込んでいる。すべての練習が終わるのが夜になることもある。そんな状態で翌日の授業を受けて、集中できるはずがない」(148ページ)
同ページで引用されている元阪神のマートン選手の指摘も傾聴に値しますので、ここに紹介します。
「日本人は、野球の練習を八時間することもある。半面、人生において大切な教育がおろそかになっていませんか。スポーツだけ続け二十代後半から三十代でやめたら、どうやって生きていくのでしょうか。僕も野球を終えた後の人生でやりたいことがたくさんある。少し残っている単位をとるために大学に戻って勉強をしたい。残りの人生を豊かにしたいのです」(134ページ)
まったくその通りでしょう。こうした教育上の問題もさることながら、私がもっとも衝撃を受けたのは「食トレという拷問」(124ページ)が、高校の現場で行なわれていることでした。「(選手の身体が貧弱なので)『ごはん三杯』を必須として、選手たちに食べさせていた。しかし、上手くいかなかった。選手たちは我慢して食べようとはしたが、席を立ちあがると吐き出した」(128ページ)。これのどこが「教育の一環」なのでしょうか。流行りの言葉を使って表現すれば、「食ハラ」と言われても仕方ないでしょう。にもかかわらず、氏原氏によれば、このような「食トレーニング」が、高校野球界では大流行している(125ページ)。ここまで来ると、もはや言葉もありません…。
私は中学では「野球小僧」でした(下手でしたが)。母校は、甲子園出場約30回、春の甲子園準優勝2回の古豪です。野球大好きな大学院の恩師とは、何度も野球をプレーしました。MLBもよく観ます。ですが、高校野球「甲子園」大会は、地方予選を含め、一切、観なくなりました。正確に言うと、「正気」を失った甲子園は観たくないのです。「責任を取らない大人が…子どもの夢を勝手に大きくして、慢心させる環境は良くない」(79ページ)。ある高校球児の述懐です(ご参考までにPRESIDENT Online の記事もご覧ください)。私は、そんな大人でいたくありませんね。

氏原氏は、以下の問題意識から本書を執筆したそうです。
「これまで日本人の心を打っていたはずの『甲子園』は、正気をうしなっている…『甲子園中毒』によって何が生じているかに気付いてくれるよう願って、この本を記す」(7-8ページ)。
多くの日本人そして高校球児の「正気」を失わせる「甲子園」とは、いったい何なのでしょうか。ある高校球児の回想によれば、「甲子園が魅力的すぎる」(23ページ)のだそうです。どうも、この「魅力」に病理の根源があるようです。では、何が高校野球「甲子園」大会を多くの人の「正気」を失わせるほど「魅力的」にしているのか。残念ながら、私は本書に「答え」を見つけることができませんでした。ただし、異常なほどメディアが取り上げることと関係しているのは、誰もが疑わないでしょうiRONNA。
1つのアマチュアスポーツに過ぎない高校野球「甲子園」大会は、なぜ国民から受信料を領収して運営されている公共放送局であるNHKにより、毎年欠かさず全試合、実況中継されるのか、私は常々不思議に思っています。NHKウェブサイトによれば、NHKは「公共の福祉と文化の向上に寄与することを目的に設立された公共放送事業体」です。そうだとするならば、甲子園大会をNHKが全国に配信することは、「公共の福祉」と「文化の向上」に寄与するのですよね。
日本国憲法にも規定されている「公共の福祉」は、さまざまな事典にいろいろな定義が紹介されていますが、つきつめると「社会全体の利益」という意味のようです。「文化の向上」は、これも捉えどころがない概念ですが、文部科学省によれば、どうやら芸術や歴史などの保護や振興といったようなイメージのようです。他方、高校野球は芸術ではなく、スポーツです。ですから、高校野球「甲子園」大会を全試合、受信料の一部を使って放映することは、素直に考えれば、「文化」を向上させるとは言えないでしょう。
残るのは、「公共の福祉」です。NHKが多大なコストを支払ってまで高校野球「甲子園」大会を番組として全国に流す目的は、それが「公共の福祉」に合致するからだということになります。果たして、そうなのでしょうか。本書では、甲子園大会に出場した投手が「常軌を逸した事態」に追い込まれて、「虐待シーン」とまで表現される事件がいくつも紹介されています(31-32ページ)。こうした次々と起こる「常軌を逸した事態」を無批判に放映することが、なぜ「公共の福祉」になるのか、私にはまったく理解できません。
本書に戻りましょう。大学で教鞭をとる教育者の端くれとして気になるのは、「甲子園」を「聖地」とする高校野球は「教育の一環としての学生野球」(高野連ウェブサイトより)なのかということです。この点について、氏原氏は吐き捨てるように批判します。
「長時間練習が甲子園出場につながったことや深夜までの練習が『感動ストーリー』としてメディアに描かれるのは高校野球ぐらいだろう。教育的観点がどこにもない異常な環境は考え直すべきだろう」(134ページ、下線は引用者)「私学の強豪校などは寮を完備して専用の野球場で練習に打ち込んでいる。すべての練習が終わるのが夜になることもある。そんな状態で翌日の授業を受けて、集中できるはずがない」(148ページ)
同ページで引用されている元阪神のマートン選手の指摘も傾聴に値しますので、ここに紹介します。
「日本人は、野球の練習を八時間することもある。半面、人生において大切な教育がおろそかになっていませんか。スポーツだけ続け二十代後半から三十代でやめたら、どうやって生きていくのでしょうか。僕も野球を終えた後の人生でやりたいことがたくさんある。少し残っている単位をとるために大学に戻って勉強をしたい。残りの人生を豊かにしたいのです」(134ページ)
まったくその通りでしょう。こうした教育上の問題もさることながら、私がもっとも衝撃を受けたのは「食トレという拷問」(124ページ)が、高校の現場で行なわれていることでした。「(選手の身体が貧弱なので)『ごはん三杯』を必須として、選手たちに食べさせていた。しかし、上手くいかなかった。選手たちは我慢して食べようとはしたが、席を立ちあがると吐き出した」(128ページ)。これのどこが「教育の一環」なのでしょうか。流行りの言葉を使って表現すれば、「食ハラ」と言われても仕方ないでしょう。にもかかわらず、氏原氏によれば、このような「食トレーニング」が、高校野球界では大流行している(125ページ)。ここまで来ると、もはや言葉もありません…。
私は中学では「野球小僧」でした(下手でしたが)。母校は、甲子園出場約30回、春の甲子園準優勝2回の古豪です。野球大好きな大学院の恩師とは、何度も野球をプレーしました。MLBもよく観ます。ですが、高校野球「甲子園」大会は、地方予選を含め、一切、観なくなりました。正確に言うと、「正気」を失った甲子園は観たくないのです。「責任を取らない大人が…子どもの夢を勝手に大きくして、慢心させる環境は良くない」(79ページ)。ある高校球児の述懐です(ご参考までにPRESIDENT Online の記事もご覧ください)。私は、そんな大人でいたくありませんね。