はじめに
今日も、古事記の形状を採録します。。『最初は、1、目です。2、身一つで八頭八尾。3、身に生じたコケとヒノキ、杉。4、谷八谷、峡(ヲ)八尾を渡る、です。
前回までに、上の、1~3の形状が太鼓台の部分と説明しました。残るのは、4番目の、谷八谷、峡(ヲ)八尾を渡です。これは何で何処を言っているのでしょう。これが解ければ、オロチの形状は全て、太鼓台の部分となります。
宇摩説の著作権侵害
話が変りますが、宇摩説で「太鼓台は卑弥呼の創始」と解いています。これは、貴重な宇摩地域の伝承、芸能、太鼓台の実物、その他が加わって解けるものです。各地で太鼓台の伝承などを幾ら集めても解けるものではありません。
したがって、宇摩説の結論を「太鼓台は弥生時代創始」などと、自分のブログに利用しても、地域の人に笑われるだけです。これを書くには、卑弥呼に繋がる多くの証明が必要で、それは、宇摩郡だけに残っているものです。
実は、昨年、「太鼓台は卑弥呼(弥生時代?)の創始」などと言う一文を、何処かの太鼓台の記事に書いてありました。多分私の記事を読んだのでしょう。しかし、出所は書かず、自分で調べたような記事でした。
「卑弥呼の創始」を言うなら、宇摩説も紹介しないと、説明不足で空想(創作・想像)論になります。また、宇摩説の著作権の侵害です。つまり、宇摩説は一部を利用しても、著作権違反と、不信感を持たれるだけです。
「太鼓台は弥生時代(卑弥呼)の創始」は、宇摩説の30年に及ぶ研究で解けた物で、常識とは違うから宇摩説の全体の多くの説明が必要なのです。宇摩説の一部を利用する時は、無断で使用しないで下さい。
宇摩説は、多くの分野の学問の解明が整合して、初めて、多くの人に納得されるものです。宇摩説は常識と違うために、一部では、納得され無いでしょう。重ねて、「無断使用して、宇摩説の著作権侵害」をしないようにお願いします。
宇摩説の解釈(谷八谷、峡(ヲ)八尾を渡る)
さて、形状の、4は、文では3に続いています。だから、4には、「其の身は」の部分がありません。これは迷彩のために省いて、前文にくっ付けたのでしょう。原文には、「其の身は生む、」とあり、4の文とは続いていません。別の文です。
この「谷」と「峡」とは、太鼓台の何処を言ったのでしょう。これが解ると、これらを渡る物も判明します。この答えを先に結論から言えば、四本のカキ棒(前後で八になる)とこの間を谷と言った物です。
下に、写真を入れておきます。この写真は太鼓台の傍に寄って、カキ棒の上下を写したもので、近くから見れば、カキ棒は「谷八谷、峡八尾」になります。つまり、前面では、四つの峡と、間の三つの谷と四本目の向こう側の谷で四つです。
こうなると、この「谷と峡」を渡るものは、ロープ(かずら、蔓)になります。つまり、4番目も、太鼓台の部分を紛らわしく、書き残したものです。これらの、部分記録から、朝廷が、この山車を隠したかった事が判ります。
カキ棒とカズラ(蔓。ロープ)
下の写真は、祭りが済んで、解体中に雨が降り、ビニールを被せているので、見え難い部分がありますが、カキ棒がロープで括られています。一番奥のカキ棒は暗いのですが、良く見れば四本共に写っています。
今は、ロープですから、きれいに揃っていますが、古代では自然に育った蔓の場合、曲がりくねって、生き物が渡っている様に見えたことでしょう。

下の写真は、上の写真の下側を撮ったものです。下側に使われた多くのロープが良く判ると思います。これは、前回の「其の身は、蔓と檜と椙で生れる(作られている)」を、示す写真でも有ります。
「伊予三島市報」より
(この各部名称の図が、ロープを使った場所が良く解るので入れておきます)
そして、先に言ったように、このカキ棒が前後に八本が出ています。二枚の写真は太鼓台を担いだ時に見える位置に近いものです。つまり、カキ手の視点で書かれた太鼓台の一部を拡大した記録です。
この位置から良く見れば、「カキ棒とカキ棒の間は谷」になります。そして、カキ棒が峡に見えるのです。だから、「谷八谷、峡八尾」となり、蔓が、この谷八谷、峡(お)八尾を、渡っています。
以上で、古事記のオロチの形状、1~4までの説明を終わります。オロチの形状は全て、太鼓台の一部を記録したものです。この理由はオロチが、朝廷に不都合な神輿太鼓(太鼓台)だったので、隠すために、その一部を取り上げて書いたものです。
そのお陰で、後の人には謎の妖怪となり、太鼓台の起源は不明になったのです。しかし、オロチの神楽は、どの神楽でも、オロチ(大蛇)と言いながら、「龍」になっています。それほど、強烈に印象に残り伝え残したのでしょう。
こうして、オロチの正体が判ると、大蛇退治の史実も判って来ます。今日はこの辺で終わります。
最新の画像[もっと見る]
-
 卑弥呼の姿=2= 法皇山脈の山腹にある卑弥呼(2)
18年前
卑弥呼の姿=2= 法皇山脈の山腹にある卑弥呼(2)
18年前
-
 宇摩(高天原・邪馬台国)に残る造形-3-
18年前
宇摩(高天原・邪馬台国)に残る造形-3-
18年前
-
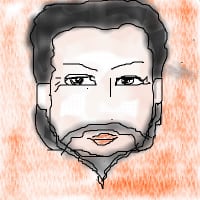 画像フォルダ
18年前
画像フォルダ
18年前












