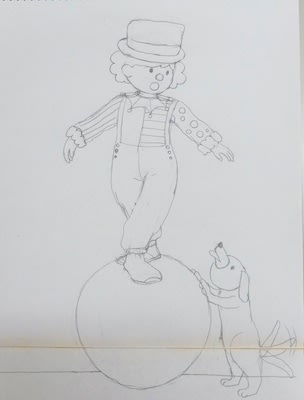この日はまず、テキスト『60歳からの文章入門』(近藤勝重 著/幻冬舎新書)のP56~P85を見ていきました。

日本語には、言葉の最小単位である「文節」(後ろに「ネ」を付けて意味をなす言葉)、次に「句」(修飾語などを含むフレーズ)、そして「文」(主語・述語などを伴い、最後に。が付く)、いくつかの文がまとまった「段落」、それらで構成される「文章」という単位があります。
小さな子どもの読む絵本の文章は、ひらがなだけで長々と文章を書くとどこで切ったらよいか分からなくなるため、文節で分けた「分かち書き」で書かれていることが多いです。
国語の授業では、自分で書くことより人が書いた文章を読み取る授業が多いため、文法について詳しく学ぶ機会があまりありません。

例えば助詞の使い分けは、外国人にとってはたいへん難しいのだそうです。
・「〜が」は主に未知の情報について付き、「〜は」は既知の場合につく助詞で、その下に新たな情報を求める働きもある。
・そして「〜も」は、共同体の雰囲気を作る助詞で柔らかいニュアンスになるが、最初に書くのは違和感がある。
・「〜へ」は方向を示し、「〜に」は帰着点を表す。(ただし関西弁では両方省略する傾向がある)
……などと、いちいち考えながら話していては会話が先に進みませんが、文章の場合は使い分けをする方が作者の意図が分かりやすくなります。
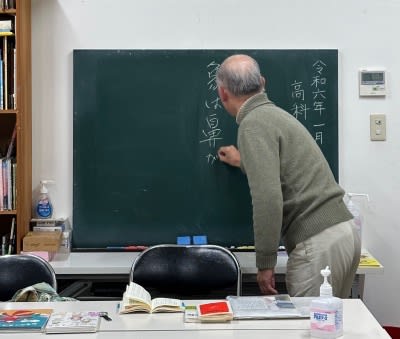
ここで、一つ問題です。
「象の鼻が長い」という文では、どれが主語でどれが述語でしょうか? ディスカッションが始まりました。
これは、日本語学者の三上章の『象は鼻が長い』(くろしお出版)に書かれていることです。
他国の言語では、主語(S)→述語(V)→目的語(O)の順番で構成される文章が
日本の場合、主語(S)→目的語(O)→述語(V)の並びになっているため、主語が略されることも多いです。
この文章では、「象は(S)」+「鼻が長い(V)」、または「象は(S)」+「鼻が長い」修飾語(+ 略されているが「動物である(V)」)とも考えられます。
参考資料として、大野晋の『日本語練習帳』(岩波書店)も見ていきました。この本によると、
・「〜は」は問題を出して、その下に答えがくることを予約する働きのある助詞だそうです。
(問題提起と答えの間にあまり長い説明文が入ると分かりにくくなるので気をつけましょう)
・もう一つ、「〜は」が二つ以上続いて出てくるとき、それはその二つを対比させる役割があります。
確かに日本語は主語を省略しても意味が通じる言語ですが、読み手にとっては主語が示されている方が書き手の意図が理解しやすいので、うまくバランスをとって書くようにしましょう。
例えば数人の人物のことを描写する場合は、誰が喋っているか、誰が動いているのか、分かりやすく書きましょう(敢えてミスリードを誘う場合は除く)。

これ以上やるとこんがらがってきそうなので、
前回も見ていった 広瀬友紀著『ちいさい言語学者の冒険――子どもに学ぶことばの秘密』 (岩波科学ライブラリー) の続きをやりました。
・子どもにとって、「ん」「っ」「ー」を一拍と数えるのは難しい〜世界の言語を見ても、日本語の数え方の方が少数派である。
・子ども特有の言い間違いに、「とうもろこし→とうもころし」など、文字を発音しやすい順に入れ替える(音位転換)ことがある。
これらは、日本語を身につける課程で自然と正されていくようです。
休憩をはさんで、後半は課題についてです。
前回皆さんが提出した「わらう」をテーマにした文章は、新年に起こった大震災と「笑うこと」を結びつけたものが多かったようです。
特にそう指定されていたわけではないのに自然とそうなったということは、それだけ印象的な出来事だったからでしょう。
提出されたものの中には、以前提出して先生にチェックしていただいたものを修正して、再度提出された作品もありました。
高科先生は、「それは歓迎します」と言っておられますので、どんどんブラッシュアップした作品を仕上げてください。
ここで一つ注意しなければならないのは、書き手は自分は知っているのでその設定で書きますが、読み手は初見では初めて知る情報なので、できるだけ分かりやすく書く必要があるということです。
推敲していくうちに大切な情報まで抜け落ちないよう、気をつけてください。
さて今回の課題はまた動詞シリーズに戻って、「めでる(愛でる)」です。
自分がいちばん愛でているモノ・コト・ヒト・場所・味・音楽…なんでも構いません。
好きなスタイルで、好きなボリュームで、思う存分書いてください。
提出は次回2月10日、第6回目の授業の時です。
よろしくお願いいたします。