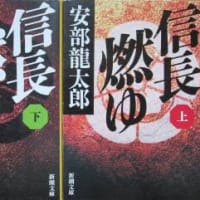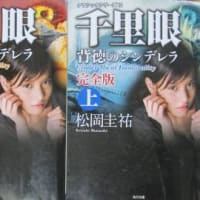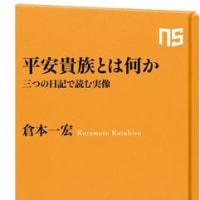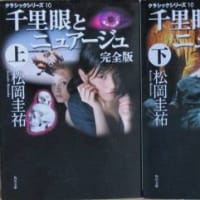タイトル通り、仏像の「顔」に焦点をしぼり、日本における仏像の「顔」の表現、その造形が時代とともに変化してきている事実をつぶさに分析して解説した本である。
本書は2013年9月に刊行された。手元の本は第1刷。
仏像の前に立ち、仏像の「顔」を眺めて、「何ともいい顔」と感じる。この「何とも」とは何かということをテーマに取り組んだのがこの本である。仏像の種類や仏像全体・全身の様式や造形を解説する書はたくさんある。しかし、仏像の「顔」に着目し分析・解説する本は珍しいと思う。
序章の第2パラグラフで、著者は次のように述べている。
”仏教は、信仰の対象として、ブッダの姿をイメージした仏像を造り祀りました。仏像は「仏」の代わりではなく、「仏」そのものとなり、仏像を拝むことは、「仏」を拝することでした。そこで、信仰の対象となるにふさわしい仏像の姿として、最も「顔」が重視されたのは、いうまでもありません。仏像の「顔」には、形としての「顔」だけでない、人の心に訴える何らかの意味があるはずです。” (p2)
この「何らかの意味」を究明する仏像拝顔の時空をまたぐ旅が本書である。
本書の目次を見れば、その要は一目瞭然である。仏像の「顔」の形と表情が時代とともに変化してきた事実とその特徴は、その章立てと章の見出しに明示されている。そう言われれば、確かに・・・・と感じる。
目次のご紹介に併せ、その章の該当箇所で取り上げ分析されている仏像の一端のいくつかを、その名称で併記してみよう。どのように分析されていくのかへの誘いになることだろう。
第1章 仏像の誕生 ----- インドと中国
1 インドの仏像 --- 半眼と見開いた眼
サリ・バロール出土弥勒菩薩坐像、チャウパーラ出土仏頭
2 中国の仏像 --- 端正な顔から豊満な顔へ
藤井有鄰館菩薩立像、永青文庫如来坐像
雲岡石窟第20窟如来坐像、龍門石窟奉先寺洞廬舎那仏
第2章 飛鳥時代の仏像 ----- 杏仁形の眼・古拙の微笑
法隆寺金堂釈迦三尊像、法隆寺夢殿救世観音像
第3章 白鳳時代の仏像 ----- あどけない顔・おおらかな表情
中宮寺半跏思惟像、法隆寺観音菩薩像、法隆寺夢違観音像
第4章 天平時代の仏像 ----- 国家仏教と威厳
薬師寺薬師三尊像、東大寺法華堂不空羂索観音像、東大寺戒壇院四天王像
第5章 平安時代前期の仏像 ----- 個性的な顔
新薬師寺薬師如来坐像、神護寺薬師如来坐像、東寺講堂不動明王像
第6章 平安時代後期の仏像 ----- 尊容満月の如し
平等院阿弥陀如来坐像、
第7章 鎌倉時代の仏像 ----- 力強さと写実
願成就院不動明王立像、鎌倉大仏
本書は、仏像の「顔」の特徴の分析、並びに仏像そのものについての論考を鎌倉時代までにとどめている。そして、これ以降の仏像彫刻を語る出版物が少なくなる理由を著者は明記している。
「近年かなり見直されてきてはいますが、その理由としては、鎌倉時代までに比べて、信仰のあり方や財政基盤、造像技術と仏師組織などに充実と高まりがなく、各時代の個性を発揮するような優れた仏像が造られなかったことが大きいと思われます」(p169)と。
最後に第8章が続く。「仏像の『仏』たるゆえん ----- 開眼供養と白毫相」という見出しで終章がまとめられている。
なぜか。「仏像の顔」にとって、「開眼」が特別な意味を持つ故である。歴史上で特に有名なのは、東大寺大仏の開眼供養会。著者はこれに関連させて開眼について語る。
「開眼供養会という儀式を行ない、彫刻としての仏像に仏の『たましい』を入れて、仏として本当の意味の仏像にします」(p172)と。
仏像が美術彫刻と一線を画するのは、この開眼供養会という儀式を経て初めて真に「仏像」になる点にある。それを再認識した。
著者は最後に、「仏の三十二相」の一つである「白毫相」について説明している。白毫相が何かは知っていた。だが、白毫相そのものについて、経典の記述に基づく一歩踏み込んだ知識として、本書で学ぶ機会を得た。一つの副産物である。
最後に仏像の「顔」について、著者の分析・指摘の一端を引用し、覚書を兼ねてご紹介しよう。
*「あどけない顔」の特徴
丸顔であること、眼と耳の位置が大人に比べて低く、顔を上下に二分割した時に眼がその線上、あるいはそれ以下にあること、眼と眼が離れていること、眉と眼が離れていること、鼻柱が短いことなど。 p68
*日本の仏像の瞼(特に上瞼)を見てみると、ほとんどが一重瞼です。 p72
二重瞼の像(の例もある:付記)が7世紀後半白鳳時代に集中していること p72
*眉は、仏像の顔形をいう場合に非常に重要な部分の一つです。・・・・・眉は動物にない極めて人間的な部分なのです。・・・・・・眉には、表情をつくる大きな役割がある点に注目してみましょう。・・・・・仏・菩薩像の眉がほとんど目立たないのは、眉を目立たせないことで、人間と一線を劃する意味があったのではないでしょうか。 p73-74
このように分析的に仏像の顔を拝見したことはなかった・・・・そのことに気づいた。
ご一読ありがとうございます。
補遺
ペシャワール博物館 :「西遊旅行」
ペシャワール博物館は、隠れた名所 パキスタン情報セクション :「no+e」
雲崗石窟 :ウィキペディア
【世界遺産】雲崗石窟とは?|高い彫刻技術と仏教思想! :「skyticket」
龍門石窟 :ウィキペディア
龍門石窟 :「丹沢 森のギャラリー」
聖徳宗総本山 法隆寺 ホームページ
聖徳宗 中宮寺 ホームページ
奈良 薬師寺 公式サイト
華厳宗大本山 東大寺 ホームページ
新薬師寺 公式ホームページ
弘法大師霊場 遺迹本山 高雄山神護寺 ホームページ
真言宗総本山 教王護国寺 東寺 ホームページ
世界遺産 平等院 ホームページ
高野山真言宗 天守君山 願成就院 ホームページ
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
本書は2013年9月に刊行された。手元の本は第1刷。
仏像の前に立ち、仏像の「顔」を眺めて、「何ともいい顔」と感じる。この「何とも」とは何かということをテーマに取り組んだのがこの本である。仏像の種類や仏像全体・全身の様式や造形を解説する書はたくさんある。しかし、仏像の「顔」に着目し分析・解説する本は珍しいと思う。
序章の第2パラグラフで、著者は次のように述べている。
”仏教は、信仰の対象として、ブッダの姿をイメージした仏像を造り祀りました。仏像は「仏」の代わりではなく、「仏」そのものとなり、仏像を拝むことは、「仏」を拝することでした。そこで、信仰の対象となるにふさわしい仏像の姿として、最も「顔」が重視されたのは、いうまでもありません。仏像の「顔」には、形としての「顔」だけでない、人の心に訴える何らかの意味があるはずです。” (p2)
この「何らかの意味」を究明する仏像拝顔の時空をまたぐ旅が本書である。
本書の目次を見れば、その要は一目瞭然である。仏像の「顔」の形と表情が時代とともに変化してきた事実とその特徴は、その章立てと章の見出しに明示されている。そう言われれば、確かに・・・・と感じる。
目次のご紹介に併せ、その章の該当箇所で取り上げ分析されている仏像の一端のいくつかを、その名称で併記してみよう。どのように分析されていくのかへの誘いになることだろう。
第1章 仏像の誕生 ----- インドと中国
1 インドの仏像 --- 半眼と見開いた眼
サリ・バロール出土弥勒菩薩坐像、チャウパーラ出土仏頭
2 中国の仏像 --- 端正な顔から豊満な顔へ
藤井有鄰館菩薩立像、永青文庫如来坐像
雲岡石窟第20窟如来坐像、龍門石窟奉先寺洞廬舎那仏
第2章 飛鳥時代の仏像 ----- 杏仁形の眼・古拙の微笑
法隆寺金堂釈迦三尊像、法隆寺夢殿救世観音像
第3章 白鳳時代の仏像 ----- あどけない顔・おおらかな表情
中宮寺半跏思惟像、法隆寺観音菩薩像、法隆寺夢違観音像
第4章 天平時代の仏像 ----- 国家仏教と威厳
薬師寺薬師三尊像、東大寺法華堂不空羂索観音像、東大寺戒壇院四天王像
第5章 平安時代前期の仏像 ----- 個性的な顔
新薬師寺薬師如来坐像、神護寺薬師如来坐像、東寺講堂不動明王像
第6章 平安時代後期の仏像 ----- 尊容満月の如し
平等院阿弥陀如来坐像、
第7章 鎌倉時代の仏像 ----- 力強さと写実
願成就院不動明王立像、鎌倉大仏
本書は、仏像の「顔」の特徴の分析、並びに仏像そのものについての論考を鎌倉時代までにとどめている。そして、これ以降の仏像彫刻を語る出版物が少なくなる理由を著者は明記している。
「近年かなり見直されてきてはいますが、その理由としては、鎌倉時代までに比べて、信仰のあり方や財政基盤、造像技術と仏師組織などに充実と高まりがなく、各時代の個性を発揮するような優れた仏像が造られなかったことが大きいと思われます」(p169)と。
最後に第8章が続く。「仏像の『仏』たるゆえん ----- 開眼供養と白毫相」という見出しで終章がまとめられている。
なぜか。「仏像の顔」にとって、「開眼」が特別な意味を持つ故である。歴史上で特に有名なのは、東大寺大仏の開眼供養会。著者はこれに関連させて開眼について語る。
「開眼供養会という儀式を行ない、彫刻としての仏像に仏の『たましい』を入れて、仏として本当の意味の仏像にします」(p172)と。
仏像が美術彫刻と一線を画するのは、この開眼供養会という儀式を経て初めて真に「仏像」になる点にある。それを再認識した。
著者は最後に、「仏の三十二相」の一つである「白毫相」について説明している。白毫相が何かは知っていた。だが、白毫相そのものについて、経典の記述に基づく一歩踏み込んだ知識として、本書で学ぶ機会を得た。一つの副産物である。
最後に仏像の「顔」について、著者の分析・指摘の一端を引用し、覚書を兼ねてご紹介しよう。
*「あどけない顔」の特徴
丸顔であること、眼と耳の位置が大人に比べて低く、顔を上下に二分割した時に眼がその線上、あるいはそれ以下にあること、眼と眼が離れていること、眉と眼が離れていること、鼻柱が短いことなど。 p68
*日本の仏像の瞼(特に上瞼)を見てみると、ほとんどが一重瞼です。 p72
二重瞼の像(の例もある:付記)が7世紀後半白鳳時代に集中していること p72
*眉は、仏像の顔形をいう場合に非常に重要な部分の一つです。・・・・・眉は動物にない極めて人間的な部分なのです。・・・・・・眉には、表情をつくる大きな役割がある点に注目してみましょう。・・・・・仏・菩薩像の眉がほとんど目立たないのは、眉を目立たせないことで、人間と一線を劃する意味があったのではないでしょうか。 p73-74
このように分析的に仏像の顔を拝見したことはなかった・・・・そのことに気づいた。
ご一読ありがとうございます。
補遺
ペシャワール博物館 :「西遊旅行」
ペシャワール博物館は、隠れた名所 パキスタン情報セクション :「no+e」
雲崗石窟 :ウィキペディア
【世界遺産】雲崗石窟とは?|高い彫刻技術と仏教思想! :「skyticket」
龍門石窟 :ウィキペディア
龍門石窟 :「丹沢 森のギャラリー」
聖徳宗総本山 法隆寺 ホームページ
聖徳宗 中宮寺 ホームページ
奈良 薬師寺 公式サイト
華厳宗大本山 東大寺 ホームページ
新薬師寺 公式ホームページ
弘法大師霊場 遺迹本山 高雄山神護寺 ホームページ
真言宗総本山 教王護国寺 東寺 ホームページ
世界遺産 平等院 ホームページ
高野山真言宗 天守君山 願成就院 ホームページ
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)