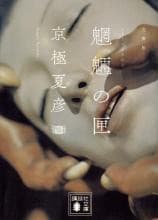ごく身近に長らく置いていた一冊を読み終えた。書棚には文庫本を中心に信長関連の小説等で収集した本が60冊近く眠っているので、ほんの一歩を進めたに過ぎないのだが・・・・。
「あとがきにかえて」によると、日本経済新聞にほぼ1年9ヵ月にわたり連載発表された後、手直しを経て、平成13年(2001)6月、日本経済新聞社より単行本が刊行された。その後、平成16年(2004)10月に新潮文庫化されている。手元にあるのはこの版。
3月27日夜、カンテレで「歴史ミステリーVS超能力!本能寺の変&坂本龍馬暗殺の謎解きSP」というテレビ番組を視聴した。本能寺の変と坂本龍馬暗殺というキーワードに惹かれてだった。この番組のために来日し出演した女性超能力者は、最終的に明智光秀の謀反は単独犯行と感じるという結論を出していた。歴史学者の同意感想も述べられていた。その最中にこの上下本を読んでいたので、本書のストーリーの進展は一層興味深かった。
著者自身が文庫本の「あとがきにかえて」に端的に本書の位置づけ等を語っている。ここをまず読まれるのが一番かと思う。そのおすすめだけで感想を終えても十分かと思う。
が、覚書を兼ね「あとがきにかえて」に触れつつ、読後感をまとめておきたい。
まず、本書のタイトルから、本能寺の変を眼目にしていることは一目瞭然である。何が語られるか、そこにまず関心が向かう。
そして、読み始めて、本書の構成に意識が向く。著者自身が本書の背景設定を「序章」で次のとおり、明確にするからである。
*本能寺の変から35年後に本能寺の変の経緯を書き留めることに着手するという設定。
*著者は近衛家の門流で清華家の三男坊・清麿。変の当時、15歳で、わずか2年間だが、信長に小姓として近侍していた。信長公から「たわけの清麿」と呼ばれていた。清麿は当日(6/2)、他所に使いに出ていたので、難をまぬがれた。
*洛北、寺町通にある阿弥陀寺の信長公の墓に詣でる。信長公についてこれから一書を書くという報告をする。
この時住職から墓守りをする一人の男に引き合わされる。その男は森坊丸だった。
清麿は森坊丸から変当日の本能寺と信長の状況・事実を回顧譚として聞き取る。
坊丸は「本能寺の変の背後には、朝廷も関わった数々の陰謀があった。それを知っておられるがために、清玉上人は秀吉の手の者に害され、誠仁親王は割腹せざるをえない立場に追い込まれたのじゃ。そのようないきさつを何ひとつ知らず、物書きどもが見てきたような絵空事を書き散らしておる」(上、p52)と清麿に語る。
*本能寺の変が起こった時、阿弥陀寺は西の京の蓮台野にあった。一方、本能寺は、当時、堀川四条の北東方向、油小路通と蛸薬師通の辻の南東側が寺の中心辺りだった。
*この時(大坂の陣から2年後)、太田牛一の『信長公記』が世に流布していた。
*清麿の執筆動機は、「さるやんごとなきお方から、変について書き残してほしいという依頼を受けた」(上、p52)からと坊丸に語る。禁裏の学問所にて、秘蔵の文書や記録、公家の日記などを自由に調査でき、史資料として使うことを許されるという設定になっている。(上、p53)
*『御湯殿の上の日記』『兼見卿記』『多聞院日記』などの記録における記事の抜けや改ざんなどが引用され、内容が分析され、考察されていく。
つまり、信長から「たわけの清麿」と呼ばれた第三者の視点から本能寺の変に関わった人物たちが捉えられていく。
本能寺の変の経緯が、清麿によるルポルタージュという形で進展していく。
これが読者に対して説得力を生み出していく一因になる。
さらに、<序章 阿弥陀寺の花>には、上記の設定の凡その記述とパラレルに、天正10年(1582)6月2日早朝に起こった本能寺の変当日の状況並びに信長の死が描き出される。つまり、本能寺の変そのものの結末がこのストーリーの冒頭に提示される。
結果が最初にあり、<第1章 左義長> は、天正9年(1581)の年明けから始まる。最終章の <第16章 見果てぬ夢> は、「その頃、先発隊から本能寺の包囲を終えたという知らせを受けた明智光秀は、八千の本隊をひきいて桂川の渡河にかかっていた」(下、p543) の一文で終わる。つまり、本作は1年半という期間に凝縮した形で、なぜ本能寺の変が起こったかをルポルタージュ風に描きあげている。
<あとがきにかえて> の第2文に著者は「本能寺の変を公武の相剋という視点から描きたいという構想は、『関ヶ原連判状』を書いた頃から持っていた」(下、p544)と記す。
本能寺の変の主人公といえば、織田信長と明智光秀で、この二人の相剋ということになる。だが、この『信長燃ゆ』の主人公は織田信長と近衛前久の二人だと私は思った。明智光秀は准主役として位置づけられている気がする。そういう視点と感じるストーリーの進展にこの小説のおもしろさがあるように思う。
朝廷と明智光秀が共謀して本能寺の変が起こったという朝廷黒幕説がこのストーリーの仮説として根底にある。その朝廷の中において、信長の思考・戦略・行動に対峙して、常に帝の権威を維持し、朝廷の仕組みを維持・存立させて、武士よりも朝廷が上位にあらんと緻密な策謀を練る中心人物が近衛前久なのだ。信長に対立する立場なのだが、外見は信長の野望に協力・協調する姿勢をみせ続ける。信長の基盤を弱体化させ、切り崩そうと策謀する前久のスタンスと行動が描きこまれていく。前久のスタンスを知りつつ、それをねじ伏せて行こうとする信長。清麿が分析して眺めた本能寺の変に至る本質は、この二人の駆け引きの中に内在する。信長と前久の駆け引きが本作の読ませどころと言える。
前久は明智光秀を信長抹殺という共謀の形に取り込み、先頭に立たせていく。一方で、光秀に知らせずに信長打倒への策略の全体展開を推し進める。この前久の巧妙さは、なるほどありえるという方向に読者を誘っていく。この点、さすがである。
「時間の幅を短くして信長や前久の政治的な動きや内面を克明に描きたかった」(下、p545) と著者は記す。公武の相剋という政治的駆け引きと内面心理の動き。これが様々な局面で織り込まれている。両者の駆け引きは読者として楽しめるプロセスでもある。前久の息子・信基が信長に心酔していて、常に前久に対立する形で登場するのもおもしろい。父の前久が反対しようと、信長の武士、政治家としての魅力を代弁していることになる。
正親町天皇の嫡子で東宮の誠仁親王の夫人・勧修寺晴子が登場する。京での馬揃えについて、朝廷から安土への使者となる佐五の局に、晴子が身分を偽り、若狭の局と称して随伴する。これが晴子と信長の出会いとなる。この若狭の局を信長が記憶していたことから、後に思わぬ事態が契機ととなり、二人の恋が始まって行く。
本能寺の変が歴史の経緯を描く縦糸とすれば、この晴子と信長の関係はこのストーリーの横糸として、時間軸の進展の要所要所に織り込まれていく。
読者にとっては、事の成り行きの推移を楽しめる横糸である。この晴子の思いを介として、当時の朝廷における天皇周辺の状況がうかがえて興味深い。副産物として、当時は皇后という地位がなかったことを本書で知った。その理由は、皇后という地位を維持存続させる財源的基盤がなかったからという。また天皇の譲位、即位についても、その儀式の実施費用に窮しているのが朝廷の実態だったという。戦国時代の朝廷というものを今まで考えたことがなかった。例えば、平安時代と比較する意味でも、朝廷について、その実態を歴史的変遷の中で捉え直してみるために、改めて学ぶ必要性という課題が残った。
本書で印象に残る文を引用しご紹介したい。
*耐えきれぬ苦しみを抱えて生きていかねばならぬ者にとって、涙は絶望の淵から立ち上がるための心やさしき伴侶である。 (上・p43)
*多くの人は神仏に加護を求めるが、信長は神仏の力を我が身に取り込もうとしたのである。 (上、p298)
*信長が焼き討ちをかけたのは、比叡山が浅井、朝倉勢に身方して軍勢を山上にとどめたからだと言われている。
だが事の発端は、信長が近江国に散在する山門領を横領し、返還要求に応じなかったことだ。
比叡山側は三千院の門跡であられる応胤法親王を通じて朝廷に訴え、勅命をもって返還させようとした。 (上、p443)
→ このことを本書で初めて知った。史実を述べている箇所と理解した。
*真実とはかけ離れたことばかりが、歴史という名のもとにまことしやかに書き継がれていく。 (下、p184)
*信長が戦っていた相手は、個々の勢力ではない。人々の心の中にまで根強く張り巡らされた、こうした旧い意識なのである。 (下、p429)
*著者は、「たわけの清麿」に明智光秀について、次のように評させている。
「こうした陰謀に加担するには、あまりにも誠実で真っ直ぐな心の持ち主だったのである」(下、p428)と。
本作の全体構成としてのエンディングが興味深い。歴史時代小説、フィクションとしての醍醐味が遺憾なく盛り込まれていると思う。
終章は、興味深い場面で終わる。信長の死という側面とは別に種々の想いが残る。
明智光秀の心境は本能寺の変が成功したその時点ではどうだったのか・・・・。
羽柴秀吉はいわば漁夫の利を得られる立場になれる状況をもらったようではないか。
前久は、誠仁親王は、晴子は・・・・・・
それぞれの人物の行動と心理のあり様、そこを楽しむことができると思う。
ご一読ありがとうございます。
補遺
本能寺跡 :「京都観光Navi」
「本能寺の変」を調査する 発掘ニュース82 :「京都市埋蔵文化財研究所」
本能寺の変 :ウィキペディア
織田信長 :ウィキペディア
近衛前久 :ウィキペディア
戦場に出陣した破天荒な貴族・近衛前久の波乱万丈人生【麒麟がくる満喫レポート】:「サライ.jp」
明智光秀 :ウィキペディア
森成利 :ウィキペディア
森長隆 :ウィキペディア
勧修寺晴子 :ウィキペディア
上京区の史蹟百選/阿弥陀寺 :「京都市」
阿弥陀寺 (京都市上京区) :ウィキペディア
法華宗大本山 本能寺 公式サイト
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
「あとがきにかえて」によると、日本経済新聞にほぼ1年9ヵ月にわたり連載発表された後、手直しを経て、平成13年(2001)6月、日本経済新聞社より単行本が刊行された。その後、平成16年(2004)10月に新潮文庫化されている。手元にあるのはこの版。
3月27日夜、カンテレで「歴史ミステリーVS超能力!本能寺の変&坂本龍馬暗殺の謎解きSP」というテレビ番組を視聴した。本能寺の変と坂本龍馬暗殺というキーワードに惹かれてだった。この番組のために来日し出演した女性超能力者は、最終的に明智光秀の謀反は単独犯行と感じるという結論を出していた。歴史学者の同意感想も述べられていた。その最中にこの上下本を読んでいたので、本書のストーリーの進展は一層興味深かった。
著者自身が文庫本の「あとがきにかえて」に端的に本書の位置づけ等を語っている。ここをまず読まれるのが一番かと思う。そのおすすめだけで感想を終えても十分かと思う。
が、覚書を兼ね「あとがきにかえて」に触れつつ、読後感をまとめておきたい。
まず、本書のタイトルから、本能寺の変を眼目にしていることは一目瞭然である。何が語られるか、そこにまず関心が向かう。
そして、読み始めて、本書の構成に意識が向く。著者自身が本書の背景設定を「序章」で次のとおり、明確にするからである。
*本能寺の変から35年後に本能寺の変の経緯を書き留めることに着手するという設定。
*著者は近衛家の門流で清華家の三男坊・清麿。変の当時、15歳で、わずか2年間だが、信長に小姓として近侍していた。信長公から「たわけの清麿」と呼ばれていた。清麿は当日(6/2)、他所に使いに出ていたので、難をまぬがれた。
*洛北、寺町通にある阿弥陀寺の信長公の墓に詣でる。信長公についてこれから一書を書くという報告をする。
この時住職から墓守りをする一人の男に引き合わされる。その男は森坊丸だった。
清麿は森坊丸から変当日の本能寺と信長の状況・事実を回顧譚として聞き取る。
坊丸は「本能寺の変の背後には、朝廷も関わった数々の陰謀があった。それを知っておられるがために、清玉上人は秀吉の手の者に害され、誠仁親王は割腹せざるをえない立場に追い込まれたのじゃ。そのようないきさつを何ひとつ知らず、物書きどもが見てきたような絵空事を書き散らしておる」(上、p52)と清麿に語る。
*本能寺の変が起こった時、阿弥陀寺は西の京の蓮台野にあった。一方、本能寺は、当時、堀川四条の北東方向、油小路通と蛸薬師通の辻の南東側が寺の中心辺りだった。
*この時(大坂の陣から2年後)、太田牛一の『信長公記』が世に流布していた。
*清麿の執筆動機は、「さるやんごとなきお方から、変について書き残してほしいという依頼を受けた」(上、p52)からと坊丸に語る。禁裏の学問所にて、秘蔵の文書や記録、公家の日記などを自由に調査でき、史資料として使うことを許されるという設定になっている。(上、p53)
*『御湯殿の上の日記』『兼見卿記』『多聞院日記』などの記録における記事の抜けや改ざんなどが引用され、内容が分析され、考察されていく。
つまり、信長から「たわけの清麿」と呼ばれた第三者の視点から本能寺の変に関わった人物たちが捉えられていく。
本能寺の変の経緯が、清麿によるルポルタージュという形で進展していく。
これが読者に対して説得力を生み出していく一因になる。
さらに、<序章 阿弥陀寺の花>には、上記の設定の凡その記述とパラレルに、天正10年(1582)6月2日早朝に起こった本能寺の変当日の状況並びに信長の死が描き出される。つまり、本能寺の変そのものの結末がこのストーリーの冒頭に提示される。
結果が最初にあり、<第1章 左義長> は、天正9年(1581)の年明けから始まる。最終章の <第16章 見果てぬ夢> は、「その頃、先発隊から本能寺の包囲を終えたという知らせを受けた明智光秀は、八千の本隊をひきいて桂川の渡河にかかっていた」(下、p543) の一文で終わる。つまり、本作は1年半という期間に凝縮した形で、なぜ本能寺の変が起こったかをルポルタージュ風に描きあげている。
<あとがきにかえて> の第2文に著者は「本能寺の変を公武の相剋という視点から描きたいという構想は、『関ヶ原連判状』を書いた頃から持っていた」(下、p544)と記す。
本能寺の変の主人公といえば、織田信長と明智光秀で、この二人の相剋ということになる。だが、この『信長燃ゆ』の主人公は織田信長と近衛前久の二人だと私は思った。明智光秀は准主役として位置づけられている気がする。そういう視点と感じるストーリーの進展にこの小説のおもしろさがあるように思う。
朝廷と明智光秀が共謀して本能寺の変が起こったという朝廷黒幕説がこのストーリーの仮説として根底にある。その朝廷の中において、信長の思考・戦略・行動に対峙して、常に帝の権威を維持し、朝廷の仕組みを維持・存立させて、武士よりも朝廷が上位にあらんと緻密な策謀を練る中心人物が近衛前久なのだ。信長に対立する立場なのだが、外見は信長の野望に協力・協調する姿勢をみせ続ける。信長の基盤を弱体化させ、切り崩そうと策謀する前久のスタンスと行動が描きこまれていく。前久のスタンスを知りつつ、それをねじ伏せて行こうとする信長。清麿が分析して眺めた本能寺の変に至る本質は、この二人の駆け引きの中に内在する。信長と前久の駆け引きが本作の読ませどころと言える。
前久は明智光秀を信長抹殺という共謀の形に取り込み、先頭に立たせていく。一方で、光秀に知らせずに信長打倒への策略の全体展開を推し進める。この前久の巧妙さは、なるほどありえるという方向に読者を誘っていく。この点、さすがである。
「時間の幅を短くして信長や前久の政治的な動きや内面を克明に描きたかった」(下、p545) と著者は記す。公武の相剋という政治的駆け引きと内面心理の動き。これが様々な局面で織り込まれている。両者の駆け引きは読者として楽しめるプロセスでもある。前久の息子・信基が信長に心酔していて、常に前久に対立する形で登場するのもおもしろい。父の前久が反対しようと、信長の武士、政治家としての魅力を代弁していることになる。
正親町天皇の嫡子で東宮の誠仁親王の夫人・勧修寺晴子が登場する。京での馬揃えについて、朝廷から安土への使者となる佐五の局に、晴子が身分を偽り、若狭の局と称して随伴する。これが晴子と信長の出会いとなる。この若狭の局を信長が記憶していたことから、後に思わぬ事態が契機ととなり、二人の恋が始まって行く。
本能寺の変が歴史の経緯を描く縦糸とすれば、この晴子と信長の関係はこのストーリーの横糸として、時間軸の進展の要所要所に織り込まれていく。
読者にとっては、事の成り行きの推移を楽しめる横糸である。この晴子の思いを介として、当時の朝廷における天皇周辺の状況がうかがえて興味深い。副産物として、当時は皇后という地位がなかったことを本書で知った。その理由は、皇后という地位を維持存続させる財源的基盤がなかったからという。また天皇の譲位、即位についても、その儀式の実施費用に窮しているのが朝廷の実態だったという。戦国時代の朝廷というものを今まで考えたことがなかった。例えば、平安時代と比較する意味でも、朝廷について、その実態を歴史的変遷の中で捉え直してみるために、改めて学ぶ必要性という課題が残った。
本書で印象に残る文を引用しご紹介したい。
*耐えきれぬ苦しみを抱えて生きていかねばならぬ者にとって、涙は絶望の淵から立ち上がるための心やさしき伴侶である。 (上・p43)
*多くの人は神仏に加護を求めるが、信長は神仏の力を我が身に取り込もうとしたのである。 (上、p298)
*信長が焼き討ちをかけたのは、比叡山が浅井、朝倉勢に身方して軍勢を山上にとどめたからだと言われている。
だが事の発端は、信長が近江国に散在する山門領を横領し、返還要求に応じなかったことだ。
比叡山側は三千院の門跡であられる応胤法親王を通じて朝廷に訴え、勅命をもって返還させようとした。 (上、p443)
→ このことを本書で初めて知った。史実を述べている箇所と理解した。
*真実とはかけ離れたことばかりが、歴史という名のもとにまことしやかに書き継がれていく。 (下、p184)
*信長が戦っていた相手は、個々の勢力ではない。人々の心の中にまで根強く張り巡らされた、こうした旧い意識なのである。 (下、p429)
*著者は、「たわけの清麿」に明智光秀について、次のように評させている。
「こうした陰謀に加担するには、あまりにも誠実で真っ直ぐな心の持ち主だったのである」(下、p428)と。
本作の全体構成としてのエンディングが興味深い。歴史時代小説、フィクションとしての醍醐味が遺憾なく盛り込まれていると思う。
終章は、興味深い場面で終わる。信長の死という側面とは別に種々の想いが残る。
明智光秀の心境は本能寺の変が成功したその時点ではどうだったのか・・・・。
羽柴秀吉はいわば漁夫の利を得られる立場になれる状況をもらったようではないか。
前久は、誠仁親王は、晴子は・・・・・・
それぞれの人物の行動と心理のあり様、そこを楽しむことができると思う。
ご一読ありがとうございます。
補遺
本能寺跡 :「京都観光Navi」
「本能寺の変」を調査する 発掘ニュース82 :「京都市埋蔵文化財研究所」
本能寺の変 :ウィキペディア
織田信長 :ウィキペディア
近衛前久 :ウィキペディア
戦場に出陣した破天荒な貴族・近衛前久の波乱万丈人生【麒麟がくる満喫レポート】:「サライ.jp」
明智光秀 :ウィキペディア
森成利 :ウィキペディア
森長隆 :ウィキペディア
勧修寺晴子 :ウィキペディア
上京区の史蹟百選/阿弥陀寺 :「京都市」
阿弥陀寺 (京都市上京区) :ウィキペディア
法華宗大本山 本能寺 公式サイト
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)