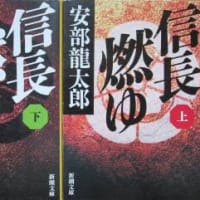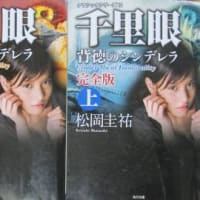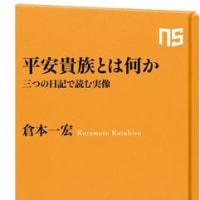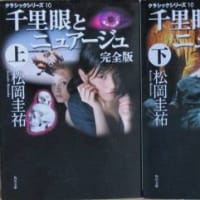2月下旬に谷津矢車著『憧れ写楽』(文藝春秋)を読んだ後、写楽関連でネット検索をしていて、本書の題名と出会った。その時、本書が昭和58年度第29回江戸川乱歩賞受賞作であることを知った。受賞は42年前になる。当時、なぜ気づかなかったのだろう。写楽に関心を抱くようになったのは、その後の時代だったのかもしれない。
この賞、調べてみると2024年度には第70回という歴史を刻んでいる。
本書は、昭和58年(1983)9月に単行本が刊行された。
地元の図書館の蔵書にあったので、借りて読んだ。1983年10月第5刷発行である。
 現在文庫本では新装版が出ている。これはその表紙
現在文庫本では新装版が出ている。これはその表紙
今や、ロングセラーの一冊になっているのだろう。
読もうと思った動機は勿論、題名に「写楽」が含まれていること。そして、写楽と「殺人」がどう関係するの? 時代設定は江戸時代? という疑問。
本書を読み始めてわかったのは、現代小説であること。
<プロローグ> は2ページにわたり、一本の掛軸の画を描写する。その掛軸の画面の左上部に、<寛政戊午如月 東洲斎写楽改近松昌栄画>と書き込まれていることを記す。後に、その書き込みを発見したのが写楽を研究する独身の研究者・津田良平だと読者にはわかる。彼は、私立の武蔵野大学で浮世絵を教えている西島俊作のゼミの10回生であり、西島の研究室に助手として残り、写楽を研究している。津田は「写楽研究ノート」という論文を発表していた。助手としては4年目。先輩で8年目の岩越が助手としていた。
ストーリは、一転して東京の篆書家・嵯峨厚(56)が探索むなしく遺体として沖合の海上で発見されるという状況から始まっていく。
嵯峨厚は、篆書家であるとともに浮世絵研究者としても著名で、「東京愛書家倶楽部」を主催する会長でもあった。在野の浮世絵研究者として著書も多数出版していた。嵯峨は研究上の見解の相違からここ5年来、いわゆる冷戦状態の関係にあった。
西島は、アカデミックな性格を持つ「江戸技術協会」に所属し、理事を務めていた。
嵯峨は、反協会的な姿勢をスローガンにして生まれた「浮世絵愛好会」の中心的人物の一人だった。この両会の対立が二人の冷戦を生んだのだ。嵯峨の死は、それが自殺か他殺かは別にして、西島にとっては論敵がいなくなったことを意味する。
この両会の対立が、まずこのストーリーの背景に存在する。
津田は、西島門下生であるがあることから破門状態になっている先輩の国府とは有効な関係を維持していた。この国府との関わりが、嵯峨の死という問題に津田が巻き込まれる一因にもなる。国府は嵯峨の失踪後に、嵯峨の義弟・水野に同行し、嵯峨の探索に関わっていたのだ。岩手県警の小野寺が、国府を訪ねてきたことが縁で、その時国府と一緒だった津田は、小野寺との面識ができる・・・・袖触り合うも多生の縁が深くなる方向に進展することに・・・・・。
津田は、「東京古書会館」での古本市に注文した本を受け取りに行く。そこで、嵯峨の義弟。水野に出会う。津田は展示会専門の古書商の水野から、一枚一枚写真を貼り付けた画集を譲られることになる。それは、白い帯に「清親序文入り、肉筆画集」と水野が記した古書で秋田蘭画だった。「湖山荘主人収蔵品名幅図録序」の末尾に「明治40年12月 清親」と記名がある。浮世絵の終焉を飾った絵師・小林清親が序文を書いた画集だった。
国立のアパートに戻った津田は、夕食後にこの画集を見始める。
これが、プロローグにリンクしていく。「東洲斎写楽改近松昌栄」という記入。これが写楽研究者である津田の関心を惹きつけていく・・・・・。
この小説の興味深いのは、この画集が契機となり、津田はこの画集のルーツを探求し始める。写楽と秋田蘭画の結びつきの信ぴょう性について。
津田の現地調査旅行に、国府の妹・冴子が興味を示し同行することになる。
その調査プロセスで、現地の古書店主たちとの交流が深まって行く。
このストーリーの前半は、津田が緻密な探求、分析のプロセスから写楽について一つの仮説「秋田蘭画説」を構築するプロセスが描きこまれていく。これ自体が一つの謎解きミステリーである。
この小説の起草された時点までに、写楽の正体と目される人物仮説について、昭和32年(1957)の円山応挙説から始まり、昭和56年(1981)の山東京伝説まで、13の人物仮説が、本文に一覧として列挙されている。これも興味深い。いくつかの説は見聞していたが、こんなにあるとは知らなかった。その後さらに増えているのだろうか。この箇所を読み写楽について興味がさらに深まった。
津田の仮説と論証について、報告を受けた西島教授はその仮説を認め、それを世界に発表するという方向で行動をとり始める。ここには、西島教授が言葉巧みに助手津田の仮説を己の業績にしていくやり口が描かれていく。こういうこと、あるだろうな・・・・そんな気にさせるシニカルな視点が盛り込まれている。
その過程で津田は疎外された立場に置かれていく一方で、己の仮説に新たな疑問点を見つけていく。仮説が破綻する可能性・・・・・。
仮説の構築を確かなものにするには、新たな謎解きミステリーに立ち向かう必要性が現れる。
津田の仮説に基づく論文が発表されたのち、西島が自宅で焼死する事件が起こる。
冷戦状態にあった嵯峨と西島が共になくなってしまった。これらは自殺なのか他殺なのか、事故死なのか。謎が深まる。
写楽を因とした殺人事件という観点が浮上してくる。ストーりーの後半は、殺人事件の謎解きミステリーが展開していくことになる。
そして、最後は、写楽秋田蘭画説構築の基盤となる証拠の中に仕組まれていたカラクリの謎解きに転じていく。津田自らがその謎の部分を発見する!!
実在した人物、史実としての人間関係と交流、実在した文物などを基盤にして、そこに巧妙に織り込まれたフィクションが、緻密な写楽仮説を構築させ、さらにそれを突き崩し破綻させる。そこに殺人事件を必然性のあるものとして組み込んでいく。実に巧妙なミステリーになっている。
40年という歳月を経ているが、色褪せてはいないストーリー展開である。ロングセラーであることを納得させる。実におもしろい。
今、NHKでは蔦屋重三郎を主人公とする大河ドラマ『べらぼう』が進行している。
この小説の中に、次のような会話が出て来る。引用する。
「そのまま田沼が権勢を誇っていたら、秋田藩も安泰、蔦屋も万万歳ってとこだったろうが、天明6年に田沼が失脚したことによって蔦屋の経営も苦しくなり始めたんだろう。だが、それまでの間に築きあげた強力な基盤があるから、何年かは持ちこたえた・・・・そこに第一回の発禁処分を言い渡された」(p166)
この第1回目は、天明8年で喜三二の『文武二道万石通」で、翌寛政元年に二冊が発禁。寛政3年に京伝の作が4回目の発禁処分になる。
こんな史実に絡んだ会話が織り込まれている。なぜ、写楽が生まれたかの背景話としてである。現在の大河ドラマとの接点が含まれているところも、興味深かった。この文脈では、「男に意地」が蔦屋に絡むキーワードになっている。
このくだり、私にとっては、副産物としておもしろく読めた。
秋田蘭画というのが存在したというのも、私には初めて知った副産物だった。
このストーリーの最終ステージで、津田の根底にあった心理を対話者が津田にあざやかに指摘している箇所がある。(p297)
「君は、あの画集を自分が掘り出したものと完全に信じた。」
「偶然に手に入れたものだと思い込ませることが、この計画の最も大切な部分だった」
この根っ子の心理がどのようにカラクリに組み込まれて行ったのか。楽しんでいただきたい。
ご一読ありがとうございます。
補遺
東洲斎写楽 :ウィキペディア
東洲斎写楽 作品一覧 :「日本文化遺産オンライン」
ユリウス・クルト :ウィキペディア
小島烏水 「江戸末期の浮世絵」:「横浜市立図書館デジタルアーカイブ」
小林清親 :ウィキペディア
小林清親一覧 :「秋華洞」
鳥高斎栄昌 :ウィキペディア
秋田蘭画とは? :「秋田県立美術館」
秋田蘭画 :ウィキペディア
世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画 :「水と生きるSUNTORY」
観光スポット:角館エリア :「仙北市」
角館 :ウィキペディア
朋誠堂喜三治 → 平沢常富 :ウィキペディア
朋誠堂喜三治(平沢常富) :「名古屋刀剣博物館 名古屋刀剣ワールド」
山東京伝 :ウィキペディア
蔦屋重三郎 :ウィキペディア
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
この賞、調べてみると2024年度には第70回という歴史を刻んでいる。
本書は、昭和58年(1983)9月に単行本が刊行された。
地元の図書館の蔵書にあったので、借りて読んだ。1983年10月第5刷発行である。
 現在文庫本では新装版が出ている。これはその表紙
現在文庫本では新装版が出ている。これはその表紙今や、ロングセラーの一冊になっているのだろう。
読もうと思った動機は勿論、題名に「写楽」が含まれていること。そして、写楽と「殺人」がどう関係するの? 時代設定は江戸時代? という疑問。
本書を読み始めてわかったのは、現代小説であること。
<プロローグ> は2ページにわたり、一本の掛軸の画を描写する。その掛軸の画面の左上部に、<寛政戊午如月 東洲斎写楽改近松昌栄画>と書き込まれていることを記す。後に、その書き込みを発見したのが写楽を研究する独身の研究者・津田良平だと読者にはわかる。彼は、私立の武蔵野大学で浮世絵を教えている西島俊作のゼミの10回生であり、西島の研究室に助手として残り、写楽を研究している。津田は「写楽研究ノート」という論文を発表していた。助手としては4年目。先輩で8年目の岩越が助手としていた。
ストーリは、一転して東京の篆書家・嵯峨厚(56)が探索むなしく遺体として沖合の海上で発見されるという状況から始まっていく。
嵯峨厚は、篆書家であるとともに浮世絵研究者としても著名で、「東京愛書家倶楽部」を主催する会長でもあった。在野の浮世絵研究者として著書も多数出版していた。嵯峨は研究上の見解の相違からここ5年来、いわゆる冷戦状態の関係にあった。
西島は、アカデミックな性格を持つ「江戸技術協会」に所属し、理事を務めていた。
嵯峨は、反協会的な姿勢をスローガンにして生まれた「浮世絵愛好会」の中心的人物の一人だった。この両会の対立が二人の冷戦を生んだのだ。嵯峨の死は、それが自殺か他殺かは別にして、西島にとっては論敵がいなくなったことを意味する。
この両会の対立が、まずこのストーリーの背景に存在する。
津田は、西島門下生であるがあることから破門状態になっている先輩の国府とは有効な関係を維持していた。この国府との関わりが、嵯峨の死という問題に津田が巻き込まれる一因にもなる。国府は嵯峨の失踪後に、嵯峨の義弟・水野に同行し、嵯峨の探索に関わっていたのだ。岩手県警の小野寺が、国府を訪ねてきたことが縁で、その時国府と一緒だった津田は、小野寺との面識ができる・・・・袖触り合うも多生の縁が深くなる方向に進展することに・・・・・。
津田は、「東京古書会館」での古本市に注文した本を受け取りに行く。そこで、嵯峨の義弟。水野に出会う。津田は展示会専門の古書商の水野から、一枚一枚写真を貼り付けた画集を譲られることになる。それは、白い帯に「清親序文入り、肉筆画集」と水野が記した古書で秋田蘭画だった。「湖山荘主人収蔵品名幅図録序」の末尾に「明治40年12月 清親」と記名がある。浮世絵の終焉を飾った絵師・小林清親が序文を書いた画集だった。
国立のアパートに戻った津田は、夕食後にこの画集を見始める。
これが、プロローグにリンクしていく。「東洲斎写楽改近松昌栄」という記入。これが写楽研究者である津田の関心を惹きつけていく・・・・・。
この小説の興味深いのは、この画集が契機となり、津田はこの画集のルーツを探求し始める。写楽と秋田蘭画の結びつきの信ぴょう性について。
津田の現地調査旅行に、国府の妹・冴子が興味を示し同行することになる。
その調査プロセスで、現地の古書店主たちとの交流が深まって行く。
このストーリーの前半は、津田が緻密な探求、分析のプロセスから写楽について一つの仮説「秋田蘭画説」を構築するプロセスが描きこまれていく。これ自体が一つの謎解きミステリーである。
この小説の起草された時点までに、写楽の正体と目される人物仮説について、昭和32年(1957)の円山応挙説から始まり、昭和56年(1981)の山東京伝説まで、13の人物仮説が、本文に一覧として列挙されている。これも興味深い。いくつかの説は見聞していたが、こんなにあるとは知らなかった。その後さらに増えているのだろうか。この箇所を読み写楽について興味がさらに深まった。
津田の仮説と論証について、報告を受けた西島教授はその仮説を認め、それを世界に発表するという方向で行動をとり始める。ここには、西島教授が言葉巧みに助手津田の仮説を己の業績にしていくやり口が描かれていく。こういうこと、あるだろうな・・・・そんな気にさせるシニカルな視点が盛り込まれている。
その過程で津田は疎外された立場に置かれていく一方で、己の仮説に新たな疑問点を見つけていく。仮説が破綻する可能性・・・・・。
仮説の構築を確かなものにするには、新たな謎解きミステリーに立ち向かう必要性が現れる。
津田の仮説に基づく論文が発表されたのち、西島が自宅で焼死する事件が起こる。
冷戦状態にあった嵯峨と西島が共になくなってしまった。これらは自殺なのか他殺なのか、事故死なのか。謎が深まる。
写楽を因とした殺人事件という観点が浮上してくる。ストーりーの後半は、殺人事件の謎解きミステリーが展開していくことになる。
そして、最後は、写楽秋田蘭画説構築の基盤となる証拠の中に仕組まれていたカラクリの謎解きに転じていく。津田自らがその謎の部分を発見する!!
実在した人物、史実としての人間関係と交流、実在した文物などを基盤にして、そこに巧妙に織り込まれたフィクションが、緻密な写楽仮説を構築させ、さらにそれを突き崩し破綻させる。そこに殺人事件を必然性のあるものとして組み込んでいく。実に巧妙なミステリーになっている。
40年という歳月を経ているが、色褪せてはいないストーリー展開である。ロングセラーであることを納得させる。実におもしろい。
今、NHKでは蔦屋重三郎を主人公とする大河ドラマ『べらぼう』が進行している。
この小説の中に、次のような会話が出て来る。引用する。
「そのまま田沼が権勢を誇っていたら、秋田藩も安泰、蔦屋も万万歳ってとこだったろうが、天明6年に田沼が失脚したことによって蔦屋の経営も苦しくなり始めたんだろう。だが、それまでの間に築きあげた強力な基盤があるから、何年かは持ちこたえた・・・・そこに第一回の発禁処分を言い渡された」(p166)
この第1回目は、天明8年で喜三二の『文武二道万石通」で、翌寛政元年に二冊が発禁。寛政3年に京伝の作が4回目の発禁処分になる。
こんな史実に絡んだ会話が織り込まれている。なぜ、写楽が生まれたかの背景話としてである。現在の大河ドラマとの接点が含まれているところも、興味深かった。この文脈では、「男に意地」が蔦屋に絡むキーワードになっている。
このくだり、私にとっては、副産物としておもしろく読めた。
秋田蘭画というのが存在したというのも、私には初めて知った副産物だった。
このストーリーの最終ステージで、津田の根底にあった心理を対話者が津田にあざやかに指摘している箇所がある。(p297)
「君は、あの画集を自分が掘り出したものと完全に信じた。」
「偶然に手に入れたものだと思い込ませることが、この計画の最も大切な部分だった」
この根っ子の心理がどのようにカラクリに組み込まれて行ったのか。楽しんでいただきたい。
ご一読ありがとうございます。
補遺
東洲斎写楽 :ウィキペディア
東洲斎写楽 作品一覧 :「日本文化遺産オンライン」
ユリウス・クルト :ウィキペディア
小島烏水 「江戸末期の浮世絵」:「横浜市立図書館デジタルアーカイブ」
小林清親 :ウィキペディア
小林清親一覧 :「秋華洞」
鳥高斎栄昌 :ウィキペディア
秋田蘭画とは? :「秋田県立美術館」
秋田蘭画 :ウィキペディア
世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画 :「水と生きるSUNTORY」
観光スポット:角館エリア :「仙北市」
角館 :ウィキペディア
朋誠堂喜三治 → 平沢常富 :ウィキペディア
朋誠堂喜三治(平沢常富) :「名古屋刀剣博物館 名古屋刀剣ワールド」
山東京伝 :ウィキペディア
蔦屋重三郎 :ウィキペディア
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)