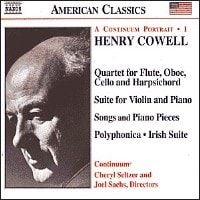ここで著者・石原千秋氏が言う《記号学》とは、
「『漱石』を歴史的文脈に置き直すことで、『漱石神話』を、いや『漱石神話』の〈読者〉を問い直すこと」(「はじめに」)
である。つまりは、「則天去私」のようなフレーズに、教訓じみた意味を持たせるのではなく、「歴史的文脈」の中に置き換えることで、「時代の言葉」としての意味を浮き彫りにしようとするのであり、同時代文学として、読者がテクストから受け取って意味を明らかにしようとする試みである。
そのために著者に選ばれたキー・ワードは、「次男坊」「長男」「主婦」「自我」「神経衰弱」「セクシュアリティー」である。「セクシュアリティー」だけは、多くのことばを代表しての単語であるが、他はすべて漱石文学にそのままの形で登場する。
分りやすい例を挙げると「神経衰弱」。
「神経衰弱とヒステリーは時代とともに生れ、時代とともに消えた『病』なのである」(「第五章 神経衰弱の記号学」)が、漱石文学では『猫』から既に登場している。
「運動をしろの、牛乳を飲めの、冷水を浴びろの、海の中へ飛び込めの、夏になつたら山の中に籠つて当分霞を食へのとくだらぬ注文を連発する様になつたのは、西洋から神国へ伝染したバン近の病気で、矢張りペスト、肺病、神経衰弱の一族と心得ていゝ位だ」
ここでは皮肉混じりに使用されている「神経衰弱」も、『道草』では夫婦間の非言語的交通(ノンバーバルコミュニケーション)として、女性の「ヒステリー」に拮抗するものとして表現されていると著者は言う。
また、『行人』の一郎に関しては、「まちがいなく性差のある言説で自己の『不安』を編成しているのだ。一郎は、『文明の病』としての神経衰弱を、さらに先鋭化させて、〈知〉の病に作り変えることで、自らのアイデンティティーを生きていると言えよう」。
したがって、「漱石文学において、男であることは神経衰弱を病むことに外ならなかった。すなわち、男として生きることは、一つの悲劇であったのだ。その意味で、神経衰弱とは無縁の『三四郎』の小川三四郎、『明暗』の津田由雄の存在は興味深い。彼らはどのような『男』だったのだろうか」と、疑問を投げかけて、次章の「第六章 セクシュアリティーの記号学」へ論旨を進めていく。
これで、著者の方法論と構成について、概略は分ったであろう。
確かに、この方法論・構成によって、今までの文藝評論には見えてこなかった部分が、明らかにされた側面がある。
ただし、新聞小説の読者が、そこまでの深い意味を受け取っていたかどうか、その点に若干の疑問は残る(無意識の内に受け取っていた、と言われればそれまでなのであるが)。
そういう意味から見れば、著者にとっては、やや本筋からずれた話題にはなるが、「終章 方法としての東京」の方が、現代の読者にとっては、納得がしやすいことであろう。
石原千秋
『漱石の記号学』
講談社選書メチエ156
定価:本体1500円(税別)
ISBN4062581566
「『漱石』を歴史的文脈に置き直すことで、『漱石神話』を、いや『漱石神話』の〈読者〉を問い直すこと」(「はじめに」)
である。つまりは、「則天去私」のようなフレーズに、教訓じみた意味を持たせるのではなく、「歴史的文脈」の中に置き換えることで、「時代の言葉」としての意味を浮き彫りにしようとするのであり、同時代文学として、読者がテクストから受け取って意味を明らかにしようとする試みである。
そのために著者に選ばれたキー・ワードは、「次男坊」「長男」「主婦」「自我」「神経衰弱」「セクシュアリティー」である。「セクシュアリティー」だけは、多くのことばを代表しての単語であるが、他はすべて漱石文学にそのままの形で登場する。
分りやすい例を挙げると「神経衰弱」。
「神経衰弱とヒステリーは時代とともに生れ、時代とともに消えた『病』なのである」(「第五章 神経衰弱の記号学」)が、漱石文学では『猫』から既に登場している。
「運動をしろの、牛乳を飲めの、冷水を浴びろの、海の中へ飛び込めの、夏になつたら山の中に籠つて当分霞を食へのとくだらぬ注文を連発する様になつたのは、西洋から神国へ伝染したバン近の病気で、矢張りペスト、肺病、神経衰弱の一族と心得ていゝ位だ」
ここでは皮肉混じりに使用されている「神経衰弱」も、『道草』では夫婦間の非言語的交通(ノンバーバルコミュニケーション)として、女性の「ヒステリー」に拮抗するものとして表現されていると著者は言う。
また、『行人』の一郎に関しては、「まちがいなく性差のある言説で自己の『不安』を編成しているのだ。一郎は、『文明の病』としての神経衰弱を、さらに先鋭化させて、〈知〉の病に作り変えることで、自らのアイデンティティーを生きていると言えよう」。
したがって、「漱石文学において、男であることは神経衰弱を病むことに外ならなかった。すなわち、男として生きることは、一つの悲劇であったのだ。その意味で、神経衰弱とは無縁の『三四郎』の小川三四郎、『明暗』の津田由雄の存在は興味深い。彼らはどのような『男』だったのだろうか」と、疑問を投げかけて、次章の「第六章 セクシュアリティーの記号学」へ論旨を進めていく。
これで、著者の方法論と構成について、概略は分ったであろう。
確かに、この方法論・構成によって、今までの文藝評論には見えてこなかった部分が、明らかにされた側面がある。
ただし、新聞小説の読者が、そこまでの深い意味を受け取っていたかどうか、その点に若干の疑問は残る(無意識の内に受け取っていた、と言われればそれまでなのであるが)。
そういう意味から見れば、著者にとっては、やや本筋からずれた話題にはなるが、「終章 方法としての東京」の方が、現代の読者にとっては、納得がしやすいことであろう。
石原千秋
『漱石の記号学』
講談社選書メチエ156
定価:本体1500円(税別)
ISBN4062581566