
国子監
第五節 明代の北京の文化
明代の北京は封建政治と軍事の中心であり、且つ封建文化の堡塁(ほうるい)であった。ここで、統治する立場を占めた文化は封建文化であった。これは封建統治階級の独占した文化であった。しかし、直接一般の人々に属する民間文化と進歩した文化も絶えず闘争の中で成長した。
統治階級の北京での文化統治
明朝の統治者が北京に建都後、直ちに北京にいくつかの文化教育機構を設置した。明の統治者はこれらの機構をを用いて文化を独占し、同時にまたこれらの機構を利用し、地主階級の子弟を養成、選抜し、それによりさらにうまく封建統治を維持しようとした。明朝廷で試験を管轄していたのは礼部で、礼部の主な職責のひとつは三年に一回の会試と殿試であった。明朝では、地主階級の子弟は会試や殿試を通じて選抜され、上層の統治グループの中に入ることができた。このため三年毎に、何千何万の受験生が北京に集まって来た。会試、殿試の主要な内容は、四書五経から出題される問題に、八股の対句形式の文章を作ることで、八股文は一定の格式に基づいていなければならず、「聖人の代わりに立言」しなければならず、且つ朱熹の四書注を根拠にしなければならなかった。八股文は成化帝(9代。1465年 - 1487年)の時に始まり、その後、一般に名誉や利益を求める地主階級の知識分子の間で広まり、思想的には完全に程朱理学の範囲内に限られていた。
明朝の最高学府である国子監は地主階級知識分子を養成するところで、一般の人々は根本的に入学できなかった。明朝の国子監は二か所あり、南京のものは南監と呼ばれ、北京のものは北監と呼ばれた。国子監の中には孔子廟、講堂、宿舎、図書館、刻書処があり、国子監に入学し勉強する生員を監生と呼んだ。第5代宣徳帝(1425-1435年)の時、北京の国子監で学習する学生は約1万人に達し、明朝中葉でも5、6千人おり、その中で国子監に寄付をする人数はもっと多かった。ここにはまた各地の少数民族の学生もおり、高麗、シャム(暹罗。タイの古称)、ベトナムの学生もいた。学生は主に四書を読み、八股文を学び、学習の内容はまた程朱理学の範囲を越えてはならなかった。
明朝廷はまた太医院、欽天監、四夷館にそれぞれ学習班を附設して専門の人材を育成し、ここで学習するのも地主階級の子弟であった。太医院は大方脈、小方脈、婦人、瘡瘍(腫瘍)、針灸、眼、口歯(口腔)、接骨、傷寒(腸チフス)、咽喉、金鏃、按摩等、13科に分かれていた。1443年(正統8年)、ここで人の体の各つぼの位置を示した銅の人形が鋳造され、この銅の人形はたいへん高い科学的価値を備え、しばしばこれを用いて針灸科の学生の試験が行われた。欽天監には天文、暦日、回回、漏刻の4科が設けられ、これ以外に観象台(天文台)が設けられ、この中には各種の測定用の計測器が置かれた。四夷館は八つの館に分かれ、学生たちはここで各種の少数民族と各国の言語や文字を学習し、その中にはモンゴル語、チベット語、ウイグル語、タイ語、ビルマ語、梵語があった。
明朝廷は更に地主階級の知識分子を組織し、図書編集の仕事に従事させた。図書編集の目的は、文化を独占し、より多くの人を集めて封建統治者に奉仕させるためであった。明初に南京で『永楽大典』を編集した時は、2100人余りの文人が参加し、この本を編集した後、皇帝はこれを北京に運び、文淵閣の中に置き、皇帝の御覧に供する以外は、特別な許可が無ければ、如何なる人も中に入って読むことを許されなかった。
『永楽大典』は全部で22,937巻あり、中国で最も古く、最大の百科事典であり、中国で最も貴重な文化遺産である。明朝では正副二部を写し取っていたが、正本は既に消失し、副本は今日尚300冊余り現存する。これらの貴重な図書は大多数が英仏連合軍と八か国連合軍が北京に侵攻した際、帝国主義者により焼かれたり掠奪されたりした。
明朝廷はまた多くの禁令を発布し、全ての統治者の利益に反する、進歩的、民主的な思想、文学、小説、戯曲については、徹底的に破壊した。しかし、封建地主階級が如何に文化を独占し、文化に損害を与えても、民間文化と文化の進歩は依然として争いの中で成長し、発展した。
王学左派の北京での活動
明朝初年、封建統治者は客観唯心主義の程朱理学(宋、明代の唯心論哲学思想で、程は程顥(ていこう)・程頤(ていい)兄弟、朱は朱熹(しゅき)(朱子)のこと)を強力に提唱し、程朱理学は地主階級知識分子の思想の中で支配地位を占めるものであった。

程顥・程頤兄弟
明朝中葉になって、程朱理学の思想界での支配的地位は動揺を始め、王陽明が広く宣伝した主観唯心論の「致良知」(「良知」(先天的に人の心にそなわった理性知)を推し究め発現すること)学説がこれに代わって流行した。王陽明は「天地万物は皆吾が心中に在り」、「物の理(ことわり)は吾が心に外ならず」、そのため彼は「致良知」を用いて程朱の「挌物致知」(後天的知を拡充(致知)して自己とあらゆる事物に内在する個別の理を窮め、究極的に宇宙普遍の理に達する(挌物)ことを目指す)に反対した。王陽明の学説と程朱理学は同様に唯心主義の範疇に属し、何れも統治階級の利益を擁護するものだった。しかし、王陽明の弟子の王艮(おうこん)らに到り、彼らは程朱理学に対しなお反対しただけでなく、君主専制体制についても厳しく非難した。王艮らは比較的一般大衆に近く、彼らに同情していたので、「王学左派」に発展し、王学の対立者となった。
王学左派の代表は、王艮を除き、他に顔山農、梁汝元、李贄らがいた。
梁汝元は顔山農の学生で、彼には空想的原始社会主義の理論があり、同族の人の「貧富互助、有無相通」を主張した。こうした理論は正に当時の農民の未来の見通しに対する一種の理想と互いに符合し、そのため彼の理論は一部の人々の擁護を得ることができた。嘉靖年間、梁汝元は北京で「辟谷(断食)派会館にて、四方の士を招来し」、会館を利用して講演を行い、当時の統治者の専制や腐敗した権力に対して攻撃を加え、「方技雑流、これに従わざるは無し。」明朝の人は、北京は嘉靖から隆慶年間にかけ(1522-1572年)、商人や侠客が活躍し、そのいわゆる侠客とは梁汝元などを指した。梁汝元のこうした活動は、統治者をたいへん不安に感じさせ、彼らは百方手を尽くして彼を逮捕しようとした。万暦初年、張居正が宰輔(宰相)になり、専制統治を強め、湖北巡撫に梁汝元を殺すよう、ほのめかした。
王学左派のもうひとりの代表人物は李贄(りし)で、1601年(万暦29年)通州に来て講義を行った。李贄は君主専制、旧礼学、程朱一派の理学に反対した。彼は孔子が提起した是非の基準も疑ってみるべきだと考え、卓文君が司馬相如と駆け落ちをしたのは「良き伴侶をうまく選んだ」のだと考えた。彼は民間の文学、芝居、民間歌謡をたいへん好み、彼が評注を加えた『忠義水滸伝』の中で、梁山泊の好漢たちにも心からの同情を寄せた。李贄は当時の政治制度、統治思想に猛烈な攻撃を展開したので、彼が通州に来るや、北京の統治者たちは恐れおののき、甚だしきは彼を「魔物」と呼んだ。

李贄
統治者たちが李贄を恐れるのは、李贄の思想が多くの人々の共鳴を得ているからであった。1602年(万暦30年)になり、明朝朝廷は「敢えて乱道を唱え、世を惑わし民を偽る」という罪状で李贄を逮捕し、北京に連行した。この時、李贄は既に76歳の老人であったが、彼は自分が無実の罪に貶められたことにたいへん憤懣し、錦衣を着て獄中で刀で喉を割き自殺した。
李贄の専制に反対し個性の解放を追求する思想は、当時たいへん進歩した思想であった。李贄は統治者たちに対し真正面から痛撃を与え、当時圧迫を受けていた人々の願望を最大限表現した。明、清の統治者は李贄が書いた『蔵書』、『焚書』、彼が評注を加えた『忠義水滸伝』などに対して、何度も焼き払うよう命令を出したが、しかしながらこれらの書物はずっと社会の中で人々に読み継がれていた。
李贄の墓は今なお通県にあり、彼を記念するため、新たに修築されている。
文学
明朝統治者は八股文で人々の思想を束縛し、甚だしき場合、検閲によって専制主義に抵触する書物を書くことを厳禁した。こうした措置は文学の発展を甚だしく阻害した。
永楽年間の北京遷都以後、専制主義の中央集権体制が安定期を迎え、この時北京の文人の中で、地主階級が天下太平を引き立て、その功績をほめたたえた「台閣体」の文章が出現した。明の翰林、李時勉の『北都賦』がその一例である。
明朝中葉以後、封建士大夫たちの文壇では、専らことばのあやを弄した 台閣体はもはや歓迎されず、これに代わり起こったのが、「前後七子」の復古派の文体であった。復古派は、「文は必ず秦漢、詩は必ず盛唐」を主張し、ひたすら古人を模倣しなければならず、そのため形式の上でも内容でも如何なる創造的な成果も見られなかった。万暦年間になり、進歩性を帯びた文学が活発になり、反復古主義の改良運動が出現した。これは明らかに当時の社会経済の発展と、哲学の先進思想の影響を受け、生まれたものである。反復古主義改良運動の提唱者は公安、竟陵の両派で、公安派の代表は袁宗道、袁宏道、袁中道の三人で、彼らは文学での模倣に反対し、「挌套」(格式、型を守ること)に反対し、 「文は必ず秦漢」の復古主義者に反対し、「ただ情感を表現し、型にとらわれない」ことを主張した。彼らと李贄は、「師友」(師として敬い仰ぐほどの友人)の関係で、李贄の言葉や行動に対し、たいへん敬服していた。彼らは、当時正に日増しに盛んに興っていた小説、芝居、民間歌謡、メロディを好み、圧迫を受けていた大衆に対しても一定の同情を感じていた。彼らが書いた文章は比較的わかりやすく親しみがあった。袁氏兄弟は北京に住んでいたことがあり、多くの北京の名所に関する文章を書いている。竟陵派の代表は鐘惺、譚元春らで、彼らも復古に反対であった。竟陵派の作家、劉侗が書いた『帝京景物略』は、北京城郊外の庭園の古跡を描いた名著で、多くの北京をたたえる詩歌や、北京に関する史料を記録している。
公安派、竟陵派の作者は皆地主階級の知識分子であり、彼らの生活圏は限られており、一般大衆との接点は少ない。彼らの闘争性は希弱で、とりわけ 公安派には退廃的消極的な一面があった。
芝居
明朝統治者は民間の芝居の歌詞や曲に対しても厳しい制限と危害を加えた。永楽年間、刑科給事中の曹潤がこう上奏した。「今後、人民は雑劇を歌い演じる際、戒律を守る仙人や道士、妻への忠義を守る夫、夫に節操を守る妻、親孝行の子や孫、人に善行を勧め平和を喜ぶ者は禁じないが、帝王や聖賢を冒涜する歌詞や曲、皇帝の登場する芝居、戒律を守らず、敢えて収蔵、語り伝え、出版販売する者は、その場で逮捕、護送、訴訟、追求する」。「上意を承った内容:これらの歌詞や曲は、告示後、五日以内に処分し、役所に行き焼却すること。敢えて収蔵した者は、家族全員殺害する。」(顧起元『客座贅語』巻10『国書榜文』)ここから、明初の統治者は大衆的なシナリオや歌詞をたいへん恐れていたことが分かる。また、当時「帝王や聖賢を冒涜」した芝居は確かに既に結構あったことが分かる。
明の統治者が大いに提唱したのは、彼らの統治に有利な芝居であった。例えば、明初の朱有燉 らが創作した雑劇は、その内容が封建倫理を大いに宣伝するものであることを除き、でたらめでとりとめがない仙人や仏教道教の物語で、農民蜂起に対し極端に中傷していた。そして当時の宮廷の勲戚(功績のある皇族)たちは専らこうした雑劇によって退屈しのぎをした。宮廷内で流行した「宮戯」(宮廷内で上演された人形劇)には「打稲」「過錦」などの芝居が含まれ、これらはなおさら単調で退屈なものだった。ただ民間の人形劇を利用して、半身を水上に浮かべたものがあり、これは「宮戯」の中でも最も人々を惹きつけたものだった。
明朝中葉になり、都市の商工業が日増しに盛んになると、こうした都市の住民たちにたいへん喜ばれる芝居が雨後の竹の子のように広がってきた。この時、各地で上演された民間雑劇は既に千余りにもなっていた。多くの劇の脚本が統治者による出版禁止や上演禁止の処分を受けていたが、その中で強烈な反封建的な礼儀道徳意識を備えた『小尼下山』、『墻頭馬上』などは依然として広く伝わり、しかも上演され、更には『元夜鬧花灯』(水滸伝の中の物語)さえも禁止できなかった。さらに注目すべきは、江南の芝居までもがたいへん速いスピードで北京に入って来たことで、万暦年間、弋陽腔(よくようこう。江西省弋陽県から始まった地方劇の節回し)や昆曲が北京でたいへん流行した。更には統治者までも「宮戯」は単調だと感じ、何人かの宦官に命じて宮廷外の芝居の演出を勉強させた。外の芝居は既に 宮戯を圧倒していた。
1583年(万暦11年)明代の著名な演劇作家湯顕祖(とう けんそ)が北京にやって来た。彼は科挙の受験で来たのだが、政権当事者の排斥に遭い、すぐに故郷へ帰ってしまった。湯顕祖の哲学思想は王学左派に近く、彼は李贄に対してもたいへん尊敬していた。文学の面では、彼は公安派の、ただ人の情感を表現するという主張に完全に同意し、芝居の上で過度に音韻や形式、韻律を重んじることに断固反対した。そのため彼が創作した脚本の中でも音韻や形式、韻律の制限を打ち破り、その構成や思想内容に注意した。彼の代表作、牡丹亭は、労働者も含む北京の人々が最も愛し、幅広く伝播した劇本である。この劇の中で、彼は一組の男女の恋愛の物語を通じ、自由で幸福な愛情をたたえ、彼らの個性解放を強く求める心情と、人間性を奪う礼儀、道徳がもたらす情け容赦の無い鞭打ち(鞭笞)を描写した。
長編戯曲の昆曲が北京に伝わって以後、専ら勲功のある皇族や王公が楽しんだ朱有燉のような作家が創作したものは、とっくに正に進展する巨大な浪の中に埋没してしまった。芝居の劇団はこの時も王侯の邸宅から劇場に移動した。今日の広和劇場の前身、査楼は、明末には既に建てられていた。












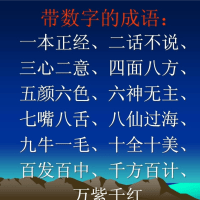







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます