今回の記事は文科省の大学改革についての記事をソースにしています。
文科省は教育を通して豊かな人間性を育てようとは微塵も考えておらず、常に、我々庶民の税金を使って、外郭団体に流し込むことしか考えていません。
そして、それが最期の悪あがきとなりそうな大学改革の指針が発表されました。
・・・・・・・・(文科省が発表した「2020年大学改革」驚きの中身 グループ化…ってどういうこと?2018年4月8日 6時0分 現代ビジネス)
地方国大・私大の経営を統合
少子化時代の大学運営について、文部科学省が「大改革案」を示した。
その内容は大胆で、2020年度から、各地方で大学をグループ化したうえで、新法人を作って、一体化した経営を行うというもの。しかもその枠組みは国公立・私立の垣根を超えるもので、一体経営によって各地域の個性をより強く打ち出すことで、大学経営の安定と学生への求心力を高める狙いがある。
少子化で各大学の経営体力が落ちるなか、地域の国公私立大をグループ経営にすることで乗り切るというものだが、この改革が成功する可能性はどれほどなのか。
この新法人は、表向きは「経営基盤を強化しグループの強みや特色を打ち出す」ために設立されるものである。グループ内の大学で共同教育課程を編成したり、施設・設備の相互利用や入試業務などの事務作業を共同化することで、各大学の得意分野に資金・人材を集中させることができるという理屈だ。
だが、このような施策を打ったところで、少子化に歯止めがかからない以上、経営破綻に追い込まれる大学が現れるのは時間の問題だ。だからこそ、文科省はその先を見通して、大学の破綻時には新法人が学生や教職員のセーフティネットになることを期待しているという「本音」がある。
新しく作られる法人は一般社団法人「大学等連携推進法人(仮称)」なるもので、文科相が新法に基づき認定する仕組みになっている。その新法人に、国立大学法人、公立大学法人、学校法人がそれぞれ運営費を拠出し、理事や職員を派遣する。
こうした仕組みは、'90年代後半に相次いだ金融機関の破綻処理策を彷彿とさせる。'90年代以前には、日本の金融機関は破綻するはずがないという「神話」がたしかにあった。ところが、バブル崩壊に象徴される経済変動を目の当たりにすると、その神話は崩壊する。それでも、金融機関を潰してはいけないという議論が巻き起こった。
結局、金融機関の破綻後の仕組みを作らなかったことにより、日本経済全体が受けたダメージはより大きくなった。こうした前例を考えると、大学の破綻処理の仕組みを考えておくのは正しい。ただし、その方法として「新法人」が適切であるかどうかは精査する必要がある。
金融機関の場合は、破綻にともなう混乱を最小限に留めるため、「資金援助方式」が優先されることになっている。この方式では、破綻した金融機関の事業を救済金融機関に移管し、その救済金融機関に支援を行う。あくまで、新たな法人を立てて受け皿を作るようなことはしない。
この考え方から見れば、文科省の提案する大学運営の新方式は、必ずしもコストの面で「最小」とはいえない。国立大学法人、公立大学法人、学校法人という法人格縦割りが障害となり、事業の移管がスムーズにできないからである。これを解決するためには、まず大学の法人格を一本化したほうが早いし、新法人を作る必要もなくなる。
穿った見方をすれば、新法人の設立は文科省官僚の新しい天下り先の確保の手段にも見える。
とにもかくにも、学校法人の破綻に備えるうえで、よりコストがかからない方法はほかにもあるのだ。
『週刊現代』2018年4月14日号より
・・・・・・・(転載ここまで)
>少子化で各大学の経営体力が落ちるなか、地域の国公私立大をグループ経営にすることで乗り切るというものだが、この>改革が成功する可能性はどれほどなのか。
>穿った見方をすれば、新法人の設立は文科省官僚の新しい天下り先の確保の手段にも見える。
これらの記事を読んで私が感じたことは、純粋に天下り先である、私立大学が不人気+少子化で定員割れしているため整理される恐れがあるため、「国立大学、公立大学ブランド」とコラボして天下り先の不人気地方私立大学を存続させようとしているように思えました。
そもそも学歴神話はとっくの昔に崩壊しています。

給料を減らし、物価を上げ、重税を課す現在の政府のやり方に、多くの家庭がこどもを大学にいかせるほどの経済力がなくなっていますし、大卒でも大企業に就職したとしても、外回りの営業職のようなブルーカラーをさせられる心身ともに困憊しうつ病になって辞めて行くか自殺するハメになると情報が出回ってしまい、「大学に行くメリットが少なくなっている」と多くの若者が気付き始めています。

それに気付いていないのは、固定観念に縛られた親の世代であり、未だに見栄と虚栄心だけで、大金をつぎ込んでこどもを大学に通わせているのです。
私が警察官時代に先輩を見ていて思ったのは、出世していく人は高卒警察官ばかりだったということです。
逆に巡査部長や警部補でくすぶってるのは有名大学を卒業した人達が多かったことに驚いていました。
しかし、今から思えば、警察という仕事は検事の代行捜査をしているだけで実際はブルーワーカーなのです。
ですから、検事というホワイトカラーの指揮下に入り手足のように動けることが大切であり、自発的に何かをする能力は求められていないのだと解ります。
そういった組織の特徴を鑑みれば、世の中の仕事は高卒で十分働けますし、実際は15歳から即戦力となりえます。
多くの大学生は、先行きの不安から目を逸らすように、サークル活動やコンパ、アルバイトに明け暮れてただただ悪戯に時間を浪費しているに過ぎません。


目端の聴く学生は大学を中退して、自分のやりたい仕事、業界に飛び込んで行きます。
そうやって活路を見出すのが世の中で、学校の試験のように常に答えが決まっていない、無限の可能性を秘めている場であると親はこどもに教育していくことが、学歴神話に騙されないマインドセットだと考えられます。










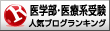









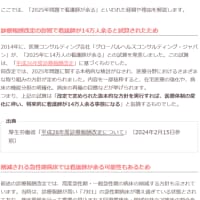






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます