政府は、人口減少していく日本において、医師や看護師が余ってくることが分かっています。
ですから、医学部定員も減らすことになっています。
(医学部臨時定員を削減へ 27年度に厚労省、医師過剰備え2025年1月21日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA216900R20C25A1000000/#:~:text=%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E3%81%AF21%E6%97%A5,%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A%E3%81%A7%E5%8D%94%E8%AD%B0%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82)
しかし、看護業界だけは時代に逆行して、看護大学をどんどん新設していっています。
(医療系でない大学まで…なぜ? 止まらない看護大学の新設ラッシュ、25年間で20倍に増加 https://www.kango-roo.com/work/1102/)
看護師の4年生化を進めているのは、日本看護協会です。
そして新設大学や学科を許可しているのは文部科学省です。
2025年には看護師が14万人余ると言われているのに。
ここまで来ると、「文科省と日本看護協会による詐欺行為」としか言いようがありませんね。
・・・・・・・・・・・・・・・・
看護師求人を見てください。
多くの病院は新卒看護師よりも、卒後教育が終わっている(とされる)第2新卒を1年中募集しています。
「病院は新卒はいらない。即戦力となる中途採用に力をいれている状況」です。
過去記事にもありますが、日本の主要産業は「自動車」と「医療」です。
特に、コロナ禍によって、政府は国民の生活に直結する「経済」よりも「病院・医療」を守ってしまいました。
病院医療を守るために、とてつもない補助金を投入したのです。
その結果何が起こったのか?というとコロナ禍の中、医者たちが権力を振り回し続けたのです。
言いたい放題、政治にも口出しし始めたのです。
医療が力を持ち過ぎたため、医療産業を本格的に弱体化させる動きが、財務省を中心として2023年あたりから始まりました。
その影響により、2025年現在、実際に病院の倒産件数がどんどん増えていっています。
(詳しくは以下の動画をご覧ください)
【後編】相次ぐ病院の倒産、廃止、そして適正配置へ……この難局を医師はどう乗り越えるのか
・・・・・・・・・・・・・・・・・
実は、日本がこうなることはラプトブログで予言されていました。
『RAPT有料記事730(2023年3月25日)2023年に入ると、悪の力は急速に衰え、義の力が強力にこの世を動かすようになる。世の中が神様の御心にかなった世界へと急速に変化していくだろう。https://rapt-neo.com/?p=58104』
高齢者人口が増え、医療よりも介護の需要が増えていく一方、「名ばかり急性期」が不要となって削減されていくことは決定しています。
病院は少ないコストで看護スタッフを育成しなくてはならないため、「資格を持っているから」という理由だけで採用できなくなってきています。
「看護師免許を取得しても仕事がない」時代に入るのです。
かつては、「介護は給料が安い」と言われていましたが、今、介護の人出不足で、介護の給料がどんどん上がっています。
一方、看護師の給料は横ばいです。(給料が上がっても、職場環境が改善されていないので離職は多い)
・・・・・・・・・・・・・・・
医療介護業界は社会になければならない仕事だと思います。
ただ、この業界に対して「仕事がなくならないから」とか「給料が良いから」という安直な理由だけで選択しない方が良いということを最後に付け加えたいと思います。
(「2025年問題で看護師が余る」といわれた理由 https://kango-oshigoto.jp/media/article/248/)
ここでは、「2025年問題で看護師が余る」といわれた経緯や理由を解説します。
診療報酬改定の影響で看護師が14万人余ると試算されたため
2014年に、医療コンサルティング会社「グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン」が、「2025年に14万人の看護師が余る」との試算を発表しました。この試算は、「平成26年度診療報酬改定」に基づくものでした。
同改定では、2025年問題に関する本格的な検討がなされ、医療分野におけるさまざまな取り組みの方針が定められました。内容を一部抜粋すると、在宅医療の強化や、病床の機能分担の明確化、病床の再編の目標などが挙げられます。
つまり、上記の試算は「改定で定められた抜本的な方針を実行すれば、医療体制の変化に伴い、将来的に看護師が14万人余る事態になる」と指摘するものでした。
削減される急性期病床では看護師が余る可能性もあるため
前述の診療報酬改定では、高度急性期・一般急性期の病床の削減する方針も示されています。当時は、診療報酬が高い「7対1」の急性期病床が増え過ぎている状態とされており、病床再編を行って需要の見込まれる回復期病床・地域包括ケア病床の割合を増やす方針が固められました。
つまり、試算において「余る」とされた14万人の看護師は、同改定によって削減が決められた急性期病床で働く方を指していたのです。
実際に、急性期病床の数は減少してきています。厚生労働省の「地域医療構想、医療計画について(23p)」によると、2015年から2020年にかけて、高度急性期病・急性期の病床は約76.5万床から約70.3万床に減少しました。一方、回復期病床は約13.0万床から約18.9万床に増えています。確かに、急性期病棟の削減に伴って看護師が余る可能性もありますが、徐々に配置換えが行われているため、職を失う看護師が急増することは考えにくいでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)






















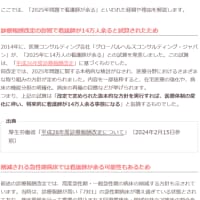

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます