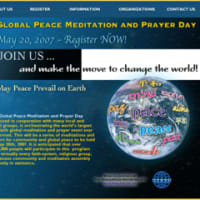小乗には四聖諦、三十七道品、三学というカリキュラムがあるわけですが、大乗の波羅蜜乗には「布施」「持戒」「忍耐」「精進」「禅定」「智慧」という六波羅蜜があります。ダライ・ラマは、「三学」や「戒律」という小乗の教えが修行されていなければ、大乗の教えを実践することは困難だ、と言います。さらに、
******************
大乗仏教の修行である六波羅蜜の修行や、愛と慈悲、そして菩提心を育む修行がされていない状態で密教の修行に入ろうとしても、それは、まったく不可能なことでしかありません。・・・
チベット仏教は、小乗、大乗、密教の教えをすべて備えた修行の道であると言われますが、密教の修行をするためには、顕教という小乗と大乗の修行を段階的に実践しておくことがまず必要です。(58~59頁)
******************
と言います。つまり、小乗は大乗の土台、大乗(顕教)は密教の土台であり、その段階を踏んで修行しなければならないというわけです。
法然・親鸞によって開花した日本の浄土門は発想が根本的に違います。法然・親鸞は、小乗(そして大乗)の教えをそのまま実践することは、専門的僧侶でさえとうてい不可能だと考えて、念仏一念という易行道を開発しました。そこには小乗→大乗→密教といった段階的プログラムはありません。チベット仏教は、法然・親鸞以前の専門的僧侶の養成プログラムなのです。ですから、チベット仏教を修行するということはたいへんなことなのです。すべてをなげうって修行一筋に邁進しなければ、とうていものになるはずはありません。
五井先生の『阿難』にも書かれているように、仏陀の時代から、専門的僧侶には厳しい修行が課せられていました。チベット仏教は、そのような仏陀時代からの修行内容を密教にまで拡大して受け継いでいると言えるでしょう。仏教大学でちょっと勉強したきりで、あとは肉食妻帯し、ぜいたくで安易な生活をしている日本の多くの仏教僧侶は、チベット仏教から見たら、僧侶の名に値しないということになるでしょう。
さて、私は深く研究してはいませんが、チベット密教にはチャクラを開いたり、クンダリーニを覚醒させる様々な瞑想法があるようです。それがチベット仏教の今日人気の源泉になっているのでしょう。しかし、そういう修行を中途半端に行なうと、人によっては一種の霊能力に目ざめることもありますが、それは人格を歪め、かえって危険になる場合もあります。麻原彰晃やオウム真理教がその典型です。
そういうことを避けるために、ダライ・ラマは、密教の修行を開始する以前に、小乗と大乗の教えをきちんと学び、実践しておかなければならない、と強調しているものと思われます。その中でも彼が最も重視しているのが、空の理解と菩提心です。
******************
大乗仏教の修行である六波羅蜜の修行や、愛と慈悲、そして菩提心を育む修行がされていない状態で密教の修行に入ろうとしても、それは、まったく不可能なことでしかありません。・・・
チベット仏教は、小乗、大乗、密教の教えをすべて備えた修行の道であると言われますが、密教の修行をするためには、顕教という小乗と大乗の修行を段階的に実践しておくことがまず必要です。(58~59頁)
******************
と言います。つまり、小乗は大乗の土台、大乗(顕教)は密教の土台であり、その段階を踏んで修行しなければならないというわけです。
法然・親鸞によって開花した日本の浄土門は発想が根本的に違います。法然・親鸞は、小乗(そして大乗)の教えをそのまま実践することは、専門的僧侶でさえとうてい不可能だと考えて、念仏一念という易行道を開発しました。そこには小乗→大乗→密教といった段階的プログラムはありません。チベット仏教は、法然・親鸞以前の専門的僧侶の養成プログラムなのです。ですから、チベット仏教を修行するということはたいへんなことなのです。すべてをなげうって修行一筋に邁進しなければ、とうていものになるはずはありません。
五井先生の『阿難』にも書かれているように、仏陀の時代から、専門的僧侶には厳しい修行が課せられていました。チベット仏教は、そのような仏陀時代からの修行内容を密教にまで拡大して受け継いでいると言えるでしょう。仏教大学でちょっと勉強したきりで、あとは肉食妻帯し、ぜいたくで安易な生活をしている日本の多くの仏教僧侶は、チベット仏教から見たら、僧侶の名に値しないということになるでしょう。
さて、私は深く研究してはいませんが、チベット密教にはチャクラを開いたり、クンダリーニを覚醒させる様々な瞑想法があるようです。それがチベット仏教の今日人気の源泉になっているのでしょう。しかし、そういう修行を中途半端に行なうと、人によっては一種の霊能力に目ざめることもありますが、それは人格を歪め、かえって危険になる場合もあります。麻原彰晃やオウム真理教がその典型です。
そういうことを避けるために、ダライ・ラマは、密教の修行を開始する以前に、小乗と大乗の教えをきちんと学び、実践しておかなければならない、と強調しているものと思われます。その中でも彼が最も重視しているのが、空の理解と菩提心です。