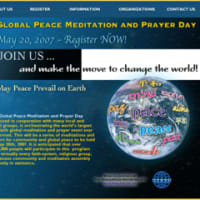清水勇氏の新著『ある日の五井先生』は、世界平和の祈りの提唱者、白光真宏会の初代会長である五井昌久師の日常の言行を記録した書物である。清水氏は白光真宏会の青年部長、総務部長、教宣部長を歴任した方で、しかも五井先生のお住まい(会長室)のすぐ近くの宿舎に住んでいたので、五井先生の身近に接する機会が多かった。清水氏の著書からは、五井先生の愛深くて気さくで飾らない人間性が生き生きと伝わってくる。現代の聖者とはこういう人をいうのであろう。
著書や講演では素晴らしい宗教的真理を説いていても、日常生活では冷酷であったり、金銭欲や権力欲にまみれていたり、自己中心的であったとしたならば、その人は本ものの宗教者とは言えない。その人は、言っていること・書いていることと、行なっていることが分裂していることになる。宗教者は単なる思想家や神学者ではない。予言者や霊能者でもない。全人格をもって神仏のみ心を現わし、実践する人でなければならない。
聖者というと、何か超越的な能力を示したり、奇跡を引き起こしたり、未来を予言したりするような人を想像するかもしれない。あるいは、常人には行ない得ない自己犠牲的な愛行を想像するかもしれない。もちろん、五井先生にもそういう話題は枚挙にいとまがないほど存在した。しかし、五井先生は普段は、神秘的なことはめったにおっしゃらなかったし、行ないもしなかった。『ある日の五井先生』の中で五井先生は、「わたしほど当たり前の人間はいないだろうね」と語っている。
「当たり前」が世間の人々と同じレベルの「当たり前」では、ただの俗人であるが、五井先生は、仏教的に言えば「一切智」を体得した覚者でありながら、高い悟りの世界から衆生のもとに降りてきて、庶民と同悲同喜しながら、その中で人々を導いた。五井先生は「小聖は山にこもり、大聖は市井に住む」ともおっしゃっていた。
釈迦やキリストにもない、五井先生の特長の一つは、その明るさとユーモアであろう。晩年の五井先生は、世界の業を一身に引き受けて浄化するために、肉体的には病人のような状態であったが、そのような中でも、自分を「お床の中の男」と称し、いつもユーモアを忘れなかった。そのようなエピソードが清水氏の著書にはいくつか紹介されている。
筆者も、清水氏ほど頻繁ではないが、五井先生に接する機会があった。五井先生が逝去してすでに二十数年になるが、清水氏の著書からは、五井先生が、在世当時そのままの声と姿で語りかけてくる。五井先生を直接知らない方も、この本を通して、現代に生きた聖者にまみえることができるだろう。
著書や講演では素晴らしい宗教的真理を説いていても、日常生活では冷酷であったり、金銭欲や権力欲にまみれていたり、自己中心的であったとしたならば、その人は本ものの宗教者とは言えない。その人は、言っていること・書いていることと、行なっていることが分裂していることになる。宗教者は単なる思想家や神学者ではない。予言者や霊能者でもない。全人格をもって神仏のみ心を現わし、実践する人でなければならない。
聖者というと、何か超越的な能力を示したり、奇跡を引き起こしたり、未来を予言したりするような人を想像するかもしれない。あるいは、常人には行ない得ない自己犠牲的な愛行を想像するかもしれない。もちろん、五井先生にもそういう話題は枚挙にいとまがないほど存在した。しかし、五井先生は普段は、神秘的なことはめったにおっしゃらなかったし、行ないもしなかった。『ある日の五井先生』の中で五井先生は、「わたしほど当たり前の人間はいないだろうね」と語っている。
「当たり前」が世間の人々と同じレベルの「当たり前」では、ただの俗人であるが、五井先生は、仏教的に言えば「一切智」を体得した覚者でありながら、高い悟りの世界から衆生のもとに降りてきて、庶民と同悲同喜しながら、その中で人々を導いた。五井先生は「小聖は山にこもり、大聖は市井に住む」ともおっしゃっていた。
釈迦やキリストにもない、五井先生の特長の一つは、その明るさとユーモアであろう。晩年の五井先生は、世界の業を一身に引き受けて浄化するために、肉体的には病人のような状態であったが、そのような中でも、自分を「お床の中の男」と称し、いつもユーモアを忘れなかった。そのようなエピソードが清水氏の著書にはいくつか紹介されている。
筆者も、清水氏ほど頻繁ではないが、五井先生に接する機会があった。五井先生が逝去してすでに二十数年になるが、清水氏の著書からは、五井先生が、在世当時そのままの声と姿で語りかけてくる。五井先生を直接知らない方も、この本を通して、現代に生きた聖者にまみえることができるだろう。