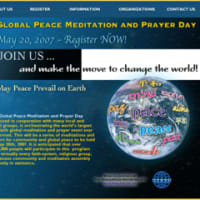八月下旬に京都で第八回世界宗教者平和会議世界大会が開かれた。この平和会議は、日本の宗教者が世界の諸宗教の代表者に呼びかけて発足したもので、第一回も一九七〇年に京都で開催された。不定期に四~五年に一度、世界各地で開催されてきたが、今回は三六年ぶりに日本での開催となった。
今日、世界各地で多発している紛争の原因の一つが宗教対立にあることは否定できない。九・一一事件以降、キリスト教・ユダヤ教世界とイスラム教世界との「文明の対立」が激化している感がある。宗教は本来、人間の心の中に平和を築き、平和世界の建設に貢献するべき活動であるはずなのに、残念なことである。そのような時に、様々な宗教の代表者がともに世界平和を目指して一堂に会して話し合うということは、たいへん有意義なことだと思う。
ただし、「平和会議」となると、平和を阻害している具体的な問題の解決がどうしても話題の中心になりがちである。今回の会議でも、「紛争予防」「武器拡散、軍縮、安全保障」「暫定的公正と人権」「子供とHIV/エイズ」「貧困撲滅」「環境」などの問題について分科会が開かれた。いずれも重要な問題ではあるが、宗教者の会議で具体的な成果を得ることは困難であろう。とくに日本の宗教者は対社会的な実践活動が苦手である。会議の日本関係者は、「正直言って、議論への積極的な関与は難しい。命の危険と隣り合わせの国から来る宗教指導者が多い中で、平和に慣れきってしまった日本人が議論をリードするのは無理だ」と述べたという(毎日新聞)。実際、日本の宗教者の影は薄かったようだ。海外の代表者は、「広島・長崎の被爆を経験した日本の宗教者は、平和を追求するうえで特別な役割を果たす」と何度も述べたが、これに対して日本の宗教者はまともな応答ができなかったのである。
しかし、日本の宗教者は本当に世界の宗教界に対して何も提言できないのだろうか?
白光真宏会の前会長である故五井昌久師は、第一回会議の日本代表の一人であった。五井師は会議で、「宗教者の役割は政治や経済の問題の解決ではない。宗教者の本分はあくまでも、そういう問題を生み出す人間の心の問題の解決である。様々な宗教が対立を超えるためには、誰もが納得できる世界平和を希求する共通の祈りを定め、ともに祈ることが必要だ」と提案した。この提言は今日ますます重要である。祈りは単なる心弱い願望ではない。人類の集合的意識を変える強力なエネルギーの発振である。まず日本の宗教者が、宗教の違いを超えてともに世界平和を祈る姿を世界人類に模範として示すべきであろう。
今日、世界各地で多発している紛争の原因の一つが宗教対立にあることは否定できない。九・一一事件以降、キリスト教・ユダヤ教世界とイスラム教世界との「文明の対立」が激化している感がある。宗教は本来、人間の心の中に平和を築き、平和世界の建設に貢献するべき活動であるはずなのに、残念なことである。そのような時に、様々な宗教の代表者がともに世界平和を目指して一堂に会して話し合うということは、たいへん有意義なことだと思う。
ただし、「平和会議」となると、平和を阻害している具体的な問題の解決がどうしても話題の中心になりがちである。今回の会議でも、「紛争予防」「武器拡散、軍縮、安全保障」「暫定的公正と人権」「子供とHIV/エイズ」「貧困撲滅」「環境」などの問題について分科会が開かれた。いずれも重要な問題ではあるが、宗教者の会議で具体的な成果を得ることは困難であろう。とくに日本の宗教者は対社会的な実践活動が苦手である。会議の日本関係者は、「正直言って、議論への積極的な関与は難しい。命の危険と隣り合わせの国から来る宗教指導者が多い中で、平和に慣れきってしまった日本人が議論をリードするのは無理だ」と述べたという(毎日新聞)。実際、日本の宗教者の影は薄かったようだ。海外の代表者は、「広島・長崎の被爆を経験した日本の宗教者は、平和を追求するうえで特別な役割を果たす」と何度も述べたが、これに対して日本の宗教者はまともな応答ができなかったのである。
しかし、日本の宗教者は本当に世界の宗教界に対して何も提言できないのだろうか?
白光真宏会の前会長である故五井昌久師は、第一回会議の日本代表の一人であった。五井師は会議で、「宗教者の役割は政治や経済の問題の解決ではない。宗教者の本分はあくまでも、そういう問題を生み出す人間の心の問題の解決である。様々な宗教が対立を超えるためには、誰もが納得できる世界平和を希求する共通の祈りを定め、ともに祈ることが必要だ」と提案した。この提言は今日ますます重要である。祈りは単なる心弱い願望ではない。人類の集合的意識を変える強力なエネルギーの発振である。まず日本の宗教者が、宗教の違いを超えてともに世界平和を祈る姿を世界人類に模範として示すべきであろう。