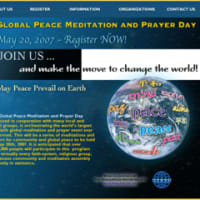クリント・イーストウッド監督制作の映画『硫黄島からの手紙』を観た。
昭和二十年二月、小笠原諸島の硫黄島には、圧倒的な軍事力を誇る米軍が押し寄せた。この島を米軍に渡せば、この島は米空軍の基地にされ、そこから日本本土への空襲が行なわれることになる。すでに日本の敗色は濃かったが、島を奪われることを一日でも引き延ばし、その間に日本政府にアメリカとの和平交渉を少しでも有利に進めてもらうために、栗林忠道中将は、将兵全員の戦死を覚悟の上、硫黄島を死守することを決意した。
アメリカ駐在武官を経験した栗林中将は、アメリカの巨大な経済力と軍事力を知悉していた。戦争末期、「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦陣訓に呪縛され、各地の日本軍は戦略的には無意味な玉砕攻撃をしかけていたが、栗林中将は玉砕を禁じ、硫黄島全体に地下壕を張り巡らし、そこからゲリラ攻撃をしかけて、米軍の消耗を狙った。当初、五日間で終わると米軍が見ていた島の占領は一ヶ月あまりも要した。この戦闘で二万九三三名の日本軍は二万一二九名が戦死、アメリカ軍も、七千名近い戦死者と二万人以上の戦傷者という、大きな被害をこうむった。
硫黄島は、米軍の歴史の中で最も悲惨な戦闘で、アーリントン墓地には、硫黄島の摺鉢山に星条旗を押し立てる六人の米兵の群像が建てられ、硫黄島は米軍の英雄主義の象徴となっている。
イーストウッド監督は、『父親たちの星条旗』という映画で、硫黄島の戦闘とそれに参加した米兵のその後を描いたが、『硫黄島からの手紙』では同じ戦闘を日本軍の視点から描いた。映画そのものは、戦闘場面が中心で(それも実際の悲惨さからはほど遠い)、太平洋戦争末期の日本の政治的・軍事的状況の背景説明がなかったし、栗林中将の人間性の掘り下げも今ひとつであり、また日本の社会の描き方も事実とずれている。しかし、アメリカ人がほとんど日本人俳優だけが登場する映画を作り、しかも「アメリカ=正義、日本=悪」という単純な図式に陥らず、日本人を対等な存在と見ていることは評価できる。
映画の最後の場面で、栗林中将は、「後世の日本国民は自分たちが硫黄島で戦ったことを必ず思い出し、諸君の霊に涙して黙祷してくれるだろう」と語る。今上陛下は平成六年に硫黄島に行かれ、「精根を込め戦ひし人未だ地下に眠りて島は悲しき」という御製を作られた。私たちは、今日の日本が、大勢の人々の尊い犠牲の上に築かれていることをあらためて想起し、戦没者への追悼とともに、日本を、世界平和に貢献し、世界の人々から尊敬される立派な国にしていかなければならないと思う。
※硫黄島については、以前も書きました。
昭和二十年二月、小笠原諸島の硫黄島には、圧倒的な軍事力を誇る米軍が押し寄せた。この島を米軍に渡せば、この島は米空軍の基地にされ、そこから日本本土への空襲が行なわれることになる。すでに日本の敗色は濃かったが、島を奪われることを一日でも引き延ばし、その間に日本政府にアメリカとの和平交渉を少しでも有利に進めてもらうために、栗林忠道中将は、将兵全員の戦死を覚悟の上、硫黄島を死守することを決意した。
アメリカ駐在武官を経験した栗林中将は、アメリカの巨大な経済力と軍事力を知悉していた。戦争末期、「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦陣訓に呪縛され、各地の日本軍は戦略的には無意味な玉砕攻撃をしかけていたが、栗林中将は玉砕を禁じ、硫黄島全体に地下壕を張り巡らし、そこからゲリラ攻撃をしかけて、米軍の消耗を狙った。当初、五日間で終わると米軍が見ていた島の占領は一ヶ月あまりも要した。この戦闘で二万九三三名の日本軍は二万一二九名が戦死、アメリカ軍も、七千名近い戦死者と二万人以上の戦傷者という、大きな被害をこうむった。
硫黄島は、米軍の歴史の中で最も悲惨な戦闘で、アーリントン墓地には、硫黄島の摺鉢山に星条旗を押し立てる六人の米兵の群像が建てられ、硫黄島は米軍の英雄主義の象徴となっている。
イーストウッド監督は、『父親たちの星条旗』という映画で、硫黄島の戦闘とそれに参加した米兵のその後を描いたが、『硫黄島からの手紙』では同じ戦闘を日本軍の視点から描いた。映画そのものは、戦闘場面が中心で(それも実際の悲惨さからはほど遠い)、太平洋戦争末期の日本の政治的・軍事的状況の背景説明がなかったし、栗林中将の人間性の掘り下げも今ひとつであり、また日本の社会の描き方も事実とずれている。しかし、アメリカ人がほとんど日本人俳優だけが登場する映画を作り、しかも「アメリカ=正義、日本=悪」という単純な図式に陥らず、日本人を対等な存在と見ていることは評価できる。
映画の最後の場面で、栗林中将は、「後世の日本国民は自分たちが硫黄島で戦ったことを必ず思い出し、諸君の霊に涙して黙祷してくれるだろう」と語る。今上陛下は平成六年に硫黄島に行かれ、「精根を込め戦ひし人未だ地下に眠りて島は悲しき」という御製を作られた。私たちは、今日の日本が、大勢の人々の尊い犠牲の上に築かれていることをあらためて想起し、戦没者への追悼とともに、日本を、世界平和に貢献し、世界の人々から尊敬される立派な国にしていかなければならないと思う。
※硫黄島については、以前も書きました。