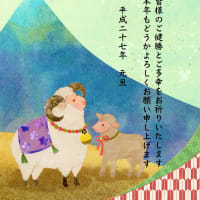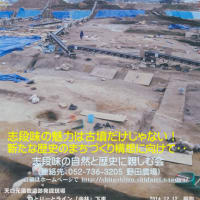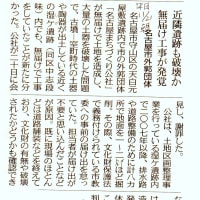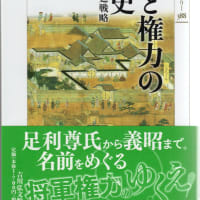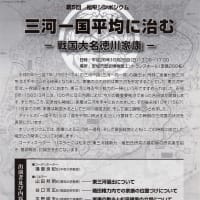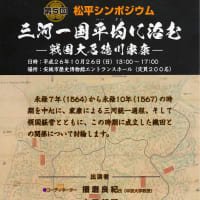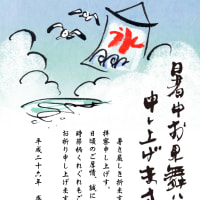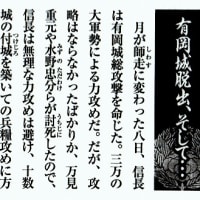飯高山 萬勝禅寺
岐阜県恵那市山岡町馬場山田175 Visit :2006-10-14 10:30
●飯高山 萬勝寺(いいだかさん まんしょうじ)
[由緒]――「萬勝寺リーフレット」から抜粋、編集――
♦飯高山 萬昌寺
この寺の前身は、萬昌寺(まんしょうじ)と称し、当初は修験道の寺として開基された。平安時代に入って、修験道が真言・天台の二宗と結びつき大きく成長したことから、萬昌寺は天台宗の寺院として栄えていった。
寺傳によれば、萬昌寺の開祖は慈覺大師(圓仁。延暦十三年(794)~貞観六年(864))といわれ、本尊千手観世音菩薩は、慈覺大師の三札一刀の作であった。慈覺大師は、比叡山延暦寺の三代座主で傳教師(最澄)の開いた基礎を固めて、全国に天台の教団を拡大していった、天台創立当時の高僧である。その教化(*1)は都に留まらず、故郷の下野(*2)はもとより陸奥(青森)、出羽(秋田)までに及んでいる。当時の東山道は神坂越(*3)の難所をひかえていたため、多くはその脇道として山岡から上矢作を経ての道(*4)を利用していた。圓仁も脇道を辿りその途中の飯高(当地)へ教化に訪れたのは、齢六十代半ばの天安二年(858)頃であったろうと推察されている。
圓仁が開祖して三百二十四年後の文治元年(1185)、美濃国遠山庄(*5)地頭に任命された加藤影廉の子・影朝は岩村(*6)に定住し遠山姓を名乗り、美濃遠山氏の祖となった。
この後遠山氏は岩村を本家とし、明智、苗木(*7)等々七つに分かれて、恵那全域に勢力を拡大していった。影朝の築いた岩村城から4Kmと離れていない萬昌寺も当然その影響下にあり、岩村遠山氏、明智遠山氏の庇護を受けていた。
記録によれば、この頃の萬昌寺は、現萬勝寺よりも西方にあり、七堂伽藍(山門、佛殿、法搭、庫裏、僧堂、浴室、東司)、佛法道場、仁王門を備え山内寺院(不動院、孤月坊、大聖坊、般若坊、尊勝寺、内光寺、苦別堂)、鎮守白山大権現、田澤山中薬師ケ寺の都合十二院、観音堂は十二間(約22m)四面とあり、堂々たる大寺であったと伝えられている。
その後四百年近くは全盛期にあったものの、戦国時代となり元亀三年(1572)、武田信玄の家臣秋山信友の率いる三千の兵が東美濃を襲い、遠山一族は奥三河の徳川軍の兵も率いて上村(上矢作町)で奮戦するも、明智城主遠山影行は敢えなく討ち死にした。翌天正二年(1574)正月、武田勝頼が本格的な東美濃侵攻を開始し、岩村城をはじめとし苗木など周辺の十六城を攻め落として進軍し、明智城に向かう途中、萬昌寺に美濃の兵が潜んでいるのを恐れて境内に火を放ち、栄華を誇った飯高山萬昌寺は無念にも、わずか一日にして焼失の憂き目に遇った。この焼失に伴い貴重な史料は全て失われてしまった。萬昌寺には、明智城落城の元亀三年(1572)までは、明智城主遠山景行の二男利景(1542-1614)が、住職として入り(*8)自休と名乗っていたが、落城に際し遠山一門から還俗を勧められ、二十八歳にして自ら民部利景と名乗り、一族の長として僧から戦国武士へと転身を遂げた。慶長五年(1600)、関ヶ原の戦いで明智城を奪還し、三年後にあらためて家康から城を賜り六千五百三十一石を拝領し、漸く安穏な晩年を送れるようになった利影は、慶長十九年(1614)、遺言に旧栖萬昌寺の再興を頼み世を去った
♦妙法山 萬勝寺
遺言により、二年後の元和二年(1616)、萬昌寺炎上から四十余年後にして、ようやく萬昌寺境内に新しい堂宇が建立された。
利影の菩提寺である龍護寺(*9)住職であった椽室和尚は、村の有力者・後藤新右衛門、春日井総右衛門、桜井某の協力によって、戦禍を免れた圓仁作の本尊千手観世音菩薩を観音堂に安置し、本堂には新たに南無十一面観世音菩薩像を本尊として奉ったことから宗派、山号、寺号ともに改め、開山を椽室和尚とする臨済宗妙法山萬勝寺が誕生した。
当時の檀家は僅か二十数戸で、無冠、無位の僧侶が守る寺(平僧地)であり、寺格は決して高くはなかったが、約百年後の、宝永六年(1709)から延享元年(1744)の間には、尾張國から冶工第四代水野平蔵政武を招いて喚鐘を新鋳するまでに寺の形態は次第に回復していった。それから更に百年を下った文政期(十九世紀初め)(*10)になると、和田(*11)の与作という人物が中心となって萬勝寺に鐘を造ることを発願し、村内外に喜捨(*12)を求めたところ七十一両一分が集まったという記録が残っている。これにより寺格は低いものの土地の人々の信仰は篤かったことがうかがえ、尾張から鐘鋳師水野太郎左衛門を招いて出来上がった鐘は、恵那の地にさぞかし美しく鳴り響いたことであろうと観想される。
廃仏毀釈の波を乗り越え昭和に至ったが、同十六年(1941)二月、失火により堂宇を全て失ってしまった。しかしながら、阿弥陀堂の千手観世音菩薩像、本尊の南無十一面観世音菩薩像をはじめとした各佛像は幸いにもその難を免れることができた。
同十九年(1944)、第二次世界大戦により前年に出征した第十九代玄勇和尚は逝去した。
当時、寺も無し住職も居ない中、少ない檀家が一丸となって萬勝寺の再興に尽力したことで、同二十一年(1946)、本堂、観音堂、庫裏が出来上がった。
昭和三十九年(1964)明俊和尚が第二十代住職となり、壇信徒の支援により山門、鐘楼、庫裏、庭園を再建することができた。
♦飯高山 萬勝寺
平成四年(1992)、老朽化した本堂を再建したのを契機に、日頃壇信徒から“飯高さん”と親しまれてきたことから、山号を「妙法山」から、従前の「飯高山」に改号した。
同十三年(2001)、二十一世紀到来と符牒を合わせるが如く、第二十一代となった浩和尚の誕生を記念して、平成稀にみる見事な観音堂が落慶した。戦国時代、昭和と二度の危機をかいくぐってきた千手観世音菩薩像は今なお厄除け観音として人々の信仰を集めている。
[註]
*1=きょうけ。布教活動。
*2=下野国 (しもつけのくに) は、かつて日本の地方行政区分だった国の一つで、東山道に位置する。領域は現在の栃木県とほぼ同じ。延喜式での格は上国、遠国。野州 (やしゅう) と略されることがある。現在の関東地方の北部中央、北関東の中央に位置する。
*3=恵那山の北東、神坂山(みさかやま)手前にある峠を越える険しい山道。岐阜県中津川市神坂。
*4=国道257号線、岐阜県恵那市山岡町から上矢作町。
*5=岐阜県恵那市山岡町。旧遠山村。
*6=岐阜県恵那市岩村町。
*7=岐阜県中津川市苗木。
*8=戦国時代、武家は後継者争いを防ぐため下の子供達を寺に預けた。
*9=りょうごじ。岐阜県恵那市明智町東山町1389-1。明智城山麓、北北東約380m。
*10=『尾張の鋳物師』(名古屋市立博物館 部門展図録)によると、文政十二年(1829)水野太郎左衛門政辰作梵鐘は現状「失亡」としるされており、文政年間(1818-1830)と年代が整合する。銘文に「住持 宗活・妙法第一座前龍護比丘仁宿文雅銘」とあり、当時の住職は「宗活」であったことが分かる。(下記、第十一代水野太郎左衛門政辰作梵鐘を参照)
*11=岐阜県恵那市山岡町馬場山田1300-1400付近の旧「和田」。
*12=きしゃ。進んで金銭や物品を寺社や困っている人に差し出すこと。
●第四代水野平蔵政武作(年紀名なし)の喚鐘
(宝永六年(1709)相続~延享元年(1744)没までの三十六年間内の作品)
銘文
-----------------------------------------------------------------------------------------------
東 濃 陽 恵 那 郡 飯 高 郷
妙 法 山 萬 勝 禅 寺 半 鐘 之
銘 并 序 欽 惟
鐘 之 功 徳 甚 大 也 悉 不 伸 厥
功 略 而 挙 大 意 吾 租 宗 門 下 徒
不 □ 諸 刹 而 □ 聞 鐘 悟 道 之
旨 村 次 之 人 民 不 跨 寺 門 而 主 礼
佛 聞 梵 之 心 謂 聞 声 端 的 随
-----------------------------------------------------------------------------------------------
分 有 功 永 掛 在 梵 宮 普 繞 益
有 情 雖 然 如 是 准 是 知 無 功
徳 将 是 得 活 功 徳 矣 其 豈
可 竭 言 也 哉
銘 曰
形 容 似 小 世 名 半 鐘
声 動 南 北 響 伝 西 来
晨 昏 驚 夢 古 今 破 聲
-----------------------------------------------------------------------------------------------
下 根 猶 緩 上 智 稍 忽
聞 々 潤 益 事 々 豈 同
魔 群 堪 感 佛 令 顕 功
法 界 平 等 虚 谷 圓 融
知 慈 機 用 普 利 無 窮
未 九 月 如 意 珠 日
施 主 岩 村 之 住 人 松 田 氏 正 勝
-----------------------------------------------------------------------------------------------
自 明 安 済 菴 主
爲 菩 提 寄 進 之
現 住
禅 恕 首 座 新 添
尾 州 名 古 屋 鍋 屋 町
冶 工 水 野 平 蔵
藤 原 政 武
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[銘文註釈]
解読不明の“□”の文字については、喚鐘の撮影をした際、撮影ミスでピントが合っていなかったことで、残念ながら判読は不可能となった。
●第十一代水野太郎左衛門政辰作梵鐘――<佚亡(いつぼう)> <<参考>>
(文化六年(1809)生まれ、文政三年(1820)家督相続、天保九年(1838)没)
『濃飛両国梵鐘年表』から抜粋――
紀元:文政十二年(1829)三月
所有者:恵那郡馬場山田村 飯田郷 妙法山萬勝寺
鋳物師:尾州名古屋住 水野太郎左衛門尉 藤原政辰
銘文:・住持 宗活
・妙法第一座前龍護比丘仁宿文雅銘
直径:47.0
☆旅硯青鷺日記
山門を入ると、正面奥深くに真新しい威風堂々とした観音堂が辺りを圧しており、左手奥には、静寂な本堂が建立され、境内は掃き清められ静と動の見事なバランス配置となっていました。庫裏をお訪ねすると、法要にお出掛け直前のご住職が、気忙しい中を依頼した史料を整えてくださり、寺庭様が喚鐘を撮影していた本堂までお届けいただきました。精しい史料を入手できましたことで、やや長文の投稿となりました。
取材に快くご対応下さいまして、まことにありがとうございました。
水野平蔵家系圖http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/7551e73084352a9a4d23ed9ccc7f9104