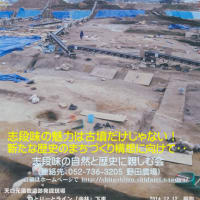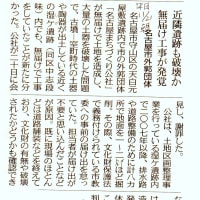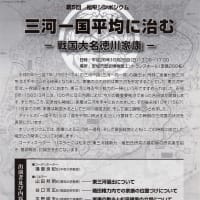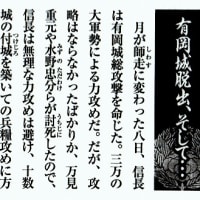●岡崎藩士 水野平三郎
(水野三郎右衛門家庶流水野五郎左衛門嫡男)
『茶摘は八十八夜から始まる』山本周五郎著
(『山本周五郎全集二十七巻』収録 P27短編 発行 新潮社1982 年8月 絶版)
――[ダイジェスト]
この物語は、寶永元年(1704)年間に、山川水野・岡崎水野藩に興った出来事である。
先ず最初に当時の時代背景を述べると、当代藩主は山川水野第五代水野忠之で、元禄十二年(1699)八月、実兄である岡崎藩主水野忠盈(ただみつ)に嗣子がなかったことから養子となり、家督を相続し官途銘を監物、のち和泉守と称した。水野家でこの監物を称したのは常滑水野家が最初とされるが、三代城主水野監物守隆が失脚後は、当家祖忠元・二代忠善・五代忠之・六代忠輝・七代忠辰(ただとき)が監物を称した。当主忠之は元禄十四年(1701)三月十四日、赤穂藩主浅野内匠長矩が吉良上野介義央に、営中松の廊下で刃傷に及んだ事件では、赤穂藩邸に入り騒動が起こらぬよう取計らう旨仰せ付けられた。翌元禄十五年(1702)七月二十六日、本多出雲守政利(*1)が庄内酒井家から預け替となる。同年十二月十五日、赤穂義士四十七士が、仇討ちを遂げ幕府に出頭したことで、義士の内、間重次郎光興ら九名を幕命により三田中屋敷へ預かり、厚遇し賞賛の言葉を贈った。その後、二月四日裁定により義士九名の切腹の儀を執り行う。後に忠之は将軍吉宗の老中として享保の改革に携わり一万石加増され六万石を領した。当岡崎藩の城代家老は水野三郎右衛門であるが、年代から見ると初代守信から数えて四代目の元英、五代目元亮、六代目元の何れかになろうが、史料が得られないことから現時点では特定はできない。更に庶流家老水野五郎左衛門も別掲系圖によれば、二代可勝の子で水野三郎右衛門を嗣いだ元貞の弟、可秀、正辰、信利、信遙の何れかの内の末裔と思われ、順序から行くと二男の可秀の可能性が高いが、こちらもまた詳細は判明しない。(『新訂寛政重修諸家譜』第六巻・外を参照)
物語の初めは、寶永元年(1704)、岡崎水野藩老職・水野五郎左衛門が江戸詰藩士・嫡男平三郎を国許に呼び戻すところから始まる。当家は九百七十石ばかりの禄高で、当時は岡崎城西約1Kmを流れる矢矧川、現在の矢作川(やはぎがわ)の堤防工事の総奉行を勤めており、平三郎を自分の助役に命じた。矢矧川は二年続で暴風洪水にやられ堤防が決壊していた。平三郎は、光円寺(*2)の普請現場詰所に通勤していたが、助役は他に二人居り退屈な閑職であった。勤務後は仲間を誘って町に飲みに出かけ夜になってから家に帰るという生活が続いた。平三郎は腕が立って男前で金遣いが綺麗だったから友達仲間に好かれる以上に、岡崎女郎衆に騒がれ「殿町(*3)の若旦那がみえた」と聞けば、他の座敷に出ている女たちまでそっと抜け出してくるという有様であった。彼は「俺は三河武士だ」という爽やかな自尊心があり、意志は強く、友情にも酒にも女にも溺れなかった。
そんな日々を重ねる中、詰所の支配鈴江主馬から「そう飲んでばかりいていいんですか」と言われた言葉が潜在意識となり彼を悩ました。それを切掛けに一旦は断酒を決意するが、誘われるまま、またぞろ廓通いを続けた。しかし主馬の言葉は頭から離れず、すっかり悄気込んだ。ある夜仲間と別れた後、伝馬町の通り(*4)で、夜更けで雨も降っているのに簑笠をつけた人夫が四五人ずつ組になって濡れながら道の掃除をしていた。明日どこかの太守でも通るのだろうか。いつもなら眼にも付かないのだが、いきなり頭を殴られでもしたかのような衝撃を受けた。殿町筋の屋敷に着くと、客間に灯りが点り客の、城代家老で水野家の本家に当たる水野三郎右衛門と江戸家老の分家で老職の拝郷内蔵助と父が密談を交わしていた。その内容は、先にお預かりとなっていた本多出雲守政利の処分に付いて薬害の決議を謀っていた。客が帰った後で、平三郎は父に出雲守の相伴役(*5)に立候補した。父から、他人のことより自分の行動を改めるようにと諭されると、そのこともあり、お願いする気になったと打ち明けた。
出雲守政利には初めは侍臣五人と侍女三人が付いていたが、政利のために手討ちにされたり、乱暴に絶えかねて逃げてしまい、岡崎には萩尾という若い侍女がただ一人従ってきたという。政利は既に五十は過ぎていたものの、躰は大きく力があり敏捷であったことから、一度暴れたら手が着けられず、岡崎に来てからでも、相伴役の者が三人も斬られ一人は重傷を負った。朝から酒を飲み、衣食住に贅沢を言い、それが通らないと暴れ出し直ぐに抜刀するので、気が収まるまで近寄ることすら出来なかった。
平三郎は父からこの行状を聞いたが、申請は撤回せず相伴役を仰せつかった。北の丸にある政利の住む屋形は、藩主忠之の祖父忠善の隠居所として建てた質素な造りであった。相伴役交替の挨拶をすると、政利からは、まず最初に屋形の文句を聞き、次いで食事か粗末だとか衣服調度についてなど数々の要求をされた。平三郎は当たらず障らず受け流し、五日間様子を見ていた。その間、政利が酔うと暴れるだけ暴れて疲れ切って寝てしまうと、長屋へ引き下がる平三郎に侍女の萩尾は彼に好感を持ちつつ、そっと侘びを入れ、これからのことを頼んだ。幕府から預けられた者を無断で城外に住まわせるのは違法ではあるが、平三郎は六日目にようやく思案が決まり、願い出て政利を城北にある大林寺(*6)に移した。居所は住職の隠居所で部屋は三つあり厨が付いていた。政利は「いよいよやるか、断じて自決はしないし、手を束ねて切られもせぬぞ」と言ったが平三郎は相手にしなかった。萩尾に協力を求め承諾を得ると、転居した当日から酒を禁じた。政利は怒って食事をしなかったが、定刻以外の食事は出さぬと宣言した。平三郎もまた断酒をして六日目であり禁断症状が現れてきた。彼は出雲守を利用して自身の過酷な禁酒策を敢えて計ったのである。この苦しさを政利とともに乗り切る決心は今度こそ揺らがなかった。禁断症状と空腹から、政利はまたもや抜刀し平三郎に何度も斬りかかったが、その都度投げ飛ばされついには伸びてしまった。その間萩尾は泣きながら止めに入ったが平三郎から一蹴された。眠ってしまった政利から離れ、平三郎は萩尾に自決を拒めば毒害という相談まで出ていることを告げた。しかし萩尾はこんな不自由な暮らしならいっそ、その方が幸せかもしれないと無感情に言った。そこで平三郎は自分の酒と遊蕩のことを語り、止める止められない、その抵抗しがたい誘惑から逃れられない己で有るからこそ、政利の苦しみが身に染みて解るのだと打ち明けた。政利の立場に立ってみて、死ぬ決心があるのなら行状を改めること位は出来ると思い、政利に今必要なものは同情や哀れみではなく、立ち直らせる鞭と立ち直る力となる鞭だと、萩尾に諭した。
その夜十時頃、平三郎は布子半天に股引という姿で、寝ている政利を起こし、同じような格好に着替えさせ、草鞋を履き頬被りをして提灯に火を灯し、裏門を出て伝馬町の人足問屋に行った。箱車に塵取と箒が入っており、政利に提灯を持たせ平三郎が車を引いて東進し、両町も通り抜け畷道のかかり欠町で車を道の端に止め、箒と塵取りを二組取り出し、その一組を政利に渡した。政利は取るより早くそれを放り出し「俺は平八郎忠勝の孫だ。たとえ改易、配流となっても、平八郎忠勝の正統であることに変わりはない。その俺に道掃除をしろといのうか」と震えながら言った。平三郎は政利の腕の付け根を満身の力を込めて掴んだ。「貴男が忠勝公の曾孫なら、私は岡崎の老職、水野五郎左衛門の嫡男です。――わかりますか――家柄や血統はその人間の価値には関係ありません、貴方は忠勝公の正統であることを誇るよりも、むしろ羞じるべきでしょう、六万石の家を潰し、家臣を離散させた、そのことを考えてください、旧御家臣の中には路頭に迷っている者があるかもしれない、それをよく考えて下さい」そして政利をぐっと揺りたてた。「貴方お一人にさせはしません、私もやります」と云って彼は手を放した(*7)。
岡崎は街道でも繁盛第一といわれる土地柄で、早打(*8)や急飛脚などが夜でも往来するし、それらの爲に、夜明かしの建場茶屋(*9)や旅籠なども幾軒かあった。また参勤交代で上り下りする諸侯にも、ここでは「馳走触(*10))」をするので、町筋は常に掃除を怠らないよう厳しい規則があり、大藩諸侯が宿泊するときなどは、、夜間でも火の用心や掃除のために人が出た。平常はむろん日暮までではあるが、人馬の往来はたとえまばらであったとしても終夜絶えないことから、道筋は牛馬の落とした不浄や切れた草履や紙屑などでかなり汚れていた。住居の大林寺から直線距離で、東南東約3Kmの所にある欠村から西に戻り、投町、両町、伝馬町へ掛けて、政利が提灯で照らし、平三郎が掃除をしつつ車の四つに仕切られた箱の中にそれぞれを分別して入れていく。伝馬町の手前まで来て二人は一休みした。政利は昨日から食事をしていなかったし、働くなどとということは生まれて初めての経験であったから、その疲れもいっそうひどく、凍てついた地面に直に腰を落とし両足を投げ出しうめき声を上げた。その前を荷馬車や飛脚が通り過ぎて行く。彼らは生計を立て妻子を養うため、この寒空を夜も眠らず働き続けている。世の中には食うためだけに懸命な人達が数え切れないほど沢山いる。「考えてみてください、貴方は今まで一度でもそう言う苦労をなさいましたか、配所(*11)暮らしをなさるようになってからも、衣食住に不自由はなさらなかったでしょう、そこをよく考えてみてください、かわりますか」と平三郎は政利に諭し、いやがる政利を否応なく立たせ掃除を続けさせた。しかし平三郎は、いま自分の口から出た言葉が、他人に云うより自分に云うべきことであったと気づき、自分自身が恥ずかしくなり、良心に鋭い痛みを感じた。
政利は「このままでは済まさぬ、今にきっと思い知らせてくれるぞ」と震えながら呟いた。伝馬町を左に曲がり六地蔵町を済ませると、車はほぼ一杯になった。時刻も午前四時近くで、政利は空腹と疲労で立っているのが漸くという風に見えた。平三郎は二人の道具をしまい車を曳き伝馬町の問屋に帰り、店の横から奥にまわり板囲いで分別されて積まれた汚物や塵の、その仕切り通りに持ち運んできた物を始末した。
井戸端で手を洗い、両町の方へ後戻りし町中の「あわ雪」と障子に書いた夜明かし茶屋に入り、平三郎は魚や海老を揚げたものを入れた、つまり今で云う天ぷらうどんを食べた。政利は「こんな下賎なものは食えるか、無用だ」と食べなかった。意地になっているばかりではなく、過度の空腹と激しい疲れとで、食べ物などは受け付けない状況であった。明くる夜も、その次の夜も、そしてそれ以来ずっと休まずに毎晩出かけて道掃除をした。十日目ぐらいまでは力ずくで連れださなければならなかった。平三郎自身も武芸で鍛えた若い筋骨を備えてはいたが、日常と違った動きをすることで、初めの内は躰の節々が痛み、立ち居に不自由を感じるほどであった。政利の方は、年も年だし、かつて労働らしいことをした試しはないことから、どんなに応えたかはおよそは察しがついた。しかし平三郎は見て見ぬふりをして一晩も休ませようとはしなかった。十日目を過ぎる頃から、政利はようやくおとなしくなった。半月近く経ったある日など、夕方から雨になったので「今夜は休もう」と云うつもりだったが、時刻が来ると政利は黙って出かける仕度をした。平三郎はふと目の内が熱くなるように思い、寺の庫裏へ行って簑を借りてきた。その夜の仕事の後、政利は初めてうどんを食べた。熱い物は食したことはなく、始めは舌を焦がしたが、用心して食べ終わり、茶店を出ると怒ったような声で「うまかった、あんなうまい物は初めてだ」と云った。政利の態度は次第に変わってきており、周囲の見聞にも興味を持ち始め、馬子や駕籠屋、人足、百姓たちのする事や話すことを、熱心に見たり聞き入ったりした。陰暦十一月中旬のこと、京へ上る老中の行列が入ることになり、作法触(*12)が出た。掃除は常より入念に、町筋では盛砂三箇所、家の前には水手桶、箒などを出す等々であった。政利は、町役の指図で人々が走り回るのを眺め、平三郎から「作法触」の仔細を聞くとその事の大げさに驚いた。その頃にはもう茶店に寄ることが楽しみになったようで、うどんもお代わりをするし、他の客の話を聞いて、くすくす笑うようなこともあった。
陰暦十一月下旬になって、平三郎は父五郎左衛門から呼ばれ、久方ぶりに殿町筋(*3)に帰った。父は、平三郎があまりにも熱心に頼んだので、道掃除の手続きをとりその手配をした経緯から、むろん道掃除のことは知っていたが、どうせ長続きはしないだろうと思っていた。しかし平三郎から報告を聞いて直ぐには信じられず一々念を押して聞き返した。平三郎はできるだけ控えめに話し、飾ったり誇張したりしないよう注意した。
五郎左衛門から政利の行状が改まったのかと聞かれ、この様に変わって来たという事実を申し上げた、とだけ答えた。また道掃除を思いついた経緯を問われ、いつでも止められると信じていた酒や遊蕩が、いつの間にか止められなくなっていた事実に、当時はそこから脱却しようと努力したが、それがどんなに困難であるかが解り、殆ど絶望仕掛けていたことを正直に白状した。そしてあの夜、客間で本家の水野三郎右衛門や老職の拝郷内蔵助が父と密談を交わしていたのを聞き、「詰腹」とか「毒害」とかいう言葉を耳にして、自分のことではないかと思ってぞっとしたが、直ぐにに本多侯のことだと解った。自分と同じ病に悩む者同士、というような気持ちになり、本多侯の弱さや苦しさや心の痛みが解るだろうと思い相伴役を願い出たことなどを語った。同夜酔って帰る途中、小雨に濡れながら道掃除をしている人夫たちの姿を見たとき、かつて経験したことのない鋭い良心の痛みを感じたことも打ち明けた。道掃除がどんな効果があるのかとの父の尋ねに対し、何も考えなかったと答え、これからも続けていく積もりだと応じた。予て五郎左衛門が公儀に伺いを立てていたところ、今般、やむを得なければ詰腹を切らせろとの沙汰があった。それに対してどう返答をしたらよいかと平三郎に訊いた。問答の末、御乱行は修まるものと信じ、その責任は自分が負うと答えた。父は了解したが、気を許すと後悔するぞと戒めた。
大林寺に午後三時頃帰り着き、萩尾が庫裏の植え込みのところで寺の下男から酒の徳利を受け取っているところを目撃した。襟を掴みあげ萩尾を問い詰め、今日で三度目と知れた。杉戸の所に立った政利は、刀を後ろ手に隠し無礼者と絶叫しながら平三郎に踏み込んだ。平三郎は肩に掛けて投げ、右手を首に当てて締め付けた。梶尾が後ろから助命を嘆願したことで、平三郎が政利に梶尾の身を案じ詰問すると、「こまちは俺の娘だ」としゃがれ声で応じた。萩尾が泣き伏し政利が云った意味が判った。政利は云ってはならぬ事を云ったことに狼狽し前言を翻した。政利を助け起こし平三郎は無礼を詫びた。
平三郎は、暗くなるまで薪割りをした。彼は食事は自分の部屋で摂るが、政利から初めて一緒にするようにと云われ、政利の座敷で夕食を共にした(*13)。食事が終わると、政利は待っているようにと告げ、萩尾を従え部屋を出た。間もなく戻ってきたが、政利は継ぎ裃に着替え小刀を差していた。座に就くと萩尾は膳部を片付け、自分は脇に下がって座った。なにか予期しない事態が起こるであろう事は察したが、見当もつかなかった。政利が「明日の公儀への答申は待つようにと、老職に伝えて貰いたい」という言葉に続き「俺は自決する」と云い、そこで口をつぐみ両手を膝に置いて目をつむった。再び口を開こうとした直前、平三郎はようやく狼狽しながらも、自決などという問題は既に消えている、過去のことだ。自分のやり方にご不満があるのかと尋ねた。平三郎が度々押し止めるのを遮りゆっくりと話し始めた。この四十日の間に多くのことを見聞きし経験し学んだ。これは自身の過去、そして今までどんな人間であったかをはっきりと炙り出してみせたと。さらには、茶店で話される、年貢の滞り、店賃の滞り、借金がかさみ一家が離散し、夜逃げをし、盗みに入って捕らわれ、自殺をする、そしてそれを話す者は、殆どが面白半分で、悲しんだり心を痛めたりする様子がなかった。どうしたことかと不審に思ったがそう言う悲惨な出来事に慣れているだけではなく、いつかは自分の身にも同じようなことが巡ってくる、いつか自分もそうなるだろう、そして、その時には切り抜ける道がないことを見通しているためだと解った。――俺が何をしてきたかということは多くの者のが知っている通りだ、領主としてはもちろん、単に人間としても俺は屑に劣ると。平三郎の、今こそこれまでの償いをなさるときではないのか、との言葉に、今生ではできない、償うことか余りにも多すぎるし、その力もない、今生では不可能なこと、と述べた。これに対し、平三郎は、安穏な御余生が送れるようにと、それだけを念じて相伴役に上がったのであり、そのためにこそ力ずくで御意に逆らい、道掃除などという下賎なことまで強いた、それはただ御余生が平安であるように願ったためだと心情を述べた。いや、自決すると決めた今ほど、平安な気持ちは俺にはなかった、と落ちついた口ぶりで遮り、過ぎ去った五十年よりも、この四十日余の間に、俺は人間の生き方を知った、それで充分だ、老職から公儀へ答申するということを聞いたとき、俺は胆が決まったのだ、そうあってはならない、これ以上生き延びてはならない、五十余年に渡る罪の償いはできなくとも、死に時だけは誤りたくない、この気持ちは平三郎にも解るはずだ、と。平三郎が頭を垂れ、萩尾が嗚咽する中、今宵の内に老職に公儀への答申は止めること、そして明日、俺の見知らぬ検視と介錯人をよこしてくれるように伝えてくれときっぱりと告げた。政利はそこで声を緩め、平三郎には世話になった、礼は云わぬ、礼を言わぬ上にもう一つ頼みがある、こまちのことだ。解っています、萩尾殿のことでご心配はいりません、私が確かにお引き受けいたします、と平三郎が食い縛った歯の間から云った。それで心残りはない、こまち、盃を持って参れ。政利が盃を取り萩尾が銚子を持った。一際強く風が渡り裏の竹藪が潮騒のように鳴り立った。
[註]
*1=父の本多政勝は、従兄弟であり本多家宗家である大和国郡山藩主本多政朝の後を相続し襲封した。このことは、政朝には嫡男の本多政長が居たが、僅か六歳という年齢で、幼君の擁立を家訓で禁じていたことから代わって政勝が襲封したものである。当然、政勝の後は政長と定められていたのだが、政勝は次第に実子の政利に家督相続をさせたいと願うようになり、政勝・政利親子は、大老酒井忠清に取り入ったが、家臣の都築惣左衛門による忠言により、政長を養嫡子と定められた。 その後、政勝が死去すると、即座に大老・酒井忠清に裏工作した結果、政勝の遺領十五万石の内、九万石を政長に、六万石を政利に相続する幕府の裁定が下った。これを世に九・六騒動という。しかし、この騒動はこれに終わらず、政利は十五万石全てを相続できなかった怨みにより、延寶七年(1679)夏、政長を毒殺したとも伝えられている。 しかしながら、政長の後継は、養嫡子本多忠国が相続し、同時に陸奥国福島藩へ移封となり、政利も同年六月、播磨国明石藩へ移封された。この移封に伴い、政利は六万石の内三万石を宗家である忠国に返還し、新たに三万石を賜っている。
その後、政利は家政を乱した咎により天和二年(1682)、一万石に減封され陸奥国岩瀬藩に転封となった。更には、同藩においてもなお不行跡が改まらないとして、元禄六年(1693)一万石も没収され遂に除封となり、自身は出羽国庄内藩主酒井忠真のお預かりとなった。酒井家には十年居たが、この間に酒乱の癖が昂じ、酒井家で預かりを断ったことから、元禄十五年、三河国岡崎藩主水野忠之にお預け変えされた。
*2=愛知県岡崎市八帖町字往還通70
*3=両側に武家屋敷が軒を連ねていたところで老職水野五郎左衛門の自邸がある所。今の愛知県岡崎市康生町付近か。
*4=愛知県岡崎市伝馬通
*5=しょうばんやく。主となる人に従って、行動を共にする世話役。
*6=愛知県岡崎市魚町1丁目6。
*7=これらの言動については、前述の元禄十四年(1701)三月十四日、赤穂藩主浅野内匠長矩が吉良上野介義央に営中松の廊下で刃傷に及んだ事件を、多少なりとも皮肉って云っているのであろうか。
*8=馬を走らせて急用を伝える使者。
*9=江戸時代、街道筋で人足が駕籠や馬を止めて休息した所。
*10=宿泊する大名の格式によって、出迎え見送り、宿所の世話、接待、饗応などをすることで、おもに町奉行がその衝(大切な役目)に当たっていたが、別に専任の者がいて城中との間の取り持ちをした。これが馳走番である。ことに尾張家や紀州家が泊まるおりには「お話し相手」にも出なければならない、規式作法(定まった作法)に精しく、また目端の利く(素早く適切な判断を下す)者でなければ勤まらぬ役であった。
*11=はいしょ。罪を得て流された場所。
*12=町役人の勤めで、町の騒音を取り締まり、道を清めたり、水手桶を出したり盛砂をしたりする。
*13=原文では、月日が記されていないが、一説では、政利は寶永四年(1707)陰暦十二月八日、六十七歳で死去、法名は法性院殿雪窓覚夢で岡崎能見源空寺に葬られたとあり、小説の流れからいくと、寶永元年(1704)年から更に三年間も経過した後に、死去したようには理解し難い。