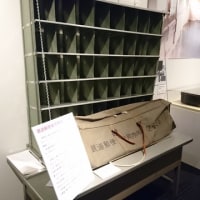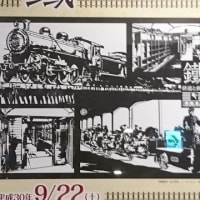12月23日(日) クリスマス時期に六波羅蜜寺に行く
大学鉄研かつ経済学部K田ゼミ同期生のT内氏と、お昼に江坂で待ち合わせました。クリスマス直前のこの日に、なぜかインド料理を食べながら久しぶりの再開を喜び合います。さて、T氏が私に、「これから、どこへいくんや?」と聞いてきました。私の希望「六波羅蜜寺に行って、空也上人像を見たい。それから時間があれば三十三間堂にも行きたい。」を伝えます。T内氏は、「かまへんで。一緒にいこか」と言ってくれました。仏教発祥の地、インドの料理を食べ終え、我々は仏像を拝みに京都に向かいま す。
す。
地下鉄で淀屋橋に向かい、そこから京阪特急に乗り換えます。その際、何も言わないのに2階建て車両の2階席に着席します(これぞ、鉄ちゃん同士のあうんの呼吸)。特別料金不要の鉄道車両の中では、おそらく見晴らしが日本一良い車両で京都を目指します。七条で普通に乗り換え五条へ。地下にある五条駅の階段を上り一歩外に出た瞬間、風が冷たく感じると同時に、<京都のにおい>がしました。<京都のにおい>がいかなるものかを他人に説明することは困難でありますが、学生時代の4年間を京都で過ごした私が言うのです。やっぱり<京都の街のにおいは>存在するのです。その京都臭ぷんぷんの裏通りをてくてく歩いていくと、少し迷いましたが目的の六波羅蜜寺に4時前に到着。
 空也上人像を見る為、拝観料を払って裏の宝物収蔵庫に入ります。と受付の方が、「今から○○(早口でよく聞き取れなかった)が始まりますから、本堂で○○を見に行ってから来て下さい。」と入ってくる人全てに、まるで追い返す様に声を掛けています。我々も急遽、御本尊の前に、訳の分からむままに、あわてて坐り込みます。既に周囲は人でいっぱい。やがて袈裟を着たお坊さんがマイク片手にこれから行われる儀式について、概要を説明してくれました。
空也上人像を見る為、拝観料を払って裏の宝物収蔵庫に入ります。と受付の方が、「今から○○(早口でよく聞き取れなかった)が始まりますから、本堂で○○を見に行ってから来て下さい。」と入ってくる人全てに、まるで追い返す様に声を掛けています。我々も急遽、御本尊の前に、訳の分からむままに、あわてて坐り込みます。既に周囲は人でいっぱい。やがて袈裟を着たお坊さんがマイク片手にこれから行われる儀式について、概要を説明してくれました。
これから行われる仏事は、踊躍念仏(ゆやくねんぶつ)と呼ばれるものです。千年前に念仏をはじめられた空也上人は、口で唱えるだけでなく、身振り手振りでも表現され、それが現在に伝えられたものとの事。鎌倉時代に入ると、町のあちこちで念仏が流行。ところが、民衆が集団で行う念仏は為政者や同業者から弾圧を受けはじめました。そこでこのお寺では、空也上人以来の法灯を絶やすまいと、夕暮れに本堂内陣で密かに念仏が唱えられるようになりました。鉦を叩きながら行われるこの念仏は、歴代住職の口伝で伝えられてきたとの事です。昭和53年になり、はじめて一般に公開される様になりました。ビデオ・カメラでの撮影と録音は厳禁とのこと。巷では、「かくれ念仏」とも言われているようです。
なんか予想もしない展開になってきました。
およそ30分弱の間、つい30年前までは世間に数百年間秘密にされてきた儀式が、面前数メートルで展開されています。数人のお坊さんが念仏を唱え、鉦を敲きながら本尊の前をぐるぐる周り、最後に聴衆と一緒に念仏を唱えます。
最後に、その場にいた参拝客全員に順番に焼香をさせてもらい、お札までもらってから本堂を退出しました。後から聞いたところでは、この踊躍念仏は毎年、12月13日から31日の間の夕暮れ時に行われる季節限定の貴重なものだったようです。1年間に自分が犯した罪を消滅させ、新年が良き年であるよう祈る意味があるとのことで、見終えた後はすっきりした気持になりました。
←↓境内にあったポスターより
 私が高校時代に使った山川の日本史の教科書に、空也上人像の写真が掲載されていました。念仏を唱える口から六体の阿弥陀が現れたという伝承を、そのまま彫刻にしてしまったという、衝撃的かつ分かりやすいこと、この上ない作品です。いつか、実物を見て見たいと思っていましたが、ようやく拝むことが出来ました。運慶の四男、康勝の作とのことで写実的彫刻です。どうしても目がいってしまう、口から出ている六体の阿弥陀は、針金で表現していたんですね。
私が高校時代に使った山川の日本史の教科書に、空也上人像の写真が掲載されていました。念仏を唱える口から六体の阿弥陀が現れたという伝承を、そのまま彫刻にしてしまったという、衝撃的かつ分かりやすいこと、この上ない作品です。いつか、実物を見て見たいと思っていましたが、ようやく拝むことが出来ました。運慶の四男、康勝の作とのことで写実的彫刻です。どうしても目がいってしまう、口から出ている六体の阿弥陀は、針金で表現していたんですね。
平清盛座像など、その他の収蔵物も一級品ばかり・・・・。私はしばし見とれていましたが、気がつけばもう5時前。本日の見仏記もおしまいです。
同行の仏像に興味が薄いT内氏には、私のわがままに付き合わせて、少し悪いことをした気がしましたが、私としては秘儀が観られて予想外、大満足のお寺探訪でありました。
↑京都の裏通りでねこさんのお出迎えをうけました「おこしやす!」とでも言っているのでしょうか。それとも・・・