
燃えるような紅葉と湖を描きました。
8年前の秋、東北を旅しましたが、
特に十二湖付近では、ここ川崎周辺では見ることができない紅葉の鮮やかさに感動、
思わず声をあげたことでした。
その中でも鶏頭場が池あたりの景色が思い浮かび、
2016.11.14付拙ブログでアップしたものを描き直そうと思いました。
でも水彩画の筆を持つのも久しぶり(約1ヵ月)のこととて、
まずは柴崎春通先生の紅葉を確認してから描こうと。
そうです、マジシャン・柴崎春通先生のyoutube動画です。
今回は、「ウェットインウェットで、静かな湖と紅葉を描く」から、刺激と技法と、
そしてこちらからも感動を賜りながら描かせていただきました。
自分の写生だけでは、なかなかこのように大胆には描けないものです。
さあーて、私にとってはちょっとした長旅が始まります。
折角ですのでメモとして残しておきたいと思います。
【ユダヤの行動原理とこれからの日本】
全体の目次:2024.10.28付拙ブログによります
第1章の目次
第1章 【古代】古代イスラエルの誕生
本章での用語
第1節 古代イスラエル国家・ユダヤ教の誕生と
ディアスポラの始まり
第1款 聖書時代
[父祖アブラハム]
[モーセによる出エジプト]
[王政時代]
[王国の分裂]
第2款 第二神殿時代
[キリストの登場]
[ディアスポラの始まり]
[ラビ・ユダヤ教の時代]
[中世]
第2節 ユダヤ教の主な特徴
[「シェマア イスラエルの朗読」にみる唯一神]
[モーセの十戒にみる唯一神]
[ユダヤ人のためだけの選民思想]
[成文と口伝 二つのトーラーによる実践]
[ユダヤの人にとって「時間」は特別なもの]
[十戒は、大半が“~なかれ”との否定的な表現]
[相異なる事象を、共に神の思し召しとする強さ]
[特にキリスト教との対比でみれば]
以下「参考」
△申命記にはユダヤ人の日本渡来を思わせる記述がある。
△近代以降においては、二つのメシア論がある。
第1章の主な参考文献など
・・・本論に入ります・・・
【ユダヤの行動原理とこれからの日本】
【ユダヤの行動原理とこれからの日本】
第1章 【古代】古代イスラエルの誕生
本章での用語
本章での用語
聖書:紀元前に、約千年にわたって書かれたイスラエルーユダ文献の集成。
神ヤハウェが選民イスラエルをいかに導き教育したかを示すユダヤ教の聖典。
ヤハウェ:聖書に書かれている神
モーセ五書:創世記、出エジプト、レビ記、民約記、申命記のこと。
トーラー:神から授けられた宗教上・生活上の教示。
成文トーラー(モーセ五書)と口伝トーラーから成る。
タルムード:ラビ達が社会百般の事象に関する口伝・解説を集めたもの。
ミシュナ(口伝律法)とゲマラ(注釈・解説)から成る。
ミシュナ:タルムードの主な構成部分。ラビの口伝を集成したもの。
ラビ:ユダヤ人の宗教的指導者。
メシア:聖書では、ユダヤ人が出現を待ち望んだ救世主。
シナゴーグ:ユダヤ教の礼拝・集会所。
ディアスポラ:ユダヤ人のパレスチナからの離散。また離散したユダヤ人。
啓典(の民):啓典(唯一至高神の啓示を記した書。コーラン、モーセ五書、福音書など)を信じる民。
ユダヤ:個所に応じて次の言葉を使っていますが厳密ではありません。
ユダヤ人、ユダヤの民、ユダヤの人たち、ユダヤ共同体、ユダヤ教、ユダヤ教徒など。
第1節 古代イスラエル国家・ユダヤ教の誕生とディアスポラの始まり
第1款 聖書時代(本款特に年表に関わる部分は主に、駐日イスラエル大使館hpから)
本拙論の主な舞台は、
地中海の東海岸でヨルダン川西側、今のレバノン、イスラエルあたり、
即ちパレスチナ又はカナンと呼ばれたところ。
それぞれに、
パレスチナは、今のガザ地区などに住むアラブ人の起源とされるペリシテ人から、
カナンはユダヤの聖典である聖書から来た言葉とか。
[父祖アブラハム]
聖書の記述は天地創造から始まるが、ユダヤ人とアラブ人の共通の父祖がアブラハムで、
正妻の子孫がユダヤ人、仕え人の子孫(砂漠に追放)がアラブ人という設定になっている。
約4,000年前(BC17世紀)アブラハム一行は、
現在のイラク南部とされるカルデヤのウルからカナンに地(パレスチナ)へと導かれる。
途上、ハランという町で、
神ヤハウェから「あなたはここを出て、私の示すカナンの地へ行きなさい」と。
主は更に現れて仰せになった。
「わたしはこの地をあなたの子孫に与える」と。
これが「約束の地カナン」とのこと。
やっと授かった息子イサクを神に授けるという神の試練にも遭う。
イサクの子ヤコブは名をイスラエルと変え、
その12人の息子がイスラエル12部族の祖となる。
その後イスラエルの民は、飢餓状態にあったカナンの地からエジプトに移住し、
エジプト・ファラオの奴隷となり、約400年間、厳しい労働に苦しむことに。
[モーセによる出エジプト]
この民の苦しみを聞いた神からの召命を受けたモーセは、
イスラエルの民を導き、エジプトを出てカナンの地を目指す(BC13世紀)。
約40年間シナイ砂漠を彷徨中、
シナイ山で神はその教えであるトーラー(十戒を含むモーセ五書)をモーセに授与した。
ユダヤ教の原点中の原点である。
束縛からの解放と自由を表す象徴となり、
現在もユダヤの人たちは、当時のエジプト脱出時の出来事を記念して、
過越祭や七週祭等を行っているとのこと。
一方、エジプト考古学者・吉村作治氏によれば、
ヤハウェがアブラハムに彼らの地だと約束したこのカナン(パレスチナ)の地に
入ったのが今日までの中東紛争の種になっている、と。
また、世界史の歴史家・著作家・宇山卓栄氏は、
パレスチナはもともと先住のカナン人やパレスチナ人のもので、
“約束の地カナン”は正統性を得るために生まれたストーリー、とされている。
[王政時代]
カナンの地に入って約200年、
周囲の国からの攻撃の脅威にさらされ、当時の部族組織の弱さが露呈し、
部族を世襲で永久的にまとめる統治者が必要に。
最初の王であるサウルの時代(BC1,020年)を経て次のダビデ王の時代へ。
ダビデ王(BC1,004年~965年)、ミケランジェロの彫刻の人である。
ダビデの権力はエジプト国境から紅海、更にはユーフラテス川まで及ぶ地域の列強王国を築く。
国内では、古代イスラエルの12の部族を1つの王国に統一、
エルサレムに遷都し、王政を国の基礎とした。
ダビデ王を継承した息子のソロモン王(BC965年~930年)は、王国を更に強化した。
近隣諸国との盟約により王国の平和を確保するとともに、
当時の世界列強国と並ぶ国にまで押し上げた。
外国との交易を拡大する一方、銅山や金属の溶錬などの大規模産業を興した。
このソロモン王の時代に、
後にユダヤの民の日々の生活や宗教生活の中心となる神殿(第一神殿)を
エルサレムに建立し(BC960年)、同王の最たる功績とされる。
[王国の分裂]
ソロモンの死後(BC930年)、ソロモン王政と部族分離主義者の間で対立が深まり、
内乱により王国から、
北の10部族が離反し北のイスラエル王国、
南のユダ族・ベンジャミン族からなるユダ王国に分裂する(BC930年)。
北のサマリアを首都とするイスラエル王国は200年以上にわたり続き、
南のエルサレムを首都とするユダ王国もダビデの血筋を引く国王により
400年にわたり統治される。
しかしその後、イスラエル王国はアッシリア帝国に攻められ滅亡、
捕囚される(BC722年 アッシリア捕囚 失われた10部族)。
南のユダ王国もその後がバビロニアによって征服、捕囚され、
エルサレムと第一神殿は破壊される(BC586年 バビロニア捕囚)。
このバビロニアでの捕囚・第一神殿の破壊という苦難の中、
自分たちのアイデンティティーを喪失しかねない危機的状態に陥ったが、
彼らはこの時期に彼らの起源に関する様々な伝承を聖典としてまとめ始めた。
これが聖書の起源とされる。
そこでユダヤ人は神から選ばれた選民であり、
神から与えられた戒律を守っていれば必ず救世主が現れて救済されるであろう、
と強く考えるようになった、と。
第2款 第二神殿時代
その後バビロニアが滅び、捕囚から解放されパレスチナに戻り
第二神殿を再建する(BC515年)。
ペルシャ帝国、ギリシャの統治時代(BC538年~142年)があり、
BC63年以降ローマ帝国の支配下での属州時代が続く。
[キリストの登場]
ローマ帝国時代の紀元前後、ユダヤの人たちは“モーセの律法”に則りながらも、
“ユダヤとは何か”との問いかけに多種多様な思想運動を生み出し、
賢者輩出の時代とも称されていた。
そのような状況のなかで、
同じユダヤ人であるイエスが現れることとなる。
彼は、ユダヤ人に限定していた選民思想を、あまねく全人類に広げるなどの教えを説いた。
ユダヤ教長老たちはイエスを裏切り者と考え、
反逆者としてローマの総督に訴え、AD33年頃、磔刑に処される。
「イエスは3日後に蘇った」とする弟子たちは
イエスを救世主(キリスト)として崇めキリスト教の誕生と。
この“キリストが処刑されたのはユダヤ教の所為だ”
とするキリスト教側の恨みは、後の迫害などに繋がる大きな原因となる。
[ディアスポラの始まり]
その後ユダヤ側は、第二神殿の破壊(AD70年)を挟んで、
ローマとの間の、第1次ユダヤ戦争(AD66~73年)、
第2次ユダヤ戦争(AD132~135年)の敗戦等を経て、
ローマ帝国のハドリアヌス帝によりユダヤ人のエルサレムからの完全追放が発せられる(AD135年)。
ユダヤの人たちのディアスポラ(パレスチナ以外への離散)がいつから始まったのか、
その時期については諸説があるようである。
先に記した第一神殿の破壊時期(BC586年)を離散の始まりとする説(駐日イスラエル大使館hp)や、
第二神殿の破壊(AD70年)あるいはエルサレムからの完全追放(AD135年)を始まりとする説である。
後の二つの論者が多いようであるが、彼らは“本格的なディアスポラ”の始まりとしている。
WWⅡ後1,948年の新生イスラエル建国まで、
1,800年に亙るユダヤ人の本格的なディアスポラが始まる起点である。
ユダヤの人たちは、以降、
国家の3要素(領土・国民・主権)の一つ“領域”を持たない民として、
他国に寄生しながら存在を続けることになる。
[ラビ・ユダヤ教の時代]
上述の危機に際しユダヤ教を引き継いだのが、
トーラーの学びを信仰の中心に据え、聖書にまつわる膨大な伝承、議論を継承していたグループであった、と。
聖書に長けた師との意味合いからラビと呼ぶので、
新しいユダヤ教の形を「ラビ・ユダヤ教」と呼ぶとのこと。
ユダヤの人たちは、自分たちの社会が消滅の危機に瀕したとき、
社会を存続させるために、
生活のすべてを神の法によって統治する方法を模索したが、
それを象徴するのがAD200年頃編纂された「ミシュナ」という口伝律法集。
破壊された神殿に代わり学塾と呼ばれる場所を中心に、
膨大な法規が収集され、暗記され、記憶に叩き込まれて、
さらに次世代に「口伝トーラー」の形で伝えられた。
このミシュナの成立により口伝トーラーという概念が生まれたとき、
文書によって伝えられてきていた「成文トーラー」(モーセ五書)という概念も
明確に意識されることとなる。
成文と口伝のいわば二重のトーラーによって、
ラビ・ユダヤ教は、神の言葉の学習を社会の基本に据えたこととなる、と。
因みにローマ皇帝がキリスト教を公認したのは約300年後のミラノ勅令(313年)であり、
キリスト教の教義を“マリアは神の母として祀られるべき”(アタナシウス派)
として統一したのはエフェソス会議(431年)である。
なお、田中英道氏、茂木誠氏によれば、
出エジプト(BC13世紀 縄文時代)時以降に、
スサノオを代表とするユダヤ人たちの一部が第一波(当初高天原から出雲へ)として、
アッシリア捕囚(BC722年以降 神武天皇の頃)で行方不明の10支族の一部が第二波として、
それぞれ日本へ渡来、同化したとされている。
[中世](チョットだけ)
7世紀にアラビア半島に成立したイスラム教。コーランによれば、
人類はもともと争いのない正しい一つの共同体であったが、対立し多くに分かれてしまった。
そこで神は人々の争いを解決し正しい道に戻すためにそれぞれに使徒(預言者)を遣わした。
モーセがユダヤ教徒へ、イエスがキリスト教徒へ、である。
本来なら双方とも啓典(唯一神の啓示)の仲間であるはずであったが、
特にキリスト教の権威が確立されて以降、対立を繰り返し、
使徒を神格化するという過ちを犯した。
そこで神は、最後の使徒(預言者)としてムハンマドを遣わした、とする。
その時のお告げの言葉は
「ムハンマドよ、お前は唯一の神アッラーの使徒である。
罪深き人々が罰せられぬよう、神の言葉を人々に広く伝えよ。それが汝の使命である。」と。
中世では、中東を中心にイスラムが、ヨーロッパ世界ではキリスト教が
それぞれ覇権を握り、
ユダヤ共同体の大部分はこの二つの文化圏に入っていた。
イスラム圏のユダヤ共同体は同じ“啓典の民”として重用され、
とくにイベリア半島で文化的にも黄金時代を迎える。
他方、キリスト教圏では、金貸し業としての富への妬みや
聖書でのキリスト処刑へのイメージが重なり、ユダヤ共同体への襲撃が頻発した。
そして11世紀末の十字軍によるエルサレム奪還を目的とした遠征へと。
今現在イスラエルの四周の国々は殆どがイスラムばかりで、
領土を巡っての血で血を争う状況には、あらためて複雑な思いを起こさせます。
・・・ここで文字数制限となりました・・・
以下次回へ。















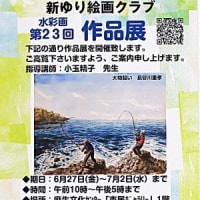








近くの大きな木、遠くの紅葉した広葉樹、高い針葉樹、晴れた空、それらを写した静かな湖面、本当にお見事に描かれていると思います。
さてさて、ユダヤ関係は一読ぐらいでは理解できませんが、異人種の協力・相互の発展を助長するはずの神(人が創造したシンボル)が、捉え方によっては抗争を生んでいる(それぞれの人種が本来の欲を神のせいにしている)のが実態のような気もします。悲しいことながら、長い抗争の歴史が語るように人類は規模・形は変わるでしょうが、引き続き自分たちの正義を信じ抗争をつづけるのでしょうね。
ユダヤ教、キリスト教そしてイスラム教、仏教を除く著名な宗教が極めて複雑で果てしない愛憎劇を生み出す原点を垣間見た思いです。
私が生きてきた途上でもイスラエルと周辺国との大きな戦争は、またかと思う程繰り返されていました。
宗教という魔物、特に一神教に拘る当該地域の民族・・・。
それなのに、一神教に固執するユダヤの失われた支族が日本にたどりつき、大和民族との同化を果たし、五穀豊穣、八百万の神々を信じる穏やかな日本の民になったとすれば、いかに日本の自然と仲間が素晴らしいDNAを作り上げたものだと驚きです。
ブログの主題はもっと広い観点から考察されているものと次回以降も興味津々です、よろしくお願いします。