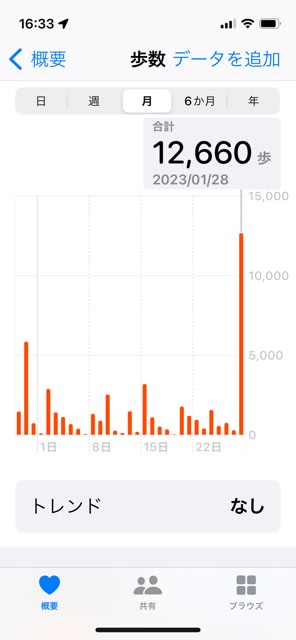城崎の大谿たに川の護岸は玄武岩を積み上げてあるそうです。
大正14年北但地震で崩れた玄武洞の玄武岩が使われています。
























天平勝宝年間(749~757)大仏開眼のために来朝したバラモン僧正が
「野崎の地は釈迦が初めて仏法を説いたハナラによく似ている」
と行基菩薩に言ったので、観音像を刻み、この地に安置したのが、この寺のはじまりと伝えられる。
藤原氏が権勢を誇った平安末期、淀川右岸に住む江口の君が、長の病を観音様に治して頂いたお礼にお寺を再興した。
江口の君とは江口にたむろしていた遊女の長者(統率者)を言う。
永仁年間(1292~1298)入蓮僧正が秦氏の協力を得て大修復をしたが、
永禄の乱(1569)によって寺の殆どが焼失し本尊の観音像だけが残った。
元和二年(1616)青厳和尚が復興し、元禄宝永(1688~1710)の頃に「のざきまいり」が盛んになりお寺も栄え現在にいたっている。
江口と野崎とは水路でつながっていて、江口の遊女は良い客がつくようにお詣りに来ていたのだろう。
満月(もちづき)の藤原道長に愛でされた小観音と言う遊女がいて、後に観音として祀られたと滝川政次郎『遊行女婦・遊女・傀儡女』で述べている。







一
野崎参りは 屋形船でまいろ
どこを向いても 菜の花ざかり
粋な日傘にゃ 蝶々もとまる
呼んで見ようか 土手の人
二
野崎参りは 屋形船でまいろ
お染久松 涙の恋に
残る紅梅 久作(きゅうさく)屋敷
今も降らすか 春の雨
江戸時代の野崎参りでは、寝屋川を行く屋形船の乗客と、川沿いの土手を歩いていく人々との間で、互いを冷やかしたり罵ったりする「ふり売り喧嘩」という口喧嘩の風習があったという。
これはあくまでも口喧嘩だけで、決して石を投げたり手を上げたりしてはいけないという暗黙のルールもあったようだ。
『野崎小唄』一番の歌詞で「呼んで見ようか 土手の人」とあるのは、この「ふり売り喧嘩」の風習を踏まえたもの。上方落語「野崎詣り」でも大きく取り上げられている。
二番の歌詞にある「お染久松 涙の恋に」とは、江戸時代に心中事件を起こしたとされるお染と久松のこと。
江戸時代の人形浄瑠璃や歌舞伎の人気演目として様々な作品に登場するが、『野崎小唄』と関連が深いのは、安永9年(1780年}に初演された近松半二『新版歌祭文』(しんぱんうたざいもん)における「野崎村の段」。











大阪府北東部、交野市(かたのし)の中央、京阪電鉄交野線の終点一帯をいう。
天野(あまの)川沿いの田園地帯で、獅子窟寺(ししくつじ)、磐船神社(いわふねじんじゃ)などがある。
また、大阪市立大学理学部付属植物園には日本原産樹木約600種のうちの約80%が植栽されている。
私部(きさべ)が居住したことにちなむ地名。
后(きさき)のためにいろいろ関係した役所を私府(きさいふ)
その任にあたる人を私官(きさいかん)といった。
后のために農耕をしたり身の回りの世話をする人々を総称して私部(きさいべ)といい、
いわゆる部民(べのたみ)。
京都府福知山の舞鶴道は私市古墳をトンネルで潜りますね。
交野市私市はいつのお后なんでしょうね。












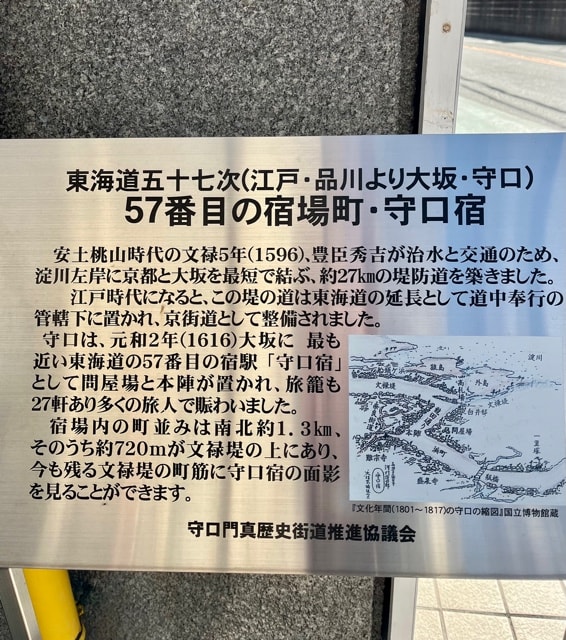



「猩々(しょうじょう)」とは、
中国に伝わる想像上の霊獣で、サルに似た体つきで紅色の体毛に覆われた動物。
その血はとても赤いとされ、猩々緋の色名は、そこから誕生した。
室町時代後期からの南蛮貿易により日本にもたらされた毛織物のうち、
この目を見張るような赤色の織物は、とくに羊毛でできた羅紗(らしゃ)に多かった。
戦国時代、多くの武士達は羅紗を陣羽織に仕立て戦場で愛用した。霊獣の力をも味方につけたかった。
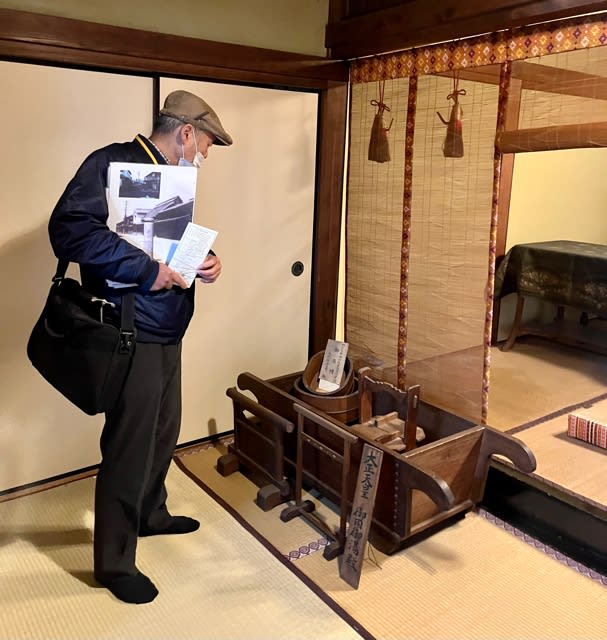







「はーい。慌てない慌てない。一休み一休み…」
一休さんによる佛教の「定義」
佛法は、障子の引き手、峰の松、火打ち袋に、鶯の声
あってもなくてもよさそうだが、
あった方が人生をより心豊かに、心安らかに生きることができるもの、それが佛法である。
なるほどね❣️