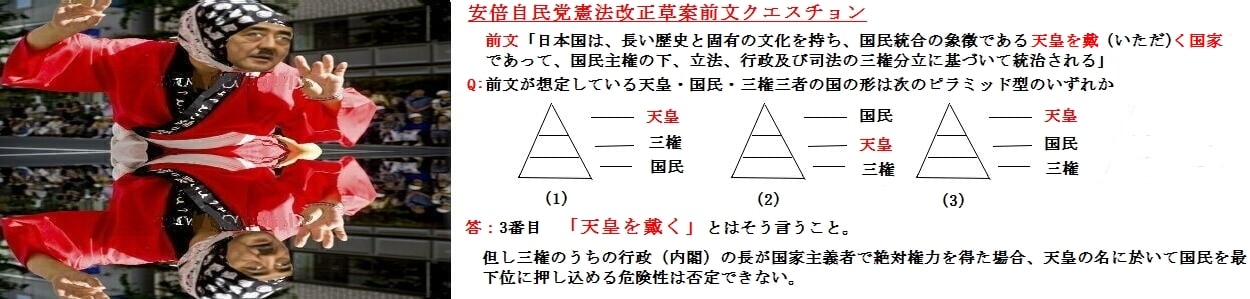
復興相の今村雅弘が2017年4月4日の記者会見での質疑応答でフリーランスの記者に対して福島原発からの自主避難を自己責任と発言したと野党が辞任を求めている。復興庁のサイトにアクセスして発言の詳細を見てみた。質疑のみ抜粋。
サイトには「問」とあるだけで、どの社の記者の発言なのか、どれがフリーランスの記者の発言か分からないから、「問」を「記者」と表記するが、今村がキレて「出ていきなさい」と発言した相手のフリーランスの記者はネットで調べて見ると、西中誠一郎記者となっている。
西中誠一郎記者の発言はどれか想像して貰うしかない。全部西中誠一郎記者の発言のようにも見えるし、そうではないかもしれない。一人だけの発言だとすると、今村はキレて質疑を早々に打ち切ったように見見える。
| 記者「今、お話があったように、31日に避難区域が解除され、そして、自主避難者の方の住宅の無償提供も打ち切られましたけれども、その週に、先週になるわけですが、避難者を中心にした全国の16の団体の方が安倍首相、それから松本内閣府防災担当大臣、それから今村復興大臣宛てに避難用住宅の提供打切り撤回と避難住宅の長期無償提供を求める署名というのを提出されました。2次署名分で約2万3,000筆、それから1次と合わせると8万7,000筆近くになる署名を提出されたんですけれども、大臣はこの署名について、申入れ内容について把握されていらっしゃるでしょうか」 今村雅弘「まだ確認はしていません」 記者「ああ、そうですか。その中で、やはり3月17日の前橋地裁の国とそれから東電の責任を認める判決が出たわけですけれども、国と東電は3月30日に控訴されました。ただし、同じような裁判が全国で集団訴訟が起こっておりますし、原発は国が推進して国策ということでやってきたことで、当然、国の責任はあると思うんですが、これら自主避難者と呼ばれている人たちに対して、国の責任というのをどういうふうに感じていらっしゃるのかということを、国にも責任がある、全部福島県に今後、今まで災害救助法に基づいてやってこられたわけですけれども、それを全て福島県と避難先自治体に住宅問題を任せるというのは、国の責任放棄ではないかという気がするんですけれども、それについてはどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか、大臣は」 今村雅弘「このことについては、いろんな主張が出てくると思います。今、国の支援と言われますが、我々も福島県が一番被災者の人に近いわけでありますから、そこに窓口をお願いしているわけです。国としても福島県のそういった対応についてはしっかりまた、我々もサポートしながらやっていくということになっておりますから、そういうことで御理解願いたいと思います」 記者「福島県の近隣、関東から関西方面ですとか、日本全国に避難されている方もいらっしゃると思うんですが、全て福島県を通すということ自体がもともと今の自主避難の実態に合わないんじゃないかなという気がするんですけど、やはり国が子ども・被災者支援法に基づいて、しっかり対策をもう一度立て直す必要があると思うんですが、それについてはどうお考えでしょうか」 今村雅弘「それは今、言いましたように、福島県がいろんな事情、現地の事情等、そういったことも詳しいわけですから、そこにお願いして、それを国がサポートするというこの図式はこのままいきたいというふうに思っております」 記者「昨日、復興庁から被災者支援総合交付金第1回の配分が発表されたかと思うんですが、今回の配分について、どのような趣旨で行ったかというところの見解をお聞きしたいんですが」 今村雅弘「これは従来からもそうですけれども、できるだけさっき言った趣旨にのっとって、復興の加速化、特にソフト面、そういったところに力を入れてやっていくということで、具体的な項目等には皆さん、お手元に行っているかな。それで見てください」 記者「ソフト面の強化ということですか」 今村雅弘「特にそれを重点に置きたいと思います」 記者「今月で熊本地震から1年たちますけれども、東北の復興を手掛けている復興庁として、熊本地震の被災地に何か取り組まれるというか、お考えはありますでしょうか。 今村雅弘「熊本については、いろいろインフラの関係は国土交通省とか農林水産省が中心にやって、それで対応できていたと思います。それに加えて、いろいろ災害公営住宅の建設の仕方とか、いろんな寄り添いといいますか、そういったソフト面での対応については、復興庁が得た知見をそれぞれ熊本県なり何なりにも提供しながら、今までもやってきたつもりであります。ですから、もうちょっとで1年云々ということなんでしょうが、今のところ、何とかうまく行っているんじゃないかなというふうには思っていますけどね。いろいろとそのときによってまた新しい問題が出てきますから、そういうときには我々が提供できる、あるいは、指導できる面はもちろんやるつもりです」 記者「以前に、熊本地震のアーカイブみたいなものをつくりたいというふうにおっしゃっていたと思うんですけど、その辺りは分かりますか。 今村雅弘「ええ、これは熊本に限らず、東北の方でもそういう動きがあるわけですから、随時、更に加えてまた熊本の分も含めて、要するに、いざというときにどうしたらよかったのか、何がまずかったのか、そういったものを総括したものを、いろんな形でまた日本全国にアピールできるようなこともやらなきゃいけないかなというふうに思っておりまして、これはまた松本大臣ともよく相談して進めていきたいというふうに思います」 記者「それは内閣府が去年の12月に熊本地震の生活支援の在り方、また、ワーキンググループが報告書をまとめていますけれども、それとはまた別にということですか」 今村雅弘「それも参考にしながら、そして、またそれにもう一つ東北の分も加味しながらやっていった方がいいんじゃないかなと。いずれにしろ、これから先に日本列島が非常に、何て言いますか、動き出したと言ったら変ですけれども、そういった状況の中で危機管理というものを、そういった意識を強めて、また、体制もしっかりやらなければいけないなということを、私も最近つくづくそういうふうに感じていますから、またいろいろそういうことはより今後の参考になるようにというつもりでやっていきたいというふうに思っております。 いざやっぱり大きな災害が起きると、非常に人命も損なわれるし、いろんな社会資本も大変傷みます。そうならないようにできるだけ防災、減災に力を入れるということが、結果的には、お金も掛からないという感じを私も強くしていますので、そういった言ってみれば強靱化といいますか、そういったことにも我々も復興庁の権限を生かしてまとめ上げていきたいというふうに思っているところです」 記者「福島県、福島県とおっしゃいますけれども、ただ、福島県に打切りの、これは仮設住宅も含めてですけれども、打切りを求めても、この間各地の借り上げ住宅とか回って、やっぱりその退去して福島に戻ってくるようにということが福島県の、やはり住宅設備を中心に動いていたと思うんですが、やはりさっきも言いましたように、福島県外、関東各地からも避難している方もいらっしゃるので、やはり国が率先して責任をとるという対応がなければ、福島県に押し付けるのは絶対に無理だと思うんですけれども、本当にこれから母子家庭なんかで路頭に迷うような家族が出てくると思うんですが、それに対してはどのように責任をとるおつもりでしょうか」 今村雅弘「いや、これは国がどうだこうだというよりも、基本的にはやはり御本人が判断をされることなんですよ。それについて、こういった期間についてのいろいろな条件付で環境づくりをしっかりやっていきましょうということで、そういった住宅の問題も含めて、やっぱり身近にいる福島県民の一番親元である福島県が中心になって寄り添ってやる方がいいだろうと。国の役人がね、そのよく福島県の事情も、その人たちの事情も分からない人たちが、国の役人がやったってしようがないでしょう。あるいは、ほかの自治体の人らが。だから、それは飽くまでやっぱり一番の肝心の福島県にやっていっていただくということが一番いいというふうに思っています。 それをしっかり国としてもサポートするということで、この図式は当分これでいきたいというふうに思っています」 記者「それは大臣御自身が福島県の内実とか、なぜ帰れないのかという実情を、大臣自身が御存じないからじゃないでしょうか。それを人のせいにするのは、僕はそれは……」 今村雅弘「人のせいになんかしてないじゃないですか。誰がそんなことをしたんですか。御本人が要するにどうするんだということを言っています」 西中誠一郎記者「でも、帰れないですよ、実際に」 今村雅弘「えっ」 記者「実際に帰れないから、避難生活をしているわけです」 今村雅弘「帰っている人もいるじゃないですか」 記者「帰っている人ももちろんいます。ただ、帰れない人もいらっしゃいます」 今村雅弘「それはね、帰っている人だっていろんな難しい問題を抱えながらも、やっぱり帰ってもらってるんですよ」 記者「福島県だけではありません。栃木からも群馬からも避難されています」 今村雅弘「だから、それ……」 記者「千葉からも避難されています」 今村雅弘「いや、だから……」 西中誠一郎記者「それについては、どう考えていらっしゃるのか」 今村雅弘「それはそれぞれの人が、さっき言ったように判断でやれればいいわけであります」 記者「判断ができないんだから、帰れないから避難生活を続けなければいけない。それは国が責任をとるべきじゃないでしょうか」 今村雅弘「いや、だから、国はそういった方たちに、いろんな形で対応しているじゃないですか。現に帰っている人もいるじゃないですか、こうやっていろんな問題をね……」 記者「帰れない人はどうなんでしょう」 今村雅弘「えっ」 記者「帰れない人はどうするんでしょうか」 今村雅弘「どうするって、それは本人の責任でしょう。本人の判断でしょう」 記者「自己責任ですか」 今村雅弘「えっ」 記者「自己責任だと考え……」 今村雅弘「それは基本はそうだと思いますよ」 記者「そうですか。分かりました。国はそういう姿勢なわけですね。責任をとらないと」 今村雅弘「だって、そういう一応の線引きをして、そしてこういうルールでのっとって今まで進んできたわけだから、そこの経過は分かってもらわなきゃいけない。 だから、それはさっきあなたが言われたように、裁判だ何だでもそこのところはやればいいじゃない。またやったじゃないですか。それなりに国の責任もありますねといった。しかし、現実に問題としては、補償の金額だって御存じのとおりの状況でしょう。 だから、そこはある程度これらの大災害が起きた後の対応として、国としてはできるだけのことはやったつもりでありますし、まだまだ足りないということがあれば、今言ったように福島県なり一番身近に寄り添う人を中心にして、そして、国が支援をするという仕組みでこれはやっていきます」 記者「自主避難の人にはお金は出ていません」 今村雅弘「ちょっと待ってください。あなたはどういう意味でこういう、こうやってやるのか知らないけど、そういうふうにここは論争の場ではありませんから、後で来てください。そんなことを言うんなら。 記者「責任を持った回答をしてください」 今村雅弘「責任持ってやってるじゃないですか。何ていう君は無礼なことを言うんだ。ここは公式の場なんだよ」 記者「そうです」 今村雅弘「だから、何だ、無責任だって言うんだよ」 記者「ですから、ちゃんと責任…… 」 今村雅弘「撤回しなさい」 記者「撤回しません」 今村雅弘「しなさい。出ていきなさい。もう二度と来ないでください、あなたは」 |
西中誠一郎記者が言っていることは自主避難者の住宅無償提供が打ち切られた、国と東電の責任を認めた判決を例に取って原発は国が国策として推進してきた政策でもあるから、国に責任がある、これまでは災害救助法に基づいてやってきたが、福島県と避難先自治体に住宅問題を任せるのは国の責任放棄ではないかと尋ねた。
対して今村雅弘は福島県が一番被災者の人に近いから、そこを窓口として国がサポートするといったことを言っているが、自主避難者の住宅無償提供を打ち切っていながら、国のサポートを言うのは矛盾が出てくる。
そして福島に戻る戻らないは「国がどうだこうだというよりも、基本的にはやはり御本人が判断をされることなんですよ」と、既にここで自己責任論の顔を覗かせている。
戻りたい意思があってカネがあり、その上職の確保が期待できれば、御本人の判断に任せて戻って家を新築するなり、あるいは借りるなすることができる。
だが、カネがなく、職の確保も難しいとなったら、戻るという選択肢は御本人の判断の埒外となる。
要するに記者が尋ねたように「帰れない人はどうするんでしょうか」と言うことになるが、この疑問に対しても今村雅弘は「どうするって、それは本人の責任でしょう。本人の判断でしょう」 と自己責任論を振りかざし続ける。
いわば国の責任ではないとのご託宣と言うことになる。
戻るという選択肢だけではなく、カネがなければ、自主避難者に対する住宅無償提供が打ち切られたことによって、避難の地にとどまるにしても、生活を成り立たせいくこと自体が困難となるケースも生じることになるが、今村雅弘の言い分はこういったケースに関しても、「それは本人の責任でしょう。本人の判断でしょう」と言うことになる。
もし不服なら、「裁判だ何だでもそこのところはやればいいじゃない」かと、そこまで自己責任行為に含めている。
このことが実際に国の責任に対する開き直りなのか、いわば責任放棄なのかどうかということになる。
記者が「3月17日の前橋地裁の国とそれから東電の責任を認める判決が出たわけですけれども」と指摘しているが、この判決は国の過失責任を初めて認定したものだという。
《吉田調書を読み解く(上)「貞観地震」への過剰反応》という表題の2014年12月2日付「The Huffington Post」記事に次のようないい術がある。
〈政府の地震調査研究推進本部が、貞観津波、明治三陸津波、昭和三陸津波のような東日本の太平洋岸を襲う大津波は、必ずしも三陸沖だけが波源となるとは限らず、今後は三陸沖から福島沖、房総沖にかけて、どこで起きてもおかしくないという報告をまとめている。
さらに2009年には、原発の地震・津波に対する安全性評価を抜本的に見直すための経済産業省の公式の会議で、福島第1と福島第2の両原発について、津波の想定を格段に厳しく見直すべきだという、専門家の具体的な指摘を東電は受けてしまう。「総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ」という、とてつもなく長い名称の会議で、2009年6月、産業総合研究所の岡村行信活断層・地震研究センター長は、東電は津波対策として貞観地震を検討すべきと明言しているのだ。〉
記事には地震調査研究推進本部がいつ報告を纏めたのか、日付が出ていないが、ネットで調べたところ、2002年ということである。
そして2009年6月には「総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ」という、とてつもなく長い名称の会議で産業総合研究所の岡村行信活断層・地震研究センター長は、東電は津波対策として貞観地震を検討すべきと明言」した。
要するに政府の地震関連の二つの組織が2002年と2009年に東北地方の太平洋岸に巨大地震が発生した場合は三陸沖だけではなく、福島沖、房総沖にかけても巨大津波が発生する危険性を指摘していた。
当然、東電は2002年時点でこの報告に基づいて貞観津波、明治三陸津波、昭和三陸津波クラスの巨大津波を想定して対策を講じていなければならなかった。そして7年経過した2009年には、その年の報告に対してどれくらいの対策を講じることができているか検証する段階に至っていなければならなかった。
だが、東電は津波に対する対策は何ら講じていなかったために検証する段階ではなかっただけではなく、2009年の議論に対しても改めて対策を講じることなく2年近く経過して2011年3月11日を迎えた。
なぜ対策を講じなっ方のだろうか。
内閣府に設置されている国家行政機関である原子力安全委員会が2009年を遡ること18年10カ月前の1990年8月30日に「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」を決定している。
その「指針27」には、「電源喪失に対する設計上の考慮」に関して次のように記している。
〈長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。
非常用交流電源設備の信頼度が、系統構成又は運用(常に稼働状態にしておくことなど)により、十分高い場合においては、設計上全交流動力電源喪失を想定しなくてもよ
。〉――
既に有名になっている全電源喪失に対する備えの不必要性の決定である。
少しぐらいの大津波が来ても、全電源が喪失することはない、いわゆる「原発安全神話」の打ち立てである。
だが、津波がが襲い、たちまち全電源が喪失状態となって原子炉を冷却する電気系統までが不能状態に陥り、原子炉内部の圧力が高まり、そのことによる原子炉の破損回避のために放射性物質を含む気体の一部を外部に排出させて圧力を下げるベントを行った際、大量の放射性物質が空気中に排出されることになった。
要するに政府の地震関連の二つの組織が東電福島原子力発電所沖の巨大津波の危険性を指摘していながら、東電に対してその対策を求めもせずに東電の自主対策に任せていたばかりか、原子力の安全確保のための規制を担当する政府の原子力安全委員会は1990年8月30日に決定した全電源喪失は考慮しなくてもいいとした、言い替えると、津波恐るに足りずといった指針を18年以上も堅持していた。
全ては国と東電の怠慢という無責任から発した福島原発事故であり、自主避難であり、その他であって、当然、事故は自然災害由来と言うよりも人災由来のそのものと言うことができる。
そうである以上、国と東電が解決すべき無責任であって、解決こそが唯一被災者に対する国と東電の責任となる。
そのことを自覚できないで、福島に帰れないのは「本人の責任だ」とか「本人の判断」だと言う。国の責任を被災者に責任転嫁する無責任以外の何ものでもない。
被災者の心に寄り添うと言ったのは安倍晋三である。寄り添うことのできない無責任な閣僚を任命した、その任命責任は安倍晋三にある。直ちに更迭すべきだろう。















