
本章に登場する若き革命児:エドワード3世 エドワード黒太子 賢明王シャルル5世 最愛王シャルル6世 ジャンヌ・ダルク 勝利王シャルル7世
百年戦争は、フランス王シャルル4世に跡取りがいなかったことに端を発する。シャルル4世の没後、従兄弟であるフィリップ6世が王位を継いだが、それに対して、イギリス王エドワード3世が異議を唱えた。
エドワード3世は、当時26歳。14歳で即位、わずか17歳で親政し、毛織物立国の基盤を築いた若き名君だった。
実は、エドワードはシャルルの叔父にあたっていて、自分がフランス王を兼ねるのが当然だと主張する。もちろん、フィリップは反発し、若いエドワードをあなどって、イギリス領にちょっかいを出す。これにはエドワードも激怒し、とうとう、イギリス軍がフランスに上陸するという、最悪の事態に至った。
パリに向かって進軍するイギリス軍に対し、フランス軍は騎兵を結集して、正面から応戦する構えだった。全身を鎧で固めて集団で突撃する騎兵は、実に過去4世紀に渡って、戦場の主力を成していた。
この騎兵隊が1万2千に、歩兵も2万以上。さらに6千人の弩部隊に、ドイツの諸侯まで、フランスの支援に回っていた。フランス軍の兵力は、イギリス軍の2倍以上。
加えて、フランス軍を率いるフィリップが53歳と、百戦錬磨の大ベテランだったのに対して、イギリス軍を率いるエドワードは、まだ35歳。経験の差は、歴然としていた。イギリスの勝ち目は、薄いかに思われた。
イギリス軍は、クレイシーのなだらかな丘の上に陣取って、フランス軍を迎え撃つ作戦を用いた。このときイギリスが用いたのは、ウェールズの猟師が使っていた、長さ1メートル近くの長弓だった。これは射程が4百メートルというもので、2百メートル以内ならば、鎧をも貫通した。イギリスは、1万1千の、長弓と槍を持たせた、農民からなる歩兵隊を丘の上に並べた。
対するフランス軍は、弩部隊を先頭に、丘を駆け登ってくる。弩は、当時最も威力のあった飛び道具で、あまりの殺傷力の高さに、法皇から使用禁止令が出されたほどだった。
だが、この弩が射程距離に入る前に、丘の両サイドの長弓から放たれた長い矢が、フランス軍を射貫いていた。弩部隊はなんとか反撃を試みるが、構造の複雑な弩をつがえるには、長弓の6倍の時間を要した。結局、ほとんど反撃できずに壊滅。
さらに悲惨なのは、騎兵だった。一方的に矢のシャワーを浴び、しかも随所に落とし穴や杭が仕掛けてあったので、バランスを崩して、大部分の騎兵が落馬。当時の騎兵は50キロもある鎧で身を固めていたので、倒れたが最後、自力で起き上がることもできない。地面でもがいているところを、槍部隊が近づいて、難無く串刺しにする。
だが、愚かにも、フランス軍はその後も、日没まで無謀な突撃を16回も繰り返し、1日にして、大切な兵をほとんど全滅させてしまう。死者2万5千人以上、捕虜も無数。
この悲惨な敗北の責任者であるフィリップは、身ひとつで逃亡した。愚かな指導者に率いられた集団が、いかに悲惨な末路を辿るかという、サンプルのような敗北であろう。
一方、イギリス軍の死者は、わずかに50名程度だったという。しかも、ろくに訓練も施していない農民たちが、2倍以上もいる職業軍人たちを相手にした上で! イギリスにとってみれば、この上ない完全大勝利に終わった。
限られた人材でも、リーダーの知恵と工夫次第で無限の力を発揮するという、サンプルのような勝利だった。その陰に、若きエドワード黒太子の尽力があったことは、よく知られている。
黒太子はエドワード3世の息子で、当時まだ16歳。しかし、クレイシーの軍の一翼の指揮を執り、初陣ながら任務を完璧に全うした。黒太子の力を抜きにして、これほどの完勝は考えられなかった、というほどの名指揮だった。
あるいは、騎士4世紀の不敗神話を終わらせた長弓作戦そのものが、黒太子の発案だったのかも知れない。彼の立場を考えた場合、少なくとも何らかの形で作戦に寄与したことは間違いなかろう。
クレイシーで若き天才将軍として名を馳せた黒太子は、10年後のポワティエでの戦いでは、イギリス軍の総司令官として全軍の指揮を執る。一方、フランス軍を指揮したのは、フィリップの息子であるジャン王。
ジャン王は、フランス騎兵隊を誇るあまり、クレイシーでの完敗の原因を農民の長弓のためだと認めず、愚かにも、父親同様、無謀な突撃を繰り返すばかりだった。黒太子は前回以上の指揮を見せ、ジャン王を捕虜にするほどの完勝を収める。北フランスは、あえなくイギリスに占領された。
だが、黒太子は、敗敵ジャン王をあくまで一国の王として尊重し、臣従の礼をもって迎える。その謙虚な態度がますます黒太子の名声を高め、騎士の鑑として今日まで語り継がれている。
しかし、その後は年をおうごとに、かつての名将軍ぶりに蔭りが見えてくる。特にリモージュでは、住民を無差別に虐殺し、その輝かしい経歴に汚点を刻むことになった。
もはや黒太子は、騎士の鑑と讃えられた、かつての謙虚な若者ではなかった。やがて病が悪化し、王位を継ぐことなく、46歳にしてこの世を去ることになる。
その後、19歳でフランスの摂政となった天才青年・賢明王シャルル5世は、30歳代までに北フランスの奪環に成功する。だが彼の死をきっかけに、またもやフランスは保守派とイギリス派に分裂した。
息子であるシャルル6世が20歳で親政し、善政によってようやく混乱は収まったが、彼は後に発狂してしまう。チャンスと見たイギリスは、シャルル6世の息子・シャルル王太子の命を狙ってフランスに上陸、仏内イギリス派と結び、イギリス領を拡大していく。フランスは、滅亡の危機に見舞われていた。
英領に呑み込まれた地域にある、わずか50世帯前後の小さな村ドンレミにジャンヌ・ダルクが生まれたのは、そんな時期だった。ジャンヌは、父親が有力者であることを除けば、どこの村にもいる、ごく普通の娘だった。家が教会の隣にあったので、ジャンヌはよく教会に通い、信仰心に篤い少女に育っていった。
またドンレミは、英領にあるのにもかかわらず、政治的にはシャルル王太子を支持していた。その中で育ったジャンヌも、次第に愛国心の強い少女となっていった。村にイギリス派は1人しかおらず、ジャンヌは、その村人を殺してやりたいと思うほど憎んでいたという。
信仰心と愛国心は、ジャンヌの生涯を決定する重要なポイントとなる。
13歳になったジャンヌは、隣村ヌフシャトーの若者から求婚される。それからまもなく、ジャンヌは、自宅の庭で聖者ミッシェルの声を聞く。その声は、ジャンヌに、フランスを救うように呼びかけたという。
この聖者について、ジャンヌは後に「声は聞こえるが、姿は見えなかった」と語っている。統合失調症の症状のひとつに「自分の潜在意識の思考が、声として聞こえる」というものがあるが、ジャンヌは、そういう傾向を持っていたのかも知れない。
声は、ジャンヌに対して
1.行いを正しくすること
2.神の望む間は処女を守ること
3.フランスに行くこと
を命じた。特に2は結婚してはならないという意味で、怒ったフィアンセは、裁判に訴えて結婚を成立させようとする。だが声はジャンヌに対し
「裁判には必ず勝つ」
と語ったという。事実、その通りになった。プロポーズを受け入れたわけではないというジャンヌの主張が通ったのだった。
声は、その後も週に2~3度の割合で続き、内容も具体的になっていった。
声は、ジャンヌに対して、まず王太子の守備隊長であるボードリクールの元へ向かうこと、軍の先頭に立つこと、さらに男装することを命じた。当時、女性の男装は、カソリックによって固く禁じられていた。
ジャンヌは「農民の娘でしかない自分に、なんでそんな大それたことができましょうか」と、声の主に泣いて哀願したと伝えられる。確かに、農民の娘として生きてきたジャンヌが、軍の先頭に立ち、職業軍人たちと戦うなど、どう考えても、無謀な自殺行為でしかない。
だが、そんなジャンヌに決断を促す出来事が起こった。ジャンヌが16歳のとき、英領の中で王太子への指示を貫くドンレミを潰そうと、イギリス派が攻めてきたのだった。
村人はジャンヌの父に率いられ、ヌフシャトーに避難する。幸いにも犠牲者は出なかったが、1月後に戻った村は、無惨に破壊されていた。ジャンヌは、故郷の家族や人々を守るため、イギリスを打ち破る他に道はないと悟る。
ジャンヌは、叔父を連れてボードリクールの城へ向かったが、案の定、相手にされない。しかし、聖者の声を聞く少女として有名になっていたジャンヌは、城の近所の大工の家に滞在することができた。その後は、毎日城に通って、執念でボードリクールとの面会を求め続けた。
そんな日々が、1年近くも続いた。ジャンヌは街中の噂となり、魔女ではないかという者もいたが、一方で、ジャンヌと面会しないボードリクールを非難する声も高まっていた。
そこでボードリクールは、司祭をジャンヌの元に向かわせる。魔女ならば、司祭を見て逃げ出すだろうという考えからだったが、当然、ジャンヌが司祭を恐れるはずもない。
さらに、ジャンヌはそのとき、まだ誰も知らなかったはずの、王太子軍のルーブレイでの敗北をすでに知っていた。ジャンヌの能力は、確かに分裂症だけでは説明のつかない、不思議なところがあったらしい。
ユングは、無意識には個人的なものと、集団や地域に共通する集合的なものがあるとした。ジャンヌはおそらく、この集合的な無意識を、他の人より敏感に感じ取る気質だったのではないだろうか。
ボードリクールもジャンヌの不思議な力を認めざるを得ず、少女の執念に屈して、ようやく会見に応じる。ジャンヌは、ボードリクールから馬と6人の護衛を与えられ、王太子のいるシノンへ旅立った。彼女が男装するのは、ここから。17歳になっていた。
シノンまでは5百キロの道程で、しかも敵陣の真っ只中を通らねばならなかったが、ジャンヌ一行は、なぜか無事シノンに到着した。城に入ったとき、大広間にはおよそ3百人の貴族や僧侶がいたが、ジャンヌは、ひと目で王太子を見分けて真っ直ぐに進み、王太子の耳元で、誰も知らないはずの王太子の秘密を囁いたと伝えられる。王太子はジャンヌを神の使いだと信じた。
しかし、ジャンヌを魔女だと疑う者も多く、彼女は教会で尋問を受けることになる。そこで彼女は「自分に軍隊を与えれば、オルレアンで証拠を見せる」と述べた。
オルレアンは、およそ半世紀に渡ってイギリスに負け続けたフランスにとって、もはや最後の砦。すでにイギリス軍に完全包囲されていたが、その守備は固く、イギリス軍の司令官も戦死。しかし、古来より籠城で勝機が開けた試しはない。7カ月もの持久戦で戦況は徐々に悪化し、陥落は時間の問題。
ジャンヌは、ここに自分を参戦させれば勝ってみせるという。17歳の農民の娘が口にする言葉とは思えない。しかし、彼女が敬虔なカソリックであることは、誰にも否定できなかった。
王太子は、ジャンヌに騎士の位、白銀の鎧、白馬、それに白旗を与え、数千の援軍と共に、オルレアンに向かわせた。陸路が絶たれていたので、城に入るには川を渡るしかなかったが、ジャンヌが到着した途端、不思議にも順風が吹き、イギリス軍に妨害されることもなく入城できたという。
このとき、ジャンヌが身に付けていた鎧は、25キロもあった。鍛えぬいた大の男でなければ、普通とても着られるものではない。彼女が屈強な体力の持ち主であったことは、容易に想像できる。丸顔の美少女で、瞳も髪も濃い色合いだったという。
ジャンヌは入城すると、まずイギリス軍に2度に渡って降伏勧告を送りつける。彼女の目的はフランスを守ることで、戦闘はできる限り避けたかった。もちろん、優勢にあるイギリス軍がこれを呑むはずもなく、オルレアン東のサンルー砦を狙って、攻撃を開始する。
ジャンヌはすぐさま砦に駆けつけ、軍の先頭に立ち、高らかに旗を掲げた。うら若き少女の、命懸けの姿にフランス兵は奮い立ち、見事にイギリス軍を撃退。翌日、ジャンヌは最後の降伏勧告を送るが、やはりイギリス軍は応じない。その翌日、ジャンヌはオーギュスタン要塞を陥落させ、さらに、補給路を塞いでいるトゥーレル要塞に向かう。
ジャンヌはここで、大砲を使って城壁に穴を開け、それから突撃するという方法を指示する。当時、フランス軍は騎士の誇りから、大砲をあまり使いたがらなかった。これはまさに素人ならではの自由な発想だった。
ジャンヌはこの戦闘で胸に矢を受け、負傷している。彼女は、戦場では常に先頭に立ち、自分の旗を掲げていた。旗を見た敵がジャンヌ・ダルクの存在を知り、戦う前に逃げるチャンスを与えるための目印として、掲げていたのだという。
だが、これは同時に、彼女が狙い撃ちの絶好の的となることを意味する。最も危険な位置で、ジャンヌは、負傷しながらも指揮を執り続けた。その姿を見て、兵士たちも、かつて無いほどに勇敢に戦った。
はたして、ジャンヌの指示通り大砲を活用したフランス軍は、またもや勝利を収めた。軍事史上も、初めて攻城戦で大砲を有効に使用したのは、ジャンヌ・ダルクだとされている。この方法の発見により、騎兵の時代に続いて、城の時代もまた、終わりを告げることになる。
ジャンヌは砦を落とした後、敵味方を問わず、戦死した者たちのために祈りを捧げた。彼女は、身を守るとき以外は、進んで敵を殺すことはなかった。そして、死んだ敵のために涙を流したという。
たちまちのうちに戦況を逆転させたジャンヌに恐れを為したのか、最後に残った北を囲っていたイギリス軍も、砦に火を放って退却。
こうして、7カ月に渡ったオルレアンでの攻防は、ジャンヌが指揮を執るようになってから、わずか4日で決着がついた。それも、指揮どころか槍も握ったことの無い、10歳代の少女の手で!もはや、ジャンヌが奇跡の聖女であることを疑う者は、誰もいなかった。
ジャンヌは矢傷を癒す間もなく、王太子をランスに向かわせる道を開くため、再び出陣する。
フランス国王は、代々ランスで聖別を受けて載冠する慣わし。しかし、今フランス王を名乗っているイギリスのリチャードは、まだこの載冠式をしていない。シャルルが先に載冠式を挙げれば、シャルルこそ正式なフランス王だという大義名分が成立する。
ジャンヌは、またもや奇跡を具現した。ジャルジョー、マン、パテーで、たて続けにイギリス軍の主力を撃破、大勝利を収める。戦いの中で、ジャンヌは大砲の着弾の位置を予知したと伝えられる。
王太子は、ジャンヌの開いた道を通ってランスに到着し、大聖堂で載冠式を挙げ、26歳にして、正式に新フランス国王シャルル7世となった。ジャンヌがシャルルと始めて会ってから、わずか4カ月。10歳代の少女が、一国を滅亡の危機から救った。
しかし、この載冠式をピークに、ジャンヌの不思議な力は衰えを見せ始める。
もともと彼女の信念は、カソリックへの信仰心と、フランスへの愛国心が、ひとつに結びついたものだった。そのシンボルが、シャルルを聖別し、国王にするという目標だった。その目標を達成してしまった今、まだイギリス軍から領土を取り返すという仕事は残っていたものの、やはり、ジャンヌのモチベーションは下がっていたらしい。
その上、ジャンヌのあまりの快進撃ぶりと人気、シャルルからの信頼は、以前からシャルルの側近たちの妬みをかっていた。彼らには、フランスのためを思うジャンヌの志など伝わらなかった。自分の保身しか目に入らなかった。真の敵は、常に内側から生じる。このような側近たちに言いくるめられ、新国王となったシャルルもまた、大恩人であるジャンヌを快く思わなくなっていった。
ジャンルは、いよいよパリを攻める。ここでも彼女は先頭に立ち、脚に矢を受けるほどの勇敢な戦いぶりを見せるが、パリ奪換を目前にして、新国王から突如、攻撃中止の命令が下る。
この退却の理由は不明。おそらくは、ジャンヌがこれ以上手柄を立てるのを快く思わない者の策謀だろう。フランスは、一人の少女に対するつまらない嫉妬のために、パリを取り戻すチャンスを失った。
彼女は、全く過失が無いのにもかかわらず、敗軍の将として退却せざるを得なかった。さらに、今まで共に戦ってきた戦友たちも、ジャンヌから引き離された。彼女は、フランス軍の主力部隊から、事実上外された。
翌年、18歳になったジャンヌは、わずかな兵と共にラニーやサンリスに出征、小競り合いを繰り返した。彼女が、
「あなたはもうすぐ捕虜になる」
という声を聞いたのは、このときだった。これ以来、二度と声はジャンヌに語りかけなかった。
それから1カ月後のコンピエーニュの戦いで、ジャンヌは声の予言通り、捕虜となった。彼女は、攻めるときは必ず先頭に立ったが、退却するときは、必ずしんがりを勤めた。そのため、ジャンヌが城に避難する前に跳ね橋が上げられてしまい、逃げ場を失って、捕えられたのだ。
当時、捕虜は身代金と引き換えに買い戻す習慣があった。しかし、新国王は、ジャンヌの身代金を払おうとしなかった。
ジャンヌがいなければ、彼はイギリス軍に捕えられ、処刑されていたかも知れない。命の恩人であるジャンヌを、新国王は見捨てた。おそらく、彼女が処刑されることも承知の上で。いかに側近に惑わされていたとはいえ、人間は、かくもおぞましく人を裏切れるものなのか! シャルルもまた、権力の魔性に敗れた一人だった。
ジャンヌは、半年以上に渡って独房に監禁された後、19歳になってすぐ、異端の疑いという名目で裁判にかけられる。ただジャンヌを処刑しては、ジャンヌは英雄になってしまう。ジャンヌに魔女の汚名を着せて処刑することが、イギリスの狙いだった。
イギリスは国家の威信を懸けて、この裁判に臨んだ。ジャンヌは拷問道具を突きつけられ、何か月も熾烈な取り調べを受けた。長い独房生活に、真冬の寒さもあいまって、健強そのものだったジャンヌも疲労し、病に侵される。
しかしそれでもジャンヌは、聖者の声を聞いたという主張を曲げなかった。彼女の賢明な受け答えの前に、イギリス側の司教も、異端の証拠をでっち上げることができない。そこで司教は、ジャンヌに異端の汚名を着せて処刑するため、ある策略を練る。
司教はジャンヌに、二度と聖者の声を聞いたと主張しないこと、男装しないことを誓わせ、それと引き換えに命を助け、独房から教会の牢に移すという条件を提示する。ジャンヌはこの条件をのみ、宣誓書に署名する。
しかし、司教は提示した条件を守らず、それどころか毎晩のように独房に男たちを忍び込ませ、ジャンヌに乱暴を働こうとした。敬虔なカソリックであるジャンヌにとって、男に汚されるのは、死にも勝る屈辱だった。
牢には、なぜか男の服が没収されることなく、そのまま置かれている。当時は、宣誓を破れば無条件に火あぶりにできた。司教は、ジャンヌの篤い信仰心を利用して、彼女に無理矢理異端の汚名を着せようとしたのだった。時として、聖職者こそ、最も信仰から程遠いところにいる。
ジャンヌも、ここに至っては、司教の見え透いた狙いが分かっていたらしい。しかしあえて、男に汚されるよりは、火刑台に上がる道を選ぶ。あくる朝、彼女は男装に戻っていた。司教の狙い通りだった。
それからわずか3日後、ジャンヌは、生きたまま火あぶりの刑に処された(通常は、処刑後に遺体を火あぶりする)。罪状は「男装した」ただそれだけだった。炎に包まれながらの、彼女の最期の言葉は、
「イエス様!」
だったという。処刑に立ち会ったイギリス人の誰もが、彼女が魔女などではないことを確信し、敵である彼女のために涙を流したと伝えられる。
こうして万事、イギリス側の計略が成功したかに見えたが、ジャンヌから英雄の称号を剥ぎ取ろうという目論見は、完全に裏目に出た。母国のために戦い続けた、いたいけな少女への、イギリスのあまりにも非道な仕打ちは、全フランスの怒りを爆発させた。
新国王シャルル7世も、側近に惑わされ、取り返しのつかない過ちを犯したことを悟った。かつてジャンヌの敵だった、フランス国内のイギリス派でさえ、この不当かつ惨忍な処刑を許さなかった。ジャンヌの死が、彼らに政治的対立を忘れさせ、人としての怒りを蘇らせた。
ジャンヌの処刑から、わずか5年後。分裂していたフランスは、32歳の若き国王、シャルル7世の元に一致団結。ジャンヌの遺志を継ぎ、国民が一丸となって、イギリスを本土から叩き出す。フランスは再び、誇りある独立と自治を取り戻した。シャルル7世が勝利王と呼ばれるのは、このゆえ。イギリスは、たった一人の少女を罠にかけて処刑したため、百年かけて手中に収めようとした大陸を失った。
一人の若者が、命を懸けて闘ったとき、不可能は可能になる。ジャンヌは、死してなお、歴史を導き続けた。
シャルル7世は、勅命によってジャンヌの復権裁判を開かせた。死者のための裁判が開かれることは前代未聞だったが、彼女を裏切り、見捨てた自責の念に苦しみ続けるシャルル7世は、新生フランスの威信を懸けて、この裁判に臨んだ。証人の誰もが、生前の彼女の信心深さを証言した。
こうして、時のローマ教皇自ら、取り返しのつかない過ちを犯したことを認め、ジャンヌへの処刑判決を撤回、改めて無罪を宣言した。フランス国民の喜びは大変なもので、全土でジャンヌの名誉回復を祝う式典が開かれた。
やがて、ジャンヌと同じ時代を生きた人々が世を去るに連れ、彼女も徐々に忘れられていった。そんなジャンヌを、歴史から発掘したのが、3百年以上後に現れた皇帝ナポレオンだった。ナポレオンが、ジャンヌを救国の英雄として讃えたことで、ジャンヌ・ダルクの名は、再びフランス全土に蘇った。
さらに、彼女の裁判の記録が出版され、その生涯がフランス国内のみならず、世界中に知られることとなった。かつての敵だったイギリスの作家バーナード・ショーでさえ、『聖女ジョーン(ジャンヌ)』でこの悲劇の少女を讃え、両国の友好に大きく貢献した。
ジャンヌ・ダルクを聖人に叙することは、フランス全国民の悲願となった。ローマは、ジャンヌの列聖を請願するフランスからの巡礼者であふれ、政府も全権大使を派遣するほどだった。ローマ教皇庁は、大規模な調査の末、1920年、ジャンヌを正式に聖人と認めた。かつて、彼女を異端として処刑の判決を下した教会が、5百年の時を経て、ジャンヌを聖人として最敬礼で遇した。
日本の源義経とフランスのジャンヌ・ダルクは、時代も3百年ほど違うし、活躍した場所も、極東と西欧でかけ離れている。にもかかわらず、その生涯に、あまりにも共通項が多いことに驚かされる。
若さ、電撃的な連勝、その後の急激な運の尽きと、恩人からの裏切り、そして炎に包まれた悲運な最期までも。ジャンヌは義経の生まれ変わりではないかと思われるほどだ。
何より、奇跡や悲劇の一言で片付けられない、衝撃的な若き天才の生涯を、今なお忘れずに語り継いでいる点では、日本人もフランス人も変わらない。歴史も文化も宗教も異なる両国民だが、人間としての怒りや悲しみに、違いはないのだろう。
続きを読む
最初から読む
百年戦争は、フランス王シャルル4世に跡取りがいなかったことに端を発する。シャルル4世の没後、従兄弟であるフィリップ6世が王位を継いだが、それに対して、イギリス王エドワード3世が異議を唱えた。
エドワード3世は、当時26歳。14歳で即位、わずか17歳で親政し、毛織物立国の基盤を築いた若き名君だった。
実は、エドワードはシャルルの叔父にあたっていて、自分がフランス王を兼ねるのが当然だと主張する。もちろん、フィリップは反発し、若いエドワードをあなどって、イギリス領にちょっかいを出す。これにはエドワードも激怒し、とうとう、イギリス軍がフランスに上陸するという、最悪の事態に至った。
パリに向かって進軍するイギリス軍に対し、フランス軍は騎兵を結集して、正面から応戦する構えだった。全身を鎧で固めて集団で突撃する騎兵は、実に過去4世紀に渡って、戦場の主力を成していた。
この騎兵隊が1万2千に、歩兵も2万以上。さらに6千人の弩部隊に、ドイツの諸侯まで、フランスの支援に回っていた。フランス軍の兵力は、イギリス軍の2倍以上。
加えて、フランス軍を率いるフィリップが53歳と、百戦錬磨の大ベテランだったのに対して、イギリス軍を率いるエドワードは、まだ35歳。経験の差は、歴然としていた。イギリスの勝ち目は、薄いかに思われた。
イギリス軍は、クレイシーのなだらかな丘の上に陣取って、フランス軍を迎え撃つ作戦を用いた。このときイギリスが用いたのは、ウェールズの猟師が使っていた、長さ1メートル近くの長弓だった。これは射程が4百メートルというもので、2百メートル以内ならば、鎧をも貫通した。イギリスは、1万1千の、長弓と槍を持たせた、農民からなる歩兵隊を丘の上に並べた。
対するフランス軍は、弩部隊を先頭に、丘を駆け登ってくる。弩は、当時最も威力のあった飛び道具で、あまりの殺傷力の高さに、法皇から使用禁止令が出されたほどだった。
だが、この弩が射程距離に入る前に、丘の両サイドの長弓から放たれた長い矢が、フランス軍を射貫いていた。弩部隊はなんとか反撃を試みるが、構造の複雑な弩をつがえるには、長弓の6倍の時間を要した。結局、ほとんど反撃できずに壊滅。
さらに悲惨なのは、騎兵だった。一方的に矢のシャワーを浴び、しかも随所に落とし穴や杭が仕掛けてあったので、バランスを崩して、大部分の騎兵が落馬。当時の騎兵は50キロもある鎧で身を固めていたので、倒れたが最後、自力で起き上がることもできない。地面でもがいているところを、槍部隊が近づいて、難無く串刺しにする。
だが、愚かにも、フランス軍はその後も、日没まで無謀な突撃を16回も繰り返し、1日にして、大切な兵をほとんど全滅させてしまう。死者2万5千人以上、捕虜も無数。
この悲惨な敗北の責任者であるフィリップは、身ひとつで逃亡した。愚かな指導者に率いられた集団が、いかに悲惨な末路を辿るかという、サンプルのような敗北であろう。
一方、イギリス軍の死者は、わずかに50名程度だったという。しかも、ろくに訓練も施していない農民たちが、2倍以上もいる職業軍人たちを相手にした上で! イギリスにとってみれば、この上ない完全大勝利に終わった。
限られた人材でも、リーダーの知恵と工夫次第で無限の力を発揮するという、サンプルのような勝利だった。その陰に、若きエドワード黒太子の尽力があったことは、よく知られている。
黒太子はエドワード3世の息子で、当時まだ16歳。しかし、クレイシーの軍の一翼の指揮を執り、初陣ながら任務を完璧に全うした。黒太子の力を抜きにして、これほどの完勝は考えられなかった、というほどの名指揮だった。
あるいは、騎士4世紀の不敗神話を終わらせた長弓作戦そのものが、黒太子の発案だったのかも知れない。彼の立場を考えた場合、少なくとも何らかの形で作戦に寄与したことは間違いなかろう。
クレイシーで若き天才将軍として名を馳せた黒太子は、10年後のポワティエでの戦いでは、イギリス軍の総司令官として全軍の指揮を執る。一方、フランス軍を指揮したのは、フィリップの息子であるジャン王。
ジャン王は、フランス騎兵隊を誇るあまり、クレイシーでの完敗の原因を農民の長弓のためだと認めず、愚かにも、父親同様、無謀な突撃を繰り返すばかりだった。黒太子は前回以上の指揮を見せ、ジャン王を捕虜にするほどの完勝を収める。北フランスは、あえなくイギリスに占領された。
だが、黒太子は、敗敵ジャン王をあくまで一国の王として尊重し、臣従の礼をもって迎える。その謙虚な態度がますます黒太子の名声を高め、騎士の鑑として今日まで語り継がれている。
しかし、その後は年をおうごとに、かつての名将軍ぶりに蔭りが見えてくる。特にリモージュでは、住民を無差別に虐殺し、その輝かしい経歴に汚点を刻むことになった。
もはや黒太子は、騎士の鑑と讃えられた、かつての謙虚な若者ではなかった。やがて病が悪化し、王位を継ぐことなく、46歳にしてこの世を去ることになる。
その後、19歳でフランスの摂政となった天才青年・賢明王シャルル5世は、30歳代までに北フランスの奪環に成功する。だが彼の死をきっかけに、またもやフランスは保守派とイギリス派に分裂した。
息子であるシャルル6世が20歳で親政し、善政によってようやく混乱は収まったが、彼は後に発狂してしまう。チャンスと見たイギリスは、シャルル6世の息子・シャルル王太子の命を狙ってフランスに上陸、仏内イギリス派と結び、イギリス領を拡大していく。フランスは、滅亡の危機に見舞われていた。
英領に呑み込まれた地域にある、わずか50世帯前後の小さな村ドンレミにジャンヌ・ダルクが生まれたのは、そんな時期だった。ジャンヌは、父親が有力者であることを除けば、どこの村にもいる、ごく普通の娘だった。家が教会の隣にあったので、ジャンヌはよく教会に通い、信仰心に篤い少女に育っていった。
またドンレミは、英領にあるのにもかかわらず、政治的にはシャルル王太子を支持していた。その中で育ったジャンヌも、次第に愛国心の強い少女となっていった。村にイギリス派は1人しかおらず、ジャンヌは、その村人を殺してやりたいと思うほど憎んでいたという。
信仰心と愛国心は、ジャンヌの生涯を決定する重要なポイントとなる。
13歳になったジャンヌは、隣村ヌフシャトーの若者から求婚される。それからまもなく、ジャンヌは、自宅の庭で聖者ミッシェルの声を聞く。その声は、ジャンヌに、フランスを救うように呼びかけたという。
この聖者について、ジャンヌは後に「声は聞こえるが、姿は見えなかった」と語っている。統合失調症の症状のひとつに「自分の潜在意識の思考が、声として聞こえる」というものがあるが、ジャンヌは、そういう傾向を持っていたのかも知れない。
声は、ジャンヌに対して
1.行いを正しくすること
2.神の望む間は処女を守ること
3.フランスに行くこと
を命じた。特に2は結婚してはならないという意味で、怒ったフィアンセは、裁判に訴えて結婚を成立させようとする。だが声はジャンヌに対し
「裁判には必ず勝つ」
と語ったという。事実、その通りになった。プロポーズを受け入れたわけではないというジャンヌの主張が通ったのだった。
声は、その後も週に2~3度の割合で続き、内容も具体的になっていった。
声は、ジャンヌに対して、まず王太子の守備隊長であるボードリクールの元へ向かうこと、軍の先頭に立つこと、さらに男装することを命じた。当時、女性の男装は、カソリックによって固く禁じられていた。
ジャンヌは「農民の娘でしかない自分に、なんでそんな大それたことができましょうか」と、声の主に泣いて哀願したと伝えられる。確かに、農民の娘として生きてきたジャンヌが、軍の先頭に立ち、職業軍人たちと戦うなど、どう考えても、無謀な自殺行為でしかない。
だが、そんなジャンヌに決断を促す出来事が起こった。ジャンヌが16歳のとき、英領の中で王太子への指示を貫くドンレミを潰そうと、イギリス派が攻めてきたのだった。
村人はジャンヌの父に率いられ、ヌフシャトーに避難する。幸いにも犠牲者は出なかったが、1月後に戻った村は、無惨に破壊されていた。ジャンヌは、故郷の家族や人々を守るため、イギリスを打ち破る他に道はないと悟る。
ジャンヌは、叔父を連れてボードリクールの城へ向かったが、案の定、相手にされない。しかし、聖者の声を聞く少女として有名になっていたジャンヌは、城の近所の大工の家に滞在することができた。その後は、毎日城に通って、執念でボードリクールとの面会を求め続けた。
そんな日々が、1年近くも続いた。ジャンヌは街中の噂となり、魔女ではないかという者もいたが、一方で、ジャンヌと面会しないボードリクールを非難する声も高まっていた。
そこでボードリクールは、司祭をジャンヌの元に向かわせる。魔女ならば、司祭を見て逃げ出すだろうという考えからだったが、当然、ジャンヌが司祭を恐れるはずもない。
さらに、ジャンヌはそのとき、まだ誰も知らなかったはずの、王太子軍のルーブレイでの敗北をすでに知っていた。ジャンヌの能力は、確かに分裂症だけでは説明のつかない、不思議なところがあったらしい。
ユングは、無意識には個人的なものと、集団や地域に共通する集合的なものがあるとした。ジャンヌはおそらく、この集合的な無意識を、他の人より敏感に感じ取る気質だったのではないだろうか。
ボードリクールもジャンヌの不思議な力を認めざるを得ず、少女の執念に屈して、ようやく会見に応じる。ジャンヌは、ボードリクールから馬と6人の護衛を与えられ、王太子のいるシノンへ旅立った。彼女が男装するのは、ここから。17歳になっていた。
シノンまでは5百キロの道程で、しかも敵陣の真っ只中を通らねばならなかったが、ジャンヌ一行は、なぜか無事シノンに到着した。城に入ったとき、大広間にはおよそ3百人の貴族や僧侶がいたが、ジャンヌは、ひと目で王太子を見分けて真っ直ぐに進み、王太子の耳元で、誰も知らないはずの王太子の秘密を囁いたと伝えられる。王太子はジャンヌを神の使いだと信じた。
しかし、ジャンヌを魔女だと疑う者も多く、彼女は教会で尋問を受けることになる。そこで彼女は「自分に軍隊を与えれば、オルレアンで証拠を見せる」と述べた。
オルレアンは、およそ半世紀に渡ってイギリスに負け続けたフランスにとって、もはや最後の砦。すでにイギリス軍に完全包囲されていたが、その守備は固く、イギリス軍の司令官も戦死。しかし、古来より籠城で勝機が開けた試しはない。7カ月もの持久戦で戦況は徐々に悪化し、陥落は時間の問題。
ジャンヌは、ここに自分を参戦させれば勝ってみせるという。17歳の農民の娘が口にする言葉とは思えない。しかし、彼女が敬虔なカソリックであることは、誰にも否定できなかった。
王太子は、ジャンヌに騎士の位、白銀の鎧、白馬、それに白旗を与え、数千の援軍と共に、オルレアンに向かわせた。陸路が絶たれていたので、城に入るには川を渡るしかなかったが、ジャンヌが到着した途端、不思議にも順風が吹き、イギリス軍に妨害されることもなく入城できたという。
このとき、ジャンヌが身に付けていた鎧は、25キロもあった。鍛えぬいた大の男でなければ、普通とても着られるものではない。彼女が屈強な体力の持ち主であったことは、容易に想像できる。丸顔の美少女で、瞳も髪も濃い色合いだったという。
ジャンヌは入城すると、まずイギリス軍に2度に渡って降伏勧告を送りつける。彼女の目的はフランスを守ることで、戦闘はできる限り避けたかった。もちろん、優勢にあるイギリス軍がこれを呑むはずもなく、オルレアン東のサンルー砦を狙って、攻撃を開始する。
ジャンヌはすぐさま砦に駆けつけ、軍の先頭に立ち、高らかに旗を掲げた。うら若き少女の、命懸けの姿にフランス兵は奮い立ち、見事にイギリス軍を撃退。翌日、ジャンヌは最後の降伏勧告を送るが、やはりイギリス軍は応じない。その翌日、ジャンヌはオーギュスタン要塞を陥落させ、さらに、補給路を塞いでいるトゥーレル要塞に向かう。
ジャンヌはここで、大砲を使って城壁に穴を開け、それから突撃するという方法を指示する。当時、フランス軍は騎士の誇りから、大砲をあまり使いたがらなかった。これはまさに素人ならではの自由な発想だった。
ジャンヌはこの戦闘で胸に矢を受け、負傷している。彼女は、戦場では常に先頭に立ち、自分の旗を掲げていた。旗を見た敵がジャンヌ・ダルクの存在を知り、戦う前に逃げるチャンスを与えるための目印として、掲げていたのだという。
だが、これは同時に、彼女が狙い撃ちの絶好の的となることを意味する。最も危険な位置で、ジャンヌは、負傷しながらも指揮を執り続けた。その姿を見て、兵士たちも、かつて無いほどに勇敢に戦った。
はたして、ジャンヌの指示通り大砲を活用したフランス軍は、またもや勝利を収めた。軍事史上も、初めて攻城戦で大砲を有効に使用したのは、ジャンヌ・ダルクだとされている。この方法の発見により、騎兵の時代に続いて、城の時代もまた、終わりを告げることになる。
ジャンヌは砦を落とした後、敵味方を問わず、戦死した者たちのために祈りを捧げた。彼女は、身を守るとき以外は、進んで敵を殺すことはなかった。そして、死んだ敵のために涙を流したという。
たちまちのうちに戦況を逆転させたジャンヌに恐れを為したのか、最後に残った北を囲っていたイギリス軍も、砦に火を放って退却。
こうして、7カ月に渡ったオルレアンでの攻防は、ジャンヌが指揮を執るようになってから、わずか4日で決着がついた。それも、指揮どころか槍も握ったことの無い、10歳代の少女の手で!もはや、ジャンヌが奇跡の聖女であることを疑う者は、誰もいなかった。
ジャンヌは矢傷を癒す間もなく、王太子をランスに向かわせる道を開くため、再び出陣する。
フランス国王は、代々ランスで聖別を受けて載冠する慣わし。しかし、今フランス王を名乗っているイギリスのリチャードは、まだこの載冠式をしていない。シャルルが先に載冠式を挙げれば、シャルルこそ正式なフランス王だという大義名分が成立する。
ジャンヌは、またもや奇跡を具現した。ジャルジョー、マン、パテーで、たて続けにイギリス軍の主力を撃破、大勝利を収める。戦いの中で、ジャンヌは大砲の着弾の位置を予知したと伝えられる。
王太子は、ジャンヌの開いた道を通ってランスに到着し、大聖堂で載冠式を挙げ、26歳にして、正式に新フランス国王シャルル7世となった。ジャンヌがシャルルと始めて会ってから、わずか4カ月。10歳代の少女が、一国を滅亡の危機から救った。
しかし、この載冠式をピークに、ジャンヌの不思議な力は衰えを見せ始める。
もともと彼女の信念は、カソリックへの信仰心と、フランスへの愛国心が、ひとつに結びついたものだった。そのシンボルが、シャルルを聖別し、国王にするという目標だった。その目標を達成してしまった今、まだイギリス軍から領土を取り返すという仕事は残っていたものの、やはり、ジャンヌのモチベーションは下がっていたらしい。
その上、ジャンヌのあまりの快進撃ぶりと人気、シャルルからの信頼は、以前からシャルルの側近たちの妬みをかっていた。彼らには、フランスのためを思うジャンヌの志など伝わらなかった。自分の保身しか目に入らなかった。真の敵は、常に内側から生じる。このような側近たちに言いくるめられ、新国王となったシャルルもまた、大恩人であるジャンヌを快く思わなくなっていった。
ジャンルは、いよいよパリを攻める。ここでも彼女は先頭に立ち、脚に矢を受けるほどの勇敢な戦いぶりを見せるが、パリ奪換を目前にして、新国王から突如、攻撃中止の命令が下る。
この退却の理由は不明。おそらくは、ジャンヌがこれ以上手柄を立てるのを快く思わない者の策謀だろう。フランスは、一人の少女に対するつまらない嫉妬のために、パリを取り戻すチャンスを失った。
彼女は、全く過失が無いのにもかかわらず、敗軍の将として退却せざるを得なかった。さらに、今まで共に戦ってきた戦友たちも、ジャンヌから引き離された。彼女は、フランス軍の主力部隊から、事実上外された。
翌年、18歳になったジャンヌは、わずかな兵と共にラニーやサンリスに出征、小競り合いを繰り返した。彼女が、
「あなたはもうすぐ捕虜になる」
という声を聞いたのは、このときだった。これ以来、二度と声はジャンヌに語りかけなかった。
それから1カ月後のコンピエーニュの戦いで、ジャンヌは声の予言通り、捕虜となった。彼女は、攻めるときは必ず先頭に立ったが、退却するときは、必ずしんがりを勤めた。そのため、ジャンヌが城に避難する前に跳ね橋が上げられてしまい、逃げ場を失って、捕えられたのだ。
当時、捕虜は身代金と引き換えに買い戻す習慣があった。しかし、新国王は、ジャンヌの身代金を払おうとしなかった。
ジャンヌがいなければ、彼はイギリス軍に捕えられ、処刑されていたかも知れない。命の恩人であるジャンヌを、新国王は見捨てた。おそらく、彼女が処刑されることも承知の上で。いかに側近に惑わされていたとはいえ、人間は、かくもおぞましく人を裏切れるものなのか! シャルルもまた、権力の魔性に敗れた一人だった。
ジャンヌは、半年以上に渡って独房に監禁された後、19歳になってすぐ、異端の疑いという名目で裁判にかけられる。ただジャンヌを処刑しては、ジャンヌは英雄になってしまう。ジャンヌに魔女の汚名を着せて処刑することが、イギリスの狙いだった。
イギリスは国家の威信を懸けて、この裁判に臨んだ。ジャンヌは拷問道具を突きつけられ、何か月も熾烈な取り調べを受けた。長い独房生活に、真冬の寒さもあいまって、健強そのものだったジャンヌも疲労し、病に侵される。
しかしそれでもジャンヌは、聖者の声を聞いたという主張を曲げなかった。彼女の賢明な受け答えの前に、イギリス側の司教も、異端の証拠をでっち上げることができない。そこで司教は、ジャンヌに異端の汚名を着せて処刑するため、ある策略を練る。
司教はジャンヌに、二度と聖者の声を聞いたと主張しないこと、男装しないことを誓わせ、それと引き換えに命を助け、独房から教会の牢に移すという条件を提示する。ジャンヌはこの条件をのみ、宣誓書に署名する。
しかし、司教は提示した条件を守らず、それどころか毎晩のように独房に男たちを忍び込ませ、ジャンヌに乱暴を働こうとした。敬虔なカソリックであるジャンヌにとって、男に汚されるのは、死にも勝る屈辱だった。
牢には、なぜか男の服が没収されることなく、そのまま置かれている。当時は、宣誓を破れば無条件に火あぶりにできた。司教は、ジャンヌの篤い信仰心を利用して、彼女に無理矢理異端の汚名を着せようとしたのだった。時として、聖職者こそ、最も信仰から程遠いところにいる。
ジャンヌも、ここに至っては、司教の見え透いた狙いが分かっていたらしい。しかしあえて、男に汚されるよりは、火刑台に上がる道を選ぶ。あくる朝、彼女は男装に戻っていた。司教の狙い通りだった。
それからわずか3日後、ジャンヌは、生きたまま火あぶりの刑に処された(通常は、処刑後に遺体を火あぶりする)。罪状は「男装した」ただそれだけだった。炎に包まれながらの、彼女の最期の言葉は、
「イエス様!」
だったという。処刑に立ち会ったイギリス人の誰もが、彼女が魔女などではないことを確信し、敵である彼女のために涙を流したと伝えられる。
こうして万事、イギリス側の計略が成功したかに見えたが、ジャンヌから英雄の称号を剥ぎ取ろうという目論見は、完全に裏目に出た。母国のために戦い続けた、いたいけな少女への、イギリスのあまりにも非道な仕打ちは、全フランスの怒りを爆発させた。
新国王シャルル7世も、側近に惑わされ、取り返しのつかない過ちを犯したことを悟った。かつてジャンヌの敵だった、フランス国内のイギリス派でさえ、この不当かつ惨忍な処刑を許さなかった。ジャンヌの死が、彼らに政治的対立を忘れさせ、人としての怒りを蘇らせた。
ジャンヌの処刑から、わずか5年後。分裂していたフランスは、32歳の若き国王、シャルル7世の元に一致団結。ジャンヌの遺志を継ぎ、国民が一丸となって、イギリスを本土から叩き出す。フランスは再び、誇りある独立と自治を取り戻した。シャルル7世が勝利王と呼ばれるのは、このゆえ。イギリスは、たった一人の少女を罠にかけて処刑したため、百年かけて手中に収めようとした大陸を失った。
一人の若者が、命を懸けて闘ったとき、不可能は可能になる。ジャンヌは、死してなお、歴史を導き続けた。
シャルル7世は、勅命によってジャンヌの復権裁判を開かせた。死者のための裁判が開かれることは前代未聞だったが、彼女を裏切り、見捨てた自責の念に苦しみ続けるシャルル7世は、新生フランスの威信を懸けて、この裁判に臨んだ。証人の誰もが、生前の彼女の信心深さを証言した。
こうして、時のローマ教皇自ら、取り返しのつかない過ちを犯したことを認め、ジャンヌへの処刑判決を撤回、改めて無罪を宣言した。フランス国民の喜びは大変なもので、全土でジャンヌの名誉回復を祝う式典が開かれた。
やがて、ジャンヌと同じ時代を生きた人々が世を去るに連れ、彼女も徐々に忘れられていった。そんなジャンヌを、歴史から発掘したのが、3百年以上後に現れた皇帝ナポレオンだった。ナポレオンが、ジャンヌを救国の英雄として讃えたことで、ジャンヌ・ダルクの名は、再びフランス全土に蘇った。
さらに、彼女の裁判の記録が出版され、その生涯がフランス国内のみならず、世界中に知られることとなった。かつての敵だったイギリスの作家バーナード・ショーでさえ、『聖女ジョーン(ジャンヌ)』でこの悲劇の少女を讃え、両国の友好に大きく貢献した。
ジャンヌ・ダルクを聖人に叙することは、フランス全国民の悲願となった。ローマは、ジャンヌの列聖を請願するフランスからの巡礼者であふれ、政府も全権大使を派遣するほどだった。ローマ教皇庁は、大規模な調査の末、1920年、ジャンヌを正式に聖人と認めた。かつて、彼女を異端として処刑の判決を下した教会が、5百年の時を経て、ジャンヌを聖人として最敬礼で遇した。
日本の源義経とフランスのジャンヌ・ダルクは、時代も3百年ほど違うし、活躍した場所も、極東と西欧でかけ離れている。にもかかわらず、その生涯に、あまりにも共通項が多いことに驚かされる。
若さ、電撃的な連勝、その後の急激な運の尽きと、恩人からの裏切り、そして炎に包まれた悲運な最期までも。ジャンヌは義経の生まれ変わりではないかと思われるほどだ。
何より、奇跡や悲劇の一言で片付けられない、衝撃的な若き天才の生涯を、今なお忘れずに語り継いでいる点では、日本人もフランス人も変わらない。歴史も文化も宗教も異なる両国民だが、人間としての怒りや悲しみに、違いはないのだろう。
続きを読む
最初から読む




















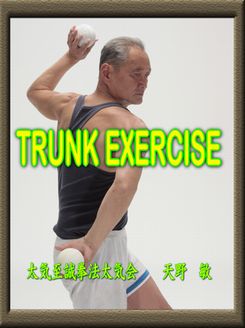

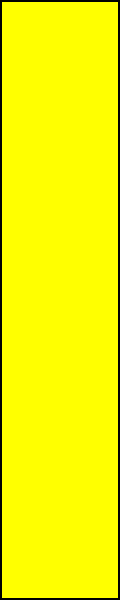





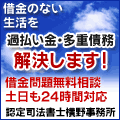
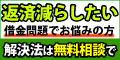






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます