
本章に登場する若き革命児:フィリッポス2世、アレキサンダー大王
歴史を動かした若者たちによる、壮大な叙事詩は、まず、紀元をはるか400年もさかのぼる古代ギリシャより、筆を起こすことにしたい。
当時、ギリシャでは、超大国ペルシャに裏で煽られて、アテネとスパルタが主導権を奪い合い、ポリス(都市国家)間の争いが絶えなかった。
そんな戦国の世に、小ポリス・マケドニアの摂政として、わずか18歳のフィリッポス2世が就任した。
政治手腕を高く評価されて、フィリッポスはまもなく正式に王位に就いた。
23歳の若き王は、ギリシャの統一を志し、農民による長槍歩兵方陣、すなわち「ファランクス」を創設し、常備軍とする。
ファランクスとは、兵士に6メートルもの長槍を持たせた長方形の隊列で、盾で矢を防ぎながら、正面から敵に突撃する。これは当時のギリシャで無敵を誇り、マケドニアはたちまち有力なポリスとなる。
同時代の人々は、
「ヨーロッパは、かつてこれほど強大な人物を知らなかった」
若きフィリッポスをそう称え、恐れたという。
フィリッポスが26歳のとき、1人の王子が生まれた。王子の名は、アレクサンドロス3世。日本では、アレキサンダーの方がなじみがあるかも知れない。マケドニア語で「敵を撃退する者」という意味の名前だった。
彼の母親は、叙事詩『イリアス』に出てくる英雄アキレウスの家系から出ていると、先祖から伝えられていた。父王が他の女性を寵愛したため、母親は王子を溺愛した。王子は自然に、母親の語るアキレウスに憧れる少年に育っていった。
王子は、13歳からというから今でいうと中学時代、大哲学者であり、「全ての学問の祖」として知られるアリストテレスを家庭教師に迎え入れ、教えを受ける。アリストテレスは当時まだ40歳そこそこだったが、プラトンの最も優秀な弟子としてその名を知られていた。父王フィリッポスとは、旧知の間柄だった。
アリストテレスは、3年間に渡って、王子につきっきりで哲学、政治学、自然科学、それに詩や劇を教えた。無敵の将軍だった父王と、伝説の英雄を語る母の存在に加え、多感な時期に王子がこの大哲学者に受けた影響は、多大なものだったろう。
アリストテレスは確かに優れた家庭教師だったが、王子には、たったひとつだけ納得できない点があった。それは、アリストテレスがギリシャ人以外の民族を全て野蛮人と考え、他民族を奴隷とすることを肯定していた点だった。
王子は、民族にかかわらず、人間は善人か悪人かで区別するべきだと考えていた。キリストが出現する300年以上も前の時代において、これは革命的な思想だった。青少年の鋭い感性は、常に大人の経験を上回る。
もちろん学問だけでなく、武芸の鍛練も怠らなかった。王子は18歳のときに初陣を飾り、父王フィリッポスと共にアテネとテーベの連合軍と対決、これを打ち破ってギリシャを統一した。それまで通りポリスの自治は認められたが、軍を動かせるのは、マケドニア王フィリッポスだけとなった。
初陣ながらも、王子のあまりの強さに、兵士たちは彼を「王」と呼び、父王を「将軍」と呼んだと伝えられる。
「マケドニアはお前には小さすぎる。お前は、自分の力で王国を築くが良い」
父王は、彼にそう語ったという。
だが、ギリシャをまとめたからといって、まだ安心はできなかった。もともとギリシャの分裂の裏には、陰で内乱を煽るペルシャの存在があった。今日において、アメリカが中東などの統一を恐れ、対立を煽っている構図と一致している。
だが、2年後、黒幕ペルシャに出兵する準備を進めていた最中、父王は暗殺されてしまう。王子は、軍に推されて急遽王位を継承した。まだ20歳だった。世界史にその名を轟かすアレキサンダー大王が、歴史の表舞台に登場した瞬間だった。
大王は、王位を継ぐと同時に、自分の立場を脅かすような身内を皆殺しにした。先王の後妻と、その娘も例外ではなかった。あるいは、父王に続いて、自分まで暗殺されようとしている気配を察していたのかも知れない。
いずれにせよ、内側から出る敵こそが、最も恐ろしい。帝王たる者、国を守るために、時には肉親をも切り捨てなければならない。その非情さを、大王はすでに備えていた。
しかし、全ギリシャが彼の即位を認めたわけではなかった。この若い王をあなどったテーベは、反乱を開始する。その知らせを聞くや、大王はただちに自ら軍を率いて討伐に向かう。4百キロの道程をわずか13日という強行軍で駆け抜けて、テーベに出現。当時の常識では考えられない電光石火の移動に、テーベ軍は完全に意表を衝かれる。
テーベの兵士は全て殺され、女子どもは命こそ奪われなかったものの、全て奴隷に売られた。そこまでやるのは、やりすぎかも知れないが、他のポリスも反乱の隙を狙っている以上、ここで中途半端な姿勢を見せるわけにはいかなかった。
大王は、先王フィリッポスのファランクスに、さらなる改良を加えている。
ファランクスには、前方の敵には強いが、側面に回り込まれると弱いという欠点があった。そこで、身軽な歩兵と騎兵に方陣の側面を守らせ、飛び道具を使う部隊に先陣を切らせた。大王自身、常に騎兵隊の先頭に立って突撃し、自ら命を懸けて敵と切り結んだ。一兵士と変わらぬ血と汗を流す大王を、部下たちは敬愛した。
「私は、ペルシャを倒すだけでは終わらない。世界中の人間を、ひとつの家族のようにまとめてやる!」
壮大なロマンを胸に、若き大王の遠征が開始された。だが、世界から見れば小さなギリシャの王に過ぎない彼にとって、その道は、死闘の連続だった。まずは、先王の悲願だった、超大国ペルシャとの決戦に挑む。このとき、大王はまだ23歳だった。
大王の率いる軍隊は、総勢4万に満たない。一方、ペルシャ軍は60万。20倍近くの戦力差があった。特に、海軍の実力差は歴然としていた。どう考えても無謀な挑戦だった。今でいえば、地方の中小企業が、国際的大企業のシェアを奪おうとするようなものであろう。事実、先陣はあっさり全滅している。
しかし、大王は壮大な理想を実現するためにも、退くわけにはいかなかった。負けるわけにはいかなかった。絶体絶命の危機を脱するため、まず大王自ら先頭に立って、60万の大軍に突撃。敵将と激しく切り結び、兜の飾りを切り落とされるほどの白兵戦を演じた。
その姿を見た兵士たちは奮い立った。闘いは、人数や物量ではなく、常に志気で決まる。一方、ペルシャ軍のダリウス王は、戦場に金銀財宝や豪華な家具、妻子まで引き連れていた。これでは、部下の志気が高まるはずがない。
見事な団結を見せる大王軍にペルシャ軍は分断され、遂に、若き大王は、奇跡の逆転大勝利を収めた。大王軍の犠牲者は、5百人に満たなかった。
大王は、降伏した敵には寛大だった。ダリウス王の母、妻、娘たちは戦場に置き去りにされ、捕虜の身となった。当時の常識として、どんな扱いを受けてもおかしくなかったが、大王は彼女たちにこれまで以上の待遇を与え、常に礼儀正しく接するよう、部下に命じた。
ダリウス王の母は、大王の高潔な人格に感激し、彼をこよなく敬愛した。後に大王が病死すると、彼女は悲しみのあまり死んでしまったという。大王に地位を追われたダリウス王でさえ、家族の保護を伝え聞くと、
「私の王座を継ぐべき人は、アレキサンダー大王の他にいない」
そう語って、大王を誉め讃えたという。
大王は、休むことなく追撃を加えた。ペルシャ海軍の要である地中海のポリス・ティルスは、沖合の小島に城壁を張り巡らせ、難攻不落を誇っていた。
陸からの攻撃では、届かない。船で近づけば、狙い撃ちされる。だが、若き大王は諦めなかった。理想の実現が己の使命なのだという信念が、大王を支えていた。
大王は、どう決断したか? なんと、島までの海を埋め立てて堤防を築き、陸続きにしようとした! もちろん、こんな戦法は前代未聞だった。「できるはずが無い」と、ティルス市民は大王をあざ笑った。
ところが、大王は本当に長い堤防を築き上げ、島を取り囲む城壁よりも更に高い矢倉を建て、弓矢や投石で攻撃した。思いも寄らない攻撃に、ティルス軍はあわてた。だが、まだ彼らの優位は動かない。船に火を付けて堤防に激突させるという荒技に出る。
負けずに、大王は堤防を伸ばし続ける。だが、ティルスの地の利はやはり動かしがたく、戦法は失敗に終わった。
それでも、大王は挫けない。
今度は、2隻の大型船を連結させ、その上に塔を建てて攻撃するという手に出る。
ティルスも負けてはいない。
鍵のついたロープで塔を引き倒そうとしたり、海中から錨を切断してくる潜水兵もいた。
文字通り、双方知恵を絞っての攻防だった。
そして、ついに城壁の一角が崩れた。
上陸さえすればこっちのもの。大苦戦の末、若き大王の元に凱歌が上がった。
最後まで降伏を拒んだこのポリスに対して、大王は婦女子を奴隷とし、残る全ての市民を処刑した。
続いて、高い丘の上にあるガザの要塞を攻めたときには、負けじと大王も丘を築き、その上に塔を建てて攻撃する。同時に、地下道を掘って城壁を陥没させた。この、想像を絶する「天地からの挟み撃ち」に、難攻不落を誇ったさしものガザも、若き大王の軍門に下る。
大王の戦法は、大軍にものをいわせた正面からの突撃が主流だった当時において、実にトリッキーなものばかりだった。数に恵まれない大王の軍には、そうするしか手がなかった。そこでは、古い考えに縛られない、若き大王の柔軟な発想が必要不可欠だったことは、間違いないだろう。
大王はエジプトに入った。エジプトは、これまでたびたびペルシャに反乱を鎮圧されていたため、大王を開放者として歓迎した。大王は、ここでアレキサンドリアを建設し、ペルシャにとどめを刺す機会を窺っていた。
そして25歳のとき、大王はいよいよ最後の決戦に挑む。
1年に及ぶ戦闘の末、ペルシャ軍は崩壊し、ダリウス王は逃亡の途中、部下に殺された。
こうして、古代オリエントに君臨した超大国ペルシャは、若き大王が立ち上がってから、わずか5年で消滅したのだった。世代交代は、いつの時代も電撃的に成される。
だが大王は、アジアをギリシャの配下に置こうとはしなかった。ペルシャ人を高官に登用し、3万人ものペルシャ人を軍に入れたり、ペルシャの儀式を取り入れたりした。さらに、1万人のギリシャ将兵とペルシャ女性との集団結婚式を挙げ、自らダリウス王の娘やアジア人のロクサネと結婚するなど、進んでアジアに溶け込もうと努力した。
あまりにも大王が現地人を重用するので、不満を持ったギリシャ人の部下から、2度も暗殺されかかったほどだった。それでも大王は、アジアとの融和を進め続けた。この件では、13人ものギリシャ人が処刑されている。
現在でもイスラム圏では、侵略者であるはずの大王を「英雄イスカンダル」と呼び、愛し続けている。敵でさえ味方に変えてしまう人徳。これが、大王の成功の秘密だった。
広大なペルシャを手に入れても、大王は満足しなかった。壮大な理想を実現するためには、まだまだ為すべきことが山ほどあった。大王の進軍は、留まるところを知らない。
世界は広い。いろいろなタイプの敵がいた。大王29歳、中央アジアのバクトリア・ソグディアナ軍との戦いでは、四方を断崖絶壁に囲まれた、山中の砦に直面する。弩も投石も届かない。
「この砦は、翼を持った兵士でない限り、近寄れないのだ!」
敵軍は砦の上から大王を見下ろし、あざ笑った。しかし、こんなことにめげる大王ではない。とある深夜、大王は3百人の隠密を放ち、岸壁を登らせる。翌朝、山頂から砦を見下ろす大勢の兵士たちに、ソグディアナ軍は慌てた。
「我が軍には、翼のある兵士がいるのだ!」
大王は高らかに叫んだ。敵軍は完全に戦意を失い、砦はほどなく占領された。
また、大王30歳のとき、インドのボルス王軍は、2百頭の象を戦車として挑んできた。
象の巨体には突撃も投石も歯が立たず、大苦戦する。
そのとき大王は、自ら斧を持って走りだし、象のアキレス腱を力任せに叩き切った。
この戦法で形成は逆転し、勝利を収めた。一戦一戦が、執念と創意工夫による、逆転のドラマだった。
大王は常勝無敗だった。しかし、崩壊は常に思わぬところから始まる。
大王は、幼少のころから愛読していた『イリアス』以外は、どんな豪華な財宝にも執着しなかった。勝利で得た膨大な財宝は、みな部下に分け与えた。ところが、大王のあまりの潔癖さのため、彼よりも部下のほうが贅沢に溺れ、遠征の目的を忘れていった。十分な財産を手に入れたのだから、これ以上危険を冒して進む必要はないと考えるようになった。理想を抱いてスタートした中小企業が、大企業になるにつれて保守化し、退廃していくように。
それに、肝心の兵士たちも、故郷に親や妻子を置いてきた身だった。始めこそ、ロマンあるいは見返りにつられて大王についてきた兵士たちも、長い進軍の疲れのため、これ以上、慣れない土地で戦い続ける気力は無くなっていた。
時代だったとはいえ、武力以外に理想を実現する手段を知らなかったことが、大王の最大の悲劇だった。
大王は、自分の心がもはや部下に届かないことを悟り、涙を呑んで引き返す。無敵だった大王軍は、自らの慢心の前に破れ去ったのだ。ここまで来て、大王と真に志を共にする者は、結局、一人もいないことが明らかになった。
しかも、残酷な運命は、孤独な大王にさらなる追い討ちをかけた。大王は帰路の途中で熱病にかかり、再びの進軍を夢見ながら、突如としてこの世を去る。わずか32歳の若さだった。
さらに、軍の4分の3が、水と食料の不足によって失われた。天は、これ以上の戦乱を望まなかった。大王の死後、帝国はあえなく分裂し、伝説の英雄アキレウスを目指した1人の若者の夢は、はかなく砂漠に消えていった。
しかし、歴史は、この大いなる夢に人生を懸け、燃え尽きた若者の死を、無駄にしなかった。
大王の遠征によって東西の文明が融合し、ヘレニズム文化が生まれた。その影響は、遠く日本にも及んでいる。
ちなみに、仏典に登場する「韋駄天」とは、実は大王のことなのだ。大王の電光石火の進軍が、人々に語り継がれていたのだった。
シーザーもナポレオンも、大王を目指して立ち上がった。
大王が世界の歴史に与え続ける影響は計り知れない。
アレキサンダー青年は、わずか10余年という短い間に、西はエジプトから東はインドにまでまたがる、空前の大帝国を築き上げた。もちろん、これだけ短い期間に、これだけ広大な領地を手に入れた例は、他に存在しない。空前絶後の超記録であろう。
彼は、歴史の黎明期において、若者の持つ無限の可能性を証明するために、生を受けたのかも知れない。
歴史には、光り輝き燃え尽きる流星のように、アレキサンダー帝国の栄光が刻まれている。
人生は短い。
青春はもっと短い。
けれどその短い青春に、どれだけの可能性が秘められているのか。
アレキサンダーは、時を超えて現代の若者に語りかける。
続きを読む
歴史を動かした若者たちによる、壮大な叙事詩は、まず、紀元をはるか400年もさかのぼる古代ギリシャより、筆を起こすことにしたい。
当時、ギリシャでは、超大国ペルシャに裏で煽られて、アテネとスパルタが主導権を奪い合い、ポリス(都市国家)間の争いが絶えなかった。
そんな戦国の世に、小ポリス・マケドニアの摂政として、わずか18歳のフィリッポス2世が就任した。
政治手腕を高く評価されて、フィリッポスはまもなく正式に王位に就いた。
23歳の若き王は、ギリシャの統一を志し、農民による長槍歩兵方陣、すなわち「ファランクス」を創設し、常備軍とする。
ファランクスとは、兵士に6メートルもの長槍を持たせた長方形の隊列で、盾で矢を防ぎながら、正面から敵に突撃する。これは当時のギリシャで無敵を誇り、マケドニアはたちまち有力なポリスとなる。
同時代の人々は、
「ヨーロッパは、かつてこれほど強大な人物を知らなかった」
若きフィリッポスをそう称え、恐れたという。
フィリッポスが26歳のとき、1人の王子が生まれた。王子の名は、アレクサンドロス3世。日本では、アレキサンダーの方がなじみがあるかも知れない。マケドニア語で「敵を撃退する者」という意味の名前だった。
彼の母親は、叙事詩『イリアス』に出てくる英雄アキレウスの家系から出ていると、先祖から伝えられていた。父王が他の女性を寵愛したため、母親は王子を溺愛した。王子は自然に、母親の語るアキレウスに憧れる少年に育っていった。
王子は、13歳からというから今でいうと中学時代、大哲学者であり、「全ての学問の祖」として知られるアリストテレスを家庭教師に迎え入れ、教えを受ける。アリストテレスは当時まだ40歳そこそこだったが、プラトンの最も優秀な弟子としてその名を知られていた。父王フィリッポスとは、旧知の間柄だった。
アリストテレスは、3年間に渡って、王子につきっきりで哲学、政治学、自然科学、それに詩や劇を教えた。無敵の将軍だった父王と、伝説の英雄を語る母の存在に加え、多感な時期に王子がこの大哲学者に受けた影響は、多大なものだったろう。
アリストテレスは確かに優れた家庭教師だったが、王子には、たったひとつだけ納得できない点があった。それは、アリストテレスがギリシャ人以外の民族を全て野蛮人と考え、他民族を奴隷とすることを肯定していた点だった。
王子は、民族にかかわらず、人間は善人か悪人かで区別するべきだと考えていた。キリストが出現する300年以上も前の時代において、これは革命的な思想だった。青少年の鋭い感性は、常に大人の経験を上回る。
もちろん学問だけでなく、武芸の鍛練も怠らなかった。王子は18歳のときに初陣を飾り、父王フィリッポスと共にアテネとテーベの連合軍と対決、これを打ち破ってギリシャを統一した。それまで通りポリスの自治は認められたが、軍を動かせるのは、マケドニア王フィリッポスだけとなった。
初陣ながらも、王子のあまりの強さに、兵士たちは彼を「王」と呼び、父王を「将軍」と呼んだと伝えられる。
「マケドニアはお前には小さすぎる。お前は、自分の力で王国を築くが良い」
父王は、彼にそう語ったという。
だが、ギリシャをまとめたからといって、まだ安心はできなかった。もともとギリシャの分裂の裏には、陰で内乱を煽るペルシャの存在があった。今日において、アメリカが中東などの統一を恐れ、対立を煽っている構図と一致している。
だが、2年後、黒幕ペルシャに出兵する準備を進めていた最中、父王は暗殺されてしまう。王子は、軍に推されて急遽王位を継承した。まだ20歳だった。世界史にその名を轟かすアレキサンダー大王が、歴史の表舞台に登場した瞬間だった。
大王は、王位を継ぐと同時に、自分の立場を脅かすような身内を皆殺しにした。先王の後妻と、その娘も例外ではなかった。あるいは、父王に続いて、自分まで暗殺されようとしている気配を察していたのかも知れない。
いずれにせよ、内側から出る敵こそが、最も恐ろしい。帝王たる者、国を守るために、時には肉親をも切り捨てなければならない。その非情さを、大王はすでに備えていた。
しかし、全ギリシャが彼の即位を認めたわけではなかった。この若い王をあなどったテーベは、反乱を開始する。その知らせを聞くや、大王はただちに自ら軍を率いて討伐に向かう。4百キロの道程をわずか13日という強行軍で駆け抜けて、テーベに出現。当時の常識では考えられない電光石火の移動に、テーベ軍は完全に意表を衝かれる。
テーベの兵士は全て殺され、女子どもは命こそ奪われなかったものの、全て奴隷に売られた。そこまでやるのは、やりすぎかも知れないが、他のポリスも反乱の隙を狙っている以上、ここで中途半端な姿勢を見せるわけにはいかなかった。
大王は、先王フィリッポスのファランクスに、さらなる改良を加えている。
ファランクスには、前方の敵には強いが、側面に回り込まれると弱いという欠点があった。そこで、身軽な歩兵と騎兵に方陣の側面を守らせ、飛び道具を使う部隊に先陣を切らせた。大王自身、常に騎兵隊の先頭に立って突撃し、自ら命を懸けて敵と切り結んだ。一兵士と変わらぬ血と汗を流す大王を、部下たちは敬愛した。
「私は、ペルシャを倒すだけでは終わらない。世界中の人間を、ひとつの家族のようにまとめてやる!」
壮大なロマンを胸に、若き大王の遠征が開始された。だが、世界から見れば小さなギリシャの王に過ぎない彼にとって、その道は、死闘の連続だった。まずは、先王の悲願だった、超大国ペルシャとの決戦に挑む。このとき、大王はまだ23歳だった。
大王の率いる軍隊は、総勢4万に満たない。一方、ペルシャ軍は60万。20倍近くの戦力差があった。特に、海軍の実力差は歴然としていた。どう考えても無謀な挑戦だった。今でいえば、地方の中小企業が、国際的大企業のシェアを奪おうとするようなものであろう。事実、先陣はあっさり全滅している。
しかし、大王は壮大な理想を実現するためにも、退くわけにはいかなかった。負けるわけにはいかなかった。絶体絶命の危機を脱するため、まず大王自ら先頭に立って、60万の大軍に突撃。敵将と激しく切り結び、兜の飾りを切り落とされるほどの白兵戦を演じた。
その姿を見た兵士たちは奮い立った。闘いは、人数や物量ではなく、常に志気で決まる。一方、ペルシャ軍のダリウス王は、戦場に金銀財宝や豪華な家具、妻子まで引き連れていた。これでは、部下の志気が高まるはずがない。
見事な団結を見せる大王軍にペルシャ軍は分断され、遂に、若き大王は、奇跡の逆転大勝利を収めた。大王軍の犠牲者は、5百人に満たなかった。
大王は、降伏した敵には寛大だった。ダリウス王の母、妻、娘たちは戦場に置き去りにされ、捕虜の身となった。当時の常識として、どんな扱いを受けてもおかしくなかったが、大王は彼女たちにこれまで以上の待遇を与え、常に礼儀正しく接するよう、部下に命じた。
ダリウス王の母は、大王の高潔な人格に感激し、彼をこよなく敬愛した。後に大王が病死すると、彼女は悲しみのあまり死んでしまったという。大王に地位を追われたダリウス王でさえ、家族の保護を伝え聞くと、
「私の王座を継ぐべき人は、アレキサンダー大王の他にいない」
そう語って、大王を誉め讃えたという。
大王は、休むことなく追撃を加えた。ペルシャ海軍の要である地中海のポリス・ティルスは、沖合の小島に城壁を張り巡らせ、難攻不落を誇っていた。
陸からの攻撃では、届かない。船で近づけば、狙い撃ちされる。だが、若き大王は諦めなかった。理想の実現が己の使命なのだという信念が、大王を支えていた。
大王は、どう決断したか? なんと、島までの海を埋め立てて堤防を築き、陸続きにしようとした! もちろん、こんな戦法は前代未聞だった。「できるはずが無い」と、ティルス市民は大王をあざ笑った。
ところが、大王は本当に長い堤防を築き上げ、島を取り囲む城壁よりも更に高い矢倉を建て、弓矢や投石で攻撃した。思いも寄らない攻撃に、ティルス軍はあわてた。だが、まだ彼らの優位は動かない。船に火を付けて堤防に激突させるという荒技に出る。
負けずに、大王は堤防を伸ばし続ける。だが、ティルスの地の利はやはり動かしがたく、戦法は失敗に終わった。
それでも、大王は挫けない。
今度は、2隻の大型船を連結させ、その上に塔を建てて攻撃するという手に出る。
ティルスも負けてはいない。
鍵のついたロープで塔を引き倒そうとしたり、海中から錨を切断してくる潜水兵もいた。
文字通り、双方知恵を絞っての攻防だった。
そして、ついに城壁の一角が崩れた。
上陸さえすればこっちのもの。大苦戦の末、若き大王の元に凱歌が上がった。
最後まで降伏を拒んだこのポリスに対して、大王は婦女子を奴隷とし、残る全ての市民を処刑した。
続いて、高い丘の上にあるガザの要塞を攻めたときには、負けじと大王も丘を築き、その上に塔を建てて攻撃する。同時に、地下道を掘って城壁を陥没させた。この、想像を絶する「天地からの挟み撃ち」に、難攻不落を誇ったさしものガザも、若き大王の軍門に下る。
大王の戦法は、大軍にものをいわせた正面からの突撃が主流だった当時において、実にトリッキーなものばかりだった。数に恵まれない大王の軍には、そうするしか手がなかった。そこでは、古い考えに縛られない、若き大王の柔軟な発想が必要不可欠だったことは、間違いないだろう。
大王はエジプトに入った。エジプトは、これまでたびたびペルシャに反乱を鎮圧されていたため、大王を開放者として歓迎した。大王は、ここでアレキサンドリアを建設し、ペルシャにとどめを刺す機会を窺っていた。
そして25歳のとき、大王はいよいよ最後の決戦に挑む。
1年に及ぶ戦闘の末、ペルシャ軍は崩壊し、ダリウス王は逃亡の途中、部下に殺された。
こうして、古代オリエントに君臨した超大国ペルシャは、若き大王が立ち上がってから、わずか5年で消滅したのだった。世代交代は、いつの時代も電撃的に成される。
だが大王は、アジアをギリシャの配下に置こうとはしなかった。ペルシャ人を高官に登用し、3万人ものペルシャ人を軍に入れたり、ペルシャの儀式を取り入れたりした。さらに、1万人のギリシャ将兵とペルシャ女性との集団結婚式を挙げ、自らダリウス王の娘やアジア人のロクサネと結婚するなど、進んでアジアに溶け込もうと努力した。
あまりにも大王が現地人を重用するので、不満を持ったギリシャ人の部下から、2度も暗殺されかかったほどだった。それでも大王は、アジアとの融和を進め続けた。この件では、13人ものギリシャ人が処刑されている。
現在でもイスラム圏では、侵略者であるはずの大王を「英雄イスカンダル」と呼び、愛し続けている。敵でさえ味方に変えてしまう人徳。これが、大王の成功の秘密だった。
広大なペルシャを手に入れても、大王は満足しなかった。壮大な理想を実現するためには、まだまだ為すべきことが山ほどあった。大王の進軍は、留まるところを知らない。
世界は広い。いろいろなタイプの敵がいた。大王29歳、中央アジアのバクトリア・ソグディアナ軍との戦いでは、四方を断崖絶壁に囲まれた、山中の砦に直面する。弩も投石も届かない。
「この砦は、翼を持った兵士でない限り、近寄れないのだ!」
敵軍は砦の上から大王を見下ろし、あざ笑った。しかし、こんなことにめげる大王ではない。とある深夜、大王は3百人の隠密を放ち、岸壁を登らせる。翌朝、山頂から砦を見下ろす大勢の兵士たちに、ソグディアナ軍は慌てた。
「我が軍には、翼のある兵士がいるのだ!」
大王は高らかに叫んだ。敵軍は完全に戦意を失い、砦はほどなく占領された。
また、大王30歳のとき、インドのボルス王軍は、2百頭の象を戦車として挑んできた。
象の巨体には突撃も投石も歯が立たず、大苦戦する。
そのとき大王は、自ら斧を持って走りだし、象のアキレス腱を力任せに叩き切った。
この戦法で形成は逆転し、勝利を収めた。一戦一戦が、執念と創意工夫による、逆転のドラマだった。
大王は常勝無敗だった。しかし、崩壊は常に思わぬところから始まる。
大王は、幼少のころから愛読していた『イリアス』以外は、どんな豪華な財宝にも執着しなかった。勝利で得た膨大な財宝は、みな部下に分け与えた。ところが、大王のあまりの潔癖さのため、彼よりも部下のほうが贅沢に溺れ、遠征の目的を忘れていった。十分な財産を手に入れたのだから、これ以上危険を冒して進む必要はないと考えるようになった。理想を抱いてスタートした中小企業が、大企業になるにつれて保守化し、退廃していくように。
それに、肝心の兵士たちも、故郷に親や妻子を置いてきた身だった。始めこそ、ロマンあるいは見返りにつられて大王についてきた兵士たちも、長い進軍の疲れのため、これ以上、慣れない土地で戦い続ける気力は無くなっていた。
時代だったとはいえ、武力以外に理想を実現する手段を知らなかったことが、大王の最大の悲劇だった。
大王は、自分の心がもはや部下に届かないことを悟り、涙を呑んで引き返す。無敵だった大王軍は、自らの慢心の前に破れ去ったのだ。ここまで来て、大王と真に志を共にする者は、結局、一人もいないことが明らかになった。
しかも、残酷な運命は、孤独な大王にさらなる追い討ちをかけた。大王は帰路の途中で熱病にかかり、再びの進軍を夢見ながら、突如としてこの世を去る。わずか32歳の若さだった。
さらに、軍の4分の3が、水と食料の不足によって失われた。天は、これ以上の戦乱を望まなかった。大王の死後、帝国はあえなく分裂し、伝説の英雄アキレウスを目指した1人の若者の夢は、はかなく砂漠に消えていった。
しかし、歴史は、この大いなる夢に人生を懸け、燃え尽きた若者の死を、無駄にしなかった。
大王の遠征によって東西の文明が融合し、ヘレニズム文化が生まれた。その影響は、遠く日本にも及んでいる。
ちなみに、仏典に登場する「韋駄天」とは、実は大王のことなのだ。大王の電光石火の進軍が、人々に語り継がれていたのだった。
シーザーもナポレオンも、大王を目指して立ち上がった。
大王が世界の歴史に与え続ける影響は計り知れない。
アレキサンダー青年は、わずか10余年という短い間に、西はエジプトから東はインドにまでまたがる、空前の大帝国を築き上げた。もちろん、これだけ短い期間に、これだけ広大な領地を手に入れた例は、他に存在しない。空前絶後の超記録であろう。
彼は、歴史の黎明期において、若者の持つ無限の可能性を証明するために、生を受けたのかも知れない。
 | アレクサンドロス変相 ―古代から中世イスラームへ―山中 由里子名古屋大学出版会このアイテムの詳細を見る |
 | アレキサンダー プレミアム・エディション [DVD]松竹このアイテムの詳細を見る |
歴史には、光り輝き燃え尽きる流星のように、アレキサンダー帝国の栄光が刻まれている。
人生は短い。
青春はもっと短い。
けれどその短い青春に、どれだけの可能性が秘められているのか。
アレキサンダーは、時を超えて現代の若者に語りかける。
続きを読む












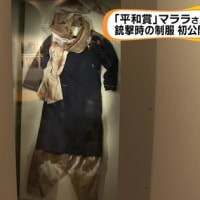







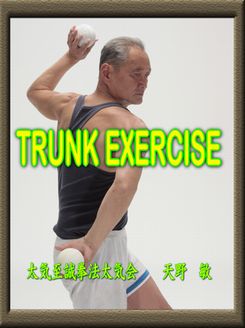















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます