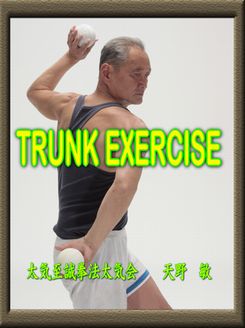空手は約600年前に「手」として沖縄で成立し、その後、大陸との交流や武器携帯禁止令などの歴史の中で、独自の発展を遂げてきた。
今日こそ数百の流派に分かれている空手だが、もともとは剛直な動きの「那覇手」と、柔曲な「首里手」のスタイルに大別されているに過ぎなかった。
那覇手を代表する型は、前後の動きを主とするサンチン、首里手の代表型は、横の動きを主とするナイファンチである。
◆本部御殿手◆
手の中でも、琉球王家の長男にのみ受け継がれたという秘伝の手がある。それが本部御殿手(もとぶうどんでぃ)だ。剛直な打撃技のほかに「取手」と呼ばれる立ち関節技も含まれる。
今日にこの秘技を受け継いだ達人として、先日惜しくも亡くなられた、12代宗家上原清吉範士が知られている。若いころには、東南アジアの戦場でこの技を駆使し、命拾いしたという。
83歳当時、第11回日本古武道演武大会で、範士の演武中の心拍数が計られたことがある。結果は、50歳代の体力だった。
御殿手では、徒手だけでなく、棒、杖、カイ、サイ、トンファー、ヌンチャク、石打ち、山刀、蛮刀、短刀、薙刀、槍、二丁剣、二丁鎌、手甲、ティンベー、エイク、さらにはホウキなど、身近にあるあらゆる武具を使いこなす。稽古に型や構えはなく、多人数相手の乱取りや、二刀のさばきがメインになる。
その奥義は「歩く」こと、頂点は「舞い」にあるという。御殿手の歩法は、膝を曲げず、上下左右に体をぶらさず、水平等速直線運動で前進することに特徴がある。自然界の水平移動は、重力の影響でたいていは変速曲線運動になるので、経験したことのない間合いの詰め方に、受けは対応できない。
これはまさに那覇手の原理を突き詰めたものだが、同時に首里手的な要素が高度に融合している。まさに、沖縄空手のエッセンスを凝縮した武芸であろう。
◆上地流◆
沖縄の古い流派である上地流では、貫手が主な武器となる。門下生たちは、貫手を徹底的に鍛え上げる。その鍛え方は尋常ではなく、爪先でバットを折ってしまうほどだ。
上地流ではフルコンタクト組手を行なっているが、ここで貫手は使えないという。しかし、それも無理のないことで、貫手は本来、接近戦で目や喉を攻めるときに効果を発揮する技術なのだ。決して無駄な鍛練ではない。
◆大日本武徳会武道専門学校◆
本土に渡った手は「空手」と改称されると同時に、試し割りで強烈なインパクトを与え、瞬く間に普及する。やがて、空手を教える公式の教育機関も成立した。それが、大日本武徳会武道専門学校である。
武専では主に柔剣道が修業されたが、空手でも全国各地の名人・達人が招かれ、大和男児を指導した。当時、修業には最も恵まれた環境だったといえるだろう。
砂袋を突き、蹴る有名な部位鍛練も、武専で生まれた。それは拳頭が血塗れになり、骨が見えても続けられた。しかし、そのままでは細菌が傷口から感染してしまうので、塩を擦り込む。あまりにも過酷な訓練に、発狂する者が続出したという。武専出身の名人としては、垂木を正拳で斬る中村日出夫が有名。
◆交歓稽古◆
終戦直後には、まだ大会やルールが確立されておらず、交歓稽古といわれる各流派の対抗試合が盛んに行なわれていた。その組み手には、各流派の持ち味が全面に押し出されていたという。
剛柔流には相手の足を踏む技があるのだが、これを下手に抜こうとして、親指の骨が剥き出しになってしまうことも多かったという。
「伝統派の空手が実戦に通用しない」などとは、とんでもない間違いだ。少なくとも、公式戦ルールが確立される以前の空手は、我々のイメージ通りの荒々しさを保っていた。
◆極真会館城西支部◆
スポーツ化を嘆く声も多い極真だが、その中でも「チャンピオン製造工場」の異名をとる城西支部は、独特の武風を漂わせている。
城西支部では、相手の攻撃を完璧にカットすることを念頭に、技術が磨かれている。その上で、ウエイトトレーニングによってパワーアップし、フットワークで相手を翻弄、下段蹴りの嵐で相手を破壊する。
また、黒帯クラスはグローブを着用しての顔面突きもトレーニングしている。
公式戦の攻防は、あくまで表の顔。極真は、今でも実戦空手であり続けている。
◆新国際空手道連盟芦原会館◆
極真は多くのフルコンタクト空手流派を輩出してきたが、その中でも最も異質で、しかも大山道場時代の実戦体質を色濃く残しているのが、芦原会館だろう。
芦原空手の特色は、サバキと呼ばれるテクニックにある。これは、相手の前進力と遠心力を利用して、頭を下げさせサイドをとるという動きで、非力な者でも安全に、打つも投げるも極めるも自在のポジションを確保することができる。
芦原会館出身の最も有名な空手家が、大道塾とパンクラスで頂点を極め、K-1やPRIDEでも活躍しているセーム・シュルトだ。実はK-1自体が、もともと芦原英幸初代館長の発案だったという。
◆心道流空手道心道会◆
座波仁吉最高師範が、沖縄古伝の空手を残そうと、剛柔流から独立して興したのが心道会である。
ここでは、組み手や巻藁突きは一切やらず、ただ、
サンチン
ナイファンチ
パッサイ
クーサンクー
セイサン
この古伝の五つの型を稽古するだけ。しかし、その驚くべき成果は、宇城憲治師範によって公開されている。組んでも寝ても自在で、取りは体の力が抜けてしまう。触れずして相手を止めることさえできるという。
◆士道館◆
極真系流派の中でも、士道館は面白い方針で実戦性を追求している。
その競技においては、けんせいの意味で顔面への掌低突きが認められ、油断を戒めるという意味で、投げや極めも反則にならない。やはり、大山道場時代の息吹を今日に伝える流派であろう。
さらに、士道館においては、空手修業の一環として、ボクシングやキックへのチャレンジも推奨している。すなわち、3つの異なる打撃系格闘競技で頂点を極めることにより、最強を証明しようというのだ。
◆硬式空手◆
互いに防具をつけてのフルコンタクトルールは、競技空手の中では、最も古い伝統を持っている。1920年代には、東大空手部員などが中心となって、すでに防具が試作されている。
空手における防具の革命が、スーパーセーフの登場だった。これにより、グローブを着用しなくても、拳サポーターのみで上段が突けるようになった。そればかりか、脳へのダメージも著しく軽減された。
セーフを開発した拳行会の久高正之は、硬式ルールを提唱する。これは、スーパーセーフと胴プロテクター、拳サポーターを着用した上で、自由に打ち合うというもので、KO決着も認めているが、実際にはほとんどポイントで決着がつく。
とはいえ、安全性を確保した上で、実戦性を追求している点で、硬式空手は最も理想的なルールのひとつといえよう。