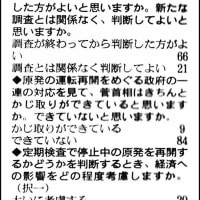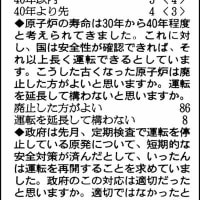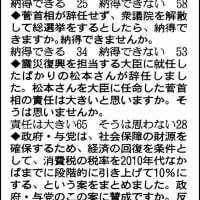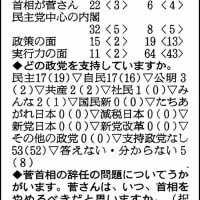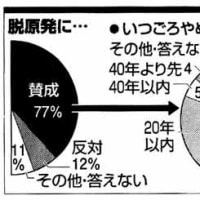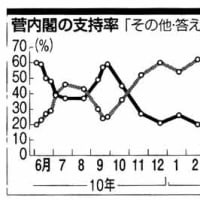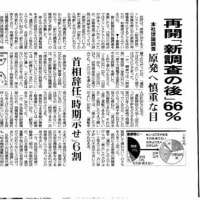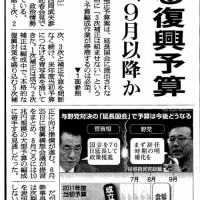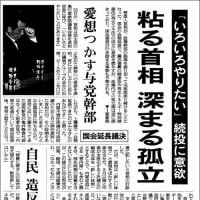11年7月18日 月曜日 07/18・各社社説
今日の社説には載らないが今朝未明になでしこジャパンがアメリカをPk戦で三対に二で下し優勝したとテレビが報道していた。
アメリカとは無理ではないかと思っていたのでうれしくてし仕方がない。でも日本のアスリートは大和男の子より撫子の方が強いということは何をさしているのだろうか然も今回は10センチ以上の体力の格差をはね除けてだからだ。
兎に角ナデシコジャパンバンザーイバンザーイ
朝日新聞(社説)
その1
特捜検察改革―社会の変化に遅れるな (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
郵便不正事件で地に落ちた信頼をいかに回復するか。最高検がこのほど検察改革の現状と今後の課題を明らかにした。
捜査に対する批判や苦情を受け付ける監察部門を設け、外部から起用する「参与」に結果を報告し、助言を求めることなどが盛り込まれた。
「共犯者はこう話している」と、うそを言って供述を引き出す尋問、食事やトイレへの配慮を欠く取り調べ、脅迫、証拠の隠匿――。監察部門に届けるべき行いとして挙げられたものを見るとため息が出る。
その2
アフガン和平―政治対話を進めよう
外国軍が撤退したからといって戦闘は終わるわけではない。紛争当事者の間の和解がなければ和平実現はおぼつかない。
アフガニスタンから米軍を中心とする外国軍の撤退が始まった。2014年末までにアフガン側に治安権限を譲り、部隊の駐留を終える予定だ。
時を合わせるように、アフガンの反政府武装勢力タリバーンと米国、カルザイ政権との間で細々ながら、和解をめざす政治対話が始まった。
タリバーンとの政治対話を求める提言をシンクタンクでまとめたピカリング元米国務次官が来日し、松本剛明外相に和解努力への協力を求めた。
10年越しの戦争は大きな転機に差しかかっている。日本はしっかり対話の進展を見守り、和平実現を後押しすべきだ。
読売新聞(社説)
福島原発事故 汚染水処理が「次」へのカギ (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
東京電力福島第一原子力発電所の事故収束作業で、政府と東電は、初期対応に当たるステップ1として、17日を期限としてきた「原子炉の安定冷却」などの目標をほぼ達成できたとの見解をまとめた。
危機的な状況は、とりあえず回避できた、ということだろう。
政府は、住民に自主的な避難を求めてきた福島県内の「緊急時避難準備区域」についても、一部解除を検討している。
原発被災者の半数近い約4万人が、避難準備区域から区域外へと避難している。避難範囲の縮小は住民にとって朗報となろう。
選挙制度改革 違憲状態放置は国会の怠慢だ (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
与野党は、「1票の格差」の是正に向けて、選挙制度改革を急がなければならない。
議員1人当たりの有権者数の格差が最大2・30倍だった2009年衆院選を、最高裁が「違憲状態」と断じ、速やかな是正を国会に迫ってから4か月近くになる。だが、衆院の論議は足踏みしている。
民主党は先日、小選挙区を「21増21減」する岡田幹事長らの提案を基に論議に入ったが、早くも決定を次の執行部に先送りした。
提案は、過疎県に配慮するための「1人別枠方式」の廃止を柱としている。別枠方式は、かつての中選挙区制度を現行制度に改める際の激変緩和措置だ。
小選挙区定数300を都道府県に1ずつ配分し、残りを人口比で割り振る。これを廃止すると、格差は1・6倍程度に収まる。
毎日新聞(社説)
節電と暮らし いっそ生活を楽しもう (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
たしかに電力不足は企業にとって大変だ。一般家庭でも暑い夏をどう乗り切るか、熱中症は大丈夫かと心配になる。しかし、マイナス面ばかり考えるとますます不安やいら立ちが募る。節電しなければならないからこそできることも考えたい。
OECD(経済協力開発機構)が5月に発表した「より良い暮らし指標」では教育、収入、安全、雇用などの分野で日本は参加34カ国の上位を占めたが、生活に満足を感じている人は40%に過ぎず、34カ国の平均(59%)をかなり下回った。客観的には暮らしやすいはずなのに、日本人が幸せを感じないのはなぜか。指数の中で日本が極端に低いのは「ワーク・ライフ・バランス」である。毎日の生活のうち日本人が食事や睡眠、家族や友人と過ごしたり趣味に使う時間はメキシコの次に少ない。
電子書籍 出版文化を守りたい (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
パソコンや専用端末で、インターネットから情報をダウンロードして読む電子書籍の市場が広がっている。しばらくは紙の本の優位が続くとしても、日本の出版界は過渡期を迎えつつある。自由な表現や言論を支える出版文化は民主主義社会の生命線だ。電子化の進行がマイナスに働かないようにしたい。
メディア関連の調査をしている「インプレスR&D」によると、2010年度の電子書籍全体の販売額は約650億円。前年度から約13%増えた。15年度には約2000億円になると予測している
産経新聞(社説)
放射線」授業復活 知らないから不安になる{/arrow_r/}(全文はここからお入り下さい)
目に見えない放射能や放射線を多くの国民が不安がっているのは、基礎的な知識がないことが大きい。昭和56年に実施された学習指導要領で中学で扱っていた放射線の項目が削られたためだ。
ゆとり教育の影響で、この30年間、放射線に関する基礎知識が教えられてこなかった。来春からの中学理科では、放射線について学ぶ授業が復活する。東京電力福島第1原発事故によって原子力への不安が広がるなか、学校教育で正しい知識を学習する意味は極めて大きい。
放射線医学の専門家からも「放射線への理解不足が不安を募らせている」との指摘がある。
海の日 守りなくして繁栄はなし (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
巨大な津波に襲われた東日本大震災の被災地などを精力的に慰問した天皇、皇后両陛下が先月8日、東京都江東区の東京海洋大学に展示されている国の重要文化財「明治丸」を見学された。
明治9(1876)年、明治天皇が東北・北海道巡幸の帰りに明治丸に乗り、三陸沖を経て横浜港に到着したのが7月20日だった。後にこの日が「海の記念日」とされ、平成7年には「海の日」として祝日に制定されるに至ったが、今は法改正によって7月の第3月曜日となっている。
日経新聞(社説)
教育を変えるとき)社会に出た人が学び続ける強い国に (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
地域特産の農産物を使って付加価値の高い食品加工業や外食事業を起こすにはどうしたらいいか――。
学校法人青山学院と大学教員で設立した人材開発会社が「農商工連携」のリーダーを育てようと5月から始めた講座は、30人の定員に対し社会人からの応募が2倍に達した
東日本大震災の影響で仕事が減り、新規事業への進出に迫られた企業の社員や中小企業経営者の参加もある。自ら学び、大震災後の苦境を乗り越えようとしている人たちだ
大学はもっと門戸開け
企業は自己啓発支援を
東京新聞(社説)
中国外交を懸念する 拡大する「核心利益」 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)
中国は主権や領土にかかわる問題を「核心的利益」として外国に妥協しない姿勢を強めた。その範囲も野放図に広げ、周辺諸国の警戒を招いている。
「国家の主権と安全、発展は外交の最優先任務だ」「国家の核心的利益にかかわる問題は絶対に、いかなる妥協も譲歩もしない」
中国外務省の馬朝旭報道局長が最近、党機関紙に発表した文章の一節。軍やマスコミばかりか外交官にも勇ましい発言が目立つようになった。今月下旬、インドネシアで開かれる東南アジア諸国連合(ASEAN)などの外相会議では中国への対応が焦点になる。
◆2009年の大転換
◆台湾から南シナ海へ
◆抑えきかない下克上
今日の社説には載らないが今朝未明になでしこジャパンがアメリカをPk戦で三対に二で下し優勝したとテレビが報道していた。
アメリカとは無理ではないかと思っていたのでうれしくてし仕方がない。でも日本のアスリートは大和男の子より撫子の方が強いということは何をさしているのだろうか然も今回は10センチ以上の体力の格差をはね除けてだからだ。
兎に角ナデシコジャパンバンザーイバンザーイ
朝日新聞(社説)
その1
特捜検察改革―社会の変化に遅れるな
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)郵便不正事件で地に落ちた信頼をいかに回復するか。最高検がこのほど検察改革の現状と今後の課題を明らかにした。
捜査に対する批判や苦情を受け付ける監察部門を設け、外部から起用する「参与」に結果を報告し、助言を求めることなどが盛り込まれた。
「共犯者はこう話している」と、うそを言って供述を引き出す尋問、食事やトイレへの配慮を欠く取り調べ、脅迫、証拠の隠匿――。監察部門に届けるべき行いとして挙げられたものを見るとため息が出る。
その2
アフガン和平―政治対話を進めよう
外国軍が撤退したからといって戦闘は終わるわけではない。紛争当事者の間の和解がなければ和平実現はおぼつかない。
アフガニスタンから米軍を中心とする外国軍の撤退が始まった。2014年末までにアフガン側に治安権限を譲り、部隊の駐留を終える予定だ。
時を合わせるように、アフガンの反政府武装勢力タリバーンと米国、カルザイ政権との間で細々ながら、和解をめざす政治対話が始まった。
タリバーンとの政治対話を求める提言をシンクタンクでまとめたピカリング元米国務次官が来日し、松本剛明外相に和解努力への協力を求めた。
10年越しの戦争は大きな転機に差しかかっている。日本はしっかり対話の進展を見守り、和平実現を後押しすべきだ。
読売新聞(社説)
福島原発事故 汚染水処理が「次」へのカギ
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)東京電力福島第一原子力発電所の事故収束作業で、政府と東電は、初期対応に当たるステップ1として、17日を期限としてきた「原子炉の安定冷却」などの目標をほぼ達成できたとの見解をまとめた。
危機的な状況は、とりあえず回避できた、ということだろう。
政府は、住民に自主的な避難を求めてきた福島県内の「緊急時避難準備区域」についても、一部解除を検討している。
原発被災者の半数近い約4万人が、避難準備区域から区域外へと避難している。避難範囲の縮小は住民にとって朗報となろう。
選挙制度改革 違憲状態放置は国会の怠慢だ
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)与野党は、「1票の格差」の是正に向けて、選挙制度改革を急がなければならない。
議員1人当たりの有権者数の格差が最大2・30倍だった2009年衆院選を、最高裁が「違憲状態」と断じ、速やかな是正を国会に迫ってから4か月近くになる。だが、衆院の論議は足踏みしている。
民主党は先日、小選挙区を「21増21減」する岡田幹事長らの提案を基に論議に入ったが、早くも決定を次の執行部に先送りした。
提案は、過疎県に配慮するための「1人別枠方式」の廃止を柱としている。別枠方式は、かつての中選挙区制度を現行制度に改める際の激変緩和措置だ。
小選挙区定数300を都道府県に1ずつ配分し、残りを人口比で割り振る。これを廃止すると、格差は1・6倍程度に収まる。
毎日新聞(社説)
節電と暮らし いっそ生活を楽しもう
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)たしかに電力不足は企業にとって大変だ。一般家庭でも暑い夏をどう乗り切るか、熱中症は大丈夫かと心配になる。しかし、マイナス面ばかり考えるとますます不安やいら立ちが募る。節電しなければならないからこそできることも考えたい。
OECD(経済協力開発機構)が5月に発表した「より良い暮らし指標」では教育、収入、安全、雇用などの分野で日本は参加34カ国の上位を占めたが、生活に満足を感じている人は40%に過ぎず、34カ国の平均(59%)をかなり下回った。客観的には暮らしやすいはずなのに、日本人が幸せを感じないのはなぜか。指数の中で日本が極端に低いのは「ワーク・ライフ・バランス」である。毎日の生活のうち日本人が食事や睡眠、家族や友人と過ごしたり趣味に使う時間はメキシコの次に少ない。
電子書籍 出版文化を守りたい
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)パソコンや専用端末で、インターネットから情報をダウンロードして読む電子書籍の市場が広がっている。しばらくは紙の本の優位が続くとしても、日本の出版界は過渡期を迎えつつある。自由な表現や言論を支える出版文化は民主主義社会の生命線だ。電子化の進行がマイナスに働かないようにしたい。
メディア関連の調査をしている「インプレスR&D」によると、2010年度の電子書籍全体の販売額は約650億円。前年度から約13%増えた。15年度には約2000億円になると予測している
産経新聞(社説)
放射線」授業復活 知らないから不安になる{/arrow_r/}(全文はここからお入り下さい)
目に見えない放射能や放射線を多くの国民が不安がっているのは、基礎的な知識がないことが大きい。昭和56年に実施された学習指導要領で中学で扱っていた放射線の項目が削られたためだ。
ゆとり教育の影響で、この30年間、放射線に関する基礎知識が教えられてこなかった。来春からの中学理科では、放射線について学ぶ授業が復活する。東京電力福島第1原発事故によって原子力への不安が広がるなか、学校教育で正しい知識を学習する意味は極めて大きい。
放射線医学の専門家からも「放射線への理解不足が不安を募らせている」との指摘がある。
海の日 守りなくして繁栄はなし
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)巨大な津波に襲われた東日本大震災の被災地などを精力的に慰問した天皇、皇后両陛下が先月8日、東京都江東区の東京海洋大学に展示されている国の重要文化財「明治丸」を見学された。
明治9(1876)年、明治天皇が東北・北海道巡幸の帰りに明治丸に乗り、三陸沖を経て横浜港に到着したのが7月20日だった。後にこの日が「海の記念日」とされ、平成7年には「海の日」として祝日に制定されるに至ったが、今は法改正によって7月の第3月曜日となっている。
日経新聞(社説)
教育を変えるとき)社会に出た人が学び続ける強い国に
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)地域特産の農産物を使って付加価値の高い食品加工業や外食事業を起こすにはどうしたらいいか――。
学校法人青山学院と大学教員で設立した人材開発会社が「農商工連携」のリーダーを育てようと5月から始めた講座は、30人の定員に対し社会人からの応募が2倍に達した
東日本大震災の影響で仕事が減り、新規事業への進出に迫られた企業の社員や中小企業経営者の参加もある。自ら学び、大震災後の苦境を乗り越えようとしている人たちだ
大学はもっと門戸開け
企業は自己啓発支援を
東京新聞(社説)
中国外交を懸念する 拡大する「核心利益」
 (全文はここからお入り下さい)
(全文はここからお入り下さい)中国は主権や領土にかかわる問題を「核心的利益」として外国に妥協しない姿勢を強めた。その範囲も野放図に広げ、周辺諸国の警戒を招いている。
「国家の主権と安全、発展は外交の最優先任務だ」「国家の核心的利益にかかわる問題は絶対に、いかなる妥協も譲歩もしない」
中国外務省の馬朝旭報道局長が最近、党機関紙に発表した文章の一節。軍やマスコミばかりか外交官にも勇ましい発言が目立つようになった。今月下旬、インドネシアで開かれる東南アジア諸国連合(ASEAN)などの外相会議では中国への対応が焦点になる。
◆2009年の大転換
◆台湾から南シナ海へ
◆抑えきかない下克上