日本学術会議(以下「会議」)の改革が漸くに始動した。
会議の存在は2020年10月に菅義偉前総理が、学術会議が推薦した新規会員候補者のうち6名の任命を拒否したことで注目され始めた。
それまで自分も、会議が「軍事技術の研究は行わない」という頑なな姿勢を堅持し、防衛・国交省の「艦船の補助推進力に帆を活用する」研究すら委託された大学を妨害したことくらいしか知らなかったが、その背景には「新規会員は退任する委員の推薦者を自動的に任命する」ことがあって、そのことが70年以上も終戦当時の一億総懺悔体質を維持していることを知った。
学術会議を所管する内閣府と自民党は、菅前総理の任命拒否騒動を受けて改革案を検討して今回の、「会議の廃止や独立行政法人化は見送って引き続き政府機関とするが、委員の任命に第三者が関与する」という、抜本的改革には程遠い結論になった。2年間かけて「この程度?」と驚いているが、それほど会議と学者の抵抗が根強かったのだろう。
軍事研究拒否の会議が紛れようもない先端軍事技術開発の中国製造2025と協力・蜜月関係にあったことが明るみにされるとともに、会議の存在と前時代的な主張が先端技術開発について列国の後塵を拝している原因とする見方が広まり、会議不要論が大勢を占めるようになった。これらの自己矛盾を正当化するためか、会議の梶田会長も「軍民双方で活用できるデュアルユースについて「単純に二分することはもはや困難」との見解を出したものの、金看板の「軍事研究拒否」は再確認にするという混乱を見せている。
内閣府案は12月6日に公表され、8日の会議総会で正式に提案されるとされていたので、さぞかし総会では学問の自由・独立について高邁な議論の応酬かと期待していたが、案に相違して「既に委員の人選を行っており混乱する」や「法制化案に書かれている見直し時期の前倒し」の質疑が大半であったと報じられている。
新聞「赤旗」は、会議に対して政府等が「問題意識・時間軸等の共有」を求めることに対して、学術会議の梶田会長が「学術には一国に限定されない普遍的な価値と真理の追求を通じ人類全体に奉仕する独自の役割がある」と述べていると伝えているが、現実には世界的に注目される画期的な宇宙理論を提唱した高名な学者が「自分は学術会議に呼ばれることはない」と発言したことを記憶しているので、「普遍的な価値と真理の追求」も「会議の定説に従順な学者は迎えるが、独自な発想は異端者として排除」と解すべきで、定説を疑うことで科学・技術・人類は進化するという世界常識からも取り残されているように思える。
左翼学者の牙城と化し、委員の相伝という形で新進気鋭の研究者に門戸を閉ざす会議は、既に使命を終えているように思える。いや、元々存在する意味が無かったのかもしれない。
最後に、会議委員若しくは委員経験者がノーベル賞を受賞したことはあるのだろうか。











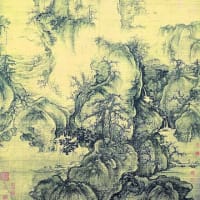








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます