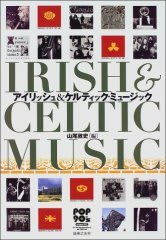先日「カントリー&ウエスタン大好き」という本の紹介記事を書いたが、本書の著者である鈴木カツ氏はその「カントリー&ウエスタン」という言葉に難色を示す人物である。「ウエスタン」という言葉は本来西部劇で使われる音楽を指すものであり、その紛らわしさゆえ「カントリー&ウエスタン」という言葉を使うのは慎むべきだという考えらしい。同じカントリー好きでも三者三様のこだわりがあるわけですな(笑)。その辺僕はというと「カントリー&ウエスタン」と聞けば 50年代、60年代にヒットした本国のカントリー、ジミー時田や小坂一也を始めとする日本人カントリー・ミュージシャン、日本語詞で唄われるカントリー・ソングなどを連想するくらいで、この言葉にカントリー・ミュージックを総称する意味合いは感じない。よってその対象範囲はあくまで限定される。そもそも言葉なんて、いつしか形骸的になることもあるわけで、個人がそれを嫌ったからといってどうなるものでもない。結局「ウエスタン」という言葉を使うか否かに関してはどっちでもいいというのが正直なところ。相変わらずいい加減な男である(笑)。
そろそろ本書の話に移ろう。「カントリー&フォーク決定盤 - ハート・オブ・アメリカ」はそのタイトルからもわかるとおり、カントリーやフォークを中心としたルーツ・ミュージックのガイドブックである。鈴木カツ氏が選定した総勢 180組のアーティストについて、それぞれ1ページないしは2ページを割き、簡単な経歴とお薦めの一枚が紹介されている。これだけのアーティストについて簡潔にまとめるのは大変な労力だったろう。遅筆な自分に置き換えると・・・う~ん、考えたくもない(笑)。アーティストはアルファベット順に並べられているのだが、それ自体にはあまり意味が無いように思える。探しやすさを考慮したにせよ、そんなのは巻末に索引を付ければ済むわけで、どうせなら年代順に並べるなり、ジャンルやスタイルごとに章を設けるなりしてほしかった。この手の音楽に精通している人ならともかく、これから開拓していこうという人にとってはその方が本当の意味で探しやすいといえるのではないだろうか。表紙には「180アーティスト&CDガイド」と書かれているが、これでは単なる人名事典である(苦笑)。そんな構成上の不満はともかく、内容は日本を代表するアメリカ音楽評論家が書いているだけに秀逸である。無駄のないスッキリとした文章は非常に読みやすく、焦点をぼかすことなく中庸にまとめていると思う。好奇心や探求心に満ちた人にとっては守備範囲を広げるキッカケとなるに違いない。新書サイズなので携帯に便利だし、本書の性格上、外出先での拾い読みにも向いているだろう。カントリー関連の書籍が極端に少ない国内においては是非揃えておきたい一冊である。
※何となく「である」体を使って書いてみました(笑)。