「こおろぎの草子」 「虫の三十六歌仙」 7~12
7、かげろふ(カゲロウ)
あはれなる 夕べはかなき かけろふの 消ゆる命を 露の一時
アワレナル ユウベ ハカナキ カゲロウノ キユル イノチオ ツユノ ヒトトキ
解釈:日の暮れて寂しい夕方のように、はかないカゲロウである私です。露が一瞬で消えていくような短い命です。
8、玉むし
いろにこき 千草の花の かずかずに 思ひみだるる 露の玉むし
イロニコキ チグサノ ハナノ カズカズニ オモイ ミダルル ツユノ タマ(ムシ)
解釈:命の短い玉虫である私は、色が濃い、数多くの、華やかな花に心が乱されます。また、花の上には、露が玉のように結んでいます。
考察;「露の玉」とすべき、を玉に続けて「玉虫」としています。そのため、露の様にはかない命の玉虫とも解釈できます。

9、みのむし(蓑虫)
恋ひわびて 涙の袖にぬれにけり わがみの痕は いきてかひなし
イワビテ ナミダノ ソデニ ヌレニケリ。ワガミノ アトワ イキテ カイナシ
解釈:人に恋をして、思うようにならず、涙で袖が濡れて、跡になってしまった。恋がかなわなければ、生きている甲斐もない。
考察:ミノムシという言葉を入れられずに、「ワガみのアトハ」と、「みの」だけをやっと入れ込んだ苦心の歌。

10、木こりむし(木こリ虫:木部を食い荒らす、カミキリの幼虫など)
人しれぬ 深山のおくに 住みなれて 朝な夕なに つま木こりむし
ヒトシレヌ ミヤマノ オクニ スミナレテ アサナ ユウナニ ツマキ コリ ムシ
解釈:人里離れた、山奥に長く棲んでいて、朝に夕に、木を切っています。
考察:「木こり」で「木を切る」、「木を切る人」ことになるが、「木こり」につづけて「木こりむし」としている。
「きこりむし」は、その名から、木の枝、幹を食い荒らす虫であると思われます。カミキリ虫の幼虫は、桑の木を食い荒らす害虫として、知られています。またある種のガの幼虫も、木の枝、幹を食い荒らします。桑の害虫として、枝や幹を食い荒らす虫は、古来から知られていたでしょう。それで、「きこりむし」を「カミキリ虫の幼虫など」と解釈しました。木を食べる虫を蠧虫(とちゅう)=キクイムシと言います。
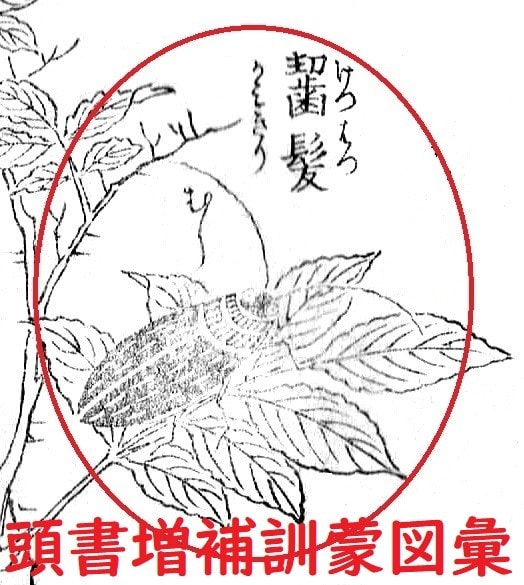
11、蝶
花の色に 心を見せて まよふ(迷う)てふ 哀れとおもへ 草の葉の露
ハナノ イロニ ココロオ ミセテ マヨウチョウ アワレト オモエ クサノハノ ツユ
解釈:花の色に、心を迷わされと言う蝶である私を、哀れと思ってください。草の葉の露よ。
考察:チョウの、古語での仮名遣いでは、テフである。
「まよふてふ」の意味は、「迷う と言う」であるが、音は「まよう ちょう」である。「てふ」の読みは、ちょう=蝶である。
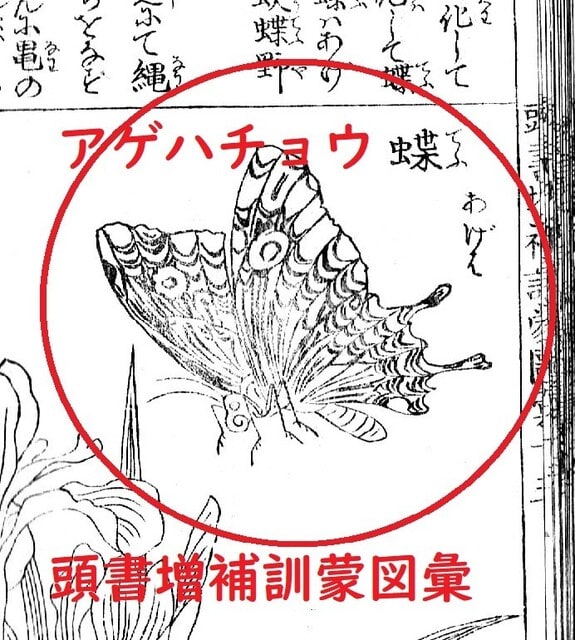
12、蜂(ハチ)
棹さして いつ(何時)か渡らむ みつせ(三つ瀬)川 はちす(蓮)の船に のり(法)を求めて
サオサシテ イツカワタラム ミツセガワ ハチスノフネニ ノリオ モトメテ
解釈:いつか死んで、三途の川に、竿をさして渡る時が来るであろう。蓮(はす=はちす)の船に乗って、来世での救いを求めて。
考察:三つ瀬川は、三途の川のこと。
ここでは、ハチス(蓮)とハチ(蜂)をかけている。










